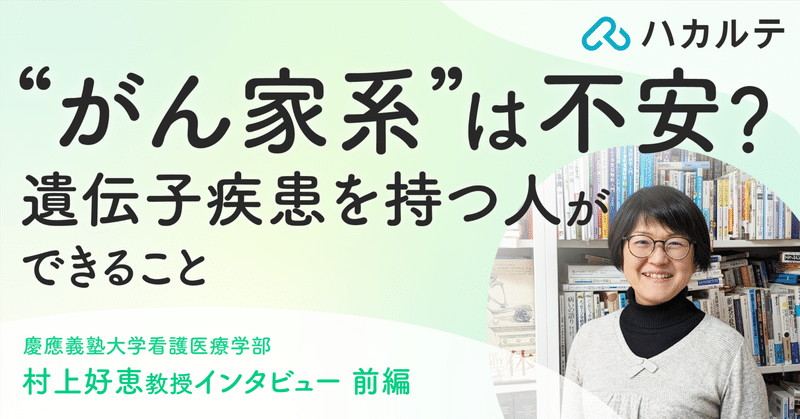
“がん家系”を怖がらないで。遺伝性腫瘍の看護の専門家に聞く「できることと心がまえ」
「“がん家系”ってよく聞くけれど、私の家系はどうだろう?」と気になったことがある方もいると思いますが、実際に自分の遺伝子について調べたことがある人は、あまり多くないのではないでしょうか?もし、がんになりやすいということがわかってしまったら怖い、と思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は、遺伝性腫瘍の看護がご専門の、慶應義塾大学看護医療学部 村上好恵教授に「遺伝性腫瘍の検査と、もし発症した場合の心がまえ」についてお話を伺いました。
プロフィール

村上好恵(むらかみよしえ)教授
1990年弘前大学教育学部特別教科(看護)教員養成課程卒業後、虎の門病院(看護師)、愛媛大学医学部看護学科(助手)、国立がんセンター研究所支所精神腫瘍学研究部(リサーチアシスタント)、聖路加看護大学(講師)、首都大学東京健康福祉学部看護学科(准教授)、東邦大学看護学部がん看護学研究室(教授)を経て、2024年より現職。
1999年兵庫県立看護大学大学院看護学研究科(修士)、2008年聖路加看護大学大学院 博士(看護学)取得。看護師、家族性腫瘍コーディネーターとして、遺伝カウンセリング外来(聖路加国際病院、埼玉医科大学総合医療センターブレストケア科、東邦大学医療センター大森病院など)担当。
市販の遺伝子検査キットではわからない。遺伝性腫瘍とは?
ーー先生は現在どのような研究をしていらっしゃるのですか?
村上:専門は遺伝性腫瘍(遺伝的要因によって発症するがん)の患者さんやご家族への看護です。遺伝性腫瘍の患者さんたちにどのような看護を提供したら良いのか、患者さんやご家族が何に困っていて、どのようなサポートをする必要があるのかという実践と研究を20年以上しています。
遺伝性腫瘍は、がんの発症と関係する生まれつきの遺伝子の変化によって発症します。そういう遺伝子を持っているかどうかは遺伝子検査によってわかるようになってきたので、もし、家系として遺伝性腫瘍の発症の可能性が高いと思われる場合には、がんを発症する前に自分で自分の体の特徴の情報を知っているということがとても大事です。
しかし、遺伝子の情報は、まだまだ解明されていないことも多くありますので、検査を行っても全てが明らかになるわけではありません。
また、遺伝子の変化を持っているからといって、100%発症するともいえませんので、一喜一憂せずに、自分の個性として冷静に捉えてほしいです。
最近はこの分野の研究もかなり進んでいます。がん遺伝子パネル検査(がん細胞に起きている遺伝子の変化を調べ、がんの特徴を知るための検査)に保険が適用できるようになったり、遺伝子解析の機械も進化したり、どんどん進歩しています。
その結果、遺伝性腫瘍の発症に関連する遺伝子の情報が同時にわかるようになってきたので、「通常のがん」「遺伝性のがん」という区別ではなく、自分の体の特徴について、情報を正しく理解して欲しいです。

ーー日本は「遺伝」に関する話はなんとなくタブーというか、あまり積極的にしない方が良いものとされている気がします。自分の遺伝情報を知ることに抵抗がある方もいらっしゃいますか?
村上:なかには「知るのが怖い」との考えから、遺伝カウンセリング外来の受診や遺伝に関する情報を知ることや遺伝子検査を嫌がる方もいらっしゃいますが、知ることががんの早期発見に繋がります。重要なのは検査によってわかった情報をどう使うかだと私は思います。
日本はまだまだこの分野の啓発が足りていないので、患者さんもご家族も、なかには医療者にも誤った認識を持ってる人はいます。
遺伝子が受け継がれてきたから私たちが生まれたわけで、遺伝性疾患だからといって偏見等で特別視するのではなく、病気を治すためにできることを優先して考えてほしいです。
ーーインターネットなどで「遺伝子がわかる」「病気のリスクがわかる」という検査キットが売られていますが、そういうものとは別なんでしょうか?
村上:そういった検査キットと、私たちがやっている遺伝子検査は全く別のものです。「遺伝子情報がわかる」といった検査キットでは、遺伝性腫瘍について知ることはできません。
もし、家族にがんになった方がいて不安な場合は、病院の「遺伝相談外来(「遺伝カウンセリング外来」など名称になっている場合もあり)」に相談してみるのをおすすめします。
遺伝相談外来では、まずご家族の疾患の状況や家系図などから情報を整理して、遺伝性腫瘍の可能性がある場合は、希望があれば遺伝子検査をします。お話を聞いてみると遺伝性腫瘍ではない場合が半分くらいです。保険適用で相談できるので、不安な方はぜひお近くの遺伝相談外来を探してみてください。
「がん家系」は不安?遺伝性疾患を持つ人ができること
ーーいわゆる「がん家系」で、親や家族ががんになった姿を見ていると、自分もがんになるのではないか?と不安になる方もいらっしゃると思います。そういった遺伝性疾患への不安や、若くしてがんになった方へのメンタルケアにはどんなことが必要でしょうか?
村上:がんを発症した家族がいると不安になる方もいらっしゃいますし、むしろ「親ががんだったので私もいずれなると思っていました」と受け入れている方もいらっしゃいます。
がんになった親御さんやご家族が病気について隠していたり、積極的に話さなかったりするとネガティブなものとして捉えられて、逆に「あなたももしかしたらがんになるかもしれないから、気をつけるんだよ」と病気についてよく話し合っているご家族だと、受け入れやすいのだと思います。
家族には心配をかけたくないから病気について話したくないという方もいますが、隠すとより辛くなるものだと思います。まずは家族で病気についてよくコミュニケーションを取ることが、不安を増大させないための第一歩です。

ーー遺伝性疾患を持つ患者さんたちが、がんを発症する前にできることはあるのでしょうか
村上:遺伝性疾患は、若くしてがんになったり、家系内で同じ種類のがんを発症している人が多かったりするなどの特徴があります。
例えば、「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)」という、乳がんや卵巣がんや膵臓がんが発症しやすいという遺伝性の腫瘍があります。
ハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが、お母様を若くして乳がんで亡くしたことをきっかけに遺伝子検査をしたら、ご自身にも乳がんの発症率が非常に高い遺伝子変異が見つかり、乳房の予防切除をしたことで話題になりました。
アンジェリーナさんをきっかけに、遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)や予防切除についての関心が高まったのは良いことだと思います。
遺伝が関係する腫瘍は他にも様々あります。
例えば家族性大腸腺腫症という病気は、その遺伝子変異を受け継いだ人は将来的にほぼ確実に大腸がんを発症するので、予防切除として大腸を全摘出します。
昔は、大腸全摘後に永久人工肛門をつくることが一般的でしたが、現在は、外科医たちの研究により小腸と肛門を手術で結合させる手術が主流になりました。しかし、それでも、大腸全摘後に排便のことで悩みが多いのは事実です。
言いづらい悩みでも…積極的に医療者に頼る大切さ
ーー予防切除でがんの発症は防げますが、その後の生活にはまた別の大変さがあるのですね。抗がん剤の副作用などもそうですが、がんに対処するための治療によって起こる悩みや体の不調には、どのように対処すれば良いのでしょうか?
村上:そういった患者さんたちに対して、看護師として心身ともにどのようなサポートをしていったらいいのかを考えるために、患者会に伺ってお話を聞くなど、長く研究をしてきました。
家族性大腸腺腫症の場合は予防切除によって大腸がんになるリスクはなくなりますが、大腸がなくなると栄養吸収障害が出てきたり、排便に悩まされたりするなど不具合が多く、QOLは下がってしまいがちです。
「こんなに大変なら、大腸をとらなければよかったんじゃないか」と思われる方もおられます。
大腸全摘後の排便障害に困っている患者さんのなかには、自宅の徒歩圏内しか外出しなくなったり、トイレの位置を知っている場所にしか行かなくなったりと、行動が大きく制限されてしまう方もいます。
排便への影響は、とくに人に相談しづらい悩みだと思いますが、やはり通っている病院の看護師などにしっかり困りごとを伝えて欲しいです。何に困っているかはご本人にしかわかりませんから、積極的に医療者に頼ることが大切です。

ーー遺伝性疾患は若くして発症することが多いということですが、まだ若く働き盛りで「がんになってしまってショック」という方もたくさんいらっしゃるでしょう。そういう患者さんはどのようにメンタルを保っていけば良いでしょうか
村上:いまは「がん」と言っても全くひとくくりにできず、発見が遅く手の施しようがないものもあれば、早期に見つかったおかげでしっかり治せるものもあります。しかし診断名としてはどれも「がん」なので、ショックを受けますよね。
最初はショックかもしれませんが、落ち着いて病気に向き合える時期になったら、正しい情報を集めて、自分のがんはどんなものなのかをしっかり認識することが大切です。
どんな種類で、どんな用語があって、エビデンスにはどんなものがあるか?生存率はどれくらいか?そういった情報を知ることで、「がん=死」といった捉え方ではなくなってくるはずです。
一人で抱え込まずに、辛い気持ちを誰かに話して、少しずつ受け止めていって欲しいです。
後編に続きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
