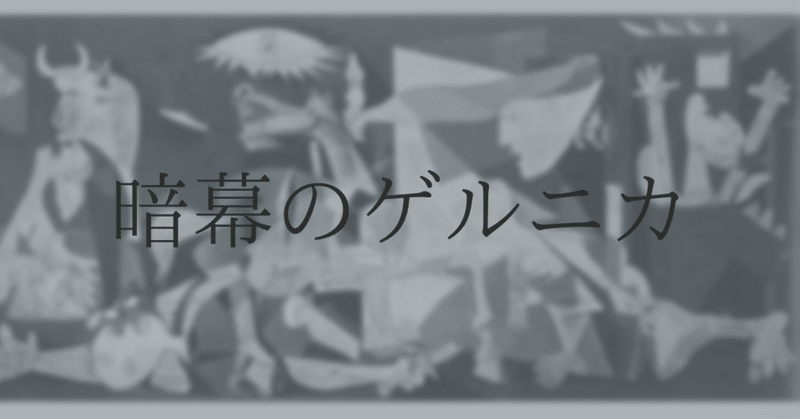
暗幕のゲルニカと年の瀬とときどきスペイン語
年末年始から体調を崩して、そのまま憂鬱な気分を引きずってnoteも開かなくなってしまった。それでも少しずつ浮上しつつあるので、久しぶりに書くことにする。
2022年大晦日、帰省の道中に開いたのは原田マハ著、暗幕のゲルニカ。
数ヶ月前に買って積読していたけれど、何となく22年が終わるまでに読み切りたかった。
新幹線はコロナ前に戻りつつある混雑ぶりだったが、何とか自由席に座れた。
ゲルニカが描かれたスペイン内戦時代と9.11同時多発テロ後の2000年代を交互に行き交いながら物語は進む。実在の人物や史実とフィクションが織り交ぜられて、想像と現実が曖昧な不思議な感覚になる。
歴史の不可逆性を簡単に壊してしまうのがフィクションの面白さだと思う。
新幹線から在来線に乗り換えて、また本を開く。乗り慣れたはずの鈍行を懐かしく感じてしまうのは、それだけ歳を取ったということでしょう。馬の背中くらい揺れる伯備線でも本がスラスラ読めるのは、高校時代に同じように揺られながら受験勉強していた名残り。
作中、パリ万博に展示されたゲルニカの前にドイツの駐在武官がやってくるシーン。
武官の男は軍靴の音を響かせてピカソに近づくと、言った。
「ーこの絵を描いたのは、貴様か」
ピカソは黒々と鋭く輝く目で武官を見据えた。この世の闇と光、すべての真実を見抜く智の結晶のような瞳で。そして、言った。
「いいや。この絵の作者はーあんたたちだ」
スペイン人らしいなって思った。私はスペインに行ったことはないんだけどね。スペイン語をやっていると、時々、こういう風にものすごく腑に落ちる表現に出会う。
例えば出産するはスペイン語でDar a luzと言うけれど、darは英語のgive、luzはlightのこと。直訳すると「光を与える」だ。母親からすれば赤ちゃん自体が光だし、赤ちゃんからすれば胎内から外へ出る瞬間、光を一身に浴びる訳だし。でも、そういうとをよくよく考えなくても直感的に言わんとする事が分かるって実は凄いことだと思う。
ピカソがドイツ人に向かってゲルニカの作者をあんたたちだ、と言った意図なんて、ごちゃごちゃ考察しなくても分かるよねって話。それが芸術ってもんだと言われればそうかもしれないけれど、芸術を“よく分からん”で終わらせてしまう人も少なからずいるから、そういう意味でこの本は美術の教科書より分かりやすい。
物語の後半、MoMAのキュレーター八神瑤子はETA(バスク祖国と自由)に拉致監禁される。そんな展開を読みながら、私は在ペルー日本大使公邸占拠事件のMRTAやメキシコのサパティスタなんかを思い出す。
大学は落ちこぼれで成績も低空飛行だったけれど、こうしてパッと連想してしまうくらいには勉強していたんだなと思うと、少しくらい頑張ってたねと自分を褒めてもいいだろうか。
実家に着いて、年越し蕎麦を食べて、あと数時間で22年も終わりという頃、無事に読了した。紅白は見逃したけれど、22年を振り返るテレビの音と読んだ後の余韻。時代は進んでいるのか、巡っているのか、そんな事を思いながら過ぎていった年の瀬。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
