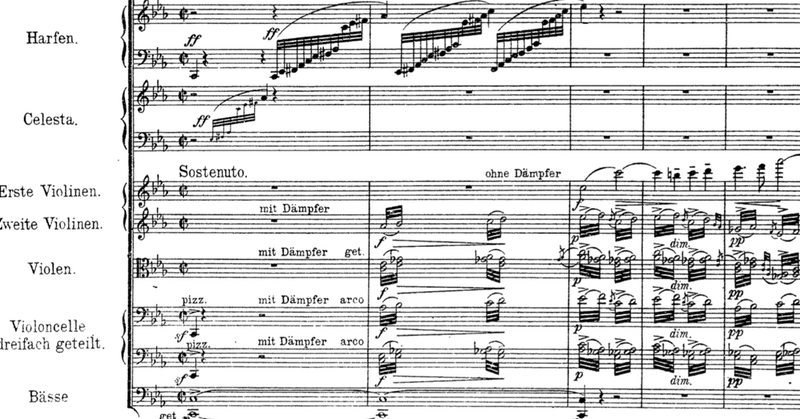#音楽
ジャンル別目次 音楽note
12/14/19 私の音楽note はじめに
12/18/19 我が青春のブラ4
12/20/19 はげ山の夜明け
12/26/19 ニュルンベルクのマイスタージンガー
12/29/19 モーツァルト レクイエム : テンポと編成
12/31/19 モーツァルト レクイエム : 楽譜
1/2/20 合奏はテレパシーで
1/3/20 モーツァルトの倚音
1/5/20 モーツァルトの短調
1/6/20
キースジャレットのバッハ平均率
以前,「キースジャレットのモーツァルト」を書いてからかなり日が経ってしまった。
平均率第1巻にスタジオ録音盤とライブ盤があるのを知ったのがつい先日。ライブ盤を注文して,まだ届いていないのだが楽しみである。
ということで,キースのバッハについてはまた別稿で。
と書いて,CDの到着を待ったのだが,コロナの影響か,1ヶ月くらい経ってから到着した。
さっそく聴いてはみたのだが,音質以外にはそれほど際