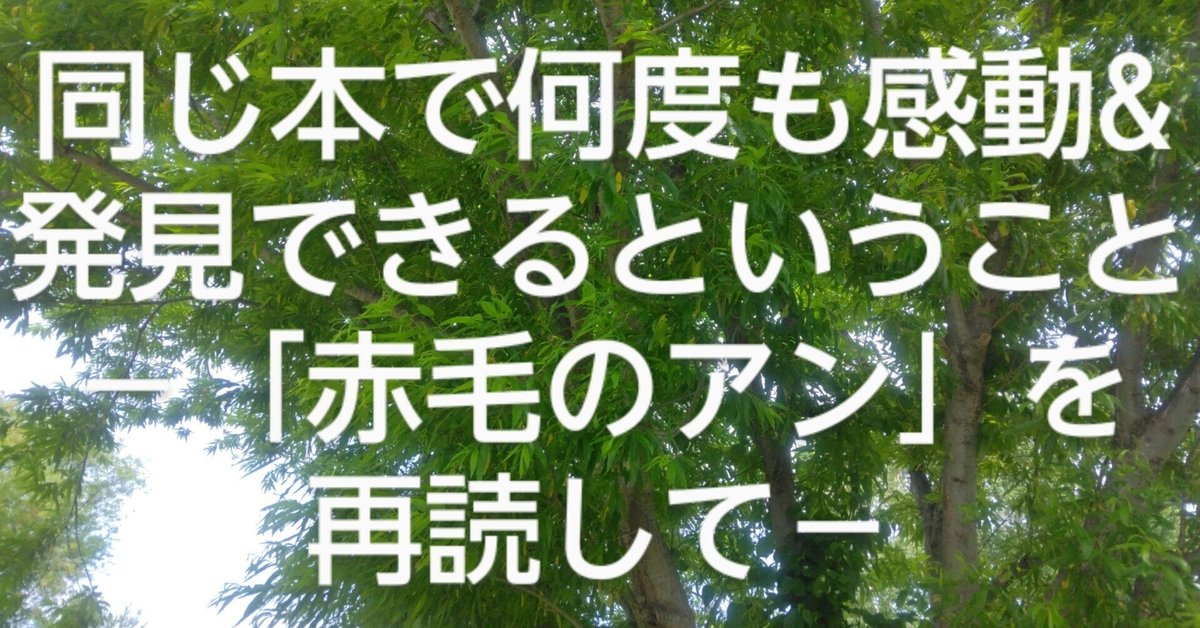
(26)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~
お手紙、つづきです。
「家にある本で、デジタル漬けになる前に『読む』習慣を」
・・・というお話をしています。
低学年までは動画やゲームがなくても家で楽しく過ごせます。
「みんな見てる」「そういう時代」は少し横においといて・・・
読む楽しみとすんなり出会える時期を大切にしたいなと思います。
・お手紙(25)はこちらからどうぞ。
(25)5歳頃から〝積読本〟と暮らすことが「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
今日は
「同じ本で何度も感動&発見できるということ
ー『赤毛のアン』を再読してー」
・・・というお話です。
さて、シオリさん。
10年前に会った時、「自分の子どもには本好きになってほしい」・・・という願いを話してくれましたよね。
「本が好き」って、本をたくさん読めることでもありますが、それと同時に、大好きな本を何度も読める・・・ということでもあると思うんです。
人によって大好きな本は違いますが、何冊も読んでいると、そのうちに「この本はすごいなぁ」・・・と、深く心に刻まれる1冊に出会うことがあります。
その1冊を、たとえば何年かに一度読み返してみると、最初はなんとも思わなかった登場人物や言葉が気になったり、物語に隠されていた深い意味に自分なりに気づいたり・・・初めて読んだ時と違う感想を持つ・・・そういうことって、あると思うんです。
――というか、それこそが読書の醍醐味、大きな魅力と言えるのかもしれません。
当たり前ですが、本に書いてあることは何も変わっていません。
変わったのは自分なわけで、違う感想を抱くようになった心境の変化や、時の流れを感じる・・・そういうものですよね。
私は、子ども達にもぜひ、こういう体験をしてほしいと願っています。
そしてまた、読書で得られる読解力・・・の面から考えた時にも、同じ本を繰り返し読んでみるのは、かなり有効だと思うのです。
「初めて読んだ時は主人公がどうなるかばかり気になっていたけど、読み返してみるとこの友達の存在が大きいよね」とか、「第1章であの人が『〇〇〇〇〇』と言っていたから、最後にこうなったんだね。今わかった」・・・と、まさに読み解くー読解―というものは、再読によって育てられるのかなぁとも思います。
単なる脇キャラだと思っていた登場人物に心を揺さぶられて感動したり、今の自分の状況を励ましてくれる言葉に出会ったり・・・よく知っているはずの物語から感動や発見を得ることだってあると思います。
(もちろんその本が、何度も読むに耐える内容・・・でなければならないですけどね)
そしてそのためには、やっぱり「家に本があること」が大切だと思うんです。結局、ここに戻ります。
――どうか、子どもが気に入った本や、何度でも読んでほしいと願う本は、家の本棚や積読本に混ぜておいてくださいね。
ところで、私にとって「何度読んでも感動&発見できる本」・・・のなかの1冊について、お話させてください。
それは、かの有名な・・・「赤毛のアン」です。
シリーズものとしては長い作品ですが、大好きなのはなんといっても最初の1作。
原作を読んだことがなくても、テレビアニメや映像化作品を見たことのある人は多いかもしれませんね。
さまざまなカタチで書籍化されていますが、私が持っているのは
「赤毛のアン ―赤毛のアン・シリーズ1―」
(作・L.M.モンゴメリ/訳・村岡花子/新潮文庫)。
とても有名な小説ですが、大まかなストーリーとしては、孤児の少女アンが、ひょんなことからマシュウとマリラという初老の兄妹に引き取られ、周囲の愛情に恵まれながら成長していく物語。
美しい自然に囲まれた、19世紀後半のプリンス・エドワード島(カナダ)を舞台にしています。
私がこれを初めて読んだのは20代だったと思うのですが、当時は「おしゃべりで明るい女の子アンがマシュウとマリラ、その周囲の人達に出会って幸せになる物語」――と感じていました。
もちろんそれは間違っていないのですが、40代になり、子育てをしながら再読した時、こう感じたのです。
あぁこれは、
「マシュウとマリラがアンを愛することによって幸せになる物語」
なんだ・・・と。
ーーそう思った時、熱いものがこみ上げました。
そして改めて気になった場面を読み返すと、マシュウとマリラ、アンが出会った最初の夜、マシュウがマリラへ言った言葉に、目の前の景色がグラリと傾くほどの衝撃を受けました。
それは・・・それを引用する前に、どういう状況かを少し説明すると、マシュウとマリラは力仕事を手伝ってくれる男の子を孤児院から引き取る予定でしたが、手違いで女の子ーーアンーーが来てしまい、マリラはアンを孤児院へかえそうと言います。ところがマシュウは、マリラにとって思いがけないことを言うんですね。
ーー以下、マシュウとマリラの会話です(アンは寝ています)。
「そうさな、あの子は、ほんにかわいい、いい子だよ、マリラ。あんなに、ここにいたがるものを送りかえすのは、因業というものじゃないか」
「マシュウ、まさか、あんたは、あの子をひきとらなくちゃならないと言うんじゃ、ないでしょうね」
たとえマシュウが、さか立ちしたいと言いだしたとしても、マリラはこんなに驚きはしなかったであろう。
「そうさな、いや、そんなわけでもないがーー」問いつめられて困ってしまったマシュウは口ごもった。「わしは思うにーーわしらには、あの子を、置いとけまいな」
「置いとけませんね。あの子がわたしらに、何の役にたつというんです?」「わしらのほうであの子になにか役にたつかもしれんよ」突然マシュウは思いがけないことを言いだした。
――「わしらのほうであの子になにか役にたつかもしれんよ」
ここは「赤毛のアン」名シーンのひとつなので、私だけがこの言葉に着目したわけでは決してありません・・・。
けれども、40代になり、子育ての合間に再読した時、
「なぜ初めて読んだ時に、これがすごい言葉だと気づかなかったのだろう」・・・と思いました。
けれどもそれが私(読み手)の生きてきた年月というものなのでしょう。
ーーもし、このマシュウの言葉が
「わしらのほうであの子になにか役にたつかもしれんよ」
ではなく、
「でも・・・可哀想な子じゃないか。引き取ってあげよう」
・・・のようなものだったら、きっとまた流して読んでしまったかもしれません。
言葉から広がるなんとも言えない滋味のような温かさがありますし、この一行でマシュウの人間性を感じますよね。
そしてもうひとつ、今の自分だからこそ「なんて素晴らしい・・・」と感じることができた場面があります。
それは第18章「アンの看護婦」というエピソード。
ある夜、親友ダイアナの妹ミニー・メイが喉頭炎(クルウプ)にかかって重体となり、ダイアナがアンに助けを求めます。両親は不在で、医者を呼ぶこともままなりません・・・。するとアンは、里親のもとで小さな子どもの世話をしていた経験を生かしてミニー・メイを適切に看病し、命を救います。
かけつけた医者から翌日、「あの幼な子の命をたすけたのは、あの子ですよ」とアンの話を聞いたダイアナの母親は深く感謝し、翌日アンを家に招待します。
じつはアンはこの少し前、ダイアナに間違って葡萄酒を飲ませ酔わせてしまい、ダイアナの母から「もう遊んではいけない」と、ひどく嫌われていたのでした・・・(これも有名なエピソードですね)。
ところがミニー・メイの一件で誤解が解け、それどころか命の恩人として深く感謝されたことで、アンの喜びは頂点に達します。
次に引用するのは、ダイアナの家から「おどりながら帰ってきた」アンが、マリラに話す場面です。
「ここにこうして立っているのは、このうえなしに幸福な人間よ、マリラ」とアンは言った。「あたし完全に幸福なのーーそうよ、髪が赤くたってかまわないの。赤い毛なんか問題じゃないのよ。バーリーの小母さんはあたしにキスして泣いて、わるかった、恩の返しようがないって言いなすったの。あたしとってもまごついちゃったわ、マリラ(後略)」
ーー「わしらのほうであの子になにか役にたつかもしれんよ」というマシュウの言葉同様に、もしこのアンの言葉が
「あぁマリラ、あたし今とっても幸せなの」・・・のようなものだったら、やっぱりこの場面だけを切り取って深く感動することは、私はなかったかもしれません。
「ここにこうして立っているのは、このうえなしに幸福な人間よ、マリラ」・・・という言葉には、それまでアンが、自分を幸福な人間だと感じることなく生きてきた・・・という背景が含まれています。
アンはそれまで、孤児だから、赤毛だから・・・自分は不幸なのだと言葉を尽くして訴えてきました(それがおとなのマリラには時折滑稽に思えて、少し笑ってしまったり・・・もするのですが)――本人にとっては切実な問題です。
けれどこの時アンは、自分がそういう生い立ちだからこそ、経験してきたことを生かして、その時ほかの誰にもできなかった「ミニー・メイの命を救う」という役割を完璧に果たすことができたと・・・わかったんですね。
――あたしが、あたしで良かった・・・。
アンの気持ちは、これに尽きるかなと思います。
不遇な生い立ちを含めて、自分というものがそこにあり、自分だからこそその仕事を果たせた・・・これ以上の幸せがあるだろうか、私はこのうえなしに幸福な人間だ・・・という思いだと感じます。ーー今風に言えば、自己肯定感ですね。
アンがそれこそ「すべての不幸の源」のように感じていた赤い髪ですら、「かまわないの」と言っているのですから、これはもう、アンが自分の殻をひとつ破って階段を一段上がった名場面とも言えるでしょう。
――20代の時には、全体的なおもしろさに紛れて、深く感じ入ることのなかったこのいち場面が、今の私には刺さるのでした。
子育てをしていると、いつも悩みます。
子どもをどんなふうに育てるべきか、子どもの幸せってなんだろうか・・・。
もちろん答えはありません。
けれども「赤毛のアン」のこの場面は、私にひとつの発想を与えてくれました。
――あたしが、あたしで良かった・・・。
――自分が、自分で良かった・・・。
子どもが人生のどこかでこんなふうに思ってくれたら、親としてはひとつの責任を果たしたことになるかもしれない・・・そんな風に思います。
子ども達にも、幸せな再読を、人生のどこかで味わってほしいです。
お手紙、続きます。
〈「何冊も」と同じくらいに「一冊を何度も読める」君の眼差し〉
・お手紙(27)はこちらからどうぞ。
(27)5歳頃から〝積読本〟と暮らすことが「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
・お手紙(1)はこちらからどうぞ。
(1)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
