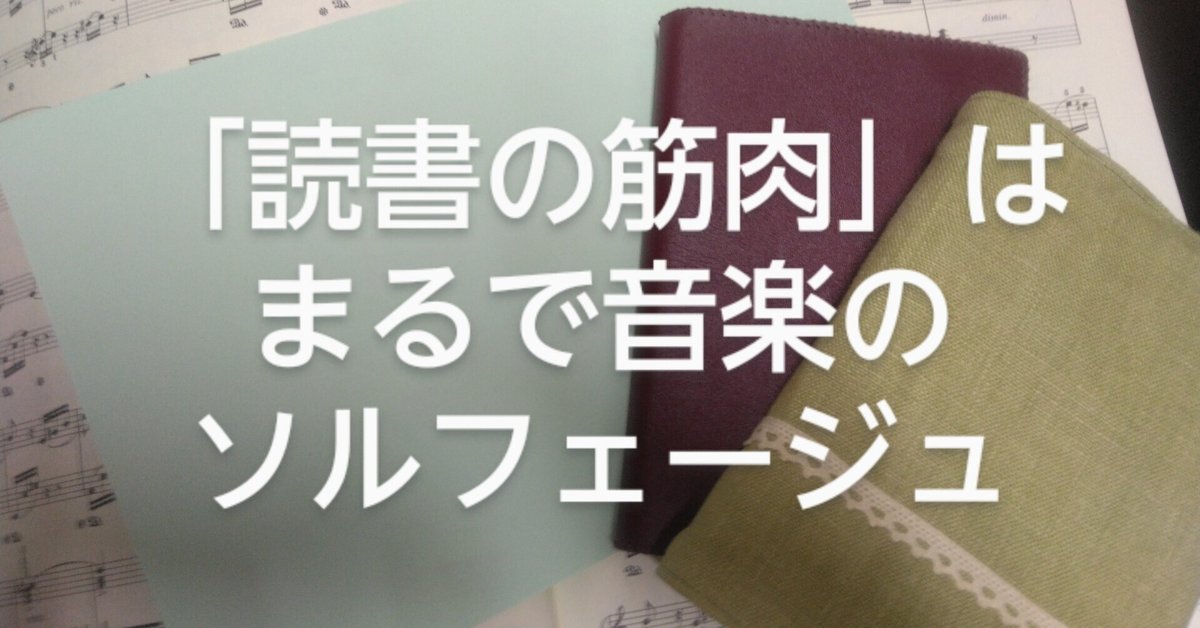
(25)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~
お手紙、つづきです。
「家にある本で、デジタル漬けになる前に『読む』習慣を」
・・・というお話をしています。
低学年までは動画やゲームがなくても家で楽しく過ごせます。
「みんな見てる」「そういう時代」は少し横においといて・・・
読む楽しみとすんなり出会える時期を大切にしたいなと思います。
・お手紙(24)はこちらからどうぞ。
(24)5歳頃から〝積読本〟と暮らすことが「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
今日は
「読書の筋肉はまるで音楽のソルフェージュ」
・・・というお話です。
さて、シオリさん。
突然ですが、シオリさんは、ピアノが弾けますか?
ピアノじゃなくても何か弾ける楽器があったり、楽譜を見て初見で歌が歌えたりするでしょうか?
ーーもしできるなら、子どもの頃に何か習っていませんでしたか?
(ちなみに私は、何も習っていなくて・・・今もできません)
子ども時代に音楽を習っていて、楽譜を見て反射的に演奏できたり、正しいメロディを歌えるところまで技術を習得した人って、その後ブランクがあっても、ある程度、体が覚えているものですよね?
同じように、子ども時代に数年間、野球やサッカーをやっていた人は、おとなになってもボールを見れば自然と体が動くのではないでしょうか?
少なくとも、何もやっていなかった人に比べればまったく違うはずーーそれが「体が覚えている」ということだと思います。
――このお話、じつは読書とも関係があるんです。
読書にも、子ども時代に身につけておくといい「基礎力」がある
・・・と私は思います。
音楽ならソルフェージュ、スポーツならドリブルやパスなどの基礎トレーニング。
・・・読書ならたとえば「読書の筋肉」というものでしょうか。
子ども時代にこの「読書の筋肉」を鍛えておくと、おとなになっても読書に対して体が反応しやすくなります。
楽譜を見るとピアノが弾けるように、考えなくても自転車に乗れるように、パソコンならキーボードを見なくても文章が打てるように。
――シオリさん、本を読むのが苦手なのは、努力不足だからじゃないと私は思います。
10年前に知り合った時、「私は本を読むのが苦手で・・・」と少しうつむいていましたが、何も悪いことも、恥ずかしいことも、後ろめたいこともありません。ごくシンプルに、そういう機会、積み重ねをするチャンスがなかったからではないでしょうか?
もちろん、音楽やスポーツとまったく同じにはできません。
大抵の人は、読もうと思えば本は読めるから。
ただ、慣れていないと読みづらい・・・その差があるんです。
――では、
具体的に読書の筋肉ってどういうスキル
なのでしょう?
これは、あくまで個人的な感覚と対話から得たものなのですが・・・。
私のまわりには、シオリさん以外にも「本を読むのが苦手」という友人が何人かいて、話を聞いてわかったことがあるんです。
ハウツー本ややエッセイなどはともかく、
長編小説を一冊読み切るのに苦労する・・・という人が多いんです。
その苦手意識には共通点があって、
・「長文を読む習慣があまりないのでとにかく時間がかかる」
・「今読んでいる部分がどう本筋に繋がるのかわからないので、モチベーションが保てず疲れてしまう」
・「本の厚みを見ただけで、いつ読み終われるのか想像がつかない」
ーーと、大体こういうことがハードルになっているようなんです・・・。
これは、読書の筋肉がないために感じるハードルなんですね。
読書の筋肉がある人は、おとなになっても比較的
「忙しくても時間を見つけて本を読む」ことができます。
「そうしたくてもなかなかできない」人との決定的な違いは、
「文章を読んで素早く情報を整理・イメージする脳の習慣」
が確立されているかどうか
・・・なのではないでしょうか。
読書慣れしている人は「見当と緩急」で本(長編)を読みます。
ひとつの言葉、1行のニュアンス、数行にわたる文章のかたまりを、パッと「見て」イメージを浮かべることができます(内容の難しさにもよりますが)。ーーなので、読むのが早いです。
そして、たとえば500ページくらいの小説を読んでいる時、「この章、本筋とどう関係してくるのかな?」と思っても、「読めばわかるだろう」と察することができますし、じっくり読むのに疲れそうな箇所は、「とりあえず表面上の文章だけ」さらりと読み流し、自分のペースで読み進めることもできます。
そうして読み終わり、全体像の記憶が新しいうちに、「難しかったけど終わってみるとこういう話だったんだ」「ここが伏線だったんだ」・・・と、確認したい場面だけ読み返すこともできます。
これを繰り返すことで、自分なりの感想を持ったり、読解力を身に付けていったり・・・読書の筋肉が自然と鍛えられていくんですね。
ピアノなら、子どもの頃に簡単な曲から始めて、「弾けた!」を繰り返すことで頭と体(指)の感覚がどんどんつながっていくような・・・感じかなと思います。
小説って、ニュース記事などにはない、小説ならではの文章のニュアンスや、独特の展開があったり、長編には長編の、短編には短編の文脈があるものなんですが、子どもの頃にある程度の冊数を読んでいると、こういうものに自然と慣れていきます。
ところが、あまり読み慣れていない人は、1行1行真剣に向き合って意味を考えてみたり(もちろん良いことなんですが)、理解のおよばない箇所や難しい表現が出てくると「わからない・・・」と思って手が止まり、「その先を読みたい」という勢いそのものが失せてしまったりする・・・いろいろな人からお話を聞いて、そういうことなんだと気づきました。
――読書の筋肉の持ち主が一冊の本に対してはたらかせる勘は、演奏者が一曲の楽譜を見て「こういう曲かな」と感じたり演奏法を考えたりすることに似ていると、私は思います(レベルの差は人それぞれでしょうが・・・)。
また、登山慣れしている人が、山の難易度や気象情報を調べてみて、上る前にある程度登山ルートを組み立てられるのとも、似ていると思います。
対象物に関して、
全体像をイメージするチカラ・・なのかもしれませんね。
私は、ある程度の年齢になってから「読んでみよう」という気持ちを持った人が、「やっぱり一冊を読み切れなかった」「すごく疲れてしまった」という結果に達してしまうのは、すごくもったいないと思っています。
いま、
本を読む人の数も、街の書店もどんどん減っている
・・・と言う話をよく聞きますよね。
本好きの裾野を広げるのなら、子ども達が本好きになるのがいちばん
です。これ以上の解決法はありません・・・。
たくさんの人が子ども時代に読書の筋肉を少しでもつけたら、
おとなになっても気軽に読書する人が増えて、10年後、20年後、
書店がなくなることもないのかな・・・と、考えたりもします。
読書の筋肉を基礎学力として考えてもらえたら、国語の一環として「読書」という教科が増えてもいいんじゃないか・・・と想像したりもします。
言葉を、文章を見てパッとイメージが湧く読書の筋肉、文脈に対する読解力は・・・私は
デジタル習熟度と同じくらい大切
だと思っています。
お手紙、つづきます。
〈文学にもソルフェージュがあればいい 文字でイメージすぐ湧く基礎力〉
・お手紙(26)はこちらからどうぞ。
(26)5歳頃から〝積読本〟と暮らすことが「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
・お手紙(1)はこちらからどうぞ。
(1)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
