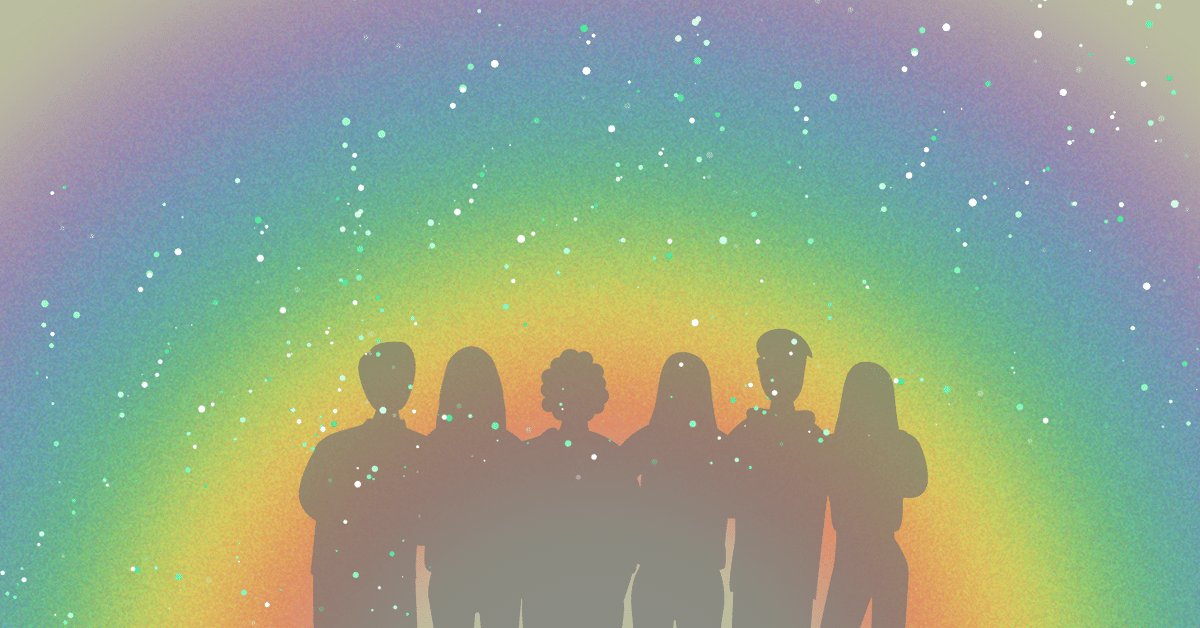
自分を大切にすると人間関係も変わってくる
今回の記事は、人間関係について書いていますが、完全に私の主観によるものです。
あくまでも一個人の意見として軽く受け止めていただけたら嬉しいです。
◇◇◇
興味を持続させる法則

私が尊敬するshogoさんがとても面白い記事を書かれていました。
この中で「興味を持つ」≠「やる気」「モチベーション」で、興味を持ち続けるためには「やる気」や「モチベーション」は相反するものだと言われています。
「興味」が一時的な感情に左右される場合が多いからこそ、継続するには”続けるルール作り”が必要だと言っておられます。
そもそも物事に興味を持つ時、無意識に何かしらの変化を求めているのではないでしょうか?
「新しい自分に出会うために」
「未来の自分が後悔しないために」
「現状を打破するために」
これ、大共感です!
せっかく変化を求めて、自分なりの一歩を踏み出しても継続できなければ、結局は何も変わらないのです。
shogoさんは習慣についての事を書かれているのですが、noteをはじめ、日々の生活全般にも通じる教訓であり、私はこれを「好きな事」を継続させるためのヒントとして響いてしまいました。
一時的な感情に流されずに継続させるための条件やルールについて考えてみます。
仲間づくり
興味をいかに持続させるかの最大の必須条件は、同じ思いを持つ「仲間」ではないでしょうか?
noteでもおなじみの私のサークル「レキジョークル」も元々はただのママ友で、うち2名はかつての同僚です。
結成からはまだ12年ほどですが、メンバーたちとのお付き合いは、長い人ですでに約25年になります。
それまでに様々な形のサークル活動を経て、今の形に収まっているのです。
(詳細は拙書第1巻にて)
正直、歴史に興味のある人は私とチコさんぐらいで、あとの人はほぼ興味がありません。
それぞれが写真撮影や食べ歩きなど、歴史ではなく自分の興味の赴くままに特別な体験をするために参加しています。
個性と協調性
皆、個性はありつつ、協調性もあります。
それぞれの距離を保ちつつ、自分なりの興味に没頭しつつも、強制されることなく協調性を持ち、一つの企画の実現にみんなで取り組んでいます。
提案する
毎年、新年会で一年の予定をざっくりと決めるのですが、いつもほぼ私が提案してしまうので、今年は皆から積極的に提案を募りました。
ここが悩みどころで、これと言った強い意見はあまりなく、結局は歴史関係に落ち着いてしまいました。
ただの「ママ友」や「同僚」が、なにか特別なテーマを持つ関係に変化したからこそ、興味は持続できていると言えます。
”近況報告”だけでは話は広がらない

最近、立て続けに懐かしい人たちと会う機会がありました。
方や次男のサッカーチームで知り合ったママ友とランチ、
方や以前勤めていた会社の同僚たちとの飲み会です。
どちらも食事をしながらお互いの近況を話し、とても楽しい時間を過ごしたのです。
しかし、私は両方の場で同じ質問をするという流れになってしまいました。
好きな事は何?
この質問を投げかけて、即答できる人はいませんでした。
もちろん、皆、それなりに人生経験を積んでいる人たちで、性格的にも人間的にも私自身は好意を寄せている方々です。
「趣味」とまではいかないまでも、「好きな事」を質問してみたら、どなたも考えてしまい、答えがすぐ出ない。
この心地よい人たちとの関係を持続させるには、共通の「好きなこと」を持ちたいと願い、それを聞いておいて、次回以降の集まりはそれに基づいた企画にして、共感し合えたら最高ではではないか。
そうすることで、私も知らなかった世界を垣間見る事ができるし、私の知る世界にも興味を示してくれるかもしれません。
そしてお互いの世界が広まる有意義な集まりになるのではないか?
ママ友は難しい
痛烈に思う事は、「ママ友」だけの関係ほどつまらないものはないということ。
基本的な話の軸は、子供の事ですが、そこには「自慢」や「謙遜」があり、どこか競争心も感じられて警戒しているのも感じます。
子供の成長とともに、受験と言うテーマが加わり、もっと成長すると、子供の恋愛ネタに発展します。
いや、私には正直なところ息子たちの恋愛に関心はありません。
もう成人して親とは別の人生を歩いているし、誰とどんなお付き合いしているかなんて干渉すべきことではなく、自分自身でちゃんと選択して欲しいと心から思っています。
今までも、何かあったら自分からちゃんと話してくれましたし、もし結婚したい人ができたなら、必ず紹介してくれるのはわかっています。
だからこそ下手な詮索は無用であり、子供の恋愛遍歴を延々と語られては、私は退屈でしかありません。
元同僚との話は進展がない
こちらはこちらで、過去の思い出話と会社のその後の変化話が主です。
最初こそこれだけで数時間は楽しめますが、正直言うと、すでに退職した私にはどこか他人事であり、それ以上の興味はありません。
過去には仕事上のみで濃厚なお付き合いがあって、お互いの性格も重々理解し合ってきたつもりでしたが、いったん退職してみると、お互いにほんの一面しか見てこなかったのだと痛感させられます。
ママ友は子たちが成長してから、
同僚とは、退職してから、
それぞれの立場や役目を離れてからが、真のお付き合いが始まるのです。
自分と言う「個」はどこにある?

いわゆる幼馴染とは会うだけで無条件で続きますが、その会うという企画がなければはじまりません。
私の場合は、毎年の中学同級生の忘年会は必ず日時と場所は決まっていますので自然と現在進行形で続いていて、そのうちの数名はなんと小学校の時からのお付き合いで50年以上も続いている人もいます。
毎年「犬鳴温泉」へ行くおばちゃんズや先日の丹波篠山のペコちゃんも、10代の頃からのお付き合いなのでほぼ幼馴染であり、一定の距離を置きながらも長く続いている関係です。
自分を尊重するということ
たとえば、誰かの親であったり、どこかの社員であったり、常に私たちは社会の中の「家族」や「会社」という組織の中で生活をしています。
親や社員であることを脱ぎ捨てて、誰かのための自分ではなく、自分のための自分をちゃんと見つめている人は意外に少ないのではないか?
だから、前述のように自分自身の「好きな事」が答えられないのかもしれません。
自分の好きな事を持たない人は、自分が何をしたいかわからない人であり、自分の為の時間を積極的に作ってこなかった事に他なりません。
それは自分を大切にしていないことになります。
「好きな事」から世界は広がる
正直、ただのママ友や同僚とのランチや飲み会だけでは、お付き合いはそんなには続かないでしょう。
今後のお付き合いを有意義なものにするには、なにか共感し合えるものが必要となります。
何か共通の「好きな事」によって、新たな思い出ができ、話題が増え、
さらにそこから新たな興味が生まれて探究心が芽生えてきます。
それも一人では限界はありますが、複数人のそれぞれの「好きな事」が合わされば知らなかった世界も知る事ができ、さらに興味の世界は広がるのです。
協力し合える仲間がいる事で、モチベーションの維持にもつながり、興味の維持に繋がるはずです。
そのためには、まずは自分の気持ちに正直になって、シンプルに好きか嫌いかを取捨するために、何がしたいか、どう楽しみたいか、それを自分と言う個人に立ち返って考えてみるべきでしょう。
限りある人生を楽しむヒントはそこにあるのです。
この記事が参加している募集
サポートいただけましたら、歴史探訪並びに本の執筆のための取材費に役立てたいと思います。 どうぞご協力よろしくお願いします。
