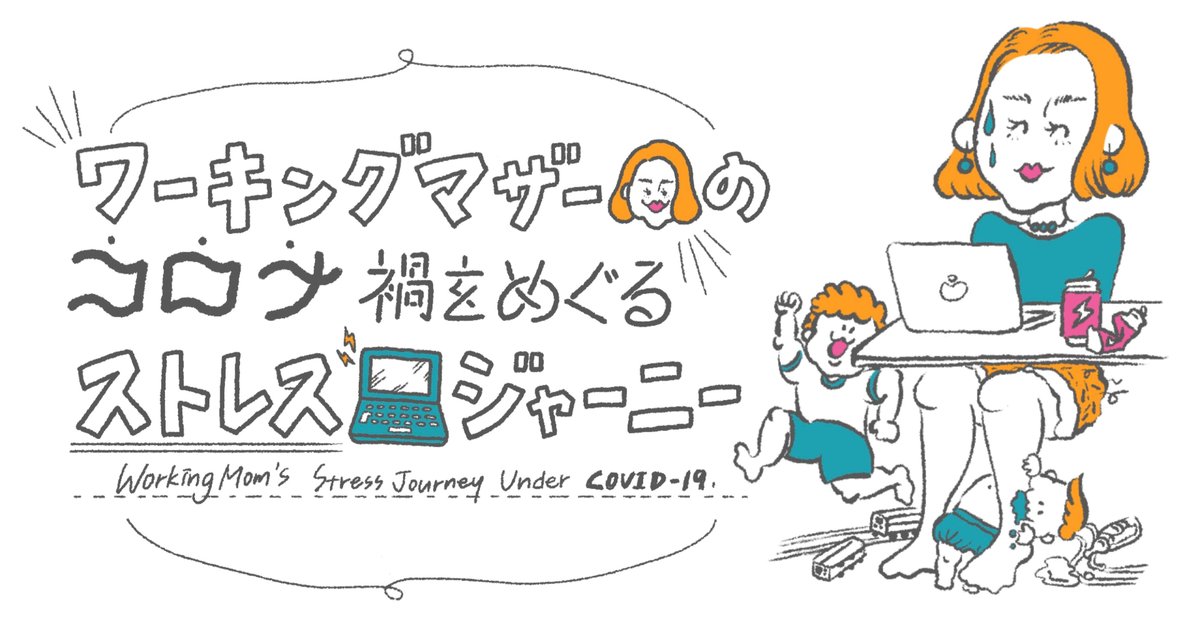
ワーキングマザーの、コロナ禍をめぐるストレス・ジャーニー
働く母親の多忙さとその多様さは群を抜いています。朝は朝食づくりと洗濯をしながらグズる子どもを起こし、職場では保育園のお迎え時間を気にしながら作業に追われ、夜も夕食にお風呂、寝かしつけと目まぐるしく、ホッとできたと思って時計を見れば、もう深夜です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言は、保育園・学校の休業や仕事の在宅勤務などを招き、子ども・母親・父親と生活者に大きな変化を引き起こしました。景気の落ち込みやビジネスパーソンの働き方については連日報道が出ましたが、家庭の様々な役割を担っているワーキングマザーについてはどうなのでしょうか?
「無機質なデータから体温のある生活を描く」をモットーに活動するこのplanning noteは、これまでコロナ禍における生活の変容が議論されてこなかったワーキングマザーに着目。消費生活のデータから、表面的な行動の変化だけでなく、その根拠となるマインドの変化も探ってみました。分析結果から浮かび上がったのは、激動するコロナ禍のなかで荒波をたくましく泳ぎ続けるワーキングマザーたちの姿でした。
それでは、データ分析から彼女たちの姿を見ていきましょう。
食品の購買データは日々のストレスの表われ!?
今回分析したのは、日本全国のスーパーやドラッグストアなど、Tポイント商圏内でのワーキングマザーの食品購買データ。コロナ前として2020年1〜2月、脅威としてコロナを避けた3〜4月、そしてコロナと共生を覚悟した5〜6月……の3期に分け、各商品やカテゴリの購入金額シェアの傾向を、見ていきました。
■分析内容詳細
抽出元:日本全国のTポイント商圏内でのワーキングマザーの購買データ
対象:12歳以下の子どもがいる、会社勤務の母親(全国)
※職業形態はライフスタイルアンケートに回答した時点のものとなる
期間:2020年1〜2月、3〜4月、5〜6月

3〜4月はレギュラーコーヒーやビスケット・米菓が増え、5〜6月にはコーヒードリンク・栄養ドリンク・炭酸フレーバー・ビール・リキュール類・アイスが急増していました。

外出自粛や休業が言い渡された3〜4月。多くの人は在宅時間が長くなり、家事や育児に加えて、ゆったりと過ごす時間が増えました。ワーキングマザーも、このときばかりは一時休戦!?、レギュラーコーヒー(コーヒー豆やドリップコーヒーなど)とビスケットを相棒に読書などを満喫する様子が想像されます。
しかし、5〜6月に入ってニューノーマルとして再び仕事が忙しくなり、在宅で家事・育児・仕事に追われるようになると、購買データからは再び多忙な様子が見えてきます。キリッと仕事モードに入るためのコーヒードリンク(コーヒー豆でなくボトルや缶に詰めた飲料であるあたり、ゆったりと時間を過ごすために飲んでいるのではなさそうです…)や炭酸飲料、無理やり体を奮い立たせる栄養ドリンクに、気分転換のためのお酒を購入しています。お菓子も、アイスなど気軽に食べられる甘いものが増えています(おやつ時間を満喫するケーキなどではないのが特徴的ですね)。3〜4月/5〜6月で、大きな購買の変化を見ることができました。
これらの購買データをまとめると、ワーキングマザーの生活スタイルとマインドの変化が見えてきます。

3〜4月:自分や子どもと向き合う自粛期間
外出自粛でおうち時間が増えた3〜4月。仕事量が減り育児や家事に時間をあてることができるようになったワーキングマザーは、時間と手間をかけて料理を楽しみ、自宅での生活をゆったりと過ごすようになりました。購買データからも、その物自体を欲求するのではなく、購買品を通して、自分や子どもと向き合う様子がうかがえます。
5〜6月:めまぐるしいストレス・ライフの切り替えスイッチ
リフレッシュや疲労回復のための飲料のシェアが伸びたことから、家事・育児・仕事のすべてを自宅でこなさなければならず、両立の難しさに苦戦し始めていることがうかがえます。3食を手際よく作らないといけない煩わしさからか、簡単に調理できる加工食品の購入も増加。オン/オフの切り替えスイッチとして購買品を活用しているのがうかがえます。
同時並行型ストレスを器用に攻略する“ニューノーマル”
コロナ前もワーキングマザーは多忙でした。朝早く起きて家事をこなし、日中は仕事に追われ、夜も子どもの世話をします。しかしその多忙さは、時間ごとで区切ると“家事or育児or仕事”に専念される一極集中型でした。通勤や保育園への送り迎え…といった“移動”がオン/オフを切り替えるひとつのきっかけになっていたのも、コロナ禍と比べると特徴的です。
一方で5〜6月の多忙さは、同時並行型です。自宅のなかで家事・育児・仕事をこなしていかなければならないため、これらの境界は曖昧になり、1人の時間やリフレッシュの機会もなくなり、ストレスを溜め込みやすくなりました。バランス良くすべてを、器用にこなしていかなければなりません。“移動”を伴わないため、会社からの帰り道に缶チューハイを買って飲む楽しみもありません。
そんな同時並行型の日常では、“時短”の対象はもはや仕事だけではありません。自炊・洗濯といった家事や、絵本の読み聞かせや公園の付き添いといった育児も、そしてストレス解消やリフレッシュでさえも(一晩愚痴を言って飲み明かす…なんて時間を贅沢に使う余裕は、もはやありません)、短い時間で、確実に、効果的に行う必要があります。
5〜6月のワーキングマザーの新しいストレスに応える商品やサービスは、どういったものでしょうか?どんなサービスが今後ヒットするのでしょうか?

例えば上記のような、家事も育児もリフレッシュも時短できるような商品やサービスが、求められるのではないでしょうか?
そのときどきで必要な事物を消費し活用することで、多種多様なストレスにも適応してきたワーキングマザーたち。コロナ禍に引き起こされたこうした生活の変化は、女性の社会進出や男女平等が希求される現代社会のなかで、(偶発的であったにもかかわらず)どこか必然性も感じさせます。夫婦が(仕事/家事といった)役割分担でなく協働によるマルチプレイヤーとして、家事も育児も仕事もこなしていく。その実践にタフネス(栄養ドリンク、お酒など)と器用さ(炭酸など)が不可欠であることが、今回の分析からは分かりました。無機質なデータから体温のある生活を、未来像を見出す──planning noteの、ライフスタイル・ジャーニーは、これからも続きます。
