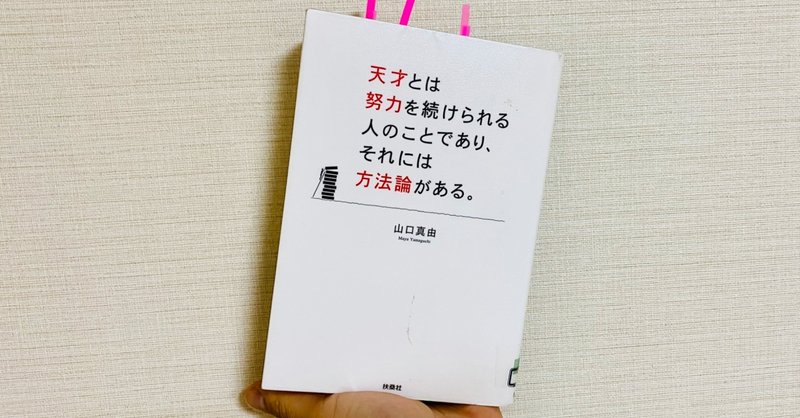
山口真由著 【天才とは努力を続けられる人のことであり、それには方法論がある。】
山口真由さん。
僕はこの人のことを本物の天才だと思っていました。
皆さん彼女の肩書きをご存知ですか?
東大法学部在学中に司法試験に合格(3年)
4年時に国家公務員第1種試験合格
首席で卒業後、財務省に入省
その後弁護士となって、現在はテレビなどでも活躍中…
えっ、なんすかこれ…?
天才も天才、もはや僕ら凡人にはこの肩書の凄さすら正直わかりませんよ(笑)
でも本当は違ったんです。
この人は正真正銘努力の人だったんです。
「そりゃ、東大出てんだからそれなりに努力したでしょうよ」とお思いのあなた。
そんな屁理屈ばっか言ってると嫌われちゃいますよ(笑)
今回なぜこの本を紹介したかったというと、タイトルの通り「努力には方法論」つまりやり方があると知ったからです。
根性論でも精神論でもなくノウハウが存在するのです。
僕自身、この本を読んで努力ができる人は特別な人ではなく、やり方を知ってる人なんだということがよくわかりました。
「努力=辛いもの」と思っている方にとってはそのハードルがグッと下がるいいきっかけになると思います。
・いまいちパッとしない
・努力の成果を実感できない
・努力がお金につながらないという
そんな皆さんにオススメしたい1冊となっています。
今回も本書の中から僕が個人的にマネしてみたいと思ったことや、皆さんも即実践できそうなことから4つピックアップしてみました。
ぜひ最後までご覧ください。
■ 努力すること=〇〇すること
最初に、努力をするというのは、ある目的のために力を尽くすことです。
「努力しろ」「もっと頑張れ」といった抽象的な捉え方ではなく、具体的に何をどうしたらいいのかというふうに考えることで格段に実行しやすくなります。
そして「努力すること」とは何かを「反復・継続」することです。
まずは、なんのために「努力するか」つまり、何を反復・継続するのかを見つけ出すことが大事になってきます。
①読書に手間と時間をかけないこと
【読書は理解するよりページをめくることが重要】
【1回の精読よりも、7回の素通しで読むべし】
◎本は読むことに一生懸命になってはならない。
◎大事なのはあくまでも反復・継続です。
そもそも1度読んだだけで理解しようとすることが誤りです。
反復・継続をしなければ人は学ぶことができません。
一を聞いて十を知る人は、私に言わせれば、その能力の高さゆえに異常な人に分類されます。
十を聞いて一を知ることができれば、大したものじゃないか、そう思います。
このように、読むことに関しては、とにかく回数をこなせと山口さんは言っています。
エビングハウスの忘却曲線のように、2時間かけて1度精読するのではなく、30分で4回ページをめくり続けた方が頭に入ります。
そして、回数を重ねることで徐々に記憶にも定着し、結果的には1回精読した人よりも学習できたことになるのです。
こういったSNSなどへのアウトプットも効果的ですね。
②努力の「8対2の法則」
【楽なもの8割、努力が必要なもの2割が黄金比】
何かを覚えるには、反復がもっとも重要で、反復すれば絶対に解けるようになってきます。
解けるようになると面白くて、さらに努力をつづけることができます。
◎今の実力では8割正解できて、解くのに努力を要するものが2割くらいのレベルが重要。
これより負担が大きいと反復できなくなり、逆にこれより負担が小さいような10割正解できるようなことを延々と続けても今のレベルよりも向上はしない。
できるだけ早く「知っていること8割、知らないこと2割」になるような状態に持っていくことが大切。
数学の問題ならすぐに解答を見る→その解答に従って解いてみる→もう一度解く
それを繰り返すことで、そのうち解答を見なくても解けるようになり、8割の問題はそのやり方で解けるようになる。
◎とにかくストレスを感じずに時間も手間もかけずに楽な方法で8対2まで持っていくこと
③朝食は早めに、昼食は遅めに
【食事の時間で1日を3分割し、有効活用する】
これは僕も実践済みで、その効果も実感している方法です。
1日3食の食事の時間をベンチマークとし、1日のスケジュールを振り分けていくという方法です。
◎昼食の時間をずらす
例えば9時半定時の会社の場合、2時間程度しか働いていないのに、お昼になったらそこでお昼休みが入ってしまいます。
2時間といえば、気分が乗ってきている時でもあるので、このブレイクはコストパフォーマンス的にももったいないです。
〜(中略)〜
しかも昼食が過ぎてしまうと、延々と休みのない午後の時間が続いてしまいます。
だから、疲れてしまうのです。
方法としては昼食を14時前後にして、1日を3分割、均等に分けるようにします。
その後遅くまで仕事や勉強をする必要がある時は、遅めの20時頃に夕飯を食べるようにします。
仕事によって、昼食を遅くすることができない人は逆に朝ごはんを早く済ませてしまいます。
つまり、早起きをして何か活動を始めてしまう。(その分夜は早めに切り上げること)
食事の時間で1日を3分割することのメリットは他にもあって、自分の能力が1日のどの時点で最大化されるのかが明らかになるということが挙げられます。
僕の場合は断然朝方でした。
ですので、夜中に変な時間に起きてしまったらもはや寝ることをあきらめて、そのまま起きてしまうようになりました。
④努力を注ぎ込む優先順位を決めておく
人生において持ち時間は有限です。何かに時間を割くことは、別のことに割けた時間を失うことを意味します。自分の人生における優先順位を決めて、そこから演繹的に行動を引き下ろしていけば、決断が一貫します
◎自分にとってもっとも優先順位の高いものはなにか?
家族との団らん、恋人、睡眠や、食事、そして仕事や趣味など。
どんなにお金持ちでも貧しくても1日が24時間であることは永遠に変えることができません。
限られた時間の中で、全てのことを平等にとはなかなかいかないので、その時間を常に何かに割り振っていくことがそれぞれに求められます。
自分がどこにどれだけ努力の時間を割くのかを明確に順位付けしておくことで、努力の優先順位がぶれなくなります。
●まとめ
・努力とは目的のために力を尽くすこと
・努力とは「反復」と「継続」である
・反復、継続は今の実力でできること8割、新たに努力を必要とするもの2割の黄金比で取り組むこと
・食事の時間、1日を3分割にしてスケジュールを振り分ける→1日の中で自分の力を最大化できる時間帯を把握しておく。
・自分にとってどこにどれだけ努力の時間を割くのかを明確に決めておく
*
努力に対する考え方は人それぞれだと思います。
言葉を聞くだけで毛嫌いしてしまう人もいれば、モチベーションが上がるという人もいるでしょう。
ただ、著者の山口さんもおっしゃっていましたが、努力すること自体が目標ではないということです。
努力はあくまでもなにかを実現するための手段なのです。
特別秀でた才能がなくても誰よりも努力すれば誰よりも大きな成果を得ることができます。
本書では他にも努力を始めるためのきっかけ、努力を続けるための習慣、最後まで成し遂げるための方法が具体的に書いてあります。
何から手をつけていいのかわからない、このまま続けていいのかわからない。
そんな方にとっては非常に有益な内容が盛り沢山です。
これを機に皆さんも新たな努力を始めてみませんか?
いただいたサポートは今後のイベントや活動費などにさせていただきたいと思います! よろしくお願いします!
