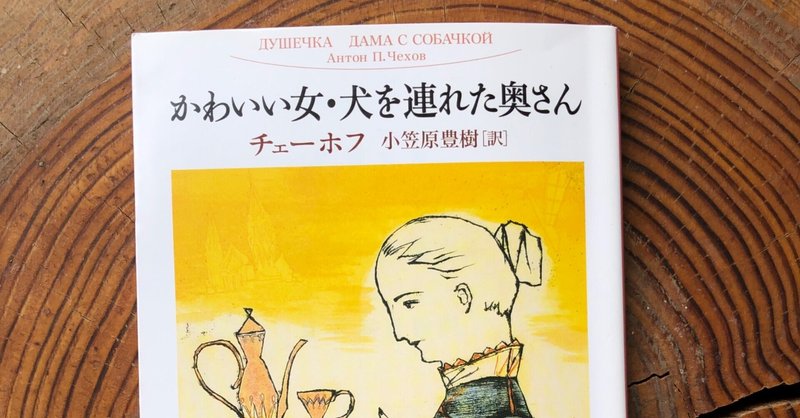
かわいい女・犬を連れた奥さん
訳 小笠原 豊樹
出版 新潮文庫
医学は正妻、文学は愛人
チェーホフの有名な言葉です。(1888年、スヴォーリンへの手紙)
19世紀のロシア文学といえば、ドストエフスキーやトルストイといった非常に重厚な文学が傑出されていました。
その中で、チェーホフは本業作家ではなく、本業医師としてのチェーホフと文学者としてシニカルでユーモア溢れる短編小説や娯楽演劇用の戯曲を得意としていました。
今回は、チェーホフの表題作2つとその他7つの短編から、3つ印象に残った作品の感想です。
「かわいい女(ひと)」(1899年)
「犬を連れた奥さん」(1899年)
「いいなずけ」(1903)
チェーホフ略歴と作風
1860年1月29日
誕生 ロシア帝国、タガンログ
1884年
モスクワ大学医学部卒業
1895年
代表作 長編戯曲 「かもめ」
1897年
大量吐血で倒れる
1899年
短編 「かわいい女」「犬を連れた奥さん」
1901年
戯曲「3人姉妹」マーニャ役の女優オリガ・クッペルと結婚
1903年
短編 いいなずけ
1904年
代表作 戯曲 「桜の園」
7月15日
ドイツの旗 ドイツ帝国、バーデンワイラー
44歳没
作風はレフ・トルストイの思想にかなりの影響を受けていると言われていますが、前述のとおり、とてもユーモアに溢れており、また風刺的であり、そして情景が浮かび上がるようなリアリズムにも溢れています。
かわいい女
チェーホフが影響を受けたトルストイから絶賛された作品。
「トルストイはその編著『読書の環』にこの作品を載せて、チェーホフを旧約聖書のバラム(『民数紀略』二十二章以下)になぞらえ、「彼も初めは詛のろうつもりだったが、詩神がそれを制してかえって祝福せしめられたものである」と述べ、このオーリャという可憐かれんな映像を、「女性というものが自ら幸福となり、また運命によって結ばれる相手を幸福ならしめんがために到達し得る姿の永遠の典型」としてたたえている。」
岩波文庫版 あとがきより引用
チェーホフ自身は、自分の意思を持たずに、すぐに他人に迎合することに対する風刺的な意味合いがあったようです。
しかし、トルストイにとって主人公は献身的愛の象徴でした。
僕にとっては、オーレンカ=カミュ「異邦人」のムルソーを明るい性格にし、角を丸めたようにも思えました。ただ、かなりの依存症なのかなとは思いましたが、、、
パートナーに状況に応じて自分の意思を持たずに献身的にされたら愛せますか?
僕は、もし妻が「迎合しか」しなかったら、どうでしょうね…。わがままでも自分の感情表現が豊かで無邪気なところが妻の良い所でもあるので、何かあったのかなと逆に心配になってしまうと思います。反面、万が一、元々そうした性格だったとしたら、僕自身の傲慢さが助長されていくかもしれません。
「かわいい」とは、難しい表現です。
天真爛漫で、感情表現豊かで、やや献身的なら、僕は好きですが!
めちゃくちゃ献身的だと、依存にしか見えなくなってくる時がきたり、もしくは、とんでもなく傲慢になってしまいそうです。
犬を連れた奥さん
ゴーリキイがこれを一読して、「リアリズムに最後のとどめをさすもの」と絶賛。
チェーホフ後期の彼の芸術性を凝縮させたような作品。
1899年に出版されました。
リアリズム溢れる文章で描かれる中年の妻子ある男と若い人妻の恋愛もの。
一途にお互い想い合う姿と風景描写は、何となく志賀直哉を思い出しました。
僕にとっては、この短編集の中で一番好きな作品でした。
ヤルタは朝霧の彼方に幽かに見え、山々の頂には白い雲が動かずに浮かんでいた。木々の葉はそよともせず、蝉が啼き、下の方から聞こえてくる単調で鈍い海のざわめきは、人を待ち受けている安らぎを、永遠の眠りを語っていた。海はまだヤルタやオレアンダがなかった頃も同じ場所でざわめき、現在もざわめき、私たちがいなくなったあとも同じように無関心にざわめきつづけるだろう。その恒久不変性のなかに、私たち一人一人の生や死にたいするこの全き無関心のなかに、恐らくは私たちの永遠の救いや、地上の生活の絶え間ない移り行きや、絶え間ない向上を保証するものが隠されているに相違いない。
(中略)
この世のことは何もかも美しいのであり、美しくないのは生きることの気高い目的や自分の人間的価値を忘れたときの私たちの考えや行為だけなのだ、
「かわいい女・犬を連れた奥さんー犬を連れた奥さん」チェーホフ 新潮文庫 p141
素晴らしく写実的でありながら、生きる事の気高さを訴えているチェーホフのこの文章が心に響きました。
いいなずけ
結核で亡くなる前年に出版された短編。
高等遊民的に生活を送る主人公ナージャとその家族、そして同様に生活を送るナージャのフィアンセ アンドレイ・アレクセイ。
そんなナージャたちの暮らしぶりにナージャの幼馴染サーシャは諭します。
「そうしてここには堂々たる建物が建ち、すばらしい庭園や、見たこともないような噴水や、すぐれた人間たちが現われる……でも肝心なのはそんなことじゃない。肝心なのは、ぼくらが言う意味での群衆、つまり現在あるがままの群衆、この悪というものがその場合にはなくなってしまうということ。だって一人一人の人間が信念を持ち、一人一人の人間が何のために生きるかを知り、だれ一人として群衆に頼ろうとはしなくなるんですからね。
(中略)
こんな淀んだ灰色の罪深い生活なんかうんざりだということを、みんなに見せつけてやりなさい。せめて自分自身にでもみせつけてやりなさい!」
「かわいい女・犬を連れた奥さんーいいなずけ」チェーホフ 新潮文庫 p254
このサーシャの言葉に僕は頷きながら読んでいました。
病で亡くなる主人公ナージャの幼なじみと44歳で亡くなったチェーホフが重なってしまいました。
ドストエフスキーやトルストイの長編大作たちも素晴らしいですが、チェーホフの短編集もいくつもの気づきを与えてくれます。
余談 村上春樹とチェーホフ
ハルキストならチェーホフとドストエフスキーが春樹の作品に度々登場するので馴染み深いかもしれません。
1Q84でも天吾にチェーホフの「サハリン島」を読ませたり、青豆が「チェーホフの銃」で自殺しようとしたり。
1Q84はジョージ・オーウェルの1984年のオマージュ的作品だと僕は思っています。全体主義での理不尽さとの対比として、チェーホフの「サハリン島」を出しているのかもしれません。
春樹はロシア文学に傾倒していたのでしょう。
#チェーホフ
#かわいい女
#犬を連れた奥さん
#新潮文庫
#小笠原豊樹
#ロシア文学
#短編
#読書
#読書記録
#読書好きな人と繋がりたい
#本
#本好きな人と繋がりたい
#恋愛
いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。
