
メンバー自己紹介② 権藤 有作(Part2)
高校受験
そんなこんな(Part1参照)しているうちに受験生になっていた私は、「とにかく実家を出たい」「周りの人とは異なる進路を歩みたい」という強い想いを抱いており、県外の高校に進学することは決めていました。
そこで私が最初に見学したのは「東京都立八王子桑志高校」。
自転車競技部がその年のインターハイに出場していたためその高校を選びましたが、あまりピンと来ませんでした。
そのピンと来なかった理由を探したことで、「部活で自転車に乗ったら自転車を嫌いになりそうで不安」「可能な限り受験勉強はしたくない」という気持ちに気付くことができました。

振り出しへ戻って進学先に悩んでいた私を救ってくれたのは、兄でした。
島根県は隠岐島前の海士町という地域にある「民宿 但馬屋」でインターンをして地元の高校生とも交流があった兄は、「隠岐島前高校」を強く勧めてくれました。
「県外からの受け入れ制度も整ってるみたいやし、偏差値自体は高くないからあんまり勉強しなくて良いと思うし、何しろあの環境で高校生活送れるのが羨ましい」という話を聞いた私は「これだ!」と思い、大阪で開かれた「しまね留学説明会」に参加しました。
説明会では小難しいことを言っていたので少し不安になりましたが、県外生の選抜方法は面接&小論文&グループディスカッションだと知った瞬間に第一志望が「隠岐島前高校」に決まりました。(ちなみに第二志望は調理科と自転車競技部のある青森山田高校。見学にも説明会にも行かずにネットの情報だけで志望しました)

親子で寝坊し、危うく乗り遅れるところでした。
軽く面接と小論文の練習をして臨んだ受験当日。
面接とグループディスカッションは持ち前の甘いマスクを活かして無事に終えましたが(やかましい)、小論文は時間が足りなくて必要な文字数の8割ほどしか書くことができませんでした。(昔から短時間での言語化が大の苦手でした)
さすがに落ちたかな、と思いました。
しかし、結果はなぜか合格!
周りの同級生たちはまだ受験を控えていたため喜ぶのはほどほどにしましたが、残りの中学校生活を気楽に過ごし、気持ち良く卒業することができました。
高校時代
島根県立隠岐島前高等学校に入学。(本土からフェリーで約3時間)
三燈寮に入寮。(学校から徒歩1分)
入学当初は「残念な竹内涼真」と呼ばれていました。(「残念じゃないよ」「大谷翔平にも似てるよね」と言ってくださる方もいました!!)
レスリング部
中学時代から筋トレをしていて体が大きかったため、入学してから毎日のようにレスリング部に勧誘されていましたが、「性格上、絶対に格闘技は向いていない」「地域活動に専念したい」「痛いのヤダ!」と思っていたので断り続けていました。
しかし、寮で仲良くしてくれていた先輩がレスリング部だったこともあり、粘り強い勧誘に負けて1年次の2学期から入部した私は、地域活動がある日は休ませてもらいながら部活を続けていました。
すると、2年生の時に、なんと2回の全国大会(インハイと国体)に出場することができました。
そう、実はレスリングの天才だったんです。
と言いたいところですが、才能は皆無でしたし、努力していたわけでもありません。ただ運が良かっただけです。
島根県にはレスリング部のある高校が母校含めた2校しかなく、競技人口も少なかったため、私の階級(個人92kg級、団体125kg級)は島根県で私ひとりしかいませんでした。(ちなみに当時の最高体重は84kg)
つまり、戦わずして県大会優勝者になれたということです。(まあ練習も大会経験も少ない小心者が全国大会では通用するはずもなく、ボコボコにされましたが笑)
案の定 格闘技には向いていない性格で、「やめたい」と言い続けていましたが、今となっては本当に入部して良かったと感じています。
地域活動
私は1年生の頃から「せっかく島に来たなら外に出なきゃもったいない」と考えていたので、とにかく地域に出ること、島民の方々と関わることを大事にしていました。
お米の種まきや、祭りの準備、冷凍工場での作業など、様々なお手伝いをさせてもらっていました。
特に漁師さんの岩牡蠣やアカモクの作業はよく通わせてもらい、休憩中に頂ける”規格外で商品にならない岩牡蠣"は最高でした。

魚釣りに本格的にハマったのは2年生の秋で、鳥取から来島されていた釣り師の方からルアー釣りを教えてもらったのがきっかけです。
それからは部活後でも時間があれば釣行するようになり、どうしても釣りができない日は釣り具を弄って欲望を満たすほどになっていました。
今の私にとって魚釣りは、「これさえできれば幸せ」と感じられるものですし、釣りがきっかけで出会えた方もたくさんいるので、釣りを好きになれて良かったと心の底から感じています。

わずか5投でこの3匹(アコウ、ヒラマサ、スズキ)が釣れました。
寮長
隠岐島前高校には「三燈寮(さんとうりょう)」と呼ばれる男子寮と「鏡浦寮(けいほりょう)」という女子寮があり、県外から来た生徒は基本的に全員が入寮する仕組みでした。

全国の高校寮の運営方法は大きく分けて2種類あります。
教員等の大人たちがルールを決めて管理する「管理寮」と、学生が自分たちで運営する「自治寮」です。
私が暮らしていた三燈寮は後者で、「みんなでつくる島家、いつでも還れる島家」というコンセプトのもと、寮長・副寮長が中心となって、ハウスマスターの小谷さん(管理人兼寮生の相談役となるお兄さん的存在)からアドバイスを頂きながらより良い寮を目指して運営していました。
基本的に寮長は1名、副寮長は1名か2名で構成され、毎年6月頃に寮生間での選挙によって決められます。
3年生は受験があるため、寮長・副寮長は2年生が担います。(特に決まりはないので1年生が担うこともありますが)
2年生になった私は、”1年生の時に迷惑をかけたことによって失われた信用を取り戻したい”(ここでは書けないようなことをやらかして、多くの方に大変なご迷惑をおかけしました)、”人に流されやすい自分を変えたい”という想いを抱いており、自己抑制の意も込めて寮長に立候補しました。
そして、5人の立候補者の中から見事選ばれた私は、その直後に選ばれた1名の副寮長とともに、「隠岐島前高校男子寮の顔」として寮を引っ張っていく存在となりました。
寮長として最初にすべきことは、寮運営の軸となる全体のビジョンを決めることでした。
なぜなら、全国から自我と個性が強い高校生が集まっていて、かつ自由度の高い自治寮をより良い方向へ進化させるためには、ビジョンを基にした共通認識を全員に持ってもらうことと、一人一人に役割を与えることが重要だと考えていたからです。
しかし、半ば自分の欲求を満たすために寮長になった当時の私は、「こんな寮にしたい!」というのが思い浮かばず、ビジョンを決めることができませんでした。
そこで私は、ひとまず目の前の課題を解決することに着手しました。
二度寝して学校に遅刻する寮生がいるという問題があった時には、朝の点呼時に全員で筋トレや声出しをして目を覚まさせたり(脳筋ブラック企業)、寮の食事(寮母さんが3食作ってくれている)が余っている時には、自分が誰よりも食べて余り物を減らしたりしていました。(大食いのコツは、最後まで「美味しいな~」と無理にでも思いながら食べること)
また、寮長時代から「見て見ぬふりをしない」ということを特に意識して生きてきました。
寮の中でも外でも、ゴミが落ちていたら拾う。トイレのスリッパが乱れていたら並べる。など、どれだけ些細なことでも、どれだけ自分が疲弊していても、気付いたことには目を背けないようにしていました。
寮をより良くするために常にアンテナを張って過ごしていたこの経験は今でも活きており、私を寮長として認めてくれた周囲の方々には本当に本当に感謝しています。
大学受験
あっという間に3年生になっていた私は、親の力を借りてまで大学に行きたいとは思っていなかったため、東京の高層ビル建設現場で働こうと考えていました。高い所好きだし。体動かすの好きだし。ものづくりしたいし。
しかし、尊敬している大人の方(ハウスマスターの小谷さん)から「大学進学は、”時間をお金で買う”っていう考え方もできるよ。親御さんにも甘えられるうちに甘えたらいいんじゃない?」というお言葉を頂いて考え方が一変し、進学を目指すことにしました。
ただ、中学時代と同様に受験勉強は断固拒否だったので、学校推薦や自己推薦で進学できるかつ、入学後も机上の学習に追われることがなさそうな大学を探していました。
そんなある日、Facebookを流し見していると、流れてきたのは「在学中に全学生が起業にチャレンジ」と書かれた専門職大学(2020年度から開学、東京スカイツリーから徒歩15分に位置する)の広告でした。
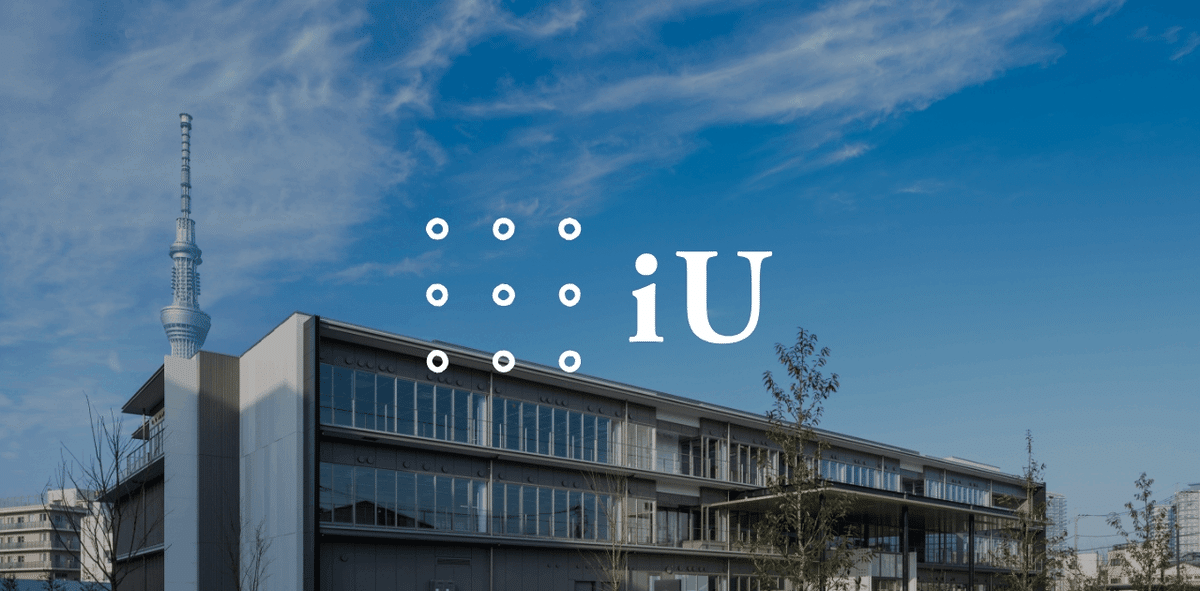
中学生の頃から何となく起業に興味があったためか、気付けばその広告からサイトを開いていました。
そこに書かれている「従来の大学と違う点は、経験を積みながら実践的に学ぶ点です」「学生全員が640時間のインターンシップを必ず経験します」「就職率0%を目指しています(全員起業が目標)」というのを目にした私は、「ここなら座学よりも行動しながら学ぶことができそう」と都合の良い捉え方をして、その大学に興味が湧いていました。
選抜方法を調べると、自己推薦の面接型を選べば面接と書類審査だけで合否判定するということが分かり、すぐに出願しました。
「新設校だからできるだけ多くの学生に入学してもらいたいはず…」と受験を軽視して直前まで釣りをしていましたが、持ち前の存在感で圧倒して無事に面接を終えました。(島根から持ってきたでっけぇキャリーケースを預け忘れて、面接室まで引いて行ったから目立ったという話は内緒で🤫)
面接は雑談のようなものでしたが(最初の1、2分は島根の離島からどうやって来たのかという話をしていました)、結果は合格!
これまた早めに進路が決まったので、喜びすぎないように気を付けながら残りの島生活を堪能しました。
全国47都道府県制覇
3年生の中で進路が決まっている生徒は1、2月が自由登校期間でした。
2月上旬に栃木県で自動車免許合宿を終えた私は、「せっかく栃木まで来たなら、まだ行ったことのない東北地方(福島県以外の5県)と新潟・富山を巡ろう」と思いつき、一人で電車やバスに乗って東北と北陸を制覇しました。

その後、「どうせなら高校を卒業するまでに全国47都道府県を制覇したい」と考えた私は、一度関西に戻り、飛行機とバスで最後の1県である長崎県へ訪れ、なんとか自己満足の旅を成し遂げることができました。

ちなみにあとの2つは、東京の「日本橋」と山口の「錦帯橋」。
磯から参加した卒業式
卒業式はオンラインで行われたため、私はギリギリ電波が届く磯から参加しました。
怒られそうなので何をしていたかは書けませんが、刺激的な卒業式でした。
卒業できて良かったです。まじで。


邪魔でした。
Part3へ続く
本当にごめんなさい!
書いているうちに次から次へと書きたいことが増えてしまい、またまた想像以上にボリューミーになってしまいました。
大学入学後の私については次回書きますので、そちらも読んでいただけると大変嬉しい限りです…。
自己紹介は次で最後にします…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
