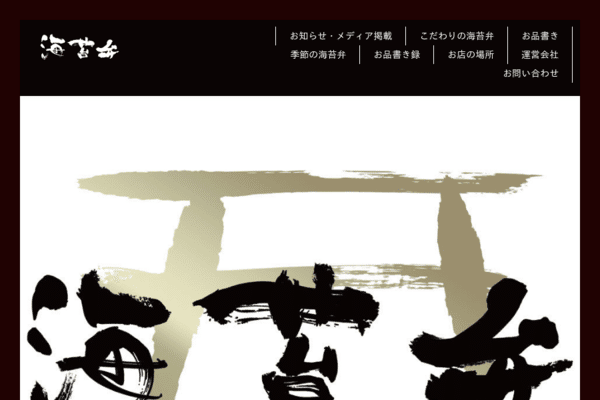「知名度にお金が支払われる」について、考える。
テレビ番組で、漫才師・ハライチ岩井勇気が語ったことが、強めに印象に残っている。
自分の収入の変化について、以前は、才能や能力や努力や工夫の成果としての作品や表現の質について、お金が支払われると思っていた。だけど、キャリアを重ねて気がついたのは、そんなことではなく、単純に「知名度にお金が払われる」のがわかった。
そんな話を、岩井がしていた。それまでうっすらと気がついていて、だけど、その一方で、それを認められなかった自分の気持ちにも気がついた。
知名度の高低、それに応じて、報酬が支払われる。
現代では、その表現の質の高さといったことも含めて、実は報酬とは直接は関係がなく、おそらくは知名度の高さ以外の尺度はない。
そのことに視聴者として、社会で生きている人間として、改めて気がつかされてしまったから、その見定めは、とても鋭く貴重だと思った。
のり弁当
他の番組で、岩井自身が、そのことを証明するかのような動きをしていた。
「もっと評価されるべき審議会」という番組で、岩井は、ある「のり弁」の話をしていた。それは、もちろん美味しいものだけど、最近になって、テレビ局で出演者に出される弁当のメニューの一つとして加わり始めている。それはラジオでのり弁の話題を取り上げた「自分の力」と話をした。
その検証のために、番組では、その弁当屋の社長にインタビューをしていた。
その答えは、思った以上に、岩井の影響を直接語っていた。2年前に開店し、その後1年ほどはそれほどお客が来なかったのに、急に人が来始めた。それも、口を揃えて、岩井がラジオでほめていた、といった言葉を残したらしい。
そして、その後、1店舗から7店舗になったのだから、確かに岩井の影響が大きかったのは間違いないようだった。
この海苔弁当も、創業時から味は変わらなかったはずで、美味しいのであれば、そのうちにお客の口コミによって売上げが伸びたことも予想できるのだけど、だけど「知名度のある人物」が「名前を告げた」ために「知名度」が上がり、そのために売り上げが一気に伸び、店舗数まで増やすことができた。
知名度に、お金が支払われる。
そのことを、岩井自身が、結果として証明するような行動をしたのだと思った。
有名な作家のペンネーム
スティーブン・キングという誰もが知っているような「有名な作家」が別名義リチャード・パックマンで小説を発表したことがある。それは、業界のルールという事情があったものの、最終的には、スティーブン・キングが書いた、ということが明らかになってから、売れ始めた、という有名なエピソードがある。
キングのペンネームだと発覚後、リチャード・バックマン名義のペーパーバックを読みたい人々が書店に殺到した
詳細を検討すれば、他にも色々な要素があるはずだけど、読者は、スティーブン・キングという「自分が知っている作家」の作品が読みたかったのだと思う。
これも「知名度にお金が払われる」ことを証明していると考えられる。
単純接触効果
ある刺激に触れれば触れるほど,それを好きになっていく現象を単純接触効果といいます。
「触れることが多い」人やモノほど「好意」を持つようになれば、それは「収入」につながりやすいのも自然だと思う。
これは「知名度にお金が払われる」につながるような事実を言っているようにも感じる。
それを、おそらくは理屈ではなく実感として知っているから、いわゆる「大物芸能人」ほど「もっと売れたい」という姿勢を崩さず、知ってもらう機会を逃さず、とても貪欲な一面があると思う。
だから、広告は嫌というほど、繰り返し「同じこと」を伝え続けている。
いくら好きな曲でも聞きすぎると飽きて嫌いになってしまうように,最適水準を超えると逆に好意度は低下していきます。「過ぎたるはなお及ばざるがごとし」ということでしょう。(「日本心理学会」公式ホームページより)
「知名度」が上がった後に、さらに「同じこと」を繰り返すと飽きられる。それは、ちょっと聞くと、とても常識的なことなのだと思うけれど、今は、そうした存在は「一発屋」と表現されることも少なくない。
そして、以前と比べて「一発屋」と言われる人が増えた気がするのは、ラジオ・テレビが中心の時代には、触れられる回数が限られていたのが、現在は動画、中でもTikTokによって圧倒的に「再生回数」が増えたことによって、あっという間に「最適水準」を超えてしまうせいなのかもしれない。
だから、「知名度」を得た後には、今度は、以前よりも「飽きられない」ための戦いがあって、さらに安らげない状況になっているのだけど、これは、誰にとっていい環境になっているのだろうか、という疑問は出てくる。
どちらにしても、「知名度」がある人が、いろいろなことをやり続ける、というのが、現在の「知名度」の保ち方になっているのかもしれない。
有名と無名
「有名人」の逆が「無名人」というのを改めて考えると、それを文字通りに解釈すると「名前が有る人」と「名前が無い人」になる。
それで反射的に思うのが、平安時代の歌人「藤原道綱母」や、「菅原孝標女」で、この人たちは「女性」というだけで名前で呼ばれていない。優れた歌人と評価されても、誰かの母であり、もしくは娘、というような表現をされている。
この人たちは、歴史的に評価されるような作品を残しながら、名前が残っていないから「無名人」に近い。その息子や、父親の名前は残っていて、もちろん特定されているから、厳密に言えば「無名人」であるわけもないのだけど、自分の名前が残っていない。
改めて考えると「有名」と「無名」はあっても、その中間の言葉がない。知名度が多いや少ないという程度の違いではなく、有るか無いかの2分法になっているから、それならば、名前が無いよりも、当たり前だけど、名前が有ると表現される「有名」に対しての憧れのようなものが、芽生えやすくなっているのかもしれない。
無名から有名へ
例えば生まれた時は、名前をつけられるから、すでに「有名人」になっている。だけど、それは、その周囲の養育者などにとっての「有名人」に過ぎず、多くの場合は「〇〇の息子もしくは娘」という見られ方になる。
それから、時間が経って成長して、その人ならではの存在だと感じさせるようになって、養育者以外にも名前が有る人として、その名前が認識されるようになる。
また学校や会社など、家の外にある組織に新たに属するようになると、自己紹介などで自らの名前を名乗っていたとしても、最初は覚えてもらえない。時間が経って、何かしらの特徴が浸透したり、成果をあげると、やっと名前を覚えてもらって「有名人」となる。
元々の「有名人」は、そのくらいの範囲内の言葉だった可能性もある。そして、それで十分に幸福だったのかもしれない。
「名前が知られること」と、「顔が知られること」
実は「有名人」と「顔が知られること」が、映像メディアが出てきて以来、あまりにも一致し過ぎてきて、そのことによって「有名人」の意味合いが少し変わってきたようにも思う。
ある有名なベテランのプロゴルファーが、最初は、顔を知られていることはやっぱり嬉しかったけれど、ある時期から苦痛になった、という話を聞いたことがある。それは、単純接触回数にも最適水準があるように「知名度」にも本人にとっては、最適水準がある、ということかもしれない。
「顔が知られること」が、ある水準を超えると苦痛になるのは、おそらくは自由を失うことにつながるのが実感として分かるから、ではないだろうか。
ただ、元々の「有名人」という意味合いに少しこだわったとして、「顔を知られる」のではなく「名前を知られる」という意味での「有名人」に限定するとすれば、その「知名度」の最適水準は、さらに上がるような気がする。
例えば、今は「顔出しNG」の活動を選ぶ人たちも少なからずいて、以前だったら、もっと少なかった「顔出しNG」での音楽活動をしながら「有名人」になる存在も多くなってきて、それは「顔を知られている」ことのデメリットが今は大きくなってしまっている事を、特にSNSが身近である若い世代ほど分かっているから、そういう選択をしているようにも思う。
「有名人」という当事者になったことがないから、あまりにも単純化しすぎるのかもしれないが、やはり「名前を知られても、顔を知られていない」のであれば、どれだけ「知名度」が上がったとしても、さらには、その名前が「ペンネーム」などであれば、通常の生活の自由度にはそれほど影響がないはずだと思う。
そうであれば、多くの人が「顔出しNG」を選びそうだけれど、やはり、それで「知名度」を得るのは、かなり難しく、それは顔に接することが少なくなれば、好意を得る確率は低くなるという理由かもしれない。だから今も、多くの「有名人」は「顔を知られること」とともに、その「知名度」を上げていく場合が多い。
その中で、「知名度」と「顔を知られること」と「自由度」のバランスでの取り方が、絶妙だと個人的に思うのは、デーモン小暮閣下の「世を偲ぶ仮の姿」。タモリやみうらじゅんや鈴木雅之らの「サングラス使用」といった戦略である。
さらには、特にミステリー作家では「覆面作家」であることが、「知名度」を上げるためにハンディにならず、逆に有利に働くようにさえ見えるのは、「分からないこと」がプラスになりやすいミステリー界の特殊事情だと思う(ミステリーに詳しい方から見たら、見当違いかもしれず、その時はすみません)。
ただ、こうしたパターンは「知名度」を考えるときに、おそらくは外せない人たちなのだと思う。
インフルエンサー
有名であることで有名。
それが、おそらくは「純粋有名人」であって、「知名度」で成り立っているということでは、そこに一番近いニュアンスの存在は、SNSでバズることによって「有名」になった「インフルエンサー」のように思う。
SNSが普及したことで、「有名人」になるチャンスは、万人に開かれたように感じさせている。ただ、そこで実際にバズって「有名人」になり「インフルエンサー」にまでなっていくには、才能や工夫や魅力や、何より「運」が必要なはずだし、やはり、かなり低い確率だと思う。
それでも現代は、何かのジャンルで卓越することで「インフルエンサー」になった場合よりも、共感を武器としてSNS内で「知名度」を上げた「インフルエンサー」の方が、支持されやすい「有名人」のような印象さえある。
だから、「有名人」になれる可能性は、少なくともSNS利用者の主観的には、以前に比べて、はるかに高くなっているように感じられる。(noteの片隅で記事を細々と書いているだけの自分自身も、そうした思いと全く無縁ではないし)。
再び「有名」と「無名」
「有名」か「無名」か。改めて、そう比べられれば、名前が有る方がいい。名前が無いと、まるで存在自体が無いように思われる。
考えたら、名前を知られている程度(大や小)を表すのであれば、こんなに「有」と「無」の二分法のような表現でない方が正確だとは思うのだけど、何かの言い伝えのようなもので、例えばある種の妖怪は、正確な名前を分かられてしまったら、その力を失うというような話も聞いたことがあるから、名前が有るか無いかの違いが圧倒的で、だから、その中間の「少し名前を知られている」といった表現がないのかもしれない。
だけど、いまだに「有名人」という言葉があって、その反対語としての「無名人」という意味合いは決して否定的なことばかりはないにしても、無名であることへの怖さが、「有名人」への可能性が以前よりも高くなっている現在の方が、もしかしたら強くなっているように思う。
「マイクロインフルエンサー」と「ナノインフルエンサー」
圧倒的に卓越した人が「有名人」になれば、納得もいきやすいし、自分と違うと思いやすい。だけど、SNSでの「有名人」は、何かのきっかけでバズって、インフルエンサーになったように見える人もいる。
だから、この届きそうに見える「有名人」という存在があると、嫉妬も含めて、飢えまで強烈ではないけれど、渇きのような微妙な焦燥感を常に感じやすくなっている可能性もある。
(「VISUMO」の記事↓によると「マイクロインフルエンサー」や「ナノインフルエンサー」という言葉もあるくらいなので)
以前は、大きく「知名度」を上げたいと思って、何かに卓越しようとして、だけど、ある時期になって諦めて、ということが多かった印象があるが、今は、何かで注目を浴びて「知名度」が上がるチャンスが昔よりも広くあるのは事実だと思う。
その上、現時点では、「知名度」の度合いに対しての収入は、以前よりも多く手に入るように見えるので、より渇望度合いが強くなっている可能性すらある。
それに加えて、その「知名度」の永続性は、かなり減っていると思う。
いろいろな人が引用しているので、またかと思われるかもしれないけれど、アーティストのアンディ・ウォーホルが言っていたような時代は、もうすぐかもしれない。
「将来、誰でも15分は世界的な有名人になれるだろう」という言葉をウォーホルは残している。
これから先は「知名度」が上がり、収入も上がったとしても、その時間は短く、その後に、再びさらに長く続く「知名度」が低い時間をどう過ごすか。
そのほうが、より重要なテーマになってくるのかもしれない。
匿名での誹謗中傷
インターネット上での匿名による誹謗中傷は、ずっと問題視されてきて、今は、その加害の立場についての記事↑まで一般的になってきたから、それは残念なことに日常化してしまったということだろう。
そんなふうに、他人事のように語れる資格も能力も私にはないけれど、個人的には、SNSもnote以外に利用したことがなく、特に今のところTwitterは、自分の攻撃性を引き出されてしまうようで怖くて使えないと思うこと自体が、自分にも誹謗中傷や罵倒などの可能性があるということだと思う。
ただ、つい誹謗中傷をしてしまうほど、普段の生活でのストレスや不安が大きい場合だけなく(これは、この記事↑のように、また違う対応の必要が検討されるべきだと思うが)、事実に基づかないと分かっていても誹謗中傷やデマによって「バズる」ことができれば、収入につながることもあるのだから、そんな戦略的なフェイクニュースを発信する人も少なくないと考えられる。
「フェイクニュースを見聞きした人の内、4人に3人以上は騙される」というのは、残念ながら事実だ。
これが事実であるとすれば、質は問わないとしても、とにかく発信する内容の「知名度」を上げることによって収入に結びつけることができるのが、今の時代の特徴かもしれないし、収入をあげるために有効な戦略であれば、フェイクニュースや誹謗中傷は、このままだと減らないはずだ。
だから、この場合も「知名度にお金が払われる」という原則は適用できそうだけれども、倫理的に言えば悪用なのだと思う。このフェイクニュースでも誹謗中傷でも、「知名度と収入」の両方を得られるようになったこと自体が、これから修正していくべき重要な課題の一つだと思う。
誹謗中傷やフェイクニュースと「特定」
SNSの投稿内容が批判や中傷で汚れている人というのは、
だいたい攻撃力が高いのですが防御力は著しく低い傾向にあります。
このように分析もされるほど、誹謗中傷をする人は珍しくなくなってしまったとも言えるのだけど、SNS上では、とても強い言葉を繰り出す本人が特定され、インタビューなどをされている記事も、これまで少なくなく目にしてきた。
どの場合も、ほぼ例外なく、その本人は、とてもおとなしく、それもそれほど悪いことと思っていなかった、といった言葉を出していて、それは、誹謗中傷によるダメージの重さとのバランスがとても悪い、という印象がある。
そして、当然だけど、その人たちは顔出しもせず、本名も出すことはほとんどない。
同様に、フェイクニュースやデマなどを繰り返して、「知名度」をあげていたような「匿名」のアカウントの本人も、自分の本名が特定されることには、とても神経質であるといった反応をした、と言われる。
この場合、自分自身でもある「匿名アカウント」が「知名度」をあげて、そのことで収入につながる可能性だけでなく、「有名人」になる気持ちよさはあったのだろうか。
ただ、こうした場合は、その正確な名前を特定されると、その能力を失うと言われているような「妖怪」に近い存在になっていたのかもしれない。
「知名度」の現在
今も「知名度」が「収入」につながるのは、変わっていない。
ただ、その「知名度」を上げるための方法は選択肢が増え、その機会は誰にでもある。だから、誹謗中傷など、手段を選ばない人も出てくる可能性も上がるという、社会的なリスクも高くなっているのかもしれない。
さらに「知名度」が上がって「収入」を得たとしても、その永続性は、とても難しくなっているから、「知名度が上がって、急速に下がった後の在り方」といった、これまでは一般的でなかった課題まで検討される必要性も出てきているのだと思う。
「知名度」と「収入」の関係は変わらないのかもしれないが、「知名度」を上げる方法の増大によって出てきている問題や課題に、まだ社会がとまどっている段階なのかもしれない。
(他にも、いろいろと書いています↓。よろしかったら、読んでいただけたら、うれしいです)。
記事を読んでいただき、ありがとうございました。もし、面白かったり、役に立ったのであれば、サポートをお願いできたら、有り難く思います。より良い文章を書こうとする試みを、続けるための力になります。