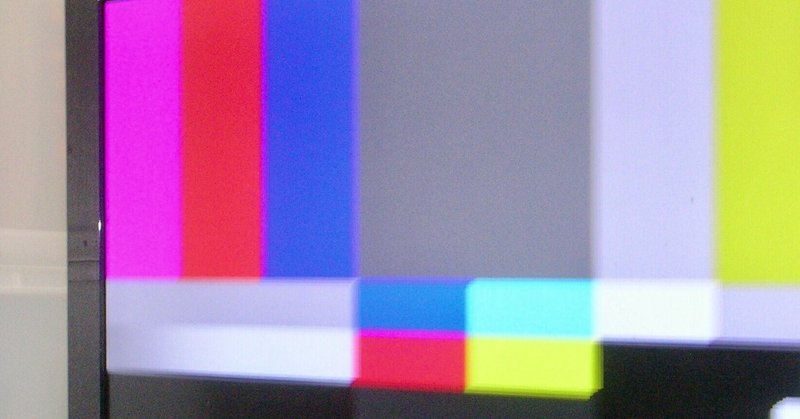
テレビについて⑥よるドラ『ここは今から倫理です』を見て、考えたこと。
個人的なことだけど、土曜日の夜中のNHKのドラマ(「よるドラ」)を、最近、よく見るようになった。そして、今のシリーズは、「倫理」がテーマになっている。
最近、コロナ禍ですっかりご無沙汰してしまっていて、さらに緊急事態宣言によって、今は運営が、どうなっているのか分からなくなってしまっているのだけど、自分にとって最初に参加して、とても充実した時間を過ごさせてもらった、いわゆる「哲学カフェ」も、テーマが「高校の倫理をおさらいする」だった。
その時に、その「哲学カフェ」の内容ではなく、参考資料としての「高校の倫理」にとまどった。
私が知っていた高校の授業で「倫理」という名前がつく授業は「倫理・社会」で、その授業内容は、寝ていたことが多かったので、語る資格はないとは思うけれど、主に「社会」のことが教科書に書いてあったはずだった。さらには、大学受験の科目として「倫理・社会」は、覚えることが少なくてありがたく、その科目を選択すると、それなりの点数も取れたのは覚えている。(何か、お恥ずかしいエピソードですみませんが)。
その「哲学カフェ」で知った「高校の倫理」は、「倫理」という名前ではあったが、中身は完全に「哲学」だった。
ここは今から倫理です
今回の「夜ドラ」は、高校が舞台で、普段は言葉少なで、職員室では完全に浮いている「倫理」の教師が主人公なのだけど、必修でもないから、授業に出ている生徒も少ない(現在のコロナ感染予防の観点から言えば、撮影に適している設定とも言えます)。
ただ、そこにいる生徒は、それぞれ切実で、現代的でもあり、普遍的な悩みや問題を抱えていて、それに対して「倫理」によって、その倫理教師が対応していく、という内容になっている。
原作は漫画らしいのだけど、学園ものは、現代では成立させるのは、とても難しい。
現代の学園ものドラマは、そんなに多く見ていないし、詳しいわけでもないのだけど、昔の「熱血教師」は、存在そのものが難しいのはわかる。最近だと、「3年A組」のように、極端な設定がないと、誠実さを表現するのも困難になっているように思う。
それに、当然だけれど、気持ちだけで、いろいろなことを突破できるようなシンプルな時代ではなくなっていることも大きい。というよりも、本来は、昔であっても「熱血」だけで解決したり、状況が良くなっていたわけではなかったのだろう、と今になって思う。
この「夜ドラ」の倫理教師は「倫理」といっても、語っているのは、やはり「哲学」で、「哲学」は必要とされる場合は、心身ともに健康で元気、というよりは、落ち込んだりやや病みぎみの時に必要だと思われる。だから、何年か前の私にも「哲学カフェ」が必要で有り難かったのだと思う。
同様に、このドラマの、その授業にいる生徒は、受験というものを考えたら、必修でなさそうな「倫理」をとる必要はないのだろうけど、無意識にでも、自分に必要なことが、ここにある、ということで授業に出ているように見える。
そして、毎回、生徒の一人に問題が起こり、そこに倫理の教師が、「哲学」を、その度に真剣に参照しながら、その生徒に対して、「正解」を使って「指導」するのではなく、教師自身も、今も考えて続けようとしながら、少しでもベターを目指したい、といった姿勢とともに、「一緒に考えていく」ように見える。
西洋哲学の最初が、ソクラテスと言われていて、40歳を過ぎてから、自分は無知である、ということを、それこそ神の啓示のように分からされてから、哲学が始まったらしいのだけど、(これも「哲学カフェ」で学びました)基本的には、哲学者は、1対1で伝えていくらしい。
このドラマの設定は、そんなことを再現しているようだけど、何しろ、倫理の教師自身が「上から」でないことが、もしかしたら現代なのかもしれないが、実は「指導」が重視され過ぎている、今までの「教育」自体に、問題があるのかもしれない、といったことまで、考えが及んだりしているから、いいドラマなのだと思う。
「倫理」という授業の意味
最初に戻って、私が、というよりは、ある年代より上の世代にとって、今の「高校の倫理の授業」は、その内容に戸惑いがあると思う。
それは、こうしたQ &Aで親切にも教えてくれているのだけど、「倫理」という授業が、今の形になったのが、1990年代初頭のようであり、そのもとの形は、さらに前なのだけど、いわゆる「ゆとり教育」の一環として出てきたもののようだった。
そして、そのいわゆる「ゆとり教育」というのは、冷静な検討もされるわけでもなく、かなり感情的に否定されるようになり、再び、教育制度は、どこに行くのかよく分からないけれど、小学校では「道徳」が教科化された、ということは、「考え方そのものへの指導」が行われているようになっていくのかもしれない。と小学校や中学校と縁が薄くなってきてしまった人間には、想像するしかない。
だけど、それは「ゆとり教育」とは、逆の方向ではないか、という予感もする。例えば、あまりにも「犠牲の精神」を称揚するような内容すぎて、「都市伝説」ではないか、とも感じたのだけど、どうやら「星野君の二塁打」も道徳の教科書に実在するそうだから、やはり逆方向であるのは間違いないようだ。(もし、やっぱり違っていたら、すみません)。
これは、それこそ、「わきまえる」ことを強要するような話に思え、ただ、文科省がこうした教科書を認可するのも、分かるような気もするのだけど、それと「高校の倫理」は、両立しないような気もするので、不思議な気持ちになる。
ドラマでやっているように、「倫理」の授業は今でもあるのだろうし、そして、現在も「哲学」を伝えているはずで、少なくとも「哲学」は、「わきまえる」とは逆の「疑え」というメッセージを強く発している部分もあると思う。
だから、この「ゆとり教育」が否定された流れの中でも、この「倫理」の授業が生き残っているのは、不思議だった。
未来への可能性
この「高校の倫理」を残した人間が誰かは知らないし、それを明確にしたいわけでもなく、想像したのは、その意図だった。
小学校や中学校に「道徳」がある。それは「わきまえる」ことを促す「指導」かもしれない。それだけだと、国家や組織は優先されるかもしれないが、個人の幸福につながる可能性は高いとは言えない。
それに対して、「哲学」は、自分で考え、時には疑うことが推奨されるから、「道徳」とは対立するかもしれないが、ただわきまえるだけの人間が、21世紀のこれからを、よりよく生きていけるかどうかは保証されない。
とするならば、小学校や中学校へ「道徳」を教科として定着したい人たちと、高校の「倫理」を残した人たちは、別なのだろう、と思う。
小学生や中学生の必修としての「道徳」に比べれば、少数になるけれど、本当に、社会を豊かにしていくのは、自分で考え、時には疑うことができる人間だから、そうした大人を育てるための「可能性」として、かろうじて高校の授業に「倫理」を残したのかもしれない。
本当は「哲学」なのだけど、「哲学」という名前にしてしまうと見つけられやすく、場合によっては「道徳派」によって、潰されてしまう可能性も高くなる。だから、「倫理」という名前の授業で、少しでも、よりよく生きるための「哲学」を学ぶ時間として、なんとか残したのはないか、と想像する。
だけど、あんまりこうしたことを考えすぎると、「陰謀論」に傾きすぎるので、ただの偶然と捉えた方がいいかもしれない。
それでも、この「倫理」の授業があるおかげで、私も「哲学」のことを考えられるようになったし、こうしてドラマとしても、楽しい時間を過ごせているので、恩恵を被っているのは間違いない。だから、少しありがたい気持ちにもなる。
(他にもいろいろと書いています↓。よろしかったら、読んでいただけたら、ありがたいです)。
記事を読んでいただき、ありがとうございました。もし、面白かったり、役に立ったのであれば、サポートをお願いできたら、有り難く思います。より良い文章を書こうとする試みを、続けるための力になります。
