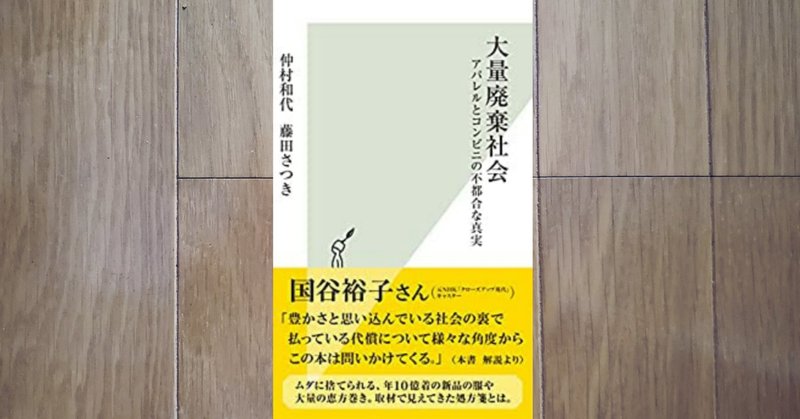
書籍解説No.15「大量廃棄社会 アパレルとコンビニの不都合な真実」
こちらのnoteでは、毎週土曜日に「書籍解説」を更新しています。
※感想文ではありません。
本の要点だと思われる部分を軸に、私がこれまで読んだ文献や論文から得られた知識や、大学時代に専攻していた社会学、趣味でかじっている心理学の知識なども織り交ぜながら要約しています。
よりよいコンテンツになるよう試行錯誤している段階ですが、有益な情報源となるようまとめていきますので、ご覧いただければ幸いです。
それでは、前回の投稿はこちらからお願いします。
第15弾の今回は「大量廃棄社会 アパレルとコンビニの不都合な真実 (仲村和代 藤田さつき)」です。

著者は「食品ロス」と「服の大量廃棄」の現場取材を通じて、現代の大量消費社会に警鐘を鳴らしています。
いくつもの課題が複雑に絡み合いながら巨大な環境問題を生み出し、解決には企業側、そして消費者側の変革が求められているといいます。
今回の記事では、本書のなかで挙げられている服の大量廃棄に焦点を当て、前回と同様に社会学の要素を踏まえながら綴っていきます。
【社会学キーワード】
高度消費社会
記号消費
シェアリング・エコノミー
社会的ジレンマ
【人々の消費行動の変化】
戦後、日本が劇的な経済復興を遂げていく過程で、三種の神器(電気冷蔵庫、電気洗濯機、白黒テレビ)、そして3C(カラーテレビ、クーラー、車)といった生活用品が一般家庭に行き届くようになっていきます。
こうした「必要消費」の段階を脱したことで社会が豊かになっていくと、次の段階では他者との差異化を目的とした「記号消費」が実践されていきます。ここでの「記号」とはブランドやデザインのことをさし、高額商品や有名ブランド品の購入によって身分差や経済格差が示されるような消費社会へと移行していきました。
更にはマス・メディアの発展に伴い、企業の広告も盛んに打ち出され、高度消費社会へと突き進んでいきます。
消費社会 ― 個人の欲望ではなく、記号の秩序こそがその駆動要因であり、消費社会についての批判や物語をも食い尽くして無効化し、記号自らが唯一の神話となっていくような社会システムなのである。
社会学 新版 (長谷川、浜、藤村、町村)
そして、近年目覚ましい躍進を遂げてきたのがファストファッションです。常に最新のトレンドを抑えた商品が出回り、流行のデザインを安価で手に入れられることが消費者側の消費意欲を刺激します。
流行の移り変わりは一層速度を上げ、「新しい」商品が気付けば「古い」商品へと格下げされ、処分されていきます。
【ラナ・プラザの悲劇と技能実習制度に見る「強者」と「弱者」の関係】
バブル崩壊を機に、メーカー側は生産コストを徹底して削減するため、低賃金労働力を求めて海外へと進出していきました。先進国の市場へ安価な服を供給し続けるため、中国から始まって、ベトナム、カンボジア、そしてバングラデシュと、人件費のより安い国に生産拠点が造られていきました。
また、そのなかでファストファッションも台頭し、グローバル規模で進む衣料品の低価格化と厳しい競争のなかで生き残りをかけた商戦が繰り広げられていきます。
洋服が大量廃棄される背景には、先進国で低価格の服が大量に消費される現状と、それを支えるために生産現場で行われてきた過酷な労働の実態があります。
生産拠点を途上国に置くことで、現地での仕事の機会を供給しているという見方もできるかもしれませんが、実状はそのような単純な話ではありません。それを象徴する出来事が、2013年にバングラデシュの首都ダッカ近郊で起きた「ラナ・プラザ倒壊事故」です。
バングラデシュは1980年代頃から縫製業で発展し始め、世界的なアパレルメーカーの生産を請け負っていることから「世界の縫製工場」ともいわれています。
しかし、その労働環境は劣悪なもので、ラナ・プラザの場合はもともと5階建てだったビルが違法に建て増しされ続けたことで、8階建てになっていました。ビルには亀裂が走り、危険であることを地元警察などによって指摘を受けていたにもかかわらず、工場は操業を続けました。
2013年4月、ラナ・プラザ崩壊。
これは、死者1,134人、負傷者2,500人以上を出す最悪の惨事となりました。
この事故は、建物検査を拒んで操業を続けさせたビルのオーナーや工場のマネージャーだけの責任とは、必ずしも断言できない複雑な事情を浮き彫りにしました。
発注する側からすれば、下請けの工場はいくらでも替えの利く存在です。もし、メーカーが要望する発注期間や金額に工場側が応じられなければ、他の工場に仕事を回すことになります。それゆえ、劣悪な環境・条件で工場を操業し、安全管理を疎かにした結果として起きた事故といえます。
利便性と安さを追求する私たちの生活は、商品やサービスを介して途上国の工場で働く労働者との生活にも深く関わっているのです。
また、こうした不均衡は海外だけではなく、国内にも存在しています。
それが、技能実習制度を利用して来日した外国人労働者の待遇です。
技能実習制度に関連する記事は以前まとめましたので、詳細はそちらを参照ください。
バブル崩壊以降、国内の多くの縫製業者は倒産を余儀なくされ、生産拠点は海外へと移転しました。途上国に工場を置き、現地の労働者を雇用することで人件費を抑えようという意図によるものです。
最初の主な拠点は中国でしたが、経済発展に伴って物価が上昇したことから、現在はベトナムやカンボジア、バングラデシュといった人件費のより安い国へと移っています。
そんななか、国内には作業行程が多くロットの小さい商品の製造が残りましたが、ファストファッションの隆盛によって服の単価が安くなり、それによってメーカーが要求する工賃も引き下げていきました。そして、例によって「その工賃では無理」というと仕事を切られてしまうことから、工場側ははメーカーの言い値で受注せざるを得ないのです。
仕事を得、工場が生き残るためには、メーカーが求める低い工賃や短い納期を受け入れるほかありません。とはいえ、その工賃で製造するには日本人の労働者を雇うだけの余裕はありません。
そこで、安い賃金で雇える技能実習生が利用されており、そこでは最低賃金割れが常態化しているといいます。
縫製の過程は、こうした強者(メーカー)と弱者(下請け業者)の関係で成り立っており、更に下請け業者が互いに仕事を奪い合うなかで次々に倒産が相次いでいます。そして、そのヒエラルキーの最下層に位置しているのが、途上国の労働者なのです。
【リサイクルすればいい?】
「安いから」と買ったものの、一度も着ることなくクローゼットや引き出しに眠っている服はありませんか。
「どうせ着なくなったらリサイクルをするのだから、たくさん服を買っても構わないだろう」
果たしてそうでしょうか。
リサイクルに出したところで服が捨てられることに対する解決、服が安く大量に作られている裏で劣悪な労働環境で働く人たちが大勢いることに対する解決には繋がりません。
ゆえに、リサイクルが課題の根本的な解決に繋がるとは言い難いでしょう。
また、本書のなかではリサイクル業者の現場の声も綴られています。そこでは、寄せられた衣類でパンク寸前の現場の声が綴られています。
また、発展途上国への寄付という選択もありますが、それ自体にも多くの議論があります。
「日本の古着はきれいなので、途上国でも歓迎されている」という説もあれば、「現地の産業を圧迫している」「先進国で追うべき負担を途上国にたらい回しにしている」などといった否定的な指摘をする人もいます。
アパレル企業はもちろんですが、消費者自身もこの問題について真剣に考えなければならない時期に来ていると思います。
【まとめ】
上述してきたように、先進国の多くの人たちが安価で高性能の衣類を消費できている一方、劣悪な環境下で過酷な労働を余儀なくされている人たちがいます。
本記事で綴ってきたような過剰生産・過剰消費のサイクルから脱却するための手段として、近年はシェアリング・エコノミー(共有経済)が急速に発達してきました。
カー・シェアリングやシェア・ハウス、ファッション・シェアリングなどを筆頭に、あらゆるモノやサービスを共有することで、空間や時間の節約及び環境負荷の少ない経済システムの実践が可能となりました。
消費者側にできることは限られていますが、まずは消費に対するマインドを変革することです。
「断捨離」「ミニマリスト」と銘打って部屋にあるものを闇雲に廃棄するのではなく、まずは目の前の魅力的に映る商品を買う前に一度踏み留まってみる。そして、買ったものの結局使わずに捨ててしまうようなことをなくすために、一歩引いて考え直すマインドセットが必要だと思います。
これらは、消費行動に限らず環境問題全般において共通していることだと思います。
個々人が自己利益を追求していけば、その先に社会的に不利益な結果が待ち受けり、こうしたメカニズムを「社会的ジレンマ」といいます。
環境問題においては、自身の日常的な行動が累積・蓄積されることで環境に確実に影響を及ぼしている一方で、目に見えるような劇的な変化がないことから確認しにくいものです。
しかし、環境破壊は確実に人間によって生み出されており、それぞれが加害者であり、被害者でもあります。
今回は服の大量廃棄の現場に焦点を当ててまとめました。
本書の後半部分では食品ロスの現場のルポルタージュが綴られています。
いずれも消費行動に対する意識を考え直させるような内容なので、興味がある方は手に取ってみてることをお勧めします。
よろしければサポートお願い致します。今後記事を書くにあたっての活動費(書籍)とさせていただきます。
