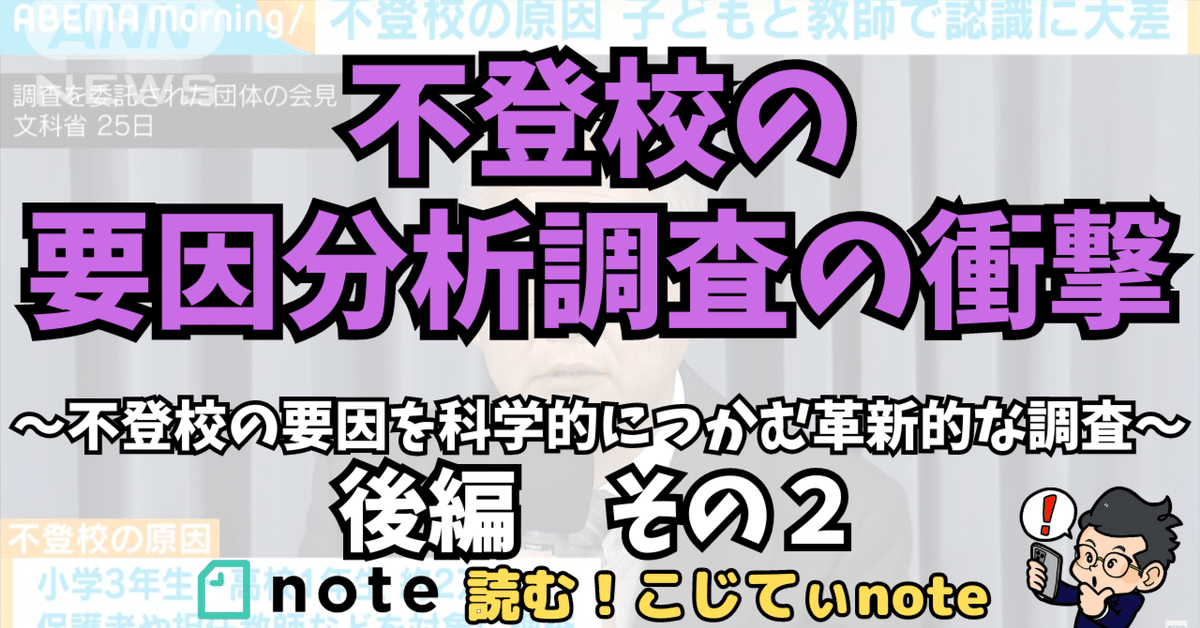
不登校の要因分析調査の衝撃〜不登校要因を科学的につかむ革新的な調査 後編 その2〜
今回の無料記事特集は多くの方から感想をいただいております。
この調査を担当した子どもの発達科学研究所は不登校支援の方向性への提言として以下の5つをまとているのを小嶋が解説してきています。
1 いじめ被害及び友達とのトラブルの予防
2 教師の行動、学校風土の改善
3 授業改善、学習支援の充実
4 児童生徒の体調、メンタルヘルス、生活リズムの注目
5 背景要因へのアプローチ
今回はまず、「学校風土」について書いていきます
2 教師の行動、学校風土の改善 その2 〜学校の風土を中心に〜
学校の風土というのはまさに「学校のきまり」などを中心に展開されている指導のことです。
調査でも「学校のきまり」が不登校と関連していると子供も教師も答えています。
どのようなことが典型的に不登校になっていく要因となるのでしょうか?
一つは、
「制服の着用」
です。
私の次男も発達障害なのですが制服を極端にきたがりません。
襟首の窮屈さ、形の窮屈さ、ネクタイの窮屈さが過敏性のある子には耐えられないのです。
そして、着る事ができたとしてもその窮屈さを紛らわすために
「緩めに着てしまう」
ので何回も指導されることがストレスになっていきます。
また、
「学校独特のルール」
も彼らを苦しめます。
「みんなが揃ってないからやり直しをする」
「静かに整然と体育館に入らないといけない」
「体育の時は体操着に着替えるのがストレス」
「先生によってルールややり方が変わる」
などなど。
これらに真剣に目を向けなくてはならない時期にさしかかっているのではないでしょうか?
3 授業改善、学習支援の充実〜授業改善の実態から〜
またこの調査では、「授業改善」についていも改善を提言しています。
不登校児童のおよそ「47%」が「授業が分からない」と答え、「成績が下がった」と37.9%が答えています。
まずは「授業改善」について、私の実感を述べていきます。
今までの職業柄、さらには昨年もたくさんの教室と授業を見てきました。
低学年の授業でも、
「何をすればいいか分からない」
「先生の話をずっと聞いている」
「教科書の音読をするだけで20分以上かける」
「分からない子供は分からないまま放置される」
「子供達同士の話し合いが延々と続き、何も解決されていない」
という授業を多く見てきました。
しかも、これは、若手だけでなく「ベテランの授業」でも多く見られたのです。
つまり、
「30〜40年以上の前の授業スタイルをずっと続けており、今の子供たちの実態に合っていない」
と言えるのではないでしょうか。
そして、さらにこの酷さは、
「中学校、高校と進むにつれて授業はひどくなっていく」
というのも私の実感です。
教師の授業改善は、ずっと現場でうたわれ続けています。
しかし、一向に改善が進まないこの闇が改善されなければ、不登校の子どもたちは救われないと考えています。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
