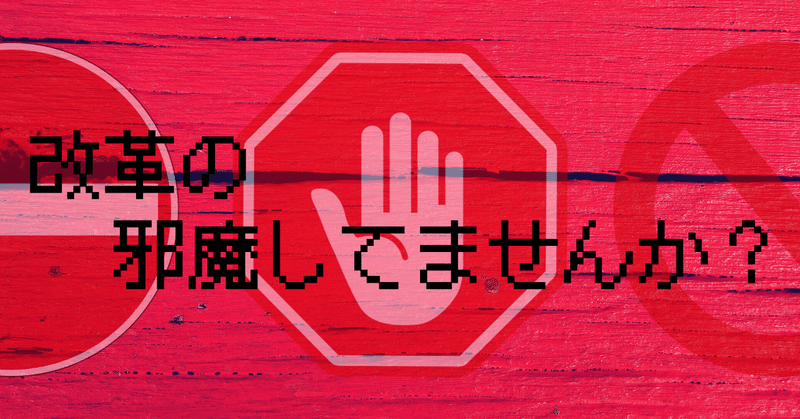
社内改革の邪魔をしてませんか?
「不安」が業務効率向上の「邪魔」をしている
今、あなたの会社では仕事のデジタル化は進んでいますか?この数年で急速にリモートワークやIT活用への関心が高まりました。しかし、多くの場合は行動制限のある中で、どのように業務を進めるかを考え、そこで「仕方なく」リモートワークやデジタルツールを活用しているように思えます。今まさに、「元に戻る」ことを前提にしている企業と「元に戻らない」を前提にしている企業との差が出始めています。そして、残念ながら「元に戻る」ことを願っている企業が多く存在しているように思えます。ではなぜ、元に戻りたいのか?よく言われるのが社内のデジタル化やDXが進まないのは経営者の理解や関心が足りないということです。ですが、最も注目すべきは、働いている側ではないでしょうか。特に、社内の業務中心メンバー達のリモートワークやデジタルツールを活用することに対する強い「不安」が社内の業務効率化や新しい価値を生み出すことへの「邪魔」をしているかもしれません。
中間管理職がDXに否定的
中小企業で多くみられるのが、中間管理職のDXに対する否定的な意見です。中にはITリテラシーが高い人や、新しいツールの活用に積極的な人もいます。ですが、多くの人は否定的ではないでしょうか。よく聞く理由としては、「必要性を感じない」や「利便性を感じない」、「今までのやり方がやりやすい」や「新しいことはわからない」などがあります。しかし、本当は常に新しいツールを活用し、部下や顧客に新たな価値を提供する責任があるはずです。私はこれまで勤めた会社で、必要のない業務を必死に守っている上司を多く見てきました。おそらく、最新のツールや新たな仕組みの中で自身の価値が低くなることを薄々感じているのではないでしょうか。このような人たちが社内の重要なポジションにいる以上、社内をアップデートすることは難しいでしょう。
自身の仕事がなくなることへの「不安」を抱いている社員が多い
中間管理職だけでなく、各部署や各チームの主要メンバーにも改革に否定的な人が多いように思えます。表向きはDXやリモートワークに賛成な態度をとっていても、何かと理由をつけて改革案に否定的な意見を言いがちです。不安の要因として「労働時間」があります。多くの人は「仕事の成果」で給料を貰おうとするのではなく、「働いた時間」で給料を貰おうとしているのではないでしょうか。当然、DXやリモートワークなど新しい仕組みを取り入れるということは作業効率を上げ、働く時間を少なくするとういうことにもなるので、「労働時間=給料」で考えている人には不都合な取り組みになります。会社員である以上は「労働時間=給料」なのですが、「成果=給料」のマインドで仕事に挑まないと企業としても個人としても良い結果になりません。なので、経営者側としては社内を改革していく際には、社員に改革の目的と金銭面の説明が重要になってきます。説明が不十分だったり、社員が納得いくものでなければ、現状の業務方法を「正当化」する意見が飛び交うことになるでしょう。
否定的な意見は業務の「無駄」を「正当化」する
業務の中心メンバーは業務の「無駄」を知っています。知ってはいるが、積極的になれないのは、デジタル化や新しいツールの導入によって労働時間が少なくなるからです。労働時間が少なくなると残業時間が少なくなり、給料が減ります。金銭面でのメリットがないため、改革案に対して否定的になってしまいます。そして、その意見は現状のやり方が正しいと主張します。人がやらなくても良いことが沢山あるとわかっていても、自分に金銭的なメリットが無い「不安」から改革に積極的に向き合えずにいるのです。金銭的な不安とは別に、労働時間にも不安があります。この不安は、「労働時間=貢献度が高い」と考えている人が意外と多いことにあります。これは、今までの評価基準にも問題があります。これまでは長く働く人が評価されがちだった環境では仕方がないことかもしれません。ですが、本来は「成果=給料」が正しいはずです。各々で抱えている不安は多様でしょう。改革を促進する側の人はこうした不安を見つけ出し、解決していかなければなりません。そして、改革に否定的な人は何に不安を感じ、どうするべきかを考えなければなりません。新しい取り組みや仕組みを導入する際は、一人ひとりの「安心」に向き合わなければいけません。
「安心」を伝える重要性
社内の改革をしていく立場の人たちは、DXによって各自の業務にどのような「影響」があるかをしっかり伝える必要があります。その影響は「金銭面」や「評価基準」、「労働時間」や「体験価値」などが働く上でどうなるのかが重要になります。働いている人はDXなどによる改革によって勤務時間が少なくなり、給料が減ることに不安になっています。また、今まで働いた時間で価値を表していた人に対し、今後の評価基準がどのようになっていくのかを明確にすると同時に、改革によって働く人や顧客に対する体験価値がどのように向上していくのか、もしくは、どのような目標に向かって進もうとしているのかを伝える必要があるでしょう。特に、「勤務時間=価値」ではないことはしっかりと伝えるべきです。
「勤務時間」や「そこにいる」では評価されない
重要なのは、自分の「得意」や「できること」は何かをしっかり理解することです。自分が何で報酬を得ているか、何を価値として提供しているかが大事なのです。報酬が発生するのは、誰かの役に立った時です。つまり、他人様に何かをして、その行為にお金を払うだけの価値があると思ってもらって初めて成り立つのです。例えば、遠くに住んでいる誰かに贈り物を届けたいと思っている人がいたとします。しかし、届けるには多くの時間が必要な上に、高額な費用が掛かります。そこに、代わりに運べる人が現れました。移動に掛かる費用は、他の人の荷物と一緒に運ぶので、それぞれから少しづつお金をもらう仕組みになっているので安価で依頼ができます。自分で届けるより時間の面でも、費用の面でもメリットがあります。そのメリットに対してお金を払う価値があると思ってもらえるからこそ、その対価としてお金がもらえます。この場合の価値とは「代わりに届ける時間」と「安価な運賃」です。このように、日々の仕事や業務がどのような価値を生み出しているかをしっかり考えなければいけません。もしかすると、あなたが価値があると思っていることは、デジタル化や新しいツールの導入によって無駄なものになる可能性があります。そして、これからの時代は便利なツールや世の中の流れによって無駄が浮き彫りになっていくでしょう。少なくとも、これから社会に出てくる若い世代は物事の価値観が全く違うと思っておいたほうがいいでしょう。便利なツールが身近にあり、普段から使いこなしている世代と古い価値観のままの人では、成果のあげ方や仕事に対する評価の面で致命的な差が生じてしまいます。
これから入社してくる新人がどのような世代の人間かを理解する
学校と会社は違う。もちろんです。しかし、学校から会社に移るとき、新人は自分が属する場が進化したことを感じたいはずです。
なのにその反対に、「よりデジタルでない環境」が待っていたとしたら、時代の波に乗っている感度の高い新人ほど、「なんだ、こんなもんか」とがっかりするに違いありません。
これから社会に出てくる人たちは、IT製品に囲まれて育った世代です。身近にデジタルがある環境で育ったため、社会に出て働く場所に、アナログな体制の会社は好みません。そして、現在の学校教育では、GIGAスクール構想によって全国の児童・生徒1人1台にパソコンやタブレットといったICT端末が配られました。これによって、よりデジタルが身近な環境になり、授業や宿題、何らかの作業をする時はパソコンやタブレット端末を活用することが当たり前になっています。小学校ではプログラミングの授業が始まったり、Googleのclassroomなどで日々の連絡事項を確認したり、アップロードされた宿題を見て自宅で学習しています。また、児童たちが卒業生への感謝を伝える動画を作成して卒業式で流すなど、便利なツールを楽しく使う取り組みも定着しつつあります。そして、私が個人的に感じていることは、フォートナイトや荒野行動などのオンラインゲームの影響です。良い面と悪い面があるとは思っていますが、あえて良い面だと思うことを言うと、普段からオンライン上で会話をしながら友達や知らない人とゲームをしているのです。彼らはデジタル空間でほぼ毎日誰かと遊んでいるわけです。中学生や高校生も、スマホでSNS用の画像や動画の加工・編集を日常的にしています。このような人からするとパソコンすら古いと思う可能性すらあります。そして、このような世代が社会にでた時、対面であろうがオンラインであろうが関係なく、便利なツールを駆使して仕事をこなしていくのではないでしょうか。基本的には今後、数年以内に入社してくる人はあなたとは全く違う環境で育ってきた、優秀な人材になると覚悟をしたほうが良さそうです。
最後に
現在、社会で活躍されている人たちは、時代の変化と向き合わなければいけません。10年前に今の世界観を予想などできませんでした。これから先の10年はもっと変化の激しい世界になるでしょう。そして、今までの成功体験や古い価値観は通用しなくなります。もちろん、それぞれが大切にしている考え方や、やり方はあると思います。しかし、時代にあっているかどうかをしっかり見極め、これからどうするべきか考えていく時期にある思います。
今回は極端なお話になってしまいました。もちろん、様々な考え方があっていいので私の意見が全てではありません。ですが、あなたが今後のことを考えるきっかけと、考える中での1つの意見として捉えてもらえれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
