
【自己啓発本解説】『心の容量が増えるメンタルの取扱説明書』
こんにちは。
今回はエマ・ヘップバーンさんの『心の容量が増えるメンタルの取扱説明書』について解説していきます。
はじめに
あなたは毎日が忙しいと感じますか?
現代に生きるほとんどの人は、仕事とプライベートの両立という無謀な試みをしています。
他人の幸せを気遣うと同時に自分の幸せを探り、お金をやりくりし、子供の世話をし、自分の思い通りにならない体験に葛藤し、やることリストをこなしながら、ゆとり時間も取り入れようと心がける。
その結果、スケジュール管理やメール対応、SNSの更新、やることリストの処理に追われる日々を送ることになります。
大前提として、あなたの人生はあなたの心を中心に回っています。
つまり、あなたの心の状態によって人生の軌道は変わります。
そのため、心をしっかり育てる必要があります。
メンタルのケアは万人の課題であり、悪化する前に対処すべきものです。
状況と組み合わせ次第で、心を病んでしまうことは誰にでもあります。
たとえば、自分の心の中にジャム瓶があるところを想像してください。
これがあなたの心のキャパです。
その中にはストレスに対する弱さを表すイチゴと、ストレスの原因を表すラズベリーが詰まっています。
ストレスに対して弱ければ弱いほどイチゴの量が増え、ストレスの原因が多いとラズベリーの量が増えます。
その要素は人によって異なり、ストレスの原因はその時々で変わります。
仮にストレスの原因がジャム瓶の容量を超えると、心の健康に支障が出ます。
ただし、周りの人に助けてもらったり、良質な睡眠を取ったり、運動したりするなど適切な対処方を学んで実践することで、ジャム瓶の容量、つまり心のキャパは増やすことができます。
置かれた状況次第で、誰でも心を病む可能性があるのか、ストレスに対する適応力を高めておくことが大切です。
この記事では心のキャパを増やしてメンタルを強くする方法を7個解説していきます。
この記事を見てメンタルが楽になった、ストレスで対処できるようになったという人は、是非いいねやコメントください。
Youtubeでも解説していますので、ぜひこちらもご覧になってください。
具体的なアクションプラン
【1個目】 快眠のコツ3つ。

気分と体は本質的につながっています。
疲労、水分不足、体調不良、空腹などの状態にあれば、大きさは違えど不快感を覚えるものです。
そして不快感があると息抜きや気分転換を怠り、睡眠不足や運動不足、病気になることで、脳と体の働きが大きな打撃を受けます。
このように基本のケアがおろそかになると、悪循環に陥りかねないです。
そこで、体の調子を整えて気分に悪影響が出ないようにすることが重要です。
まずは睡眠です。
睡眠不足は気分を著しく下げるだけでなく、認知や健康にも影響を与える可能性があります。例えば、やるべきことをやる、集中力を維持する、情報を記憶する、といった認知機能が低下します。
最近の研究によると、脳の管理をしているグリア細胞は、睡眠中に最も活発に働いて、脳の老廃物を回収すると言われています。
そのため、質の良い睡眠を十分に取ることが大切です。
ただし、皮肉なことに眠ろうと頑張るほど眠れなくなります。
睡眠を妨げる原因と解決策を3つ解説します。
1つ目、心配事全般。
朝起きたとき対処できるように、寝る前に心配事を書き出してください。
それでも心配事が浮かんできたら、「明日対処すればいい」と心に言い聞かせてください。
また、リラックスできるオーディオブックやポッドキャストを聴いて、気を紛らわせることもおすすめです。
2つ目、脳が休息モードに入れない。
ポイントは、寝る前に頭が冴えるような活動や頭を使いすぎる活動をしないことです。
毎日同じ入眠のルーティーンを行ってください。
例えば温かいシャワーを浴びる、温かい飲み物を飲む、本を読むなどです。
入眠のルーティンには、心を落ち着かせ、眠りを連想させる効果があります。
3つ目、眠れるか心配、眠ろうとがんばりすぎる。
この場合は「たとえ数時間しか寝られなくても何とかなる」と自分自身に言い聞かせてくださ
い。
あえて眠ろうとしないことも効果があります。全く眠くならない場合は、いちど布団から出てリラックスできることをやり、眠くなったら布団に戻るようにしてください。
【2個目】 食生活を見直す。

頭と体が効果的に機能するには、水と食べ物が大切です。
食事を抜いたり水分不足だったりすると、不機嫌になるのはもちろん、様々な不快感に襲われます。
逆に、たっぷりの果物や野菜を含むバランスのとれた食事をとれば、脳に限らず心身の健康に良い影響を与えられます。
また、食事は喜びの大きな源でもあります。
食事を取ることで僕たちは一息つき、体を休め、ポジティブな感情になります。
しかし、世の中には食や体重に関するメッセージが溢れています。
そのため、ダイエットしようとして食事制限をしたり、忙しい生活の中で食事を味わうこともままならなかったりします。
飲み物も同様です。
水を飲み忘れれば脱水状態になり、疲労感が出てきます。
カフェインを取ることで疲れに追い打ちをかける人もいます。
また、アルコールを使って気分をコントロールしようとする人もいますが、アルコールは大抵脳機能に悪影響及ぼします。
特別な工夫をしなくても、普段の食事を整えることで、心に良い影響を与えることができます。
次のチェックリストを使って、食生活を見直してください。
いつも決まった時間に食事をしているか、
食事制限をしているか、
バランスの良い食事をしているか、
日ごろから水分を十分にとっているか、
カフェインを摂りすぎていないか、
お酒は適量か、
ゆっくり味わいながら食事をしているか。
これらの点に着目し、食生活を改善していってください。
【3個目】 心の健康を支える5本の柱。

ここで心の健康を支えるために大切な5つの要素について解説します。
どの要素もメンタルに良い影響与えるエビデンスのあるものです。
1つ目、つながる。
幸せで健康な生活を送るために最も重要なのは、良好な人間関係だという研究結果がありま
す。
「セルフケア」という宣伝文句が溢れる世界では見落とされがちですが、幸せを得るためには人とつながりの方が有効です。
ただし、過去の経験から人もあまり信じられない人で孤立している人にとって、人とつながることは簡単ではないです。
そういう時は、会うと気分が良くなる相手、信用している相手、共通の趣味や価値観を持って
いる相手とつながることが大切です。
たとえ億劫でも、人とのつながりを作り維持する努力はしたほうがいいです。
数は少なくていいので、気の合う相手とのつながりを大切にしてください。
2つ目、動く。
運動は体の健康にいいだけでなく脳にもいい影響を与えます。
運動すると全身に血が巡り、内臓と血管の働きが良くなります。
達成感がわき、エンドルフィンが放出され、快感が生じるとともに体のストレス反応が抑えられます。
また、脳の働きだけでなく、集中や学習といった認知過程も改善されることがわかっています。
運動は何歳になっても有益です。
ただし、運動すると考えると面倒に感じると思います。
そこで「とにかく動く」と視点を変えてください。
動き回ると感情が切り替わり、心がすっきりして達成感がわきます。
ランニングやウォーキングだけでなく、掃除やヨガ、庭いじり、台所仕事、歌を歌うなど、すべて運動になります。
日常生活で行っている動きを、楽しめる運動と捉えて継続してください。
3つ目、気づく。
脳内の思考領域はほぼ全て、過去の体験と架空の未来で占められています。
この状態は正常ですが、あまりに度が過ぎると限りある脳領域は過去の体験や未来で埋めつくされ、「今ここ」で起きていることに気づけなくなってしまいます。
今この瞬間に注意を向けると、ストレス反応が抑えられ、長期的な健康効果があります。
これがヨガ、マインドフルネス、瞑想の原理で
す。
これを用いることで、日常生活での気づきを増やせます。
周りで起きていることや、自分の行動に完全に意識を集中してみてください。
散歩に出たら植物の色に目を向けてみる、料理をしながら材料の香りに注目するなどです。
時おり体の声に耳を傾けることも大切です。
休憩が必要か、散歩をしたい気分か聞いてみてください。
4つ目、学ぶ。
学習は脳を活性化させ、脳内に新しいネットワークを作り出します。
目的意識を生み、新しい考えを作り出すきっかけにもなります。
学習は脳を鍛える運動です。
知識が深まれば深まるほど、脳は細胞レベルで発達します。
しかし、学習というと、ストレスや無力感や挫折を連想しがちです。
おそらく学校のテストや試験勉強も思い出すからです。
しかし、試験を受けたり、英単語を暗記するだけが学習ではないです。
脳にとって新たな発見となるもの全てが学習です。
本を読んで新たな知識を得る、新しい言葉を習う、知らなかった場所を見つける、珍しいものを食べてみるなどです。
あまり固く考えず、柔軟に学習してみてください。
5つ目、与える。
人間には共感能力があります。
相手の不安が伝われば、こちらまで不安になります。
共感によって不快な気分になることもある一方で、周りの人に何かを与えれば、共感によって喜びを感じることができます。
人を助けると、助ける側にも良い影響があることは研究で明らかになっています。
満足感が増し、ストレスが減り、社会的なつながりが強まります。
生理学的に見ても、血圧が下がるなどの効果があり、心身の健康も良くなります。
与えると言ってもお金をかける必要はないです。
時間と気遣いこそ、あなたが人に与えられる
貴重品です。
じっくりと人の話を聞く、手伝いを申し出る、ボランティア活動をするなど試してみてください。
与える方法はいくらでもあるので、難しく考えず、自分に何ができるのか考えてみてください。
【4個目】 自分の感情を特定する。
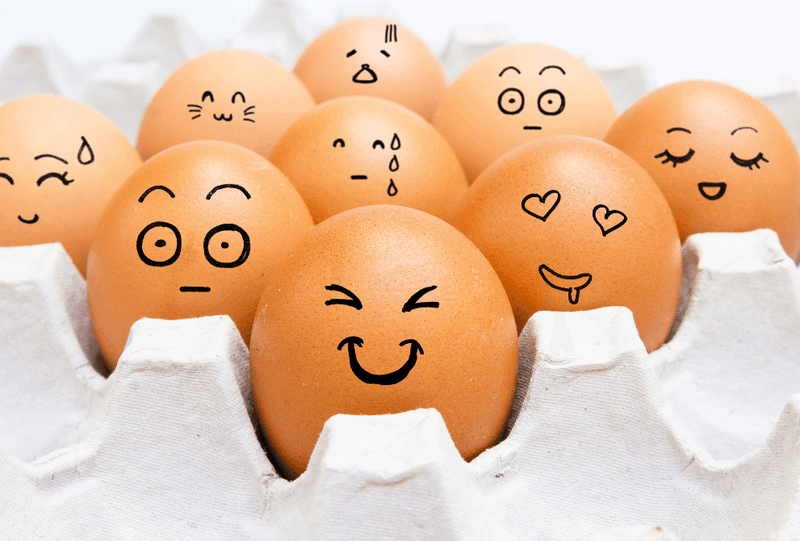
大きなライフイベントを迎えると、感情の容量は一気いっぱいになります。
一歩ひいて考える余裕がないので、自分にできることは何もないと感じたり、嫌な気分になったりします。
しかしそれに気づかず、自分を責めたりすることもあると思います。
そのような時は、自分の感情に気づき、それを正当な感情だと認め、自分に優しくしてください。
まず大切なのは自分の感情とその感情の要因に気づくことです。
おすすめは「ブレインダンプ」という方法です。
あなたの心を埋めているものを紙に全て書き出してください。
例えば、感情や思考、悩み、日々のタスクなどです。
大切なのは、感情を言葉にすることです。
脳の中身がわかれば、それにどう対処すべきか見当がつきやすくなります。
すぐに実行できそうな小さな対策から1つずつ取り組んでください。
【5個目】 SNSとうまく付き合う。

スマホやSNSを利用することで、人の心は様々な影響を受けます。
嫌な気分になったり、もともと悪かった気分がさらに悪化したりなどです。
また、いくつかの研究によると、SNSに時間をかけるほどメンタルが悪化すると言われています。
さらに、SNSは自分と他人との比較を促します。
例えばSNSを見ている若い女性は、自分の体型に不満を覚えることが多いです。
大切なのはSNSを上手に活用し、これ以上は危険だという線引きができるようになることです。
スマホやSNSの使い方が原因で嫌な気分になっている、本当にやりたいことができなくなっていると感じたら、あなた自身が支配権を取り戻す必要があります。
次の戦略を試してください。
制限時間や警告を設定できるアプリを活用し、無理のない範囲でスマホの利用を制限する。
布団に入ったらスマホを見ない。
気分を害する人のフォローを外すかミュートにする。
通知をオフにする。スマホを使いたくない時は、別の部屋に置いておくか電源を切る。
SNSには良い面もあります。
たくさんの人と交流したり、クリエイティブなものを共有したり、同じ体験を持つ仲間とつながったり、学ぶだりすることもできます。
心をケアすることとSNSを拒否することを区別して、SNSを上手に活用してください。
【6個目】 比較対象を変える。

僕たちは年がら年中タラレバ比較をしています。
「あの仕事についていればマシな人生だったのに」「あの出来事がなかったらもっと幸せだったのに」「あれとこれを達成すればきっとこんな気分を味わえるのに」などです。
現実とは別の選択肢をシミュレーションし、「こうなるはず」と思い込み、現実と比較します。
シミュレーションの結果は大抵、明るい可能性が過度に強調され、無意味な上向き比較になります。
美化された選択肢と自分との比較で生まれる感情の多くは「後悔」が関係します。
架空の完璧な選択肢と比較して、現実が勝てるわけないです。
このような時は「別の選択肢のほうがよかった保証がない」と自分に言い聞かせてください。
その選択をすれば何かが変わっていたのかさえ、わからないのが現実です。
それどころか悪い結果になっていた可能性もあります。
また、ネガティブビジュアリゼーションというテクニックが使えます。
「今もっているものをもし持っていなければ、どんな人生だっただろうか」と自問してください。
こうすることで現実より下にいる架空の自分自身に基準が落ちるため、今もっているものに感謝し、過去の選択を正当に評価できます。
心理学の研究からわかっていることなので、ぜひ試してください。
【7個目】 有意義な目標を設定する。

目標を設定すると達成したいことが明確になり、達成方法も見極められるため、成功の確率が高まります。
ただし、目標設定は簡単に聞こえるわりに、しっかりやろうとすると難しく、考えさせられることが多いです。
これを機に一度腰を据えて、次の7つのポイントを考慮し、じっくり考えてみてください。
1つ目、目標は具体的な数字で表す。
「もっと社交的になる」ではなく、「1か月につき友達1人とお茶をする」のように数字を使って具体的にしてください。
2つ目、できればいつ実行するかを決める。
例えば「水曜日は職場から徒歩で帰る」などです。
3つ目、楽しいことから始める。
積極的にやりたいことであれば、達成の可能性が上がります。
4つ目、目標を達成する自信がどれくらいあるかを 0~100%で表す。
その中でまずは50%以上の自信がある目標から始めてください。
成功すれば自信がわき、困難な目標は後からいつでも取り組めます。
5つ目、前向きな目標を設定する。
「不安に思わないようにする」ではなく、「1日に2つリラックスできることをする」と前向きな目標を立ててください。
6つ目、達成目標より学習目標を設定する。
例えば「英語のテストで 90点を取ろう」のように評価を求めるのは達成目標です。
一方、「英語を話せるようになろう」のように、自分の成長を目指す学習目標に置き換えると挫折しにくくなります。
7つ目、達成するたびに自分にご褒美をあげる。
行動を起こした結果、褒められるなどの快楽が得られると、その行動が増加します。
自分で褒めることで望ましい行動を増やしてください。
まとめ

それでは、まとめいきます。
【1個目】 快眠のコツ3つ。
1つ目、心配事があるときは、寝る前に心配事を書き出してください。
それでも心配事が浮かんできたら、「明日対処すればいい」と心に言い聞かせてください。
2つ目、脳が休息モードに入れない場合は、寝る前に頭が冴えるような活動や頭を使いすぎる活動をしないことです。
毎日同じ入眠のルーティーンを行ってください。
3つ目、眠れるか心配な場合は、「たとえ数時間しか寝られなくても何とかなる」と自分自身に言い聞かせてください。
あえて眠ろうとしないことも効果があります。
【2個目】 食生活を見直す。
頭と体が効果的に機能するには、水と食べ物が大切です。
次のチェックリストを使って、食生活を見直してください。
いつも決まった時間に食事をしていますか?
食事制限をしていますか?
バランスの良い食事をしているか?
日ごろから水分を十分にとっていますか?
カフェインを摂りすぎていないか?
お酒は適量か?
ゆっくり味わいながら食事をしていますか?
これらの点に着目し、食生活を改善していってください。
【3個目】 心の健康を支える5本の柱。
1つ目、つながる。
幸せで健康な生活を送るために最も重要なのは、良好な人間関係です。
会うと気分が良くなる相手、信用している相手、共通の趣味や価値観を持っている相手との
つながりを維持するようにしてください。
2つ目、動く。
運動は体の健康にいいだけでなく脳にもいい影響を与えます。
運動ではなく、「とにかく動く」と視点を変えてください。
掃除やヨガ、庭いじり、台所仕事なども運動になります。
3つ目、気づく。
今この瞬間に注意を向けると、ストレス反応が抑えられ、長期的な健康効果があります。
周りで起きていることや、自分の行動に意識を集中してみてください。
時おり体の声に耳を傾けることも大切です。
休憩が必要か、散歩をしたい気分か聞いてみてください。
4つ目、学ぶ。
学習は脳を鍛える運動です。
知識が深まれば深まるほど、脳は細胞レベルで
発達します。
本を読んで新たな知識を得る、新しい言葉を習う、知らなかった場所を見つける、珍しいものを食べてみるなどしてみてください。
5つ目、与える。
人間には共感能力があり、これによって不快な気分になることもある一方で、周りの人に何かを与えれば、喜びを感じることができます。
じっくりと人の話を聞く、手伝いを申し出る、ボランティア活動をするなど試してみてください。
【4個目】 自分の感情を特定する。
大きなライフイベントを迎えると、感情の容量は一気いっぱいになります。
そんなとき大切なのは、自分の感情とその感情の要因に気づくことです。
あなたの心を埋めているものを紙に全て書き出してください。
そして対策を考えてみてください。
すぐに実行できそうな小さな対策があれば1つずつ取り組みましょう。
【5個目】 SNSとうまく付き合う。
スマホやSNSの使い方が原因で嫌な気分になっていると感じたら、次の戦略を試してくださ
い。
制限時間や警告を設定できるアプリを活用し、無理のない範囲でスマホの利用を制限する。
布団に入ったらスマホを見ない。
気分を害する人のフォローを外すかミュートにする。
通知をオフにする。
スマホを使いたくない時は、別の部屋に置いておくか電源を切る。
心をケアすることとSNSを拒否することを区別して、SNSを上手に活用してください。
【6個目】 比較対象を変える。
タラレバ比較は心身によくないです。
架空の完璧な選択肢と比較して、現実が勝てるわけないです。
このような時は「別の選択肢のほうがよかった保証がない」と自分に言い聞かせてください。
また、「今もっているものをもし持っていなければ、どんな人生だっただろうか」と自問してください。
こうすることで現実より下にいる架空の自分自身に基準が落ちるため、今もっているものに感謝できます。
【7個目】 有意義な目標を設定する。
目標を設定すると達成したいことが明確になり、達成方法も見極められるため、成功の確率が高まります。
次の7つのポイントを考慮し設定してみてください。
目標は具体的な数字で表す。
できればいつ実行するかを決める。
楽しいことから始める。
目標を達成する自信がどれくらいあるかを0~100%で表す。
前向きな目標を設定する。
達成目標より学習目標を設定する。
達成するたびに自分にご褒美をあげる。
最後に、メンタルを崩すことは誰にでもあります。
心を病むことはおかしなことではなく、人間らしさでもあります。
「心の健康は体の健康や環境と切り離せないこと」「心は人生の要であり、心のケアは人生のストーリーを変える力があること」この2つを知っていることが大切です。
これだけであなたはメンタルケアの上級者です。
困難にぶつかった時、落ち込むことがあった時は、記事で解説したテクニックを1つずつ試してください。
今回の解説が勉強になった、ストレスが減った人は、是非いいねやコメントください。
Youtubeでもお金に関すること、メンタルに関することなど、日々の生活に役立つお話を『毎日』投稿しています!
お時間があればぜひご覧ください!
またこちらの本が気になった方は、ぜひご購入して読んでみてください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
