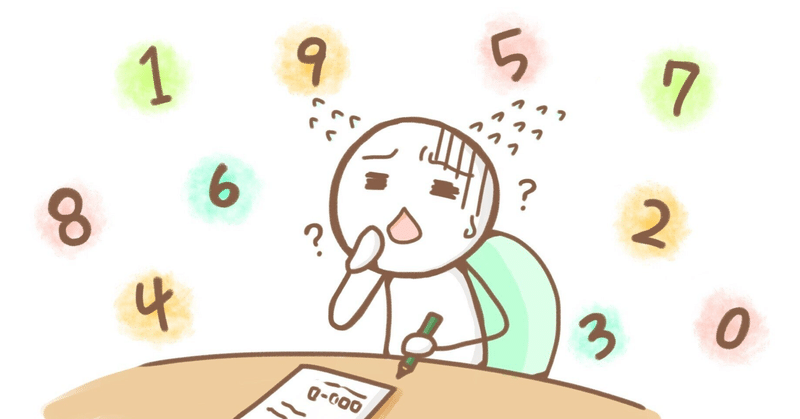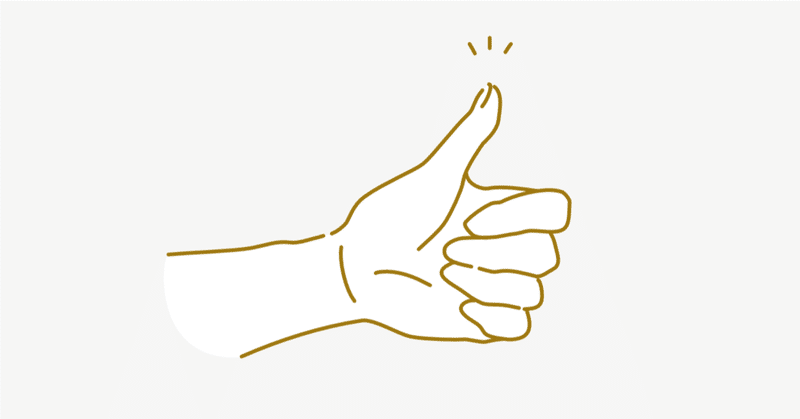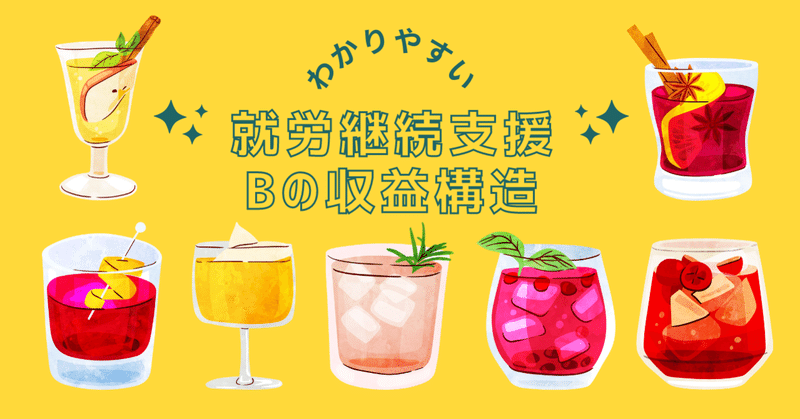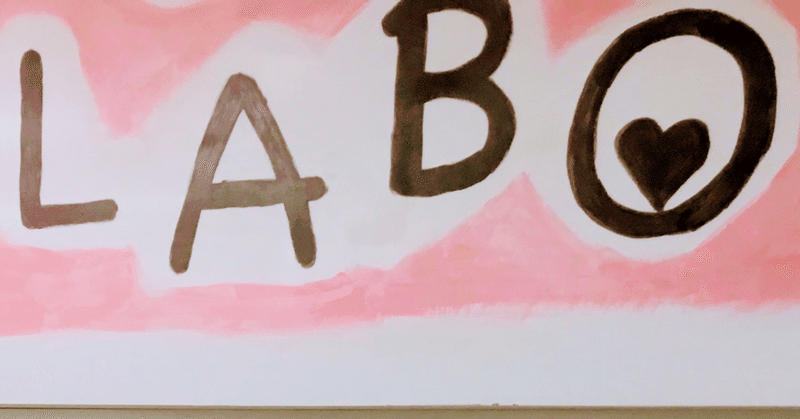
- 運営しているクリエイター
#支援員
支援者と、利用者と、工賃と、お金
就労継続支援B型で渡される工賃。
(就労継続支援B型では、雇用契約を結ばないので、工賃という名目で給料を利用者に支払います。)
今日は、その工賃やレクリエーションを通じてお金についての学びを深めるという話。
1、工賃
私の事業所では、初め、現金で工賃を支給日に渡してました。
素直に喜ぶ方もいれば、ドキドキしながら、持って帰る人もいます。
今は、振り込みにしています。
(現金支払いは、これる
支援員が言っては(思っては)いけない言葉
飲食と障害福祉を一緒に行うためには、いろいろと整備して仕組みを作っていく必要があります。
飲食店経営の本やnote、福祉サービスの情報など、それぞれでは存在するけど、一緒になってるものはほぼないので、いつも考えることになります。考えるのが好きな人は向いていると思います。
そんな中で、タイトルにもありますが、支援員が言っては(思っては)いけない言葉があるので、それは何か?という話です。
結
就労継続支援における管理者の役割
支援員をまとめる立場、また事業運営を考える立場でもある管理者の事について。
運営をしながらうまくいった事例をもとにお伝えします。
①支援員をまとめる
支援員をまとめると書きましたが、自分でコントロールしようとしたり、支配下に置くという考えでは、うまくいかないものだと思います。
支援員一人一人、支援や考え方に違いがあります。その違いになっている部分は利用者にとっては違う角度での支援となるので
就労継続支援、利用者の評価方法
私が所属している、就労継続支援では、年に2回工賃の査定を行います。
業績によっては、全員一律で工賃レベルの引き上げをすることもありますが、基本的には個々人の評価により査定を行います。
今回はその評価基準にしている事です。
1、職業準備性のチェックリストを活用
https://www.nivr.jeed.go.jp/research/kyouzai/p8ocur0000000z8w-att/
支援員と利用者の心理的安全性
最近、職場の心理的安全性について書かれた本がいくつか出ているので時々読み返すことがあります。
同僚、部下、上司などとのコミュニケーションをとる上で、意見の出やすい環境作りなどが主なテーマとなっていて、とても興味深い内容です。
今回noteを書きながら、audibleで無料で聴ける(会員登録必要)が分かったので、改めて拝聴しようかと思います。
と、前置きはここまで。
今日は、支援員と利用
リフレーミングってポジティブワードへの変換と思ってたら違った話(障害支援)
事業所で、自分意外のスタッフに対し偉そうに言って赤っ恥かいたのですが、リフレーミングはずっとポジティブワードに言い換える別の側面から物事を伝えることと思ってました。
(大きく間違ってはいないけど、広域の意味を捉えられてなかったんです。)でも、きっと同じように思ってる人多いと思うので、その話を。
リフレーミングとは、、、物事に対する考えの枠組み(フレーム)を取り替え、状況の意味を根本的に変更する
福祉事業所と委託作業の善し悪し
1個0.5円
令和の時代に、〇〇銭みたいな通貨の単位。江戸時代かよ!
って思うような仕事があるので、その話を。
昨今、AIやIOTの技術が進んできて、単純作業はどんどん機械化され人の手がかからないようになっていますが、機械導入ではなく手作業で進める仕事もまだたくさんあります。内職などもそのうちの一つです。
福祉事業所(就労継続支援B型)でもこのような仕事をしている事業所は少なくないです。
福祉事業をする前にするべき3選
今回は福祉事業を始めたときに思った、「これを先にすべきだった」と事業開始後に思ったことを3つご紹介したいと思います。
1、福祉専門の求人地域にもよると思いますが、事業をしている京都では、福祉専門の求人があります。経験者を求人かけるときには、ダイレクトで募集が確認できるので、おすすめです。
2、作業の確保実際に活動をし始めるとなかなか事業所から営業をかけて仕事を確保することが難しいです。
事前
多機能事業所、始めた時に悩んだこと(就労支援)
こんにちは、福祉事業所に初めて入った時のお話を今日はお伝えします。
多機能事業所とは、
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護などなど、複数の事業を同じ場所で提供する事業所です。
さて、私のことですが、もともと飲食業を母体とする会社が始めた福祉事業所に入りました。横浜の事業所のモデルをベースに立ち上げたので、右も左も分からない状態です。
京都で始めた事業は就労移行支援と
障害福祉事業所(就労継続支援B型)の収益構造2021年
おはようございます。
福祉と飲食店の経営をしている高橋です。
令和3年度に障害福祉サービス等報酬改定がありました。
今更ですが、現在私が従事する就労継続支援B型でどのような収益構造になっているのかをざっくり説明します。
まず、事業所が利用者に対して、工賃(1ヶ月働いた分に対する給与)の平均によって基本報酬が変わります。
工賃の全国平均はこちらです。
ちなみに、京都の私が勤める事業所での