
レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(7) 二項関係は四項関係であり四項関係は二重の四項関係つまり八項関係である
絶対無分節の自己分節の、分かれつつつながる動きの、その影を
観察・記述を可能にする。
そのための分節システムである言語。
言語の線上に自己分節する絶対無分節の影を
浮かび上がらせる。
それ自体”絶対無分節の自己分節”の影の一つである”言葉”の配列へ
それ自体は言葉をもたない無分節の分節を
置き換える。
このとき、第一の影と第二の影は互いに互いの影であり、そこでは一もニも、原因も結果も、始まりも終わりも無になる。
*
レヴィ=ストロース氏の『神話論理I 生のものと火を通したもの』を精読する試みの第七回目です。
(前回の記事(第六回)はこちら↓)
レヴィ=ストロース氏の『神話論理I 生のものと火を通したもの』を深層意味論・意味分節理論として読む。今回は神話について”記述する”とはなにをすることかという話である。
神話、音楽、詩、絵画
神話に限らず、ある何かのことを別の何かで記述する場合、そこには八項関係が動いており、複数の八項関係だけがあり、八項関係たちの「外」はない。これが前回までの趣旨である。
*
ある何かのことを、別の何かで記述する。
これは前者(ある何か)と後者(別の何か)の二項関係である。

この二項関係を「意味されるもの」と「意味するもの」がペアになった「記号」と呼ぶ場合もある。私たちの日常の言葉、例えば「りんご」と言えばあの赤くて丸いやつ、というたぐいの”意味が分かる”体験は「意味されるもの」と「意味するもの」の二項関係で説明できるような気がしてくる。
あるいは二項が別々でありながら一つに結びついている、この結びつけつつ分ける、分けつつ結びつける動きに注目して、「意味すること」とか「置き換えること」とか「結びつけること」とか「切り結ぶこと」とかいうこともできそうである。
* *
ところで、”異なるが同じ”という二項関係は、実はある四項関係のうちの半分だけが前面に現れたものであり、その四項関係は他の四項関係に媒介されることで、つかず離れずのワンセットの四項関係としてのバランスをかろうじて保っているのだ、という話が前回までの話である。

そして特に大事なことは、幾つもの四項関係のあいだには、互いに優/劣、決定する側/決定される側、結果/原因、といった二項関係を立てる必要はないということである。いくつもの四項関係は互いに互いを媒介し、支え合い、バランスを取り合っている。八項関係の外部はない(正確にはあるともないともいえない)のである。
(このあたりについて、詳しくは前回の記事の方をご参照願います)
レヴィ=ストロース氏は『神話論理』の冒頭で、神話と、音楽、詩、絵画を並べて比較していく。
「本書の企ては、個々の神話のシークエンスや神話それ自体を、音楽作品の楽器のパートのように、相互の関係において取り扱い、交響曲を研究するようにして神話を研究することだからである。」
そして特に、神話の分析は「交響曲を研究するように」行われるという。
なぜ本題の神話の分析に入る前に、音楽や詩や絵画の話をする必要があるのか?
そのワケは、神話でもなんでも言語でもってなにかのことを「分析」しようとする時に、ついつい二項関係だけにフォーカスし、二項関係をいくつもいくつも線形に配列していくパターンで「思考」してしまう私たち人類の癖のようなものに自覚的でありつづけるためであろう。
例えば、ある神話に「屋根の上で踊り続ける仮面をつけた男」というのが登場するとする。
こういうのが出てくると「屋根の上で踊り続ける仮面をつけた男」はAの象徴であり、AはBの象徴であり、Bの本当の意味はXであり、Xが出てくる理由はαであり…という具合に、しばしば「思考」は展開する。
「屋根の上で踊り続ける仮面をつけた男」=A=B=X=α
もちろん、これはこれでアリだとは思うが、レヴィ=ストロース氏はこういうのを「分節の水準が一つしかない記号体系を築こうとする、今世紀の夢想に」であるとする(p.37)。
それに対してレヴィ=ストロース氏の神話分析が特にやろうとしていることは、二項関係の裏に、底に、向こうに、見え隠れする四項関係同士の関係を関係づける絶妙な動き(つまり最小構成で八項関係を)捉えていこうということである。
そういうわけであるから、Aは実はBで、Bは実はCでという二項対立にフォーカスし、それを並べていく単線的な言い方=書き方=記述の仕方をあえて取らず、交響曲を構成する複数の楽器のパートのように、並列する複数の線が、互いに同じ主題を反復しあい、同じ姿へと近いたり、異なる姿へと離れたりしながら並列して時間を進む姿を記述する必要がある。
「音楽と神話が訴えかけているのは、聴衆の共有する心的構造にである。わたしの採用した視点は、この普遍的構造を前提にしており[…]この構造が普遍的であると言いうるためには、その客観的基盤が意識と思考の手前にあるのを認めなければならない[…]」
神話は言葉で語られる。その語りの言葉をなぞっていくと、まずはなんといっても二項関係が浮かび上がってくる。いくつもの二項関係が次々と置き換えられていく。
この「意識と思考」に捉えられる単線上に並ぶ二項関係という姿の「手前」に、そのままでは意識に登ってこない、思考されない、「普遍的構造」が動いている。この通常の言語的思考の中には浮かび上がりにくい普遍的構造をどう記述し、意識の前面に、思考の中心に引っ張り出してくるかがおもしろいところなのである。
弘法大師空海であれば、これを八項関係でもって記述しようとするところだが、レヴィ=ストロース氏はこれを同じになったり異なったりする複数の並列する線として、まずは記述してみようという。
二項関係として構成される経験
私たちは普通に生きていると、次から次へといくつもの二項関係が意識を訪れることを経験する。
「人間は色や物音がその元になるものから離れることを許さない。なるほど不明瞭な物音や漠然とした色はあるが、それは見分けたり聞き分けたりできるし、形を与えることができるとすぐに、原因に結びつけて識別したくなる。あの斑点は草陰になかば埋もれた一群れの花であるとか、あのかさこそという音はこっそりとした足音であるとか、風に揺れる小枝の音である、などなど。」
〇〇(色や物音)は××(元になるもの)である。
「色や物音」と「その元になるもの」は、不可分の”離れることを許されない”ペア、二項関係として、人間には経験される。両者の関係は「原因/結果」の関係として識別、分別、分節される。音や色や形といった「感覚的経験」は「現実を分節する第一水準」であるともいう(p.31)。
日常の経験はこの第一水準の分節、感覚的分節で動いているが、それに対して音楽や詩や絵画といった芸術は「第二の分節」を動かそうとする。
「造形芸術が先天的に事物に隷属するのは、感覚的経験(これはいうまでもなく精神の無意識的活動である)における色と形の組織が、これらの芸術に対して、現実を分節する第一水準の役割をになっているからではないだろうか。この第一水準のおかげで、造形芸術は第二の分節を導入できる。第二の分節とは、さまざまな単位の選択と配列であり、単位を技法とスタイルと流儀の要請に応じて解釈すること、つまり単位をあるコードの個人や社会の特徴となる規則に移し替えてゆくことである。」
p.31
そして特に詩のような言語による芸術の場合、第二の分節が動き始めると、感覚的経験における二項関係はその”離れることを許されない”固着性を解かれることになる。
「第二の分節のコードが活動し始めると、第一のコードの元は何であったのかという性質が忘れられる。それゆえ言語記号には「恣意的性格」が認められるのである。」
p.32
”元は何であったのか(その他ではないのか)”という分節こそ、音や色や形を、その”本来の意味”なる項にがっちりと固定した分節である。意識の表層の二項対立が固まっていたのは、それが正体/正体以外の二項対立のみに結ばれていたからである。
しかし第二の分節のコードの水準では、正体/正体以外の他にも、もっといろいろな二項対立を選択できる。
意識が見分け聞き分ける感覚的に経験できる物事の間の二項対立関係を、”正体/正体以外”以外の他の様々な二項対立と取っ替え引っ替え自在に重ね合わせることができる。
第二水準でのコードの選択を存分に楽しむことができるのが詩の言葉であり、イメージの世界である。
「詩は第一のコードのもつ潜在的意味能力を引き出して、第二のコードに組み込むのである。詩が働きかけるのは、単語と統語法からなる知的な意味作用と、この意味作用を強めたり、修正したり、あるいは反発する、もうひとつの体系の潜在的諸項つまり美的特性とにである。これは絵画においても同様である。形と色からなる対立は、同時に二つの体系に属する弁別特徴として受け取られる。知的意味作用の体系では共通の経験の遺産であり、事物による感覚的経験を切り分け構成した結果である。造形的価値の体系は、知的意味作用に統合されつつ、知的意味作用体系を調整するという条件でしか意味を持ち得ない。これら二つの分節化のメカニズムは絡み合って、両者の特性が混じり合う第三の体系を導入している。」
p.32
重要なところなので、長くなるが引用しておこう。
詩の場合
第一のコードは”単語と統語法からなる知的な意味作用”を可能にしているもの
第二のコードは"第一のコードの意味作用を強めたり、修正したり、あるいは反発する、もうひとつの体系"である。
絵画のようなイメージの場合
第一のコードは”知的意味作用の体系では共通の経験の遺産であり、事物による感覚的経験を切り分け構成した結果”
第二のコードは"知的意味作用に統合されつつ、知的意味作用体系を調整する体系"である。
日常的に経験されつつ、素朴実在論的に目の前に見えたり聞こえたりするモノに固定され固着した分節体系の諸項を、いわば自在に切ったり貼ったりできる”素材”として扱う。そしてそれらを配列し、自在に切り分け直し、組み立て直すことを許す第二の水準のコードの姿を明るみに出す。言葉やイメージの芸術にはそうした作用もある。
ここで注意したいのは第一水準のコードを自然そのもの、素朴に実在する客観的現実によって保証された確固たるものだと分節してはいけないということである。第一の水準のコードが”現”実で、第二の水準のコードが”幻想”だ、という話にしてはいけない。
「第一水準は実在するが意識されていない関係の中にあるのであって、実在し意識されていないからこそ、知られたり正確に解釈されることなく、機能しうるのである。」
p.38
ここにある「意識されていない関係」を、私はここまで繰り返し書いてきた四項関係を関係づける四項関係同士の関係(最小構成で八項関係)と言い換えてみているのである。
”さも”「自然」にみえる第一水準のコードは、人間やその意識と対立し、その外部に固定的にある何かではなく、動き続ける分節作用が析出したた最外郭の仮の安定構造である。
そして芸術的創造は、その作品の目に見え音に聞こえる第一水準の姿の向こうに、第二水準のコードの動きの影を垣間見せることができる。
音楽
ここで音楽である。
複数のコード間の関係という点で、音楽は詩やイメージとは「逆」の方向で作用するという。
「語りかけてくる自然に対して、絵画と音楽は逆の関係にある[…]。自然は人間に対して自発的に色のあらゆるモデルを提供し、ときには色の素材そのものを提供する。描くためには、再利用[…]すればよい。だが[…]自然は物音を生産するが、楽音を生産しない。楽音を独占的に所有するのは楽器と歌を創造した文化である」
p.34
イメージは、感覚的経験を素材とするものであり、第一の分節の水準の安定性とコードの固定性を人間の身体を含む確かな自然によって支えられている。
詩も日常の言葉を素材とする。つまり第一の分節の水準の安定性とコードの固定性に基づいて動き出す。社会におけるコミュニケーションを可能にする言葉の中で、伝達できるか/伝達できないかの分節の可動性を試す。
それに対して音楽は、第一の分節の水準を、自在に楽音を作り出し配列することができる楽器と演奏技術の中にもっている。つまり音楽では、第一水準が第二水準そのものの部分であることが、はじめから明かされているのである。
この点では神話も、言語を用いながら、伝達型コミュニケーションや詩とは異なり、はじめから”第二水準”の構造を中でうごいている。
音楽、神話、分節言語
「音楽という言葉と分節された言葉という対照的なふたつのタイプの記号体系のあいだで、神話は中間の位置を占めている。」
p.41
音楽 / 神話 / 分節言語
レヴィ=ストロース氏はこの三つの違いに注目すべしという。
まず音楽は「内蔵を揺さぶ」り、「各人を各人の生理的な根に触れさせる」。
対して神話は、「いわば各人の属する「グループ」を揺さぶ」り、各人を「社会的な根に触れさせる」。
「一方は(音楽は)内蔵を揺さぶり、他方は(神話は)いわば各人の属する「グループ」を揺さぶる。揺さぶるには、それぞれが、楽器と神話的図式という最高度に繊細な文化的機械を使う。」
p.42
そして「揺さぶる」ことを実現するためには「繊細な文化的機械」が必要となる。
繊細な文化的機械とは、音楽においては歌と楽器である。
そして神話における文化的機械とは、しばしば「仮面」である。
「歌と楽器はしばしば仮面と比較される。歌と楽器は聴覚の次元において、造形の次元における仮面と等価である。[…]音楽と仮面が物語る神話とは、象徴の世界では近縁なのである。」
p.43
仮面が神話を物語る。そこでは神話を語る言葉(分節言語)もまた、なにかの”本当の顔”という伝達コミュニケーション用の記号の姿から、じつは”仮面”であるという”正体”を明かすようでもある。
ちなみに仮面と神話、仮面の神話については、『神話論理』に続く『仮面の道』という本で詳しく検討されることになる。
ちなみに『仮面の道』で分析される北米大陸西海岸の神話には、釣具を用いて人間の世界とその外部との間を移行したり、水界の精霊の姉妹と結婚するも一方だけが残るとか、海幸彦山幸彦の神話に通じるモチーフが登場する。
*
序曲のおわり
さて、といったところで『神話論理』のオープニング「序曲」を読み終わったことになる。いよいよこの後から本編「主題と変奏」へと入り込んでいく。
ここまでの序論で書かれていたように、レヴィ=ストロース氏は『神話論理』を線形に配列された二項対立から二項対立への置き換えとしては記述しない。いや、活字で本になっている以上、その見た目の姿はどこからどうみても文字が言葉が線形に配列されながら言い換えられてくものになる。しかしこれは単線ではなく、複数の線なのである。交響曲の複数の楽器のパートが並列に進むように。
この進行もまた、パッと見ると前から後へ順番に進む”時間”軸上の一方向性を守っているようにみえるが、しかしそこには反復が、同一性への回帰ではなく、逆の方へとズレていく反復というか「変奏」があり、この反復される変奏のおかげで、時間の直線性と一方向性もまた、緩められていくのである。
八項関係というひとつの仮設的な分節の組み方の記述方法を足がかりに『神話論理』の鬱蒼とした森へと踏み込んでみたい。
インデックス/シンボル <> 二項関係/四項関係
目覚めている時間、私たちの明晰な意識は、そのほとんどを二項対立関係を連続的に配列するというやり方で生きている。そこではある一組の「意味するもの」と「意味されるもの」がインデックス的に(つまり必然的で他ではありえないという様相を呈しつつ固定的に)結びついている。
意味するものと意味されるものとのセットが、いくつもいくつも順番に配列され、時間と空間を切り開いていく。
*
しかし、この二項対立でなんとかなるレベルだけが「精神」というわけでもない。明晰な意識は精神のごく一部である。
古来より、精神には二つの側面があると論じられてきた。
合理 と 非合理
ロゴス と パトス
ロゴス と レンマ
知性 と 霊性
理知的 と 感情的
他にもいろいろな言い方があるけれども、例えばこのような具合にわけて、そうして前者の合理、ロゴス、理知の方に「物事の分別がついている」「話が通じる」「理路整然としている」「沈黙しない」「話が飛躍しない」などなどという人と人との伝達的なコミュニケーションの場面であるべきパターンが重ね合わされる。そして前者のロゴス系の方に高評価が与えられ、後者の非ロゴス系の方に低評価が与えられる。
ロゴス系 / 非ロゴス系
|| ||
高評価 / 低評価
|| ||
伝達に成功する / 伝達に失敗する
このようなことが今日の世界でもよく見られる。
*
ところで、深層意味論であるとか、意味分節理論などと言うと、どうも世の中的には後者の側、非ロゴスで反ロゴス、上の分別でいえば「低評価」される側の話だと思われることが多い。
これを書いている私も、しばしばよく知らない人らから「意味分節なんて意味不明で訳のわからない話はやめてほしい!!」と怒られることがある。
どうやら合理の世界から非合理の世界へ、堕落させようとしていると、思われるらしい。
* * *
合理と対立する非合理なパトスや感情、霊性やレンマの側が、分別を失った、話の通じない、理路が無限に分岐して迷子になる、話が飛躍する、得体の知れないものだと感じられるのは、それをロゴスの論理に置き換えて、ロゴスの論理でもって説明のための記述を構築することができないからである。雑なまとめ方で恐縮だが、ロゴスの論理は基本的には二項関係を一列に並べていく。
AはBである。
AはBではない。
AならばBである。
論理の教科書に出てくる例文も、こういう構造になっている。
非合理なパトスや感情、霊性やレンマの世界で起こっていることを、ロゴスの論理でもって無理矢理に記述しようとすると、次のような具合になる。
Aは非Aである。
AはAではない。
AならばBではないし非Bでもない。
こういう非ロゴスが意味不明でまっとうな言葉のやりとりを拒絶している狂気ように見えてしまうのは、言葉というものをただひたすら二項対立関係を一列にならべていくだけのことだと限定して見ているからである。
○ = ○ = ○ = ○ = ○ = ○ = ○ = ○
AはBで、BはCで、CはDで、だからAもDで…。
ところがところが、言葉というのは、ただひたすら二項対立関係を一列にならべていくだけのこと”ではない”!
(もちろん、言葉は、ただひたすら二項対立関係を一列にならべていくという姿をとることもできるし、それも立派な、というか完全な言葉の姿である。しかし、言葉とはそれだけではない。)
ロゴスの世界で一列に順番に並べていくことができるような二項の関係というのは、じつは二項の関係の関係、最低でも二つ以上の二項対立がペアになった構造の中に発生している。
しかも、この二項対立関係の対立関係(つまり四項関係)構造は、これとは別の四項関係が圧縮することで初めて生成するのであった。
ロゴスの論理が頼りにしている言葉は、社会の表通りでは二項の関係だけを表に表している。いや、場合によっては光り輝く一項だけが日常世界の目に見える光景の全てを照らし出しているかのような姿をしていることもある。
しかし、これらの一項も、二項も、実は全て、四項関係が二つ組み合わさった八項関係のなかにあり、常にこの八項関係の項として区切り出されることで存在を保っている。
表層の言葉、二項の関係が一列に並ぶしつらえの言葉だけをそのまま眺めていても、この八項関係が動いている様を見ることはできないのである。
ここに非ロゴス、パトスなり霊性なりレンマなりが出てくる。
パトスや霊性やレンマは、二項対立関係の向こうに三項関係や、四項関係や、八項関係の姿をありありとイメージできるなにかとして立ち上がらせる力をもっている。
二項対立から、いきなり八項関係に飛躍するのではなく、まず二項関係の間に両義的で媒介的な第三項(中間項)を登場させる。そしてその後に、両義的媒介的中間項同士の二項関係を立てる。そうして二項関係を三項関係へ、三項関係を四項関係へ、そして四項関係を八項関係へと展開していく。
レヴィ=ストロース氏の『神話論理』はまさにこの二項対立の間に両義的媒介項を発見し、この両義的媒介項同士の対立関係へ、さらに四項関係へ、そして複数の四項関係の関係へと展開する思考の形を捉えたものである。

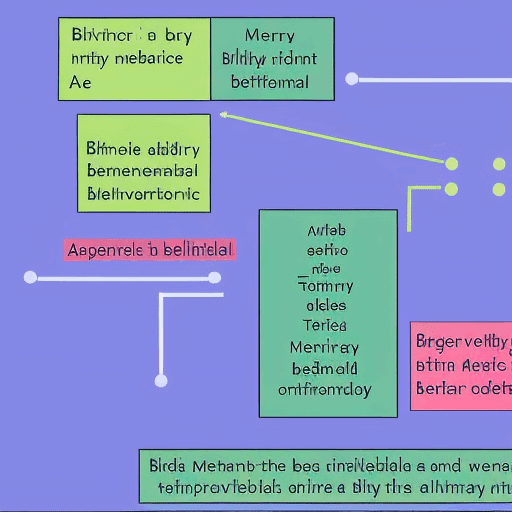
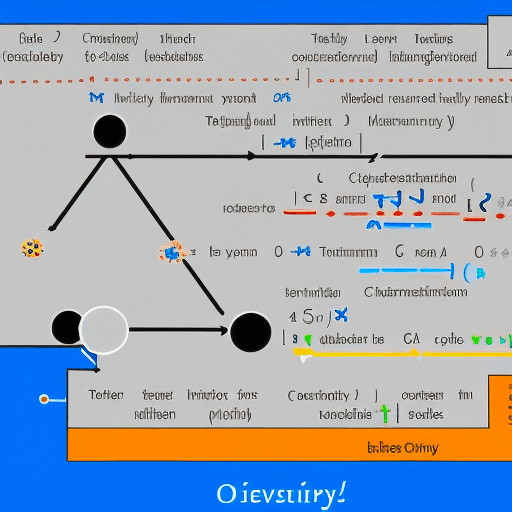
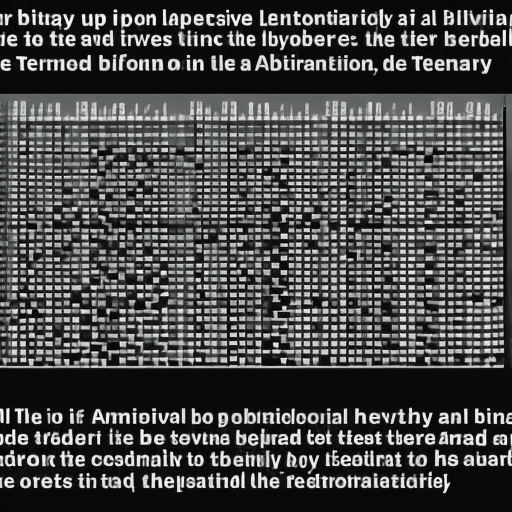
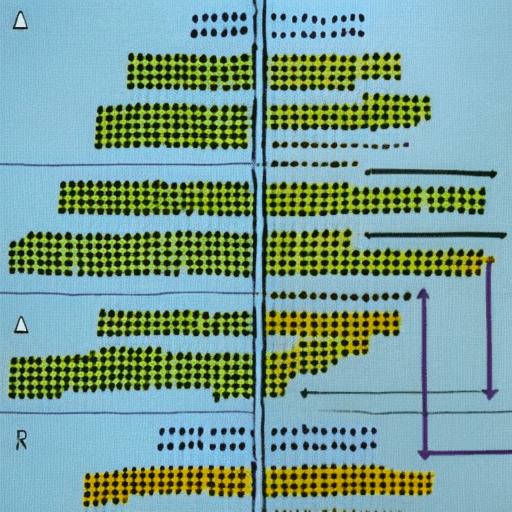
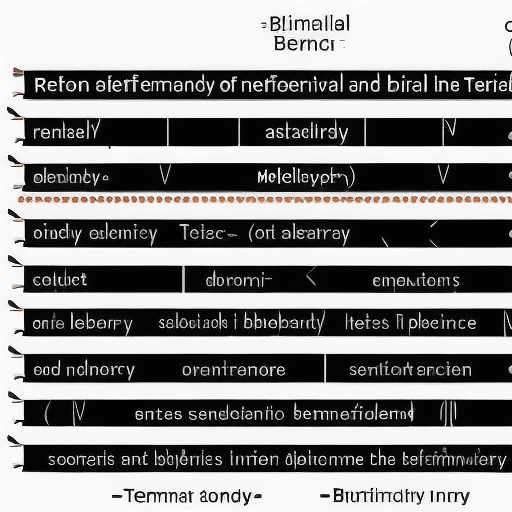
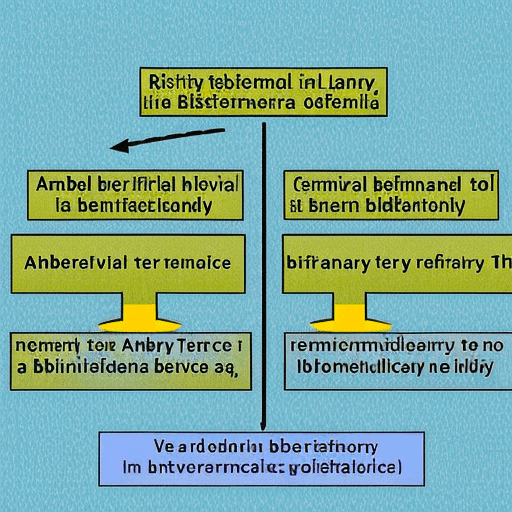
今日のAIは、ここまでの話でいえば、人間の日常の伝達型のコミュニケーションを自動化する目的で主に実用されている。
人間が感覚的、経験的、伝達用の言語でやっている分節を”教師データ”として”学習”し、入力データを最終段の最小構成としては対立関係にある二項のどちらかへ振り分けるように働いている。
われわれ人間が「知能」といえば任意の何かを対立する二項のどちらか一方へと”正しく”振り分けることだと思って、そのようにAIに教え、そのようなことを学習しやすAIを開発している。
*
しかしもし、この二項に分節する知能が、実は互いに互いを分けつつ結ぶ二重の四項関係の動きであり、その次元を減らし、人体の感覚による分節と調和させたものだとすれば…。
人間が思う「知能」は、実は八項関係で動いている。
とすれば、八項関係を切り結ぶAIを開発すると、より”深層”に迫る知性をシミュレートできるかもしれない。
この開発の際には、おそらくレヴィ=ストロース氏が分析したような、神話たちが「教師データ」となるのではないか。
というか、すでに誰かやっているのではないか??
つづく
つづきはこちら↓
過去の記事と最新の記事はこちら
関連記事
ここから先は
¥ 1,100
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
