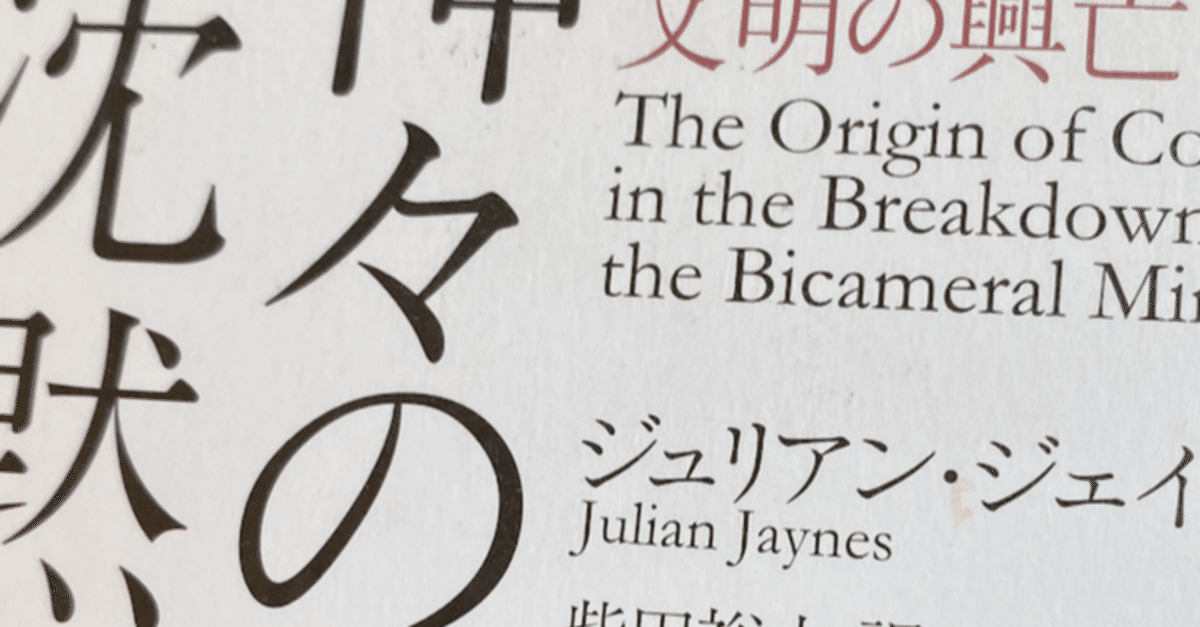
"声を聞くこと"のメディア・コミュニケーション史 - ジュリアン・ジェインズ著『神々の沈黙―意識の誕生と文明の興亡』を読んで考える
*
(前回の記事の続きですが、今回だけでもお楽しみいただけます)
(前回はこちら↓)
*
ジェインズ氏が描き出す二分心時代の始まりと終わりの物語は、今日の人類が直面している状況に通じるものがある。
二分心の時代は古代都市の誕生と同じ頃に始まった。
多数の人が集まって定住し時期を定めて一斉に農作業に勤しむ。ここで多数の人々に何をなすべきかを命じたのが二分心の「神」の部分の声、即ち、頭の中で聞こえてくる記憶された部族の長老たちの訓戒する声であったという。
そして二分心の時代が終わるのは、古代都市に集まる人々が流動化し多様化した時である。ジェインズ氏は次のように書く。
「<二分心>時代には、同じ都市の神に属していた人々は、多かれ少なかれ似たような意見を持ち、似たような行動をとっていた[…]。しかし国や神が異なる人々が外力によって激しく混ざり合ったとき、見知らぬ人が例え自分と同じように見えても違う話し方をし、反対の意見を持ち、違う行動を取るのを観察すると、相手の内面に何か異なるものがあるという仮定に行き着くかもしれない。」(『神々の沈黙』p.259)
都市に集まって暮らす人々の顔ぶれが、生まれて以来ずっとその都市に居ますという人ばかりではなくなり、他の都市や周辺の狩猟採集生活圏から移住してきた人が増えてくる。おそらく戦争や自然環境の変化がそうした移住と都市への人口集中の要因になるのだろう。
(この辺りの話は下記の文献が参考になります)
多様なルーツを持つ人が集まると、当然それぞれの人が子供の頃に聞かされ、無意識に記憶した長老たちの訓戒する声(つまり「神々」の声)は、出身部族ごとに異なるはずである。
仮に、二分心に基づく古代都市の生活が、その都市を最初に築いた祖先たち伝来の「神の声」を都市で生まれた子供たちに伝承し共有し続けることで、世代を超えて反復されてきたのだとすると、その都市の神の声を聞いたこともない人や、そもそもその都市の言葉がわからない人が増えてくると、都市生活のリズムと規律を維持できなくなる。
* *
それでは困るということで、苦肉の策で案出されたのが、意識という比喩であった。即ち「他人が意識を持っていることを無意識に想定し、その後それを一般化することで自分自身の意識の存在を推量」するようになる(『神々の沈黙』pp.259-260)。
”他人の頭の中でどういう言葉が鳴り響いているかは、私にはわからないけれども、仮にいくつかの比喩表現を組み合わせてシミュレートしてみると、おそらくこうなんじゃないか、ああなんじゃないか”、などとやることができる。
私たちは、他の人が喋っている姿を思い描くことができる。
私たちは、自分の頭の中に、誰か他者の姿を思い描きながら、その口に”その人が言いそうなこと”をしゃべらせて見せることができる。あの人ならこういう時こういうのではないか、と。
ここから転じてこの喋る他者の像を援用し、今度は「喋っている自分自身」の像を頭の中に浮かび上がらせしゃべらせる。そうしたところにその喋りの主語になるものとして「意識」が始まるのである。
(この話は下記の記事に書いていますので、詳しいことはこちらをご参考にどうぞ。)
* * *
少数対多数の一方通行から、Web状の双方向へ
この「二分心の崩壊」と「意識の始まり」は、「声」の複数化に対応した、象徴の生産と記録と配給の技術の組み替え(いわば、象徴言語と脳をサブシステムとするコミュニケーション・システムの再編)と捉えることもできる。
西暦二千年を過ぎること二十年ほど、私たちの日常のコミュニケーションのやり方は、人類史上おそらくかつてなかった程の速さと規模で激変している。
◇ ◇ ◇
そして今日進行していることも、一面では「声」の複数化であり、また別の一面では、象徴の生産と記録と配給の技術の大規模な組み替えではないだろうか??
◇ ◇ ◇
ほんの十数年前まで、世の中にはごく少数の発信者から多数の受け手へ、完成されパッケージ化され大量複製された商品としての「情報」が一方通行で同期を取りながら送り届けられるという光景がありふれていた。
テレビにラジオ、映画館に新聞雑誌にレコードにCD、そして学校と、大量生産された同じ商品からなるマス・メディア全盛の世界である。
国民国家や一国の国内市場についての私たち一人一人のイメージや、一国の「国民」としての私たちのセルフ・イメージも、マス・メディアのコンテンツとの接触を通じて形成されていた。ここで「多数の受け手」たちの一人一人は自分たちの世界と自分たち自身について、それを肯定的に捉えるにせよ否定的に捉えるにせよ、ある程度斉一なイメージを持ちやすくなっていた。
*
ところが、インターネットが社会一般へ急速に普及することによって、私たちのコミュニケーションのやり方は、従来のマス・メディア時代のものに比べてほとんど真逆になってしまった。
まず発信者は少数から多数へ(誰でも表現者・発信者)と急拡大した。
情報も未完成のままコミュニケーション・ネットワークの中を飛び交うことになった。情報は、パッケージ化されないまま、あるいはパッケージ化されることから逃れて、その制作過程を閉じられていないものとして、オープンで作りかけのブリコラージュという姿でサイバースペースを飛び交い、多数の発信者の元へ「素材」としての姿をあらわすようになった。
そしてコミュニケーション・ネットワークの構造も、少数対多数のスター構造ではなく、多様な個と個が直接つながるWeb構造へ、一方通行から双方向へ、同期型から非同期型へと変わっていった。
(スター型とかWeb型とか、コミュニケーション・ネットワークの構造の図式については色々な参考文献がありますが、例えば下記のヴィレム・フルッサー氏の『テクノコードの誕生』も参考になります。)
* *
この新しいWeb状の双方向コミュニケーションの様式の中で、互いに相容れない、時に真逆のことを言う多様な声があちらからもこちらからも上がり始める。
従来マス・メディア型のコミュニケーションが(実際には多様な差異と断絶を覆い隠しつつ)表向きは「一枚岩」的に安定しているという装いのもとに再生産し続けていた国家や市場や国民の統一性・単一性といったイメージに比べると、今日のWeb状のコミュニケーションは分断と対立、分裂と終わりのない論争ないし罵り合いの激流に見える。
◇
この状況、二分心が沈黙してしまった頃の古代都市の住民たちが置かれていたものとそっくりではないか??
世代を超えて二分心から二分心へと伝承されてきたある都市を創建した族長たちの声。これを聞いたことがないひと、聞けないひと、聞かない人が、入れ替わり立ち代わり離合集散する場となった都市では、この危機を転じて「意識」という象徴製造技術を開発し、意識的な主体同士のコミュニケーションという新しい象徴交換・記号交換のやり方を編み出したのである。
もちろん、それは一朝一夕にできることではなく、オリエントでは千年かかったのである。
* * *
今日の私たちもまた、二分心の沈黙に匹敵する困難に直面しているとすれば、これを乗り越えるには一方通行スター型のコミュニケーションとは異なる形で象徴を発生させ、交換しつつ、変容させるコミュニケーション・メディア技術を作り出さなければならない。
「意味」の様式の変容
これはインターネットがいいのか悪いのかマスメディアがいいのか悪いのか、という二者択一の問題ではない。XとY、良いと悪い、という二つの二項対立関係をどちら向きで重ねるかという問題の立て方は、言葉が私たちを迷わせる典型的なパターンである。
ここで迷わないためには、異なる二つのコミュニケーションの様式と、「意味」の発生と束の間の安定化と消滅のプロセスの二つのパターンの違いをよくよく分節することである。
マスメディアもインターネットも、どちらもそれぞれある癖を持った記号の生産と記録と配給の技術(象徴言語と脳をサブシステムとするコミュニケーション・システム)なのである。
*
おおよそ20世紀の後ろ半分の五十年間、マスメディアが具現化していたコミュニケーションでは、記号の「意味」が予め完成され確定されたものとして要求された。意味は大量生産された商品の一つ、完成品の装いをしていたのである。
完成した商品としての記号が大量に複製生産され、一方通行で、同期を取りながら、全国津々浦々の「大衆」の一人一人の目や耳へと注ぎ込まれていた。
* *
もちろん意味ということの本性からして、どのように綺麗にパッケージ化され完成品の刻印を押された記号であっても、その意味は自在に変化しうる。
個々の受け手がその情報を自在な「読み」へと展開し、新たな意味づけを行うことは、ごくありふれた、当たり前のことであった。この点では記号は個々の受け手のもとに到達した瞬間に、完成品のパッケージを破られ、日曜大工的に流用転用誤用されて、新たな意味作用を引き起こしていく。
ただし、この完成品の記号を流用転用して作り出された新たな意味は、無数の大衆の一人一人同士の間で「横」に自在に繋がったり、交換されたりすることが難しかった。大衆の一人一人が、自分の手元で発生した新たな記号の置き換え=意味をマス・メディアを通じてばら撒くのは容易なことではなかった。ノートの切れ端に教師には読めない独自の記号で記されては教室で交換されたり、大都市近郊の国道沿いのコンビニになぜか売られていた謎の投稿雑誌の小さな活字を通じてアンダーグラウンドに、ゲリラ的に、交換されていた。
* * *
ところがインターネットの登場により、意味がブリコラージュされる場は、教室でリレーされる紙片や謎の投稿雑誌のような場所から、突如として、渋谷のスクランブル交差点に走り込んだゲリラライブ用のトラックの荷台のような場所に変換されたのである。
インターネット上の掲示板やブログやSNSなどにみられるように、多様に異なる人による、多様に異なる言葉と言葉の繋ぎ変え、置き換えの激流の中では、ある言葉、ある情報の「正しい意味」などというものは、予め決定されていないし、どこかに決定しようにも必ずそこからそこから逃れ去っていく。
ある言葉の置き換え先は、ある言葉から別の言葉へ、さらにまた別の言葉へと、次から次へと転じていく。SNSで「バズる」のも、大概がこのうまい言い換え、ありそうでなかった絶妙な言い換えに成功しているものであったりする。
* * * *
誰もが言葉の言い換え方を試しに発信することができ、それが瞬時にどこからでもネットワークの全体に広まることもあるというのは、今日のWeb状のインターネットが可能にした極めて画期的なコミュニケーションの様式である。
インターネットのコミュニケーションは、言葉と言葉の置き換えのパターンを、常に流動的なものにする。
意味するということがある言葉を他の言葉に置き換えることであるとすれば、この置き換えがいつまでも新たに発生し、どこかで止められることがないということは、一面では意味の自在で多様な発生であり、反面意味が永久に定まらないということでもある。
(意味するということが言葉の置き換えであるということ。この話については下記の記事に書いているのでご参考にどうぞ)
(こちらも合わせてどうぞ)
意味が定まらないというのは悪いことではない
意味が決まらないと安心できないというのは、20世紀後半に自我を確立した世代に特有の癖なのかもしれない。
言葉の意味には「決まった正解」があるはずだという発想や、ある言葉の意味、言い換え先を、どこかに決めて、そこから動かしてはいけないという発想自体が、極めて現代的というか近代的というか、コミュニケーションするということの意味を「正解」を注ぎ込まれ暗記するゲームという装いへとアレンジしてきたメディアと、それに接続されて意識の分節システムを育てられた人に特有なものかもしれない。
◇ ◇
言葉はその太古の登場以来、むしろ、都度都度顔を合わせて会話し合う相手との間で、その時々の社会関係や会話の状況に応じて、いかようにでもその意味を、言い換え方を変えられるところに強みがあった。
20世紀の後半にあっても、人は日々雑談や噂話や飲み屋談義に勤しみ、表向きの正解に安住しようとする言葉を冗談半分の言い換えへと引っ張り込んでは面白がっていたのである。
そしてどちらかといいえばこの自在な言い換えをやめないという方が、古代以来の言語の本来の姿なのである。(逆に言えば、自在な言い換えを止める方法がなかったとも言える。強いて言えば、二分心こそ、自在な言い換えの発散を戒めブレーキをかける、最初の仕掛けだったのかもしれない)
言語コミュニケーションは、シンボルとシンボルの結び付け方を仮設的に試すことにその本来の姿がある。
今日の個々人がWeb状に双方向につながるコミュニケーション・ネットワークでは、ある言葉の「正しい(とされる)意味」を固定して、それ以上の言い換えを禁じようとするようなやり方は華麗にスルーされてしまうわけである。次から次へと言い換えが試みられる言い換えの喧騒の中で、言葉の言い換えを機械的に反復する「声」はかき消される。
今日では、言葉の意味ということが、従来のマスメディア全盛の時代に持っていた固定性という仮の姿を演じることをやめて、多義的で両義的、流動的で新たな置き換えへの転換を止めない自在な姿を現すようになる。
◇ ◇ ◇
ここで、今日の事態が複雑であるのは、マス・メディア型の言い換えをどこかで止めようとするコミュニケーションも、まだ完全に沈黙したわけでは無いということがある。テレビで地上波にチャンネルを回せば、引き続き20世紀以来の伝統的な少数の発信者から多数の受け手を目指して発信された完成済みパッケージ化済みの大量複製商品のコンテンツが一方通行的に送り出され続けている。
しかし、そういう量産マス型のコンテンツも、直ちにWeb状の双方向のブリコラージュ的制作過程の中に引き込まれて、続々と他の無数の記号へ、他の無数の象徴へと言い換え、置き換えられていく。もちろんこの言い換え置き換えは素晴らしいものからとんでもないものまで「玉石混淆」である。
これを社会がバラバラになってしまったと見るか、それとも人類が新しい局面へと踏み出した兆候と見るか。現代を生きる太古の人類たちの子孫が、今まさにその集合的な脳たちからなる象徴発生システムの性能を試されているとも言えるかもしれない。
◇ ◇ ◇ ◇
二分心の沈黙後に起きたことから、今後の可能性を推定する
私たち人類にとっての意味ということ、意味するということ、つまりコミュニケーションということは、今後どういう方向に向かうのだろうか?
二分心の沈黙後に起きたことを見ると、この双方向Webの先にどういう可能性があるのかを考えるヒントがありそうである。
*
二分心の時代、人類は、生の音声と建築物以外にコミュニケーション・メディアの技術を持たなかった。
おそらく神殿の上で右脳が発する訓戒する声を大声で朗誦する人と、それを聞きながら唱和する多数の住民の間で共同体のために個々人がなすべきことを訓戒する祖先伝来の言葉が共鳴した(今日のアリーナ・ライブ・コンサートのようなものだ。ただし拡声器はない)。
これが上手くいかなくなったとき、人類は過去の神の声、訓戒する声を文字で記して繰り返し読み上げるようになり(聖典の時代)、その後には文字を記した本を大量生産し運び配るようになり(印刷技術と産業革命。新聞と辞書の時代)、さらには電気通信技術と映像音声技術を用いて音声映像の大量コピーをリアルタイムでばら撒くまでに至ったわけである(それがテレビを核とするマスメディアの時代)。
これらはジェインズ氏に言わせれば、いずれも沈黙してしまった二分心時代の「神の声」の代わりと求める動きだということになる。
「<二分心>の時代には、ウェルニッケ野に相当する右(劣位)半球の領域には精密な<二分心>の機能があったが、発達の初期段階で<二分心>が生まれてもその発達が阻害されるような心理的な再組織化が一〇〇〇年にわたって行われ、この領域は異なる機能を持つようになった、と考えても差し支えないと思う。」(『神々の沈黙』p.155)
二分心の代わりの代わりのそのまた代わりのようなものであった新聞と完成された辞書とテレビが「沈黙」しようとする今日、人類はまた新たな二分心の「神の声」をどこかに探そうと模索し始めることになる。
「学習で身につけた私たちの意識が、今の一〇〇〇年紀に至ってもなお完全ではない[…]私たちは<二分心>の名残りに、つまり行動を制御するための古いやり方に、ある程度は助けてもらわなくてはいけない。人間は意識の誕生とともに、<二分心>の特徴だった単純で絶対的な制御の方法を捨ててしまった。今の私たちは「なぜ」「何のために」という疑問が飛び交う騒がしい世界に生きている。自分の<物語化>にどんな目的や理由を与えようかとあれこれ考えている。いわばアナログの<私>にたどらせる道筋がたくさんあるわけだ。[…]アナログの<私>と比喩の<自分>は、数々の「集団内で強制力を持つ共通認識」の合流点にいつもたたずんでいる。自分自身に極端なことを命じるには、私たちはあまりに物を知り過ぎてしまったのだ。」(『神々の沈黙』p.488)」
なぜ、何のために。
今日でも、私達は何をするにしても、理由や意味を問わずに居れないように見える。仕事をやめるにしても、誰かと一緒に暮らし始めるにしても、本を読むにしても、映画を見るにしても、何かを食べるにしても、どこかに出かけるにしても、誰かに会うにしても。しかも不要不急であるとか、「今それをする必要があるのですか?」などと問われてしまうと、ますます人に説明できるような「理由」を探さなければならないと追い詰められるわけである。
私たちは今でも、訓戒する二分心の神の声に叶うように、二分心の神の声を納得させるように、弁明のための「理由」や「意味」というポジションを充当する言葉を探し続けようとしているとも言える。
「それでも正解を決めたい」
ジェインズ氏によれば、目下が私たちが、他人に有無を言わせぬ説得力を持った「理由」や「意味」の源泉として用いているのが科学の言葉である。
「前二〇〇〇年紀に、人間は神々の声を聞くのをやめた。前一〇〇〇年紀には、まだ神の声が聞こえなかった人たち、つまり託宣者や預言者もまた、徐々に消えていった。紀元後の一〇〇〇年紀には、かつて預言者たちが言ったり聞いたりした言葉の記された聖典を通して、人々は自分たちには聞こえぬ神の言いつけを守った。そして二〇〇〇年紀には、そうした聖典は権威を失った。科学革命によって、人々は昔からの言い伝えに背をむけ、失った神の権威を自然の中に見出した。」(『神々の沈黙』p.527)
ジェインズ氏は「科学」もまた「<二分心>の崩壊に対する反応として解釈できる」という。
科学的真理を追求せざるを得ない「確実性」や「森羅万象の正体」を求める衝動は、神々の声が沈黙した後の「無」を、言葉でもって埋めようとする営みのうち、今日の世界において最も権威を持つ「集団内の共通認識」なのである。
『神々の沈黙』の本論は、次の一節で締められている。
「真実という概念そのものが[…]大昔の確実性に対して誰もが抱く根深いノスタルジアの一部なのだ。永遠の原理の揺るぎなさ、普遍的な安定性なるものがそこにあり[…]世界中を巡ってそれを探し求めることができるという考えそのものが[…]<二分心>が衰退した後の二〇〇〇年間、失われた神々を求めてきた直接かつ当然の結果だ。その昔、崩壊した原始の精神構造の間で何をなすべきか占っていたのが、今では、事実という神話の中に汚れのない確実性を探っているのだ。」(『神々の沈黙』p.539)
今日、「事実」が「あくまでも測定と観測に基づいて推定された仮のものである」という科学者にとっては既知のことを、とても嫌がる人々も少なくない。
科学的で客観的な事実なるものが、沈黙した神の声の「代わり」として求められているのだとすると、それを「仮の推定ですから」などというのはとんでも無い冒涜というように映るだろう。
小活
どうやら二分心の神の声の沈黙後、私たちはひたすら、その代わりになるものを求めていたということになる。
二分心の神の声は、訓戒する声、何をなすことが正しく、何をなすことが正しくないかをはっきり区別して教える声である。
私たちは自在にシンボル同士を置き換えることができる脳を持ちながら、同時に、現に生きている環境の中で生き延びることに寄与する選択をできるよう、確かな正しさを求めもする。
あるいはシンボルの置き換えを自在にできるということは、周囲の環境の多様な変化に柔軟に対応して、つど最適解を変更できる才能なのかもしれない。
例えば何かXについて、それが良いことか悪いことか、言葉の意味という点では、Xは善であるとも言い換えられるし、Xは悪であるとも言い換えられるし、どちらでも良いのである。
しかし、現実には、例えば目の前にヒグマが唸りを上げているとして、"このヒグマは敵であるとも言えるし、友達であるとも言えるし、どちらでも良い"などとやっている暇はない。
言葉の自在さは、吉と出ることもあれば、凶と出ることもある。
**
どちらとも言えない曖昧ない中間状態を維持しつつ、ひとたび未知の何かに遭遇すれば、素早くそれを「どちらか」に判別して応答する。これが人類の臨機応変の力なのかもしれない。人類の知性の最大の強みは、「正解を決めるけれど決めない」「正解を決めないけれど決める」という曖昧な宙ぶらりん状態を保ちつつ、周囲の環境を観察しながら最適解を変更し続けることができる点にありそうである。
言語が、人を妄念への妄執へと引き摺り込む罠になるのではなく、人の知性を拡張することに寄与するとすれば、それはどうやら言語が曖昧で宙ぶらりんなまま、両義的で、どちらでもあってどちらでもないことを言うことが許される試行と仮設のための特別なコミュニケーションの場を共同体の中に実装しておくことができるかどうかにかかっているらしい。
おそらく、人類の多くの部族が太古から密かに受け継いできた神話を伝承するための時空こそが、そうしたコミュニケーションの場なのである。
そういう場を、最新のコミュニケーション・メディア技術を用いてどのように仮設できるのだろうか??
>>続きはこちら
(これまでの記事の一覧はこちら↓)
関連note
この記事が参加している募集
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
