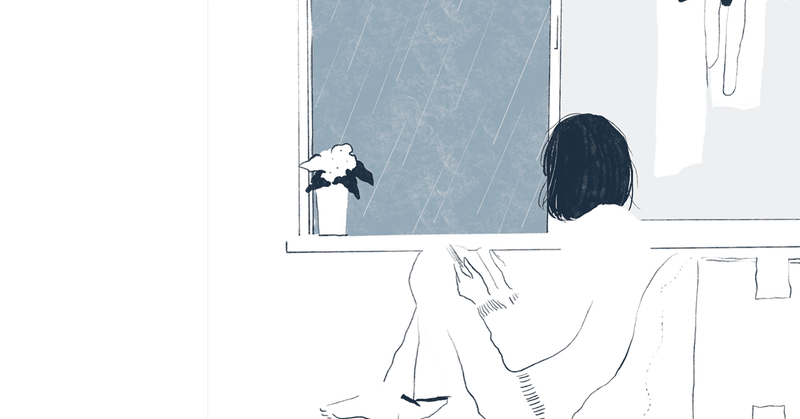
「『他者』について」への批判:2
「『他者』についてへの批判」、二回目になりますよ。
「偶然性」を尊重するという意図で書いたつもりが、逆にその「他者」の「偶然性」を否定し、打ち消してしまう
という問題点について、なぜそのような事が起こるのかについて詳しく書くぜ。
もう一度確認しておきて〜んだが、理解されないということによって達成される、未知としての「他者」だ。未知であり、理解されないものでもあり、触れられもしないものでもあるという点で、人間の認識の枠にとらわれないような真の「他者」が現れるんだが、それは、やはり偶然性を否定しているとも言えるんだな。
「他者」は、偶然性を有する者。それは、暴力を避けるための、その「他者」を守るためのもの。
しかしながら、文の内容からも分るかと思うんだが、この「他者」は、交流を欠いてる。つまり誰ともかかわらない。触れ合わない。人間にとっての重要なのは、他の人間と出会うことによって現れる、また別の姿なんだで。
他人と出会うことによって、そこには、どんな人格が現れるか分からないという偶然性が現れると考える。今まで書いてきた「他者」は、その人の偶然性をあまりに尊重し、傷つけるのを避けさせるために、その人のさまざまな姿、交流によって、他人の影響を受けながら変化していく、可能性や偶然性を否定し、亡き者にせんとしている。
人間は、傷つく者。
シャボン玉が割れないように割れないように大切にしようとしすぎることによって、そこに現れるやもしれない様々な姿を、ないことにしてしまう。偶然性を求めて、偶然性を否定しているのが、この「他者」だってこと。
これに関連してというか、おそらく参考になるかな・・・と思う文章があるので、引用する。
エマニュエル・レヴィナスは、「主体」に関してこのように述べています。
主体の破壊や消失が、無意味ではなく意味の可能性、主体の成立そのものとみなされる。(村上靖彦、2020、187)
ワタシが今まで書いてきた「他者」の批判は、これに繋がるかなと。
真の「他者」は、その「他者性」を保つためのもの。ある意味では、その他者の「主体性」と言い換えることが出来るのではと思うや。(もしかしたら、違うかもしれませんが)
その「主体性」を守ろうとするあまり、その「偶然性」を否定したとなれば、それこそが、他者の主体性を軽視し、尊重しなかったのではないかと考えられんで(他者の主体性は、そっくりそのまま「他者性」として捉えられるかについてはまだ判断しかねますが)。
むしろ、想定される真の他者性(あまりにも過保護な態度から現れる)を、人間との交流によってぶち壊すことによって、その人のより開かれた他者性(主体性)を獲得することにつながるのではないではと。
引用文は非常に考えさせられます。
私は勝手に、「他者性」を暴力に曝すこと、「理解」という枠におさめることを、「無意味」に近いものだと判断していたんだが、この意味で、「「他者」について」という最初の記事は、非常に狭い視点であったことが分かる。
むしろ、その(ある意味では保守的な)「他者性」、「他者の主体性」を、他の人間と関わりの中で、「破壊や消失」させることが、より広い他者の主体性というか、レヴィナスのように、人間の中にある主体性を生み出すと考えた方がいいかもしれんね。
では、この主体性って、どんなものなのだろうかということについては、別に機会で。たしか、参考になるような本を以前読んだことがあるので、それをまた借りてこなければなりません~。
他者を理解するのは、自分の中の枠でしか起こり得ませんが、しかし他者のより広義の偶然性や可能性、主体性というのも考慮すると、むしろその「他者」は、壊されるべきものなのかもしれません。
守るのではなく、ぶっ壊すことによって、現れる者。それが、今のところ、ワタシにとっての「他者」(人との関りを意識した場合の)。しかしながら、真の「他者」という考えが消えたわけでは...ない。以前書いた「他者」と、今回書いた「他者」は、別物であると考えた方がいいかもしれませんね。
と
今日も大学生は惟っている。
引用文献
村上靖彦.2020.レヴィナス 壊れものとしての人間.河出ブックス
サポートするお金があるのなら、本当に必要としている人に贈ってくだせぇ。
