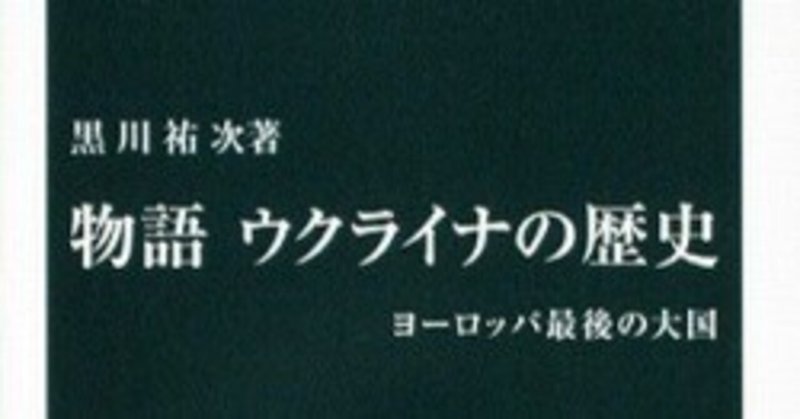
【書評】黒川祐次『物語 ウクライナの歴史』(中公新書)
最近の急な情勢の変化によって、にわかに注目されるようになったウクライナの歴史。
領域が広大で、ポーランドやオーストリア、ロシアといった国の支配を受けた経験があるウクライナ史を知るには、ネット上の無料の知識だけでは到底足りません。
「物語 ウクライナの歴史」は2002年の発行ですが、今でも格好の入門書として通用する内容だと思います。
筆者は元外交官で歴史の研究者ではありませんが、ロシア(ソ連)の史観からの学説とウクライナ・ナショナリズムに基づく学説を併記するなど、公平な叙述になるよう気を使っていると感じました。
キエフ=ルーシは誰のもの?
例えば、10~11世紀ごろに繁栄したキエフ=ルーシ公国。キエフ(キーウ)を中心に東ヨーロッパの強国となりましたが、13世紀にモンゴルの侵攻を受けて滅びました。
この国の後継者はロシアかウクライナか、それぞれの国の立場によって異なる見解があります。歴史を扱う時には、望む・望まざるにかかわらず政治が入り込まざるを得ないことがわかります。
ウクライナの語源とは?
「ウクライナ」という言葉の語源についても異なる説が紹介されています。ロシア(ソ連)を中心とした従来の史観では、ウクライナとは「辺境」を意味するとされました。
しかし、近年のウクライナでは別の説が提唱されています。古いスラブ語の「krai(切る、分ける)」に由来し、単に「土地」「国」という意味の普通名詞が地名になった、というのです。
「ウクライナはいまだ滅びず」
周知のとおり、ウクライナは大半を帝政ロシア(一部はオーストリア)に支配され、民族主義は抑圧されました。
ロシア革命の際にウクライナ人の政府が樹立され、独立の機運が生まれます。しかし、ボリシェヴィキや白軍(ロシア革命に反対する勢力)や諸外国の介入で、いくつか樹立されたウクライナ人の政府はいずれも短期間で崩壊しました。
ソ連時代には、人為的に引き起こされた飢饉(ホロドモール)によって数百万の餓死者を出しています。
これほどの苦難に満ちた歴史をたどったにも関わらず、ウクライナ人の文化やアイデンティティは消えませんでした。
ウクライナの国歌のタイトルは「ウクライナはいまだ滅びず」。今も苦難に晒されながらも抵抗を続ける人々に、深い畏敬の念を抱かざるを得ません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
