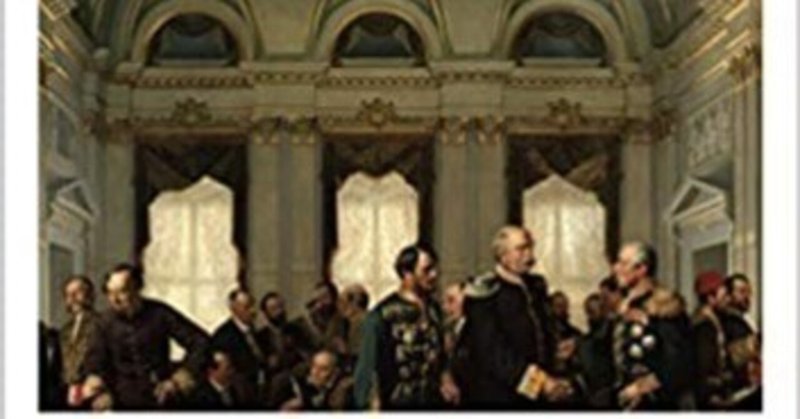
【書評】庄司潤一郎・石津朋之編『地政学原論』(日本経済新聞出版)
大きめの本屋に行くと、「地政学」をタイトルに冠した本が多く売られているのに気づきます。国際政治を地理条件から読み解くという便利さ、明快さが「地政学」の魅力でしょう。
一方、学術的な批評に耐えうるだけの書籍を見つけるのは難しいはずです。内容はあまり地政学と関係ないのに、タイトルに「地政学」と名付けてあるケースもあります。地政学の語が入っていれば売れる、という出版社の判断でしょう。
安全保障専門のシンクタンク「防衛研究所」の研究員が編集した本書は、「地政学についてきちんと学びたい」という人に非常に最適な書籍となっています。
そもそも、地政学は「geopolitics」の訳語ですが、体系的な学問とは言えません。マッキンダーやマハンといった論者は、まず提言したい政策ありきで、それに沿うように論理を組み立てているのです。「学」の字を入れるのは不適当で、むしろ「地政」「地政治」と訳した方がいいとのことです。
実際、客観性や事実におそろしく無頓着なのが、地政学のきわだった特徴である。(P144)
また、地政学は地理で国際政治を説明しようとする反面、民族が持つ文化や倫理、道徳など「形のないもの」を軽視する傾向が強いことも指摘されています。
では、学術的に問題の多い「地政学」は、なぜ現代に至るまで命脈を保っているのでしょうか。地政学者が語る理論はしばしば国にとって都合が良く、政策の裏付けにしやすかった、という部分が大きいのでしょう。
「シーパワー」や「ハートランド」といった用語がどこまで妥当かはともかく、こうした書物を通して「地政学」の教養を身に着けることには、一定の意義があるのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
