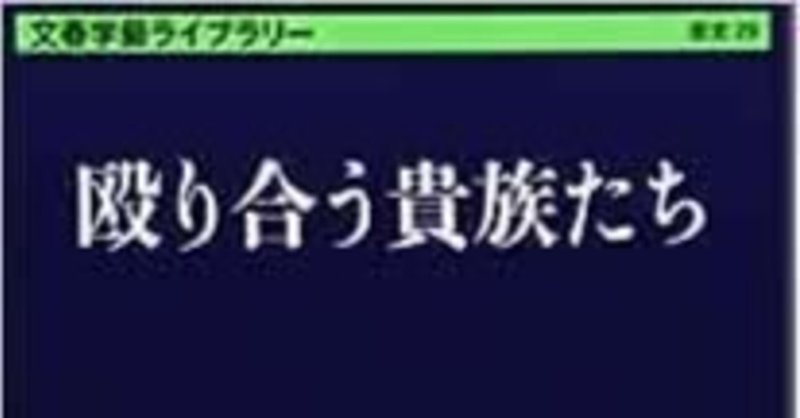
【書評】繁田信一『殴り合う貴族たち』(文春学芸ライブラリー)
平安時代の貴族といえば、和歌を詠んだり宴をしたりと、雅なイメージを持つと思います。しかし、信頼できる史料を紐解いてみると、平安貴族の実像は「雅」とは程遠い、粗暴で野蛮なものでした。
本書で主に引用される史料は、11世紀ごろの公家・藤原実資の日記『小右記』です。藤原道長の「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることの なしと思へば」という歌を記録したことで有名です。
この史料からは、血筋も良く官位も高い貴公子たちが、日常的に暴力に親しんでいたさまが明らかになります。
例えば、藤原兼隆という貴族は、「自分の家に仕える従者を殴り殺す」という驚くべき凶行をしたことが書かれています。
藤原兼房は、自らの従者4人に命じて、別の下級貴族を拉致して集団暴行を加えたといいます。
また、花山法皇の従者と、藤原伊周・隆家兄弟の従者の間で乱闘が起き、花山法皇の従者2名が殺され、首を持ち去られるという血なまぐさい事件も起きています。
「優雅でやんごとない王朝貴族」のイメージは、本書を読めば完全に打ち砕かれるでしょう。本書には触れられていませんが、「小倉百人一首」の編纂で有名な藤原定家も暴力事件を起こしたことがあります。源雅行という貴族の侮辱に激怒し、脂燭(しそく。手持ちの照明具)で相手の顔を殴ったのです。
「王朝貴族」と呼ばれる人たちは、かなりの程度、暴力に親しんでいた――というのが本書の結論です。この事実は、紫式部の傑作『源氏物語』にも関係があるといいます。
『源氏物語』の主人公である光源氏は、人格面でも優れた貴公子です。紫式部の周りにいた現実の貴公子が粗暴だったからこそ、光源氏という「理想化された貴公子」が評判を呼んだのではないか、というのです。
本書を読めば、古文や日本史の授業も退屈せず、面白いものに感じるのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
