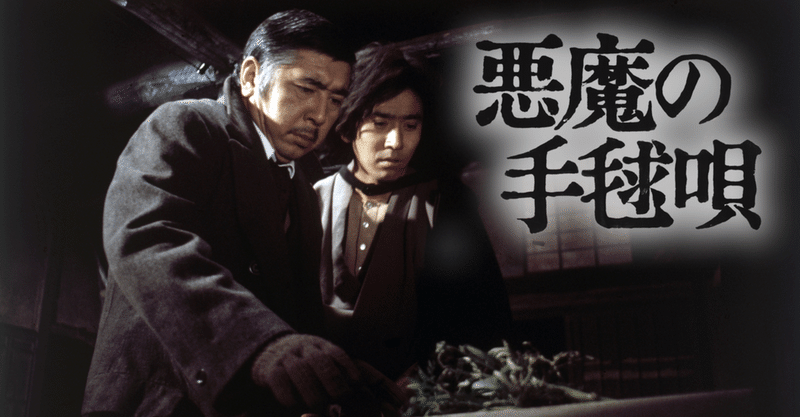
映画感想文 金田一耕助シリーズ 悪魔の手鞠歌以降
前回、金田一耕助シリーズ第1作目『犬神家の一族』の感想文を書いたが、それ以降のシリーズ作品はまとめて一つの感想文として書くことにする。
悪魔の手鞠歌

金田一シリーズ第2作目『悪魔の手鞠歌』。製作は東宝。市川崑と東宝は、1947年頃労働争議で揉めて以来疎遠になっていたが、1977年の『悪魔の手鞠歌』を切っ掛けにようやく和解したようだ。市川崑はもともとは東宝所属の映画監督だったはずなので、これで「元の鞘に収まった」……という状態である。
『悪魔の手鞠歌』のゲスト俳優は若山富三郎。老練の刑事、磯川常次郎を演じる。若い頃に関わって、しかし未解決に終わったある事件をその後20年にわたり追い続けるベテラン刑事である。自力での捜査にも行き詰まりを感じ、そこで知人の金田一耕助を頼ることにした……というところからお話は始まる。
磯川常次郎はそれなりの年齢感のある刑事という役で、渋みがあるのだが、不思議と愛嬌のあるキャラクターだ。とぼけた風合いの金田一耕助と一緒になっていると、どこか愛らしい。手紙を二人で読み上げようとするシーンは、面白くも可愛い場面だ。金田一×磯川コンビが今作だけというの惜しい。
今作も加藤武が立花捜査主任という役柄で登場する。前作『犬神家の一族』と名前こそ違うがほぼ同じ役職で登場し、あの決め台詞もあるし、粉薬を噴き出すあのネタもやってくれる。金田一と顔を合わせたとき、一瞬、お互いに「ん?」という間を置いてから「誰だお前」という台詞が入る。前作『犬神家の一族』と違う世界線なので、金田一は犬神家の事件に遭遇していないことになっているし、加藤武が演じる捜査主任と金田一は初めて会うということになっているが、どうやら別世界線で出会った記憶は頭の片隅にあるようだ。
実は似たような役柄で登場する役者は加藤武だけではなく、『犬神家の一族』で大山神官を演じた大滝秀治は『悪魔の手鞠歌』では近藤医師役で登場する。他にも同じ俳優が登場するので、一覧にしてみよう。

今回『悪魔の手鞠歌』には出演はなかったが、坂口良子や三谷昇といった俳優も、後のシリーズに何度も登場してきている。しかも、キャラクターが持っている役割もほとんど一緒だ。その作品のみに登場する固有キャラクターを別にして、その周辺にいる俳優達は毎回一緒……というのがこのシリーズの特徴だということに、私はここで気付いた。
だから、加藤武は毎回狂言回しの役に立たない刑事で、大滝秀治が物語の背景にある由来を説明してくれて、三木のり平と沼田カズやは毎回愉快な夫婦役で自覚なしにヒントを与えてくれる役割として登場してきてくれる。
「世界線が違う」という設定なので、それぞれが持っている背景が違うし、みんな金田一耕助とは初対面ということになっているが、「俳優の顔」を見れば、それぞれの役回りがわかる……というのがシリーズ全体の仕組みになっている。
(加藤武が演じる刑事は「役に立たない狂言回し」と書いたが、実は一つ、はっきり役に立っているところがある。それは、「推理を間違えること」「容疑者を間違えること」だ。加藤武が演じる刑事が「よしわかった! 犯人は○○だ」といったら、その人物は絶対に犯人ではない。見ている側はそれで容疑者の絞り込みができる……というわけだ)
(もう一つ、後で知ったことなのだが、沼田カズ子は俳優ではなく、スタッフだそうだ。どうりでオープニングクレジットに出てこないわけだ)
それで気付くのだけど、市川崑が『犬神家の一族』で生み出したもの、というのはシリーズ全体を貫き通す「フォーマット」であって、続編を作るに当たり、そのフォーマットを誰の見た目にもわかるように使い回すことでシリーズ全体の一貫性を作っていたというわけだ。そこで出演俳優と役割を一致させて、毎回登場させてくる……というのはなかなかに面白い試みだ。手塚治虫の“スターシステム”……とはちょっと違うが、こういうのもキャラクターの立たせ方の一つではないかと思わされた。
さて、今回の事件も例によって「血の因習」が事件に大きく絡んできている。やはり初見時は人物関係が複雑なので、相当に混乱する。中盤辺りは私も混乱して「どういうことだ?」と疑問ばかりだった。
ありがたいことに、今回も金田一耕助が大雑把な人物相関図を描く場面が挿入され、そこでようやく理解できた……という感じだ。
この血縁関係の複雑さがシリーズの特色だが、映画として観ている間はなかなか難儀する。『犬神家の一族』はまだ関係性をシンプルに見る方法があったが、『悪魔の手鞠歌』はちょっと難しい。
ネタバレを避けて結末の話をすると、とどのつまりは「近親相姦」を避けるために起きた凶行だった……。なのだが、この動機もちょっと疑問で……。だったら、「アンタとあの子は本当はきょうだいだよ」と言えばよかっただけの話では……? という引っ掛かりが残る。それが言えない理由もあるといえばあるのだけど……。殺人に至る狂気じみた心理がそこに感じられないことが引っ掛かる。「アンタとあの子きょうだいだよ」と言うのと、殺人を決行することと、どっちが重いんだ……で殺人を選択しちゃったというのが……。
獄門島

『獄門島』での金田一耕助の役割は、友人に頼まれて獄門島の千光寺住職・了然和尚に鬼頭千万太の訃報を知らせに行くことから始まる。死に際の鬼頭千万太は「妹が狙われている」という言葉を残していた。金田一はそのまま獄門島に逗留し、千万太の3人の妹、月代・雪枝・花子が誰から狙われているのか、また惨事が起きないように見守ろうとする……。
シリーズお馴染みのスター・システムは今回も同様で、加藤武は等々力警部と名前を変えているが、ほぼ同じ役柄で、いつもの台詞に今回も粉薬を吹いてくれる(ちなみに残る3作すべて「等々力」という役名で登場する)。大滝秀治や三木のり平も登場し、1作目の坂口良子も再登場する。今回も全員、違うキャラクターであるが、役回りが一緒である。3作目にもなると「いつもの顔ぶれ」になるので、不思議と安心感がある。
獄門島に入るシーン、島から突き出た山に不穏な雲が被さり、全体が真っ暗なシルエットとなって浮かび上がっている。なんともいえない禍々しさと美しさが同居する画面で、物語の導入部らしいゾクゾク感が画で表現されている。
驚いたのは島を去るシーン、島にかかる光が完全に変わる。明るい光が全体に当たってディテールを浮かび上がらせ、それで島の呪いが解けたことがわかるように描かれている。
アニメであれば絵画だからこういった画作りは容易だが、実写の映画でこういう絵がポンと出てくるところは流石だ。
ただお話はというと少し微妙……。というのも最後の犠牲者が出てから、金田一耕助が事件を解明するまで1時間もかかっている。『犬神家の一族』の時には最後の犠牲者が出る頃には必要な情報の提示がほとんど終わっていて、事件解明まで20分だったことを思うと、『獄門島』の展開はずいぶんゆっくりだった。
今作の場合、最後の犠牲者が出てからはじめて明らかになる情報があまりにも多く、それが「後付け」のように感じられてしまう。犠牲者はおよそ20分おきにポンポンと出て展開していったのに、それからの展開が停滞して感じられ、どうにもバランスが悪く感じられる。
今回も例によって「血の因習」が事件の切っ掛けとなっているのだが、しかしそれほどの“強制力”を感じないというのが引っ掛かる。要するに誰が本家の当主に据えるのか……という話で、ある特定人物を当主にするために残りの候補者を殺していく……というわけだが、この構造だとわざわざ殺さなくてはならない理由が見つからない。いくら友人の頼みとはいえ、なぜ言われたとおり殺人を犯さなければならないのか、その理由が弱く感じる。
『犬神家の一族』には「遺言状」という絶対的なものがあって、子孫たちが強欲ゆえに莫大な遺産を巡って血なまぐさい闘争を始めてしまう……という始まり方で、この構造であれば「血の因習」と「遺言状」「遺産」という強制力があって子孫が殺し合いを演じ、それがあたかも犬神佐兵衛が怨念となってそれぞれの背中を押しているように感じられる。『犬神家の一族』はそこで恐ろしさを感じるストーリーになっていた。『獄門島』にはそういう怖さがない。
それに容疑者にも意外性がない。『犬神家の一族』では莫大な遺産があってみんな遺産が欲しいはずだから、誰もが容疑者候補だった。『獄門島』までくると、登場人物が少ないということもあって、「じゃああの人かな」と簡単にアタリが付けられてしまう。構成の少なさはミステリとしての弱さに感じられる。
それに、繰り返すが今回も「血の因習」が背景にあるのだが、そこまでの強制力を感じないというのが一番の引っ掛かりどころ。よくよく考えると「殺す必要なかったんじゃない?」という気がしてしまう。『犬神家の一族』のような「血の呪い」めいたものを感じさせてくれないのが弱い。
というかこのシリーズ、先代がお盛んすぎる……。次から次へと子供を産んで、それが後々禍根を残すという展開になっている。そもそもの先代の性欲の強さが一番悪いんじゃないか……。いつものパターンとして「実はあの子も先代の子で……」と後々に明らかになるのだが、「おいおい、あのおっさん結局何人孕ましたんだよ」と思うと同時に「またこの展開か」とも思ってしまう。子供世代に禍根を残すべきではないな。
『獄門島』の最後、坂口良子に「どこへ帰るんですか」と尋ねられて金田一耕助は曖昧な返事をする。
どこからやって来たかわからず、どこへ帰るかもわからない人物……。市川崑監督は金田一耕助をそのように捉えていたそうだ。どこからともなく現れて、事件を解決することなく、ただ見守る存在……。市川崑監督は、金田一耕助を「天使」と語る。金田一耕助=天使というイメージがいつできあがったがわからないが、『獄門島』の時には「この世ならざる者」にしようという意思が感じられた。
女王蜂
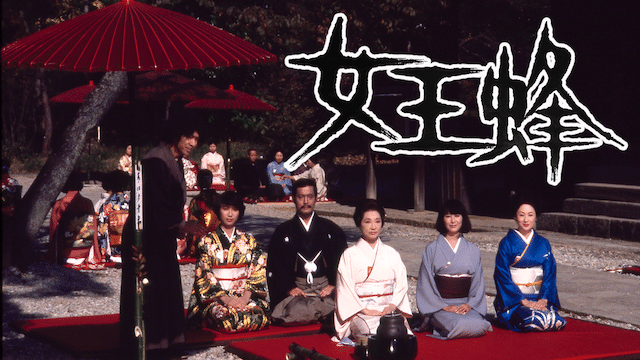
『犬神家の一族』の監督を引き受けた市川崑は、1作で終わるつもりだった。もともとミステリ好きだった市川崑は、どうしたら「映画のミステリ」は成立するのかその以前から考えていたらしく、そのかねてから考えていたものを注ぎ込んで作り上げたものが『犬神家の一族』だった。
1作で終わるつもりだった映画は、大ヒットして2作目、3作目と作ることになってしまう。市川崑は作家性の強い映画監督であると同時に、請われたら何でも引き受ける職業映画監督でもあった。1作目2作目はその以前から「考えていたもの」を映画に当てはめて、それがうまくいってヒットとなった。
しかしそこからが迷走と苦悩が始まる。
いくらシリーズ作品とはいえ、同じ作品を作るわけには行かない。どうやったら違うものになるか、どうやったら新しい面白さが生まれるのか……。その答えを出さないままに映画制作は進行してしまった。
この時代ではシリーズ映画は年1本の制作。時間は待ってくれない。現場はどんどん進行していく……。
という状況だった「金田一耕助」シリーズ。4作目『女王蜂』まで来ると、良いところは何もない。お話がぼやーっと流れていく。長い説明台詞がたくさんあるが、このシリーズは関係性が複雑なので、途中で何がなんだかわからなくなってくる。いったい何について説明されているのかわからないまま、ただただ映像が展開していく。頭が追いついていけない。
こういった作品は2回観ればいいのだけど、ちょっと急いでの視聴なのでそれもできない。
それでも編集で面白いことをやっているのはわかる。映画のちょうど半ば1時間ほどのところで2つの場面が同時に語りが進行する場面がある。金田一と加納弁護士の語りと、銀三と秀子が語る場面だ。通常なら一方のシーンが終わったら、その次のシーンが……と編集するところを、サブリミナルのようにもう一方のカットをちらちらと入れる。これで、二人の語っていることが、少しずつリンクしているような印象が感じられる。
そこから続く野点のシーンでは、惨劇が起きた後、画面が6つに分割し、その瞬間に起きたそれぞれの反応を同時に描いていく。後のテレビドラマや映画で使われるようになった手法を、早くも取り入れている。
映像もいい。和室の落ち着いた空間を、美しい映像でうまく捉えている。壮麗な屋敷を映画的な舞台としてうまく描いている。
ただ、お話が面白くない。今回も次々と犠牲者が出てしまう……という展開だが、その犠牲者に存在感がなさすぎて、殺戮シーンが印象に残らない。印象に残らないから、物語的なフックにもなっているような気がしない。
あまり面白くなった『女王蜂』だが、それでも配給収入はなかなか高い。7億9600万円。第1作目『犬神家の一族』の半分ほどだが、それ以後の金田一シリーズとしてはかなりいい成績だ。
というのも『犬神家の一族』からは高峰三枝子が出演し、『悪魔の手鞠歌』からは岸惠子が出演し、『獄門島』からは司葉子が出演している。これにすでに大ベテランとしての存在感を持つ仲代達矢も出演。それにカネボウとのタイアップで広告に力を入れて、作品と広告が一丸となって作り上げた映画で、その成果は充分に出た。
でも映画が面白いかはどうかはかなり微妙。特に事件が起きない場面がえんえん続くし、最後の事件が終わってからすべて解明されるまで1時間……。ひたすら間延びした時間を体験させられる。
『犬神家の一族』で作り上げたフォーマットは4作目まで来る頃には、もうすっかり擦り切っていた。かといってここからさらに新しい試みに挑戦するほどの余裕もない。金田一シリーズもそろそろ終わりかな……という気にさせる作品だった。
病院坂の首縊りの家

金田一シリーズの最後は、こんな始まり方だ。
ある夜、そろそろ店も閉めようかという時間に、若い女性が訪ねてくる。近くの屋敷で結婚記念写真を撮りたい。女は名前を名乗らず、それだけ言って去ってしまう。
カメラマンが女の指定した場所へ行くと、そこは廃墟だった。窓は割れているし、扉の立て付けは悪いし、壁も床もボロボロ。でも上等な絨毯が敷かれているし、奥の部屋へ案内されると金屏風と花婿衣装の男と花嫁衣装の女がいた。
後日、写真ができあがったので届けに行くと、屋敷はやはり廃墟。先日のような絨毯も金屏風もない。奥の部屋へ入っていくと……花婿の生首が天井から吊り下げられていた。
……という少し怪談風のお話から始まる今作。なかなか惹きつけられる導入部だった。
『病院坂の首くくりの家』の特色は、金田一耕助に助手ができること。草刈正雄が演じる日夏黙太郎という若者で、金田一とは対照的に元気で行動的な若者だ。金田一耕助は毎回のことだが他の誰にもなにも言わず、ふらっと姿を消し、戻ってくると何もかも知っている状態になっていることがある。今作は黙太郎という登場人物がいるおかげで、その合間を埋めてくれる。視聴者と同じく、事件の謎がわからないが、とりあえず金田一に指示されるとおり調べていき、徐々に謎が明らかになっていくという構造となっている。
ただ、対照的に金田一の存在感が薄れていく。もともと寡黙に事件の調査をする人物であったから、行動的な黙太郎という人物を前面に置いてしまうと、極端に影が薄くなってしまう。もともと金田一はあの時代でも少し古い格好だったから、そのせいもあってより背景にかすんでしまう印象があった。
お話はというと、相変わらず親世代が残した大きな問題があって、子供世代がそれに振り回されていく……という内容だ。初期シリーズほど「血の因習」は濃くはないが、親世代に対する怒りと恨みが物語の動機となっている。
ただ、そのお話があまり面白くないというのが……。おそらく原作が悪いとかそういうものではなく、うまくまとめる間もなく撮影がスタートしてしまった……そういう感じに思えてしまった。
この時代のシリーズ映画は1年おきに次々と……だったから、こういうのは仕方がなかったのかも知れない。
5作目まで来ると、『犬神家の一族』のような精彩さは完全に失われてしまっている。『犬神家の一族』で作り上げたフォーマットは最後まで残り続け、加藤武演じる狂言回しの等々力刑事は登場するし、大滝秀治演じる加納巡査(4作目では「加納弁護士」であった)は過去に起きた事件について朗々と語ってくれるし、三木のり平も登場する。でもこれらの登場人物は『犬神家の一族』の時ほど緊張感を持った構成の中に登場してこない。中心的な物語の外縁にちらちらといるだけで、そこにある物語に参加しているような感じがない。物語に対して、フォーマットが浮いてしまっているような印象になってしまっている。むしろ物語の邪魔とさえ感じてしまう。
かといって他のシリーズと同じく「ダメ映画」というわけではなくて、もう少し構想に時間をかけてくれたらな……と。シナリオを練り込む時間をあと1年おいたら、どれだけ作品が変わっていただろう。ヒットシリーズは1年おきに次々と、というのがこの時代の慣習だったからそれは仕方ない。
作品を見ていて、どことなく作品全体がフェードアウトしていくように終わっていくように思えたから、それが寂しく感じる。「ああ、終わりだな」という寂しさだけが残る、そんな作品だった。
冒頭、「小説家」という老人が登場してくる。ずいぶん棒読み演技をする人だな……と思ったら原作者・横溝正史だった。横溝正史は映画『犬神家の一族』でようやくスポットライトが当てられた遅咲きの作家だと聞いていたが、この映画の頃はもうずいぶんな年だった。
でもこの後も次々と作品を発表していくので、横溝正史作品全体を見るとまだ「中期」の作家なのだそうだ。『犬神家の一族』でようやく「始まった」作家だったのだ。人間、いつどんなときにスポットライトが当てられるかわからない。
まとめ
いろいろ書いたものの、なんだかんだで楽しんだ『金田一シリーズ』5作品。ただ間違いなく傑作だった『犬神家の一族』の後、作品が少しずつフェードアウトしていくような印象だったことが残念だった。
問題は、明らかな練り込み不足。もともと「1作で終わり」と思ってそこにすべてを注いだはずだったのに、映画会社の要請で次々と撮ることになってしまった。市川崑監督は仕事として請われたら何でも引き受ける職業監督だったから、引き受けていくうちにどんどん作品から精彩さを失っていく。作品に対する情熱は失っていくし、構成から緊張感を失っていくし……。初期作品にあった、笑いとシリアスといった心地良い緊張感は後半シリーズにはなかった。後半2作は、何を映画の核にするか、物語の中心に置くか、そこに見定めないまま、撮影が進行していったように感じられてしまった。
でもやっぱり嫌いなシリーズではないんだ。石坂浩二演じる金田一耕助のチャーミングな存在感。加藤武の茶目っ気のある芝居。大滝秀治や三木のり平、沼田カズ子、坂口良子……定番のキャラクターが役名こそ違うものの、いつも同じ役割を与えられて出てくる。
映画でなじみある顔が出てくるとなんとなく嬉しくなってしまう。シリーズ映画の醍醐味だし、そういうお馴染みの人で作り上げていく面白さというものがあった。毎回同じフォーマットで少しずつ違うことをする「戦隊もの」シリーズを追いかけていくような感覚と言えばいいだろうか。そんなシリーズを追いかけていくと、愛情ばかりが大きくなっていく。
ただ映画自体は初期の精彩さを失っていき、すーっとフェードアウトしていく。1作目『犬神家の一族』が面白かっただけに残念な気がした。
シリーズを見ていって印象的に思えたのは、金田一耕助の寂しげな表情だった。金田一耕助は、毎回事件が起きてからその渦中に入っていき、次なる事件を止めようと解決を目指す。事件の背後を調べ、関係していた人々から話を聞き……そうしているうちに、どんどん犠牲者が出てくる。金田一耕助はどんどん焦燥感に駆られていく。
金田一耕助は最終的な事件を止めることができず、最後の犠牲者が出るまでを見届けることになる。その時の反省と後悔に満ちた顔と、しょんぼりと落ちた肩が忘れられない。
この辺りについて、石坂浩二さんはインタビューでこう語っている。
「犯人は既に全てを悟ってしまっている。さらに死んでしまう。死ぬのだって、金田一は「しまった」なんて言っているけれども、そうなることをあらかじめ知っているんじゃないかなと僕は思っているんです。あれは彼女が死なないと解決がつかないんです。変に警察ざたになってみても意味のないことですから」(市川崑と『犬神家の一族』P168)
市川崑監督は金田一耕助の属性を「天使」だと考えていた。だから俗世にまつわるできごとには手を下さない。あくまでも見ているだけ。見守り、見届け、終わったらどこかへ姿を消していく。シリーズを通して金田一耕助は事件を「解決」することはなく、ただ「解説」するだけだという。
金田一シリーズは毎回、犯人の自殺で幕を閉じてしまう。金田一耕助は死体として浮かび上がった当事者の姿を見て、毎回「しまった!」と後悔の念を浮かべる。でも金田一耕助はおそらくそうなることがわかっていた。未来を見通すことができるから。いや、もしかすると“2周目”なのかも知れない。でも最後の最後に油断があって、当事者を死なせてしまう(1周目と状況が変わったのかも知れない)。金田一耕助が事件に関わるのは、人から頼まれたり依頼されたからという以上に、犯人がそれ以上間違いを犯さないため、そして犯人が自分のしでかしたことに耐えがたくなって自殺するという結末を防ぐためではないか。しかしそれを防げず、毎回、最後にはしょんぼりした背中を見せて去って行く。事件が解決して、まわりのみんなが解放された気分になるのに、金田一だけがしょんぼりして去って行く。
金田一耕助は事件を止めたいのに、どう関わっても事件を「見守る」ことしかできない。属性が「探偵」ではなく「天使」だから、どんなに鮮やかに推理を巡らしても、人が死んでいくこと自体は防ぐことはできないのだ。
金田一耕助は最後にどこかへ去ってしまうのだが、どこかそういう自分の属性に対する「諦念」と「落胆」があるように思えてしまう。そして最後までその諦念と落胆が解消されないままに終わる。
その後、2006年『犬神家の一族』は市川崑監督の手によってリメイクされる。でもやはり同じようにはならない。カメラ技術もあがったし、その周辺の技術も上がったから、色彩も音声もなにもかもクリアになっている。でも、まずいって戦後間もない昭和20年代の風景と気風は、現代の人では再現できない。空気感も違えば文化観も違うし、人の喋り方も違う。
金田一耕助というキャラクターは昭和20年代にしてすでに「古い」。あの時代にあんな格好の男はいない。それをあえて登場させるところで、金田一耕助というキャラクター感が出てくる。でもああいった風貌のキャラクターは戦後間もないあの時期にしか成立し得ない。セットや衣装を作り込めば……という話ではなく、年代が違うから同じようにすればするほど違和感が出てくる。
だから金田一シリーズはこの時代だけでしかあり得ない作品だった。後になって『犬神家の一族』や『悪魔の手鞠歌』が制作できるか? 作ったところできっと別モノになってしまう。ハードのスペックが上がっているので高精細な画面は撮れるけど、同じようにはならない。まずあの町並みが現代のどこにもないし(CGで作るしかない)、あの時代の立ち振る舞いができる人もいない(こちらはいくらCGが進化しても無理)。同じようにしようとしても、どこか違う作品になるはずだ。
だから金田一耕助が映像となって姿を現したのは、1970年代に制作されたこの映画だけでしかない。そう考えると、何か時代の狭間みたいなところで、すっと現れてすっと消えていった……。そんな不思議な男のように感じられる。そうすると、金田一耕助はどこからやってきて、どこへ去って行くかわからない、「天使だ」という説明に納得することができる。
とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。
