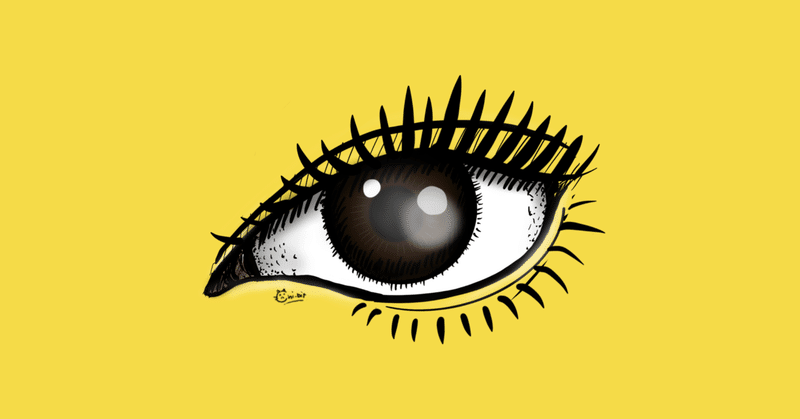
Photo by
chi_bit_
発達障害の診断名やタイプ分けではなく、相手そのものを見る ストラテラ服用日記877日目
昨日「潜伏型」ASDという単語を見た。なるほど言い得て妙というか、そういう気質を持っている人はいるなと思うし、分類するなら私もそこに入るかも?とも思う。
よくある分類では「尊大型」「孤立型」「受動型」「積極奇異型」と言われているが、この「潜伏型」は基本的には「受動型」に内包されるかなと思います。(一部「孤立型」も含まれるかも?)
自分のタイプを知るという意味ではこういった傾向の特徴があって、自分の性格がどんなタイプになるのか、メタ認知・自己認知の助けにするためにもこういう傾向を知ることは意味があると思います。
しかしながら、支援したり対話するときはこういったタイプ分けは邪魔になる。このNOTEでも何度も行ってきたが、相手を知るためにはこういったタイプ分けは余計な先入観・バイアスのもとになる。
良い支援・いい対話をするためには、そういった先入観・バイアスをどれだけ外して、その人そのものを見れるかがとても重要になる。
逆に言うと、相手そのものを見ることが、支援や対話の第一歩だと言える。
相手を見るときは、ADHDとかASDという診断名も一度まっさらにして相対する。そこから良い支援・良い対話が始まる。
先入観やバイアスが入っているということは、ジャッジしているということになります。支援や対話の前にジャッジしてしまうと、歪んで相手を見てしまう。
立場やシチュエーションによりますが、診断名やタイプ分けをしていいときとしてはいけないときを適切に判断して、自己認知やコミュニケーションを深めていけるといいなと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
