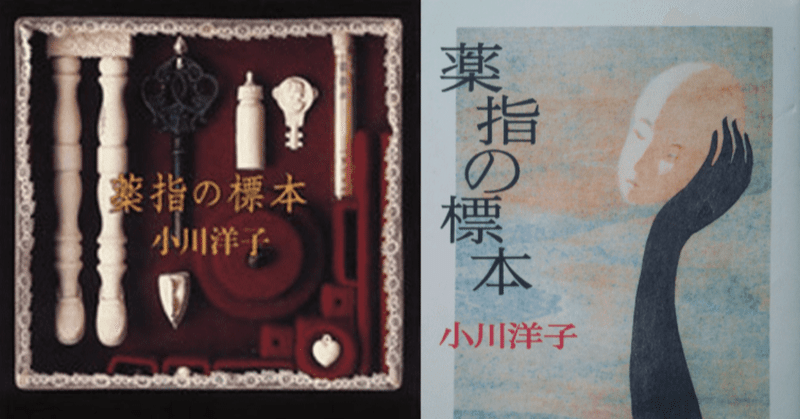
📖小川洋子『薬指の標本』読書メモ【ネタバレ有】
今日は小川洋子『薬指の標本』の感想をまとめたい。といっても、ツイートを元手にしたメモ程度である。ネタバレがあるのでご注意を!
薬指の標本について
”物との交流”――事故によって切り離された語り手の薬指は、標本となったことで、記憶となり他者となる。そして懐かしさを帯びていく。それは決して朽ちることでもなければ、腐ることでもなく、錆びることでもない。物との対話によって生まれる職人芸を見た。
「物との交流」は本作に登場するキーワードである。〈語り手〉の女性は、以前にサイダー工場に勤めていた。が、ある日事故によって薬指を切断してしまい、標本室に勤めることとなる。
標本技術士と〈語り手〉の関係性
標本技術士に素敵な靴を贈られた〈語り手〉。足にぴったりと馴染む靴は、呪縛を秘めた危険な贈り物でもあった。靴磨き職人の忠告も傾聴した上で、〈語り手〉は履き続けると決める。靴の記号ではなく、靴自体が官能性を帯びていくのは不思議な話だ。
標本技術士から贈られた靴。このアイテムが曲者である。〈語り手〉の女性の足にピッタリとはまる靴には不思議な官能性がある。これは谷崎的なフェティシズムではない。つまり靴から連想されるナオミの脚のような官能性とは異なる。靴そのものが官能的なのだ。これが面白い。
本作の設定の面白さ
四階建てのコンクリート建築の中にある標本室。語り手の前の職場のサイダー工場。保存液。試験管。ラベル。標本。並べてみると無機質に映る設定が、しっとりとした文体の中に違和感なく溶け込んでいる。無機物も人工物もどこか活き活きとしているように見えるのだ。
安部公房作品や大江健三郎『死者の奢り』になってしまいそうな設定も、著者の手にかかれば全く異なった世界になってしまう。人間と物質の世界の垣根をうまく融かして包み込んでしまう著者のまなざしは、本当に不思議なものだと感じる。
舞台設定を取り出してみると、思いのほか無骨である。
標本室は決して木造の洋館の中にあるのではない。博物館の分館のような場所でもない。ただ四階建てのコンクリート建築の一室にある。
〈語り手〉の前職がサイダー工場であるのも興味深い。大量生産工場特有の拭いがたい無機質さがあるはずなのに、いったん作品に入ってしまうと「サーダ―工場」は違和感なく溶け込んでしまう。
また、保存液、試験管、ラベル、標本。これらは今風に言えばデータベースを作るためのものである。思い出の品々は瓶の中に閉じ込められ、ラベルが貼られ、番号が付与される。一連の動作はまったく日常的で機械的なものなのに、そこには情緒的なものがある。
文体のすごみと著者のまなざし
同じ設定で私が書いたとしても、こんな静謐で穏やかな文章は書けないだろう。設定に引っ張られて、安部公房作品や大江健三郎『死者の奢り』に似た作品を書きたくなってしまう。
では、小川洋子の場合、なぜそうはならないのか?
たぶん、「物との交流」がキーワードになるのだろう。著者のまなざしは、人間と物質の垣根を融かして、ひとつの世界に包み込んでしまう。そういう誰にも真似のできない能力があるのだと思う。
これが著者が持っている文体のすごみなのかもしれない。
平素よりサポートを頂き、ありがとうございます。
