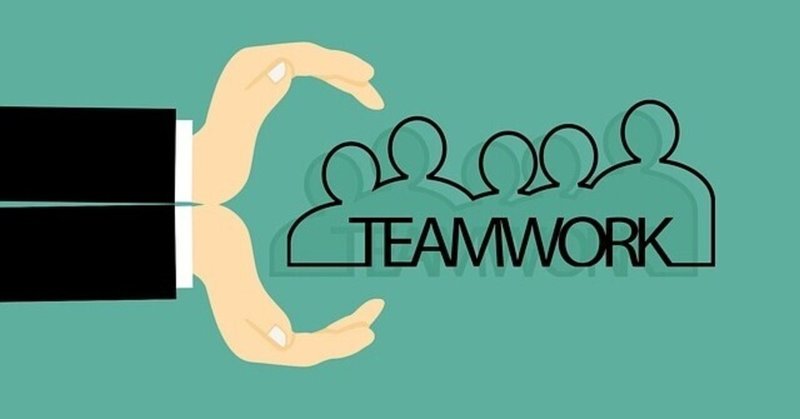
「神の経営」を学ぶ
column vol.526
当社は1月6日からスタートということで明日までが冬休みなのですが、やはり三が日過ぎるとお付き合いの企業さんからメールが届き始めており、気持ちの上では営業モードに切り替わっていきます。
ということで、今日明日はアイドリングも含めて仕事について語りたいと思います。
副社長になって丸3年が経とうとしているのですが、これまでは何となく初心者マークで許されていた部分もありました。
しかし、さすがに4期目となる今年は一皮剥けた感を出さねばと勝手にプレッシャーを感じております…。
そこで、賢人から学ぶべく、今日は〝新・経営の神様〟の呼び声高い稲盛和夫さん(京セラ名誉会長)のお知恵を拝借させていただきたいと思います。
稲盛さんとは言えば「盛和塾」。
「心を高め、会社業績を伸ばして従業員を幸せにすることが経営者の使命である」
という美しき経営哲学を学びに、世界各地から塾生が集まり、36年の活動を経て、国内56塾、海外48塾、塾生数は約15,000名に。
2019年末に閉塾いたしましたが、私を含めて多くのビジネスパーソンが書籍などを通して多くのことを学ぼうとしております。
そこで、今日は「リーダーとしての決断」と「人事評価」にスポットを当て、話を進めたいと思います。
なぜ「利他主義」が必要か?
稲盛イズムの本質は「利他主義」にあると思います。
「京セラフィロソフィ」では「自分を犠牲にしても他の人を助けてあげようとする心が利他の心だ」と定義しています。
〈PRESIDENT Online / 2021年12月31日〉
少し補足すると、結局は利他を極めると、自分に還ってくるということになります。つまり、世のため、人のためが回り回って自分のためになるのです。
しかし、人間は「まず自分のため」に判断してしまう生き物です。
これは人間(生物)に備わった本能で、基本的に「自分を一番」に考えないと生存できず、人類は滅んでしまうからです。
それはどの生物も同じで、ライオンが草食動物に対して「…この動物にも家族があって…」と狩を躊躇したら飢え死にしてしまいます。
ちなみに、人間は幼ければ幼いほど、自分勝手で我がままであるようにつくられています。
それも生存のための本能で、もしも赤ちゃんが「最近、お母さんは睡眠不足だし、お腹が空いたけど夜泣きせずに我慢するか…」と遠慮したら命が危ないのです。
つまり、「生存」を優先するために「我がまま」であるのです。
逆に言えば、大人になっても我がままな人は、生物的には「子どもから成長できていない」か「『このままだと人生終わる』といったような大きな不安感を抱いている」など、不安定な人と言えます
つまり、短期的視点で言えば、「利己的」であることは必須で、セミのように短い寿命だとしたら、それだけで良いのかもしれません。
しかし、人間の人生は長い。
そして、高度な知能を持った社会性動物であることから、利己的な人は長い年月の中で社会的に淘汰されてしまうのです…。
社会の輪と繋がっているためには、相互に尊重し合い、互いに貢献する「利他主義」が必須。
中・長期的な視点で見ると、優先すべきは「利他主義」ということになります。
だからこそSDGsにも取り組まないといけなく、「誰もが取り残されない社会を実現することが、自分も生存できる未来」というわけですね。
必ず成功する「判断の方程式」とは?
もちろん、ストレスフルな日常生活の中で、なかなか利他的に判断することは難しくもあります。
一方、職位が上がれば上がるほど、関係する人は増え、一つ一つの判断が重要となり、利他の意識が求められます。
そこで、稲盛さんはリーダーは「直感で判断してはいけない」と語ります。
「直感的に考えると、自分に都合がいいかどうかで判断してしまい、巡り巡って損をする」
ということです。
よく「良い人(優しい人)が好き」と言う方がいますが、生物学的に見ると「自分にとって都合の『良い人』(自分にとって特別優しい人)」である可能性が高いのです。
短期的にはそれで良いのかもしれませんが、相手の熱が冷めると今までの優しさが受けられなくなる可能性があります。
ビジネスも同じで、何か物事を決めない状況で自分が賛成する案は、大抵は組織にとってというよりも「自分にとって良いもの」であることが多い。
それぐらい人間は本能(生存欲求)に支配されています。
だからこそ「相手の立場で考える」。
例えば、世間の相場を知らないお客さまがいて、あるものを相場よりも高い値段で買うと仰った時、『相手がそれで良いと言っているから』と判断し、その値段で売るというケースがあったとします。
その時は、お客さまは満足されて帰るかもしれません。そして、それによって売上がつき自社の利益にもなりました。
しかしその後、そのお客さまが本当の相場を知ったらどうでしょうか?
その方は二度と自社で買い物をしないばかりか、周りに自社の悪評を広めるかもしれません。特にSNS時代の今日は怖いですね…。
短期的に見れば「得」ですが、中・長期的に見れば「損」。
この話の典型的な例でしょう。
私は歳を重ねるたびに、積み重ねてきた「利他」が影響するのが人生だと思っています。
時は100年人生時代です。
そう考えると、リーダーでなくても「相手の立場で物事を考えること」は重要ですね。
「成果主義ではみんなやる気を失ってしまう」
もう一つは「人事評価」についてです。
稲盛さんは「社員の評価ほど難しいことはない」と語っておられます。
〈PRESIDENT Online / 2021年12月29日〉
そして、成果主義に対してこのようなことを指摘されています。
「たとえ目標を達成できなくても、必死で頑張った人は頑張ったなりの評価をしてあげないと、後々、誰も頑張らないようになる。だから成果主義ではうまくいかない」
よく「公平なルールをつくれば、みんな納得する」と意見する人もいます。かつて私もそうでした。
しかし、「公平なルール」だけでは上手くいかないことを過去に痛感しています。
例えば、売上目標にこれ以上ないぐらい努力したのに達成できなかった人がいたとします。成果主義なら不合格の烙印を押されてしまいます。
ただ…どうでしょう…?
仕事の成果というのは一人の努力だけでどうなるものでもなく、クライアントや消費者、チームメンバー、競合関係、景気などなど、さまざまな要因が重なりあって初めて生まれるものです。
そして、人間は肯定され、評価され、本当の意味で頑張れる生き物です。
稲盛さんは
「これはもう理屈通りにはいきません。成果主義で、『業績が上がればボーナスを出します、ダメだったら出しません』というのは簡単なように見えますが、大企業も含めて全部うまくいっていません。成果主義ではみんながやる気を失ってしまうのです」
と語っています。
確かに「公平なルール」により不満を言われなくなるかもしれません。しかし、企業の活力は失われてしまう可能性が高い。
その状況を望む経営者はなかなかいないでしょう。
だからこそ、稲盛さんはこのように続けます。
人を評価するというのは、結局は社長が組織の中に入っていって、会合なんかにもすべて出ていって、何百人という人を心血を注いで見ていかなければならないのです。
と、人事評価は答えのない「永遠の課題」であると結論づけています。
もちろん、公平なルールづくりは目指しながらも、それだけに頼らず、一人一人の頑張りとやる気に向き合い、ルール以外の要素も包括していく姿勢が必要だということですね。
実は私、基本的にはあまり緊張しないタイプなのですが、評価会の時は心臓が終始バクバクしています。
社員を評価することは本当に怖いことで、いつも社員一人一人にちゃんと向き合えているか不安でしょうがないのです。
特にリモートワークにより、不確かなことが増えたことも否めません。
とはいえ、年が明けると年度末が見えてきます。下期の評価が迫ってきました。
稲盛さんですら、答えがなくて難しいと仰っているのだから、自分の心臓がバクバクするのは当然だと冷静さを持ち、的確な評価ができるようにベストを尽くしたい。
そんなことを改めて思った神のお言葉でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
