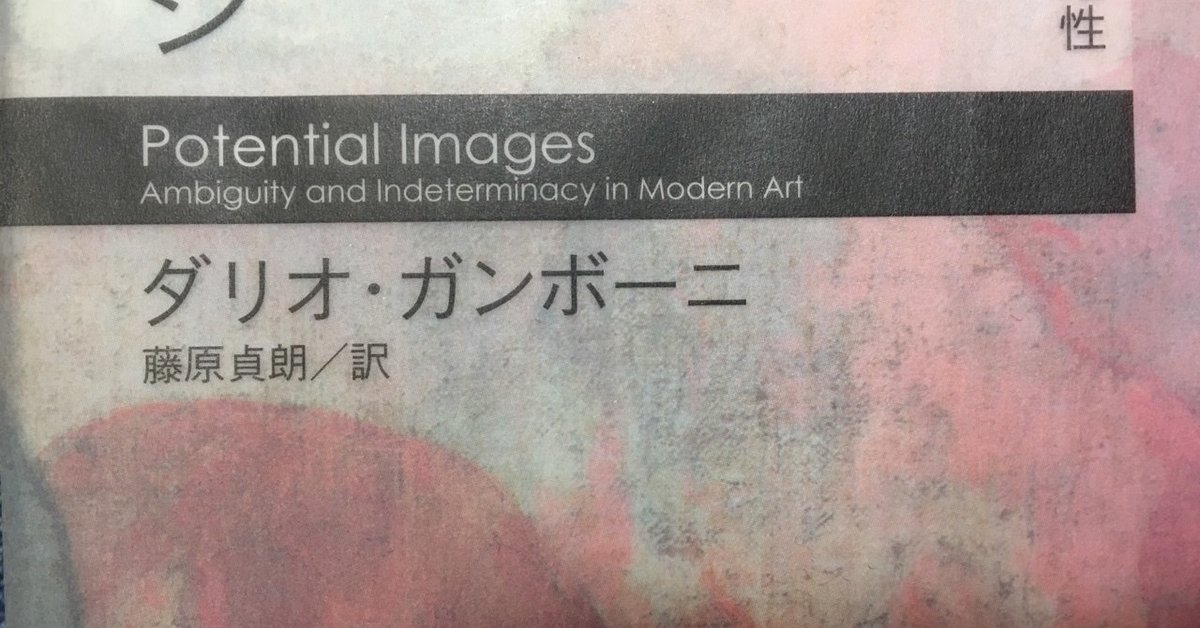
潜在的イメージ/ダリオ・ガンボーニ
「作品にとっての名誉も、作品の評価も、作品の寿命も、すべて私たちの一存で決まる」と女神は言った。
少し前に紹介した20世紀初頭のフランスの作家シャルル・ペギーの『クリオ』の中で、主人公である歴史を司る女神で、ムーサ9柱の1人、クリオの言葉だ。クリオはそのあと、こう続ける。
「たかが評価とも思うかもしれないけど、作品をめぐる評価は、作品が存在することそれ自体に等しいから、決して軽視すべきではない」と。
クリオが言及するのは文学作品のことだけど、文学作品に限らず、美術でも音楽でも、作品の価値、存在理由は作家自体のみによって決まるのではなく、それを鑑賞し評価する人たちによっても決まる。
その意味で「私たちの手に落ち、私たちに世話されることで、私たちの手中にあるという、たったそれだけのことで、作品には、いつまでも完成にいたることのない成就が与えられる」という女神の言葉は、作品に限らず、人間にとっての「意味」や「価値」全般に関わるものであることに気づく。
本書が主題とする「潜在的イメージ」とは、「観る者の精神状態」に関わるイメージ、作者の意図に呼応しながらも、観る者の介在によってはじめて完全に存在しうるイメージのことである。こうしたイメージは一般的に曖昧で、不確定的で、多義的である。
と、「モダン・アートの曖昧性と不確定性」という副題のついた『潜在的イメージ』で、著者のダリオ・ガンボーニは言っているが、このことに関しても、「曖昧で、不確定的で、多義的である」のは何も、この本で扱われる潜在的イメージと感じられる作品のみではないと思う。
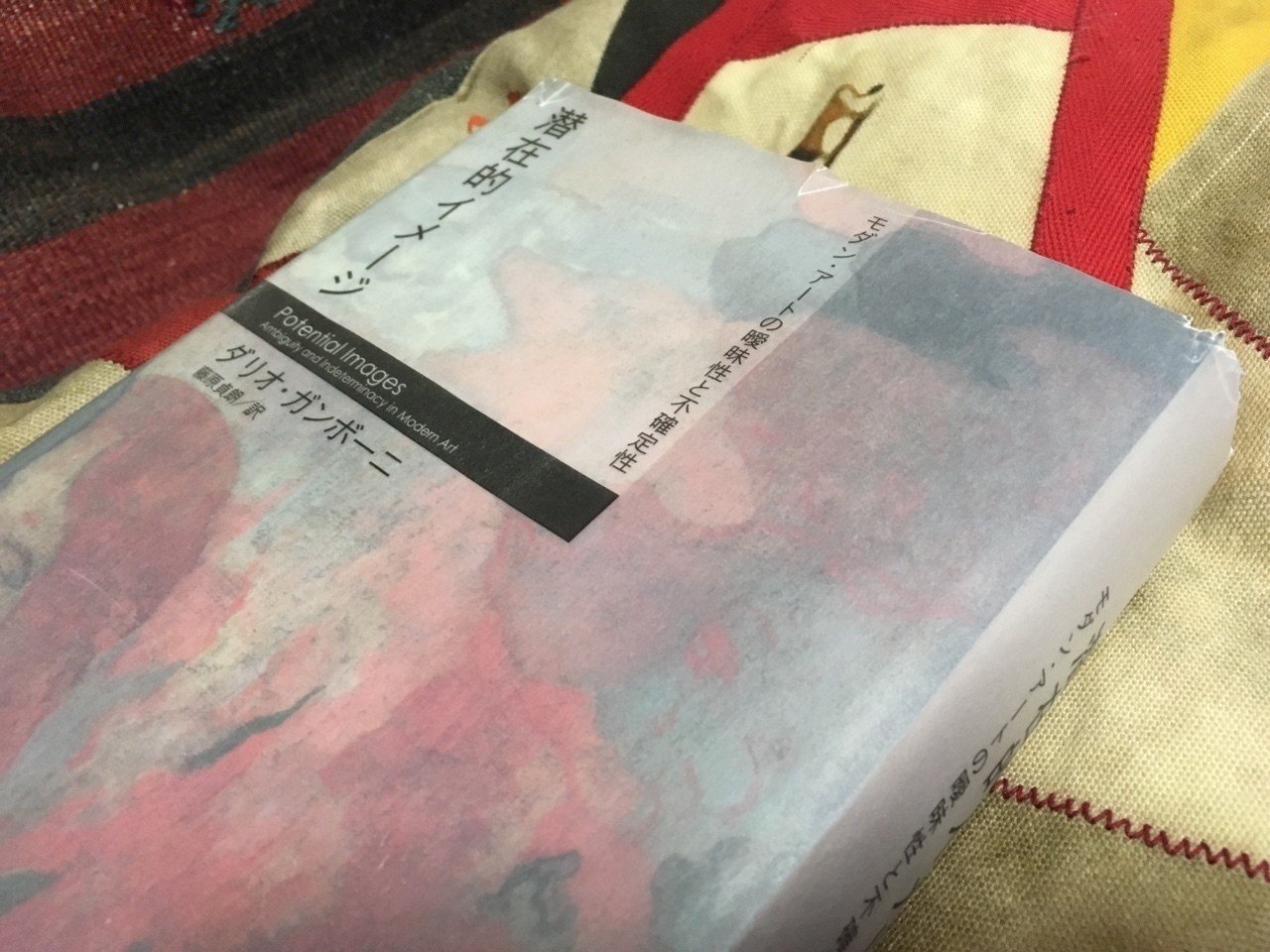
どんなに具体的な図像や具体的な物語や歴史的なシーンが描かれた絵画であろうと、女神クリオが言うように「私たちの手に落ち、私たちに世話されることで、私たちの手中にあるという、たったそれだけのことで、作品には、いつまでも完成にいたることのない成就が与えられる」。
そして、いつまでも未完成であるからこそ、どれも「曖昧で、不確定的で、多義的である」作品としてしかありえない。それは芸術作品のみならず、あらゆる人間の活動がそうした「曖昧で、不確定的で、多義的である」と思うのだ。
潜在的なイメージは抽象画に限らない
さて、2段組で500ページを超える物量のある、このガンボーニの本を読んだのは実は、1年半くらい前のことだ。
それをいまさら紹介してみようと思ったのは、意味や価値というものについての責任の大部分が情報の発信側や社会といったものの側にのみあるのではなく、他でもない個々の情報の受け手の側にそれ以上の大きさで委ねられているのだということを、この誰もが何がしかの声をあげる手段をもった環境だからこそ考えてみたかったからである。
本書でガンボーニは「潜在的イメージ」をテーマに、おもに19世紀後半から20世紀にかけての絵画における、具象から離れた表現の見られる絵画を扱っている。
具象から離れたといっても、本書で扱われるのは必ずしも抽象絵画だけではない。
より具体的なイメージを描いた絵画、例えば、ギュスターヴ・クールベが描いたリアリズムの風景画、けれど、写実的すぎるがゆえに、かえって何が描かれているのか混乱させられるようなイメージも含まれる。
というわけで、クールベは僕自身好きな画家でもあるので、まずクールベからはじめてみたい。
クールベが写実的に岩を描いた風景は見ているとゲシュタルト崩壊を起こしたかのように、岩に見えなくなってくる。

何か別のもの(例えば何人もの男の横顔)に見えそうになったかと思えば、また再び岩のイメージとして再生しようとしたりする。
もちろん、絵そのものの図像は止まっている。にも関わらず、目の前の画像に対するイメージはゆらゆらと定まることなくゆらぎ続ける感じがするのだ。
ここから考えてみてわかるのは、そもそも「潜在的」という反対語としての「顕在的」という語で表せそうなイメージも、本当にそれほど何らかのイメージが顕在化されたものかはあやしいということだろう。
そこに描かれた図像そのものも何か具体的なものを実際に描いているというより、そう見えるような文脈に従うようなルールに基づいて描いているから、そう見られる確率が高くなっているというだけではないかと思われる。
おそらく、何を描いているかが一見わかりやすく思える絵画ほど、画家は何か具体的なものをそのまま描いているというのではないのだろう。
むしろ、絵そのものの外の領域にある既知の文脈とのリンクをうまくつなげるようなものを描くことで、そこに何が描かれているかを「理解」できるようにしているのだと言ってよいのでないか。
イメージが顕在的になるのは、外的な理由から
クールベの岩の絵同様に、絵というものは、見れば見るほどゲシュタルト崩壊が起きてしまう。そんな絵というものをできるだけ見ないでいいよう、絵そのものというより外部とのリンクに目を背けさせるのが、何が描かれているかが顕在的になっている絵ではないかと疑ってみることができる。
では、どうすれば、絵そのものをそれほど見られずに、見る者に何がしかのイメージを顕在化して見せることができるだろうか?
その具体的な方法として多くのケースで用いられてきたのが、「描かれるべきものを描く」ということなのだろう。
中世においては宗教画、ルネサンス以降もそれに加えて、古典の神話を描いた歴史画が主要なジャンルであった。そうした絵においては描くべきイメージが描かれる以前に決まっている。画家は自分の絵がそうした既存の物語を描いているのだと気づかせさえすれば良い。
そのためには、絵の外ですでに成立しているルールを模写することが求められる。それは記号を使うこと、言葉を用いることに近いだろう。
絵の中に、クピドを伴った女性が描かれていればウェヌスだし、フクロウを伴った女性ならミネルヴァといったように、絵を見て何かがわかるというよりも、事前に知られているルールとの間のリンクさえ想起できるようになっていれば「顕在化」されるようになっているのだ。
つまり、絵の中のイメージが顕在的なものになる仕組みは、絵そのものの内部のみでは完結しない。絵に描かれたイメージを顕在的なものにするような社会的なシステムがあるのだ。
スウェーデンの劇作家、小説家で、絵も描いたヨハン・アウグスト・ストリンドベリについて、ガンボーニはこう書いている。
ひとたび対象が明瞭に認知されたとき、彼は「もはやなにも見えない」と言う。曖昧な対象認知をめぐる典型的体験だが、流動的な解釈学的行為を行うのみならず、曖昧さを悦楽の源泉として積極的に価値づけている点において際立っている。
ストリンドベリが描くのは、下の作品のような抽象的な作品だ。こうした絵においては、対象は明瞭に認知されない。少なくとも、そこにある対象を認知するは時間がかかる。

時間がかかるということは、認知までのあいだ、それだけ人はその絵の中になんらかの対象を探しだそうと、自分の責任において絵を見続けるわけである。
しかし、である。そこに何らかの明瞭な対象が見つかった!と感じた瞬間、「もはやなにも見えない」状態になるのだ。
既存の社会システムに顕在化した対象を絵の中に見出してしまった瞬間から、絵を見る人は絵そのものではなく、既知の情報を見ていることになってしまう。
僕らが本当の意味で絵を見ていられるのは、それが何を描いたものかがわからず、潜在的なイメージにとどまっている間だけなのかもしれない。
中間領域にあるイメージ
その意味で、潜在的なイメージというのは、そうした社会的に用意された既知の情報からはみ出た、未知のイメージであるといえる。
その点、ガンボーニが本書のはじめの方で考察する、潜在的イメージと心理学的研究との関連性が面白い。
例えば、乳幼児における対象認知の際の、自身と対象の区別と橋渡しの領域という話も興味深い。
乳幼児はどこからまでが自分でどこからが対象であるかを認知したりする際の中間領域をもっているが、大人になるとそれは消える。けれど、芸術家の活動(あるいは宗教体験)には、その失われた中間領域が用いられるという話だ。
そこは明瞭な対象が認識される前段階の潜在的な領域である。
「移行空間」(乳幼児に自己と非自己の橋渡しをする領域)や「移行対象」(幼児の初めての外的所有物とその経験的範囲の触知可能な記号)という概念を用いてウィニコットが研究したのは、主に幼年期の中間領域についてであった。彼は、こうした統覚と知覚の中間領域は「成人になっても、芸術や宗教においては本質的に具わっている」と主張し、さらに「他者に対して、他者が有していない幻影を共有するよう(……)強く要求するような症例は、明らかな精神異常の兆候である」と述べている。
『徴候・記憶・外傷』で精神科医の中井久夫さんも類似の例を紹介している。
幼児型記憶と成人型記憶を区別し、言語との関係、三者間の関係をもとにした成人型記憶が形成されるようになると、断片的で、主に静止した視覚映像で、文脈のない幼児型記憶は消し去られるというのだ。
それが外傷神経症の患者のフラッシュバックに近いと指摘されるが、ガンボーニのいう中間領域にあるものもそれに近いものではないだろうか。
はたまた、この流れで、サルトルが論じる知覚とイメージの違いについての論も興味をひく。
サルトルもまた、こうした動的な性質をイメージの本質と捉えていたようで、イメージを「一種の茫漠たるもの、根本的に不確定的なもの」と特徴づけている。また彼は、知覚とイメージの対立を相対化しつつ、「外的要素と心的要素を統合する中間領域に属するもの」の存在も認めていた。彼によれば、中間領域に属するのは、たとえば「炎のなか、あるいはタピスリーのアラベスク模様のなかに、人間の顔を読み取ったりするとき、あるいは、眠りに入るときなどに」みられる現象である。
「外的要素と心的要素を統合する中間領域」。
そこで蠢く、ひとつの意味に固定化されることを拒む動的なイメージこそが潜在的なイメージだろう。何も見えなくなる前の段階。
そして、その意味において、潜在的イメージというもののもつ意味は、さらに大きく展開する。
ヴァーチュアル、過去に投射される現在の幻影
「もうひとつ、「潜在的」という用語に関連するものとして「潜勢的(ヴァーチャル)」という言葉がある」とガンボーニはいう。
ベルグソンが好んで用いたこの言葉もまた本書で用いるのに価するものである。この哲学者はまず「可能なもの」と「現実的なもの」を対比し、前者が「過去に見出す現在の幻影(蜃気楼)」、すなわち(ここでもまた)「可能なもの」が「現実的なもの」の「遡及的な」視像にすぎないと述べつつ、「現在化するもの」に対置して「潜勢的なもの」という概念を挙げた。
過去に現在を投射すること。
そこに浮かび上がる幻影は、これから起こるであろう出来事がいまだ堕胎することなく潜在的な状態で蠢く「可能性」である。
クールベの岩の絵に浮かび上がるように感じられる男の横顔のようなイメージもまた、こうした中間領域にある可能性のイメージだといえるだろう。
そして、そのすでに描かれた過去に投射される現在の幻影としての未来の可能性の図像をどう見るかは、描いた画家の側にではなく、それを見る僕らに向かって常に開かれ、僕らはそれに責任をおっている。
そこにどんな意味、価値を見出すかは僕らに委ねられ、見る側がその意味、価値をつくりださなければ誰もそれをしない。
それを画家自身や、社会のせいにしようとしても無駄なのだ。
顕在的なルールが成立していない潜在的なイメージに対しては、見る側がその責任をおう以外にない。
そして、あらゆる面で顕在化のためのルールが機能しなくなっている現代においては、情報の発信者や社会の仕組みなどに責任をおわせることは不可能で、情報の受け手である個々人がそれぞれ責任をとる必要があるのと同様だ。
誰かの発言や行動を非難しただけでは、自身の責任を取ったことにならない。
一番わかりやすいのは、環境問題や資源問題などだろう。
誰かが悪いのではなく、誰かを非難しても始まらない。自分たち自身が動いて、自分たちが状況に意味ある改善をもたらすしかない。
作り手と受容者の関係は逆転した
それが潜在的なもの、可能性を内在したものに対する、僕ら受け手の責任だろう。いや、その意味では潜在的なもの、ヴァーチュアルなものが可視化されたモダン・アートの時代以降、受け手などという受動的なあり方は不可能になったのだ。
社会学的にいえば、19世紀から20世紀にかけての芸術界では専門分化と自立化が急速に進行し、とりわけ、このプロセスにおいて、19世紀末期は決定的であった。(とくにフランスでは)国家的な美術制度の瓦解、および制度からの解放運動によって、モダン・アートが発展する―― 私は「モダン・アート」よりも「アンデパンダン(独立派の)」芸術という呼称のほうがふさわしいと思っている。独立派の芸術家たちは、国家に代わる独自のネットワークを組織し、新たな美術市場と美術批評を開拓した。この新たな状況において、文学者および美術評論家が重要な役割を果たすようになり、美術と文学が密接な関係をもつことにもなる。(中略)こうして「前衛」美学を創案して推進する共同体の内部では、イメージの創造者としての芸術家とそれを受容する批評家の役割が、同等に重要であるとみなされるようになり、さらには、作り手と受容者の関係が逆転するような事態も生じつつあった。革新性が芸術に不可欠な特性となり、「あらかじめ準備した」メッセージを伝達するだけの作品ではなく、受容者の自由な解釈を促し、次々と新たな批評基準を要求する作品が求められるようになったのだった。
あらゆるものが可能性として、潜勢的なものとして開かれている。
作品の受け手という傍観者的な立場はもはやありえず、誰もが作品に参加できるよう、作品は開かれている。
「自分ごと」なんて言葉はそういう意味で捉える必要があるのだろう。
不満や愚痴を投げかける相手など、とうに居なくなっているということに気づくべきなのだ。
仮に不満や愚痴が言いたくなることがあったとしても、そうならなよう作品づくりにちゃんと参加しなかった自分自身の側にも責任があることを忘れてはいけないのだと思う。1つ前のnoteで「決定論に身を委ねる」と書いたのも、こうした文脈においてである。
観る者が(物質的対象としてではなく生成プロセスとしての)芸術作品の生成に貢献している事実を重視するとき、「潜在的イメージ」という概念は、視覚芸術という範疇を超えて、コミュニケーションと意味作用に関わる重要な問題を引き起こすことが明らかとなろう。
そう。このことは「潜勢的=ヴァーチュアル」なことが問題となっている以上、単に芸術作品の受容と生成に限られた話なのではなく、可能性という未来が賭けられたあらゆる領域における、他者とのコミュニケーションと相互作用、そして意味と価値の創造の活動すべてに関わることなのだと思う。
可能性にどうコミットするのか?
それを考える上で、モダン・アートにおける潜在的イメージの台頭を論じたこの本はいまの僕の思考を形成する上でとても参考になった一冊だ。
この記事が参加している募集
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
