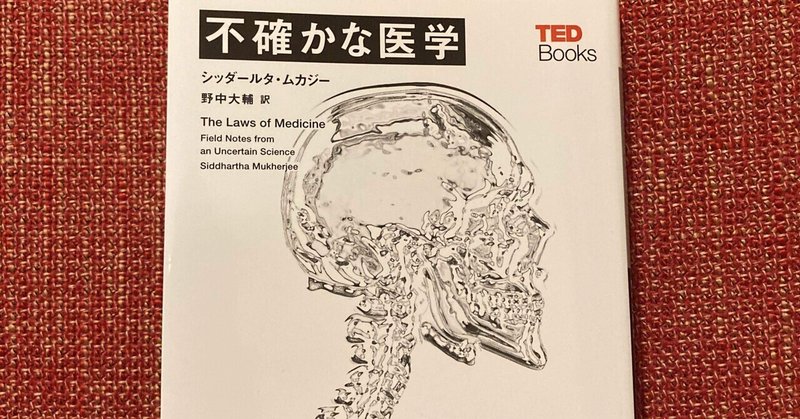
【不確かな医学】不完全な情報から適切な判断を下す
オススメ度(最大☆5つ)
☆☆☆☆
〜「もっとも未熟な科学」〜
以前読んであまりにも面白かった「遺伝子 -親密なる人類史-」の著者、シッダールタ・ムカジー氏のTEDトーク(あらゆる分野のエキスパートたちによるプレゼンテーションを無料で視聴できる動画配信サービスのこと)をもとにした本書。
本作のテーマは、情報、不完全さ、不確かさ、医学の未来である。
医療の現場で積み重ねてきた経験から、著者は冒頭で「医学がこんなにも法則のない、不確かな世界だとは思ってもみませんでした」と述べる。
今日、かつてに比べ医療の技術や検査の正確さや機器の精密さは向上したにも関わらず、なぜ、ムカジー氏は医学を「もっとも未熟な科学」と表現するのか?
その理由は、「医学の法則」というものは、実際には不確かで不正確で不十分であるからだ。
医者ではない僕らは何か病気になれば医者にかかる。そして、医者なら自分の病気を特定して適切な治療をしてくれるだろうと、全幅の信頼を寄せる。
しかし、検査の数値だけでは患者の病気を特定することは不可能だ、とムカジー氏は述べる。
結局のところ、全ての症例や症状を一定の法則や基準に当てはめることは出来ない。最終的に必要となるのは、医師と患者の対話の中で生まれる不十分な情報に基づく直感的な判断なのだ。
〜不確かで不正確で不十分な「医学の法則」〜
本書においてムカジー氏が「医学の法則」と呼ぶものは、不確かさであり不正確さであり不十分さである。
具体的には、事前知識、特異な症例、バイアス、である。
例えば、ある一つの症例から思い当たる病気にあたりをつけて検査をして、いずれの検査も正常値が出る事がある。事前知識"だけ"を基に診断をしても、何か患者が隠し事をしていた(例えば、薬物を常用していた、など)事を知らなければ、それが原因となる病気に当たりさえつけられない。
99%効果のある治療薬が、その人に効果があるかどうかはわからない。そして、その効果のない人は「例外」として扱われ、医学における法則や理論からはみ出てしまう。
とある治療法が効果的だと長年信じられている場合、その後の研究で、むしろ患者にとって有害であったことがわかった、というものが過去にいくつもある。
数々の具体的な事例から、医学という科学がどれほど不完全なものなのかという事が思い知らされ、医師ではない僕は衝撃が隠せない内容であった。
そういえば、最近の本には(医療に関係のない人が)「最先端のAIを用いて患者の病気を特定出来るようになる未来がもうすぐ来る」なんて事がよく書かれているが、本書の内容は全く逆の事を書いている。
医学は、わからなかった事がわかる様になった事で、さらにわからない事が増えた。
「医者というものは、自分でもあまりわかっていない薬を、さらにわからない病気を治すために、人間という何ひとつわかっていない相手に処方しるものである」
というフランスの思想家ヴォルテールの言葉が本書でも引用されているが、医学というものは不確かな情報の中で適切な判断をしなければならず、それは理論や数値だけで判断することはもはや不可能なのである。
〜情報や法則との向き合い方〜
さて、本書は主に医学という科学の不完全さを書いているが、もっと大きく捉えれば、僕らが科学や情報に対してどのように向き合えば良いのか、という事も教えてくれているように思える。
医学に限らず、完全な情報や完全な法則なんてものは無いのだろう。
どんな情報や法則にも例外はあるし、何が正しくて何が間違ってるかなんて事は、人によっても環境によっても状況によっても変わる。
大事なことは「何を信じるか」ではなく、不完全な情報や法則から「何を判断するか」なのだ。
医師たちは、日々患者の命を守るために不完全な情報や法則の中から適切な判断を下さなければならない。
「医者って大変だなぁ」で終わるのではなく、それを自分たちの生活にも当てはめてみるべきだ。膨大な情報の中から適切な判断・決定をしなければ、自分たちの生活や人生が大きく変わる。
たとえ、情報や法則が間違っていたとしても、判断を下した責任を情報や法則に押し付ける事など出来ない。患者の命を助けられなければ適切な判断が出来なかった医者の責任になるように、自分の人生を助けられるように適切な判断を下さなければならない責任は自分にあるのだ。
世界は不完全なのだ。そして、その中でどのように考え生きるのか模索するのも自分なのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
