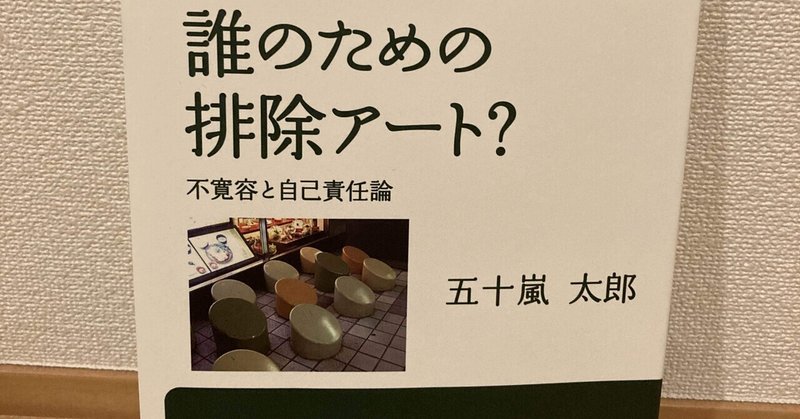
【誰のための排除アート? 不寛容と自己責任論】問題を見えなくしてしまうのが問題
オススメ度(最大☆5つ)
☆☆☆☆
〜特定の人を拒否する排除アート〜
「排除アート」とは何か。
ある特定の人を公共の場から拒否するために設置されたもの、である。
具体的には、ある特定の人というのはいわゆる「ホームレス」と呼ばれる人々であり、公園やバス停、駅のベンチには、不自然なオブジェや手すりが設置される、座面を細くする、段差や傾斜などをつける、等で人が寝転がれないようにされたものである。また、段ボールなどを設置したり出来ないように、公共の広場や地下通路にも排除アートは存在する。
有名なものでは、新宿西口地下には先端が斜めになった円筒形のオブジェ群がある。これはホームレス追い出しを目的としたオブジェであり、これが設置された1996年頃から「排除アート」の存在を世の中が認識したようだ(その当時に「排除アート」という言葉が使われていたかどうかは定かではないが)。
この「排除アート」は、都市に住む人々の他者への不寛容さを表している、と著者は述べる。
つまりは、「都市の美化」という名目で社会から転落してしまったホームレスたちの居場所をそこに住む人々が拒絶する。そして、その拒絶の意志を「アート」という形で巧妙に隠しているのである。しかし、横になれない椅子というのはホームレスたち当人にとっては明白なメッセージなのだ。
〜どれもこれも排除アートに見えてしまう〜
本書を読むと、街中にあるベンチや広場のオブジェが全て「排除」の意志を含んだものように見えてしまう。
(著者が日本中にある排除アート、と思われるもの、の写真を掲載しているのだが、いくつか実例からあれもこれも「排除アートと考えられる」と述べているので、あまりに偏りすぎた視点になりすぎないようにだけ注意したいが…)
著者の述べている視点はひとつ納得の出来る事があり、「他者への不寛容はいずれ自分にも返ってくる」という事だ。
ハッキリ言って、今の世の中で明日自分がホームレスになる可能性は決して否定出来ない。寝食の場を失った自分を想像しながら街を眺めると、居場所が全く無い事に気付く。
また、ホームレスにならなくとも、災害時に帰宅出来なくなった時に寝転がる場所がない、というのがどれだけ辛いかと考えても、やはり「家のない人」にとっての街は決して優しい場所ではない事に気付かされるだろう。
〜解決策はそこじゃない〜
しかし、こればかりは非常に難しい問題である。
日本中にある「排除アート」を取り除けばそれで終わりかといえば、僕は一概にはそうは思えない。
実際に僕は子どもの頃、近所にいた見知らぬホームレスに肩を掴まれ、恐ろしい形相で訳の分からない事を延々と言われる、という経験がある(警察官も来る事態となった)。今でも怖い記憶として残っている。
娘がいる今の状況で、心苦しいが「街にホームレスが居てもいい」とは、正直言えない。
きっと、「ホームレスが道にいるのをなんとかしてほしい」と自治体や警察に言う人は、大小あれど不安を感じてしまっているのだろう。
しかし、「ホームレスがいなくなればいい」と言って街から排除してしまうのは思考停止に等しいし、逆に「排除アートを設置する自治体や警察、はたまたそれを訴える住民は悪いやつらだ!」と言ってしまうのも同じだ。
どちらが悪い、というのは根本解決にならない。
「排除アート」は根本解決にはならない。
にも関わらず、それで問題を見えなくしてしまう現状が問題なのだ。
じゃあ、解決策はあるのか、と言われると僕は何も思いつかない。
だが、真摯に考える必要はあると気付く。
皮肉にも、意図せずに街に住む人々の見えない意識を形にしてしまった「排除アート」。
公共の場とは何か、を改めて考えさせられた1冊であった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
