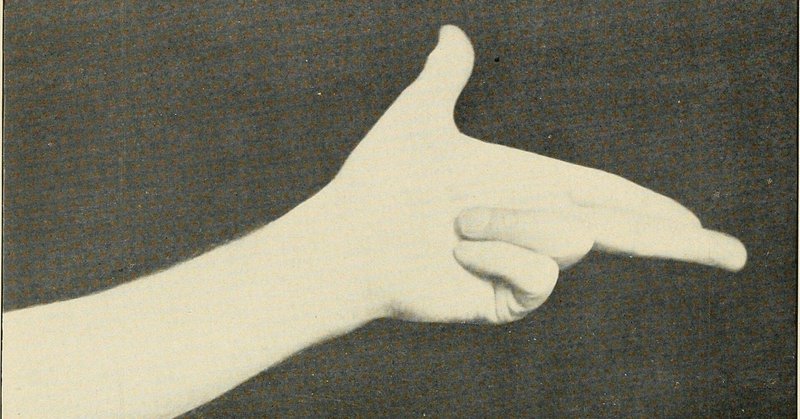
” 良い広告担当 ”であるためのディレクションマナーと、その大罪
広告担当、失格
折込チラシ、WEBバナー広告、自社HP、スマホアプリ、SEOコンテンツ、リスティング広告、新聞TV・雑誌・交通広告、ノベルティ・・・。20年近く広告主の立場で販売促進やプロモーション、マーケティングに携わり、たくさんの制作物を企画・発信してきました。ですが私自身はこうした制作を自らの手で行うスキルをほとんど持ち合わせていません。これらの制作はすべて広告代理店様、制作プロダクション様、フリーランスデザイナー様などが作り出したもので、私はこうした方々の存在に常に助けられてきました。(※執筆の都合上、以下、総じて「制作会社様」と書かせていただくことをご容赦ください。)
今も変わらず全くもってセンスのない私にとって、制作会社様は大切なパートナーで、「発注者⇄受注者」という関係でもなければ「広告主⇄制作者」という関係で捉えることも今はありません。そのプロモーション施策を一緒に成功に導くためのチームの一員として、敬意と責任をもって接することがもはや自然になりつつあります。
ところが、そうした意識がなかな身につかない方がいることも事実で、私も実際に先輩・上司・同僚・後輩がそうした違和感のある行動を取るシーンに居合わせたことが少なからずありました。そして、かくいう私自身もかつてはそうだったように思います。「発注側」「広告主」というだけでなぜか偉そうな態度を取ってしまったり、命令口調で指示を出したり、適当なメールを返したり、声を荒げて怒鳴ったり、横暴な依頼や値引きを迫ったり…。これら”広告担当、失格”のあるあるは、なぜ起きてしまうのでしょうか。

ディレクションすべきは相手ではなく、自分
こうした担当失格の方であっても、自分の顧客や営業先への対応となれば襟を正して丁寧な言葉使っているはずが、なぜか「広告主」になった途端に態度が一変してしまうのです。自分ごとに置き換えてみればわかりやすいですが、単なるお金だけの関係にも関わらず命令口調の偉そうな人の指示に従う気持ちは湧きませんし、その人のために良いものを作るどころか、むしろ反対にヒドいものを作って仕返ししてやろううという気すら頭を過ぎってしまうかもしれません。
「ディレクション(方向付け)」という言葉は、どうも偉そうで好きではありませんが、わかりやすさを優先して使わせていただくとすると、制作会社だろうが、部下、上司、同僚、親、子供、友達…相手が誰であろうと、主体者として考えるべきことは、「相手に希望する行動をとってもらうために、自分がどうあるべきか」で、相手をディレクションするためには自分自身のディレクションがまずは必要なはずです。
さて、前置きが長くなりましたが、こうした広告主としてあるべきディレクションマナーについて、意外にもインターネット上には記事がほとんど見当たりませんでした。下請法や業務委託、あるいはディレクション項目といった形式的なノウハウは多く見つかるものの、その大前提である人としてあるべきマナーは、やはり経験者にしかわからないことなのかもしれないと思い、今回書き起こしてみることにしました。
私自身も完璧にはできていないという前提で、”良い広告主”であるためのポイント、そしてその大罪を思いつく限り挙げていきたいと思います。

①「広告主(発注者)が上」という邪心を捨てる
「お金を払う方が偉い」こうした観念は、コンビニやファミレスで横柄な態度をとる人が話題に上がることなどを思い出すと、資本主義社会に生まれた私たち現代人の邪心なのかもしれません。
こと広告制作において金銭を支払う理由は立場を上にすることが目的では全くなく、制作力という専門的な技術を買わせていただくため、あるいは自分の作業を解放するのに必要な人材リソースをお借りするためです。あえてどちらが上かと言えば、圧倒的に技術や人材という資産をもった制作会社様です。ここをなぜか”お金を払う”という行為だけで「上だ」と捉えて、横柄な態度を取ったり、強い口調で指示命令をして良いと思い込んでしまう方が少なからず思い出されます。
こうした行動のデメリットは言うまでもなくモチベーションの低下です。偉そうに威張っている広告主に対して一生懸命、前向きに制作物を提供しようとする制作者などいるはずはなく、怒られまいと型にはまった当たり外れのないクリエイティブに留まってしまったり、失敗がないようにと過去採用されたクリエイティブに近いものを目指してしまったり、全くもって創造性が発揮されない方向へと制作者心理を追い込んでいきます。
ヒドい場合には、シンプルにパワハラ被害を訴えられ広告主側の担当替えを相談されたり、状況によっては下請法違反で訴えられるなど、会社にとっては相当恥ずかしい事態へと発展することもあるかもしれません。
上下関係というあり方そのものを、広告主の担当者は捨てるべきです。施策パートナーとして適した役割分担を施し、共にアイデアを出し合い、対等に施策に対する成果責任を持つ、こうした関係性を築くための人間性と行動、努力が広告担当には必要だと思うのです。

②「とりあえず作ってみてください」は恥と知る
広告やプロモーションのオリエンテーション後、よく見聞きするやり取りです。
制作会社様「この後の進め方はどうすればいいでしょうか?」
広告担当「今日の内容を踏まえて、とりあえず作ってみてください。」
まず、制作会社様のこの質問、裏を返せば、ただただ「何をすればいいかわからない」ということを言い表しています。広告担当としては、まず自身のオリエンテーションが失敗しているということに気付かなければいけません。今回のやり取りではさらにその失敗を上塗りするかのように、理解ができていない相手に「とりあえず作ってみて」というオーダーを出してしまうという始末です。
もちろん状況によって異なるため、この言葉そのものがNGというものではありませんが「とりあえず作って」「まずは作ったものを見せて」などが自分の口から出ている際には、そもそも自分の話が伝わっていないかもしれないと自身を疑うことが必要です。こうした制作系のオリエンテーションの意図が伝わないケースは、多くの場合、広告主側の担当者自身が十分な企画検討を行なっておらず、自らも明確な戦略・戦術を描けていないというケースが少なくありません。
担当者が課題、目的、方向性、戦略、戦術、リスクを検討し、しっかりと頭の中で企画を固められていないと軸がブレブレになります。その結果、指示が曖昧になるばかりでなく、「あれもやりたい、これもやりたい」のワガママ状態に陥ってしまったり、制作会社様側の質問や提案に「それでもいいと思う」などと中途半端に答えてしまい、何がOKで何がNGなのかがわからない混乱を招きます。
オリエンテーション前にしっかりと深い検討を行い、OK範囲とNG範囲の軸を自身の中で固めておくこと、場合によっては上司と握っておくことが「とりあえず作って」の恥の量産を減らす回避策です。

③「伝えた分だけ作られる」という当たり前
上でも書いたように制作会社様は、施策成功を共に目指すチームの一員であり、パートナーです。場合によっては、その後に自社のお客様になってくれる可能性もあるかもしれません。こう考えると、横柄な態度や命令口調を取ることが、プラスに働くことは絶対にないと気付きます。そして、態度や口調の丁寧さは大前提ですが、とくに面倒だと蔑ろにされるのが情報共有の丁寧さです。
例えば、「犬を書いてください」と言うか、「茶色い犬を書いてください」と言うか、「大型で、茶色く、毛が長い、耳が垂れた犬を書いてください」と言うかで、出来上がってくる「犬」は当然異なります。もしゴールデンレトリバーを描いて欲しいことが決まっているのだとすれば、最後のセリフのように丁寧にその特徴を伝えた方がその出来栄えはイメージに近いものになっていき、出し直しも少なく、お互いにスムーズな作業を進めることは明らかです。
広告やプロモーションの場合も同様です。例えば、「新発売となるこの商品のチラシを作って欲しい。販売価格は50,000円。問合せ先も忘れずに」と、情報としてこのようなスペックだけを伝えれば、当然、スペックのみのチラシデザインができあがります。恐らく「新発売!」のキャッチコピーに、大きめの商品写真、安っぽく強調された「50,000円!!」の価格記載、下部に小さく問い合わせ先がある…
これは極端な例ですが、少なからず広告担当は、どこか制作会社様に「いい感じに作ってくれる」ことを期待しがちです。ですが、情報がなければ何が「いい感じ」なのかもわかるはずがありません。預言者でもない限り、与えられた情報以上の内容をデザインすることは人間業では不可能です。それにも関わらず、初校が上がってくると「ターゲットをもっと意識してほしい」「当社のコンセプトに合わない」「キャンペーンのトンマナに合わせてほしい」などと提供していない情報でひっくり返してしまい、これもまた恥の上塗り発言を制作会社様に平気で申し入れてしまいます。
ところで、当社ではAI開発を事業にしていますが、AIは学習のために与えたデータから答えを返すことが基本になる技術(=与えたデータ以上のことは返ってこない)にも関わらず、「AIはなんでもわかる、なんでもできる」のような誤解が今もなお少なくありません。広告制作もまさにこれと同様で、「プロであるデザイナーならきっと何でも作れる」のような幻想を抱いてしまいがちです。
広告主が情報共有したの分だけ制作されるということを再認識する必要があります。私の場合ですが、少なくとも以下の情報をお伝えし、理解し、共感してもらうことを心がけています。
・背景:なぜその施策を実施することになったのか
・課題:その施策で解決したい課題は何なのか
・目的:何を達成すると成果が出たと言えるのか
・ターゲット:どのような層にその情報を受け取ってほしいのか
・ペルソナ:そのターゲットはどのような状態にあると想定されるのか
・メッセージ:その状態に対してどのようなメッセージを伝えたいのか
・アクション:メッセージを伝えた上でどのような行動をターゲットに取って欲しいのか
・リスク:競合他社や代替品との関係上、避けるべきことは何か
(※仕様、費用、納期、請求関連の基礎要件ももちろんお伝えしますが、本題とズレるため省いています)

④「細かい指示」はやはり罪
上のように考えると、「じゃあ、こと細かに制作会社に指示しよう!」となるのもよくある”広告担当、失格”パターンです。誰しも経験があることだと思いますが、先輩や上司から細かに作業内容を指示されると、やらされ仕事になり、自分のやる気を引き出すのが大変です。
前項の「丁寧に情報を共有すること」と、この「細かく指定を指示すること」とは大きく異なります。情報共有があくまで制作に必要となる環境情報や設定条件を伝えることであるのに対して、指示はデザインにまで踏み込んだ仕様を指定することになり、制作者の方の自由な発想とモチベーションを下げてしまうことになります。
もちろん制作物によってはデザインがガッチリと予め決まっていて、それ以外の自由が許されない場合もあります。ですが、デザインに関するアイデアが定まっていない場合や、クリエイティビティを求める場合には、細かな指示をすることは裏目に出てしまいます。制作のプロフェッショナルの観点で、斬新なアイデアやデザインが生み出してもらうためには、制作者の方に自由に泳いでいただくことがとても大切です。
ですが、こうしたやり方を取る際には、広告主側に必要となる覚悟があります。それは、その自由な発想を積極的に受け入れるということです。こちらの指示で自由に泳いでいただいたにも関わらず、「こういうイメージではなかった」などとお戻しすると、信頼を失うとともに、いつまでもデザインが決まらないループに陥っていきます。
関連して、望ましくない行動として言われる”丸投げ”は、もちろんそれ自体にも悪いところがありつつも、本質的な問題としては、丸投げしたにも関わらずNGを出すという点にあります。丸投げをするということは、「任せる!」と意思決定したことであって、提出されたもの全て受け入れる責任があります。それが制作の全部分であろうと、一部分であろうと同様です。「お任せします」と言うからには、それを寛大に受け止める覚悟が必要で、それが許容できる心のゆとりと権限がないのであれば、しっかりと仕様を指定するやり方を取る方法を取るのが無難です。

⑤「残念な身の丈」を認める
大手企業でのプロモーション業務を経て、現在はスタートアップ企業でのマーケティング業務に携わっている私ですが、転職当時、大きな驚きがありました。それは、大手企業(=広告費が潤沢)とスタートアップ企業(=広告費が少ない)では、残念な現実として、制作会社様の対応が違うということです。
多額の広告出稿が可能な大手企業には、実際のところ、制作会社様の営業戦略としておまけ的なインセンティブが提供されることがありますし、大手企業側もあえて戦略的に強気の姿勢を示すことでディレクションするといった交渉術を取ることがあります。こうした環境に慣れてしまう結果、いつの間にか人間性が蝕まれた担当者が生み出されていきます。大手企業であってもそんな横柄な担当者は当然許されないはずが、多額の広告費の獲得を目指した多くの営業が集まってくるのです。(「目的はあなたではなく、会社です」というやつですが。。)
反対にスタートアップ企業は、お金も少なければ、知名度もなく、もちろん積極的に駆け寄ってきてくれる営業の方などいるわけがありません。これはもはや事実として受け入れざるを得ず、そうした時、とくにスタートアップ企業の広告担当者として気をつけるべきところがあります。それは、大手企業担当者のようなセルフポジショニング(=自分自身の位置付けや立ち振る舞い)は絶対にNGということです。
複数の制作会社様によるコンペを開催し、”選ぶ立場”になりやすい大手企業と違い、スタートアップ企業はその資本力の小ささから取引を断られる可能性もあるなど、”選ばれる立場”にあります。そのため、お付き合いをしてくださる制作会社様との関係を良好に保ち、強固なパートナーシップを作ることが取るべき術です。また、広告費や知名度が少ないスタートアップ企業は、事業の先端性・革新性、言い換えれば将来ビジョンが制作会社様を惹きつけるコンテンツになります。わかりやすい数字で惹きつけられる広告費などと違い、ビジョンで共感を得るには、一社一社の制作会社様との丁寧なコミュニケーションを積み重ねていくことが自社を継続して選んでいただくためには欠かせません。
同じ広告主でも、とくにスタートアップ企業の担当者の場合は、自社の身の丈を十分に理解し、担当者が自分自身の振る舞いをディレクションすることが重要です。横柄さ、指示命令、無茶ブリなどは制作会社様を遠ざけるだけだからです。丁寧で密な関係づくりを進め、しっかりと時間を掛けて自社の夢を語り、ファンになってもらうことが大切なのです。

「人としてのお付き合い」に尽きる
多少辛辣に、また偉そうに書いてしまいましたが、私自身、今現在も制作会社様へお詫びをさせていただく大罪を積み重ね続けている日々です。上記の内容は自分自身の経験を含めたものであり、自分への戒めでもあります。(これ以外にも多数の反省ネタがあり、随時書き足していく予定です…。)
切実に思うのは、広告主⇄制作企業様の間での良好なパートナーシップに基づく会社間連携が多く実現することが、多くのマーケティング施策の成功確率を上げ、各企業の事業成長に寄与し、そして最終的に消費者の方々により良い情報をお届けする機会を増やすことにつながるのではないかということです。
私たちは、マーケター、プロモーター、ディレクター、ストラテジスト、デザイナー、ライター、広告担当、販促担当である前に一人の人間です。”人と人とのお付き合い”というごくごく当たり前のことを仕事上で実践するだけで、将来のための良好なパートナーシップが生まれてくるように思うのです。

========================================================
【執筆】
和田 崇
株式会社Laboro.AI 執行役員 マーケティングディレクター
経営学修士(マーケティング論・消費者行動論)
------------------
【ブランディング関連で執筆したnote】
・ブランディングには、「変わること」と「変わらないこと」がある
・ブランディングと脳、その“怪しい関係”
・ブランディングの絶対神、「有名になること」の先へ
・消費者視点のブランド・デザイン ー 記号としてのブランディング
------------------
【 経歴 】
立教大学大学院 経営学修士(マーケティング論・消費者行動論)。立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科 博士後期課程 中退。
2005年、KDDI株式会社に入社、コンシューマ向け商品・サービスのクロスメディアによるプロモーション施策の立案・企画運営に携わる。
2014年、全国漁業協同組合連合会に入会、水産庁が推進する地域支援プロジェクトの推進メンバーとして従事。
2019年にLaboro.AIに参画。PR・広告宣伝・プロモーション領域をメインに、マーケティング/ブランディング業務を担当。
日経クロストレンド、ニュースイッチなど、寄稿多数。一般社団法人 日本ディープラーニング協会 G検定資格保有。日本マーケティング学会、日本産業経済学会、人工知能学会、情報処理学会、各会員。
========================================================
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
