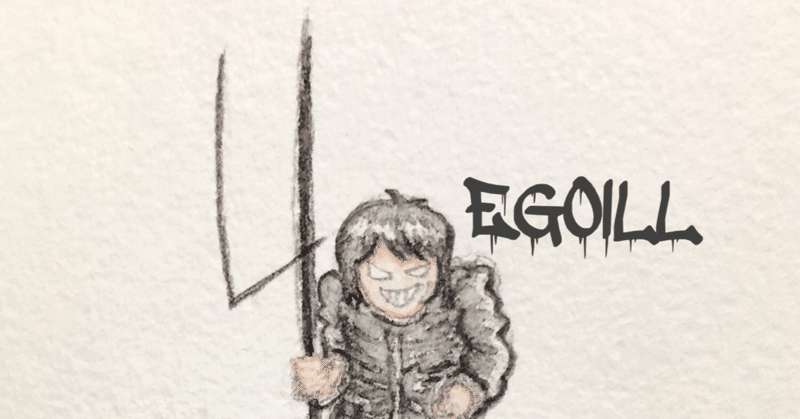
小説『EGOILL』Chapter.8
八、こんぺいとう
今にして思えば、二〇〇九年は私にとって飛躍の年であった。前年からの不平等文通に端を発し、〈語る会〉開催からアマラントス結成、蛯原蜜子の個展とアマラントスの初ライブ、締めくくりは再び〈語る会〉の開催という、それまでのゾンビ生活がまるで嘘であったかのような怒涛の一年を、全速力で翔破したのである。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで、大空高く舞い上がった私であったが、蝋で固めた急造の翼は脆かった。父ダイタロスの忠告を忘れて、太陽に近づきすぎたイカロスと同じ運命を、まさか自分が辿る羽目になろうとは、夢にも思っていなかった。
「仕事の都合で他県に転勤することになりました」
二〇一〇年三月、ドラムスの溝氏から、アマラントス脱退の意向を、何の前触れもなくいきなり告げられた(溝氏は某有名レンタルビデオチェーン店の店長であった)。その知らせは、私にとってまさに青天の霹靂であった。
三月末、私の自宅で溝氏の送別会を催した。「じゃあ、元気でな」と溝氏に別れの言葉をかけた後、車に乗り込む溝氏の姿を磯ピーと一緒に見送りながら、私は前年のある出来事を思い出していた。溝氏が、「大学時代の先輩がプロデビューしました」と言って、まだ封が切られていないCDアルバムを嬉しそうに私の自宅に持ってきたときのことである。
私たちは、居間のソファーに二人並んで腰掛け、そのCDを静かに一聴した。無言のままソファーを離れた私は、コンポの前に跪き、取り出したCDをケースに収めながら、真後ろにいる溝氏にこう語りかけた。「率直に言わせてもらえば、このバンドにはまるで特徴がないね。歌詞も平凡、曲も平凡、音がまとまっているところが逆に仇となって、更に平凡さを助長している。おまけにジャケットまで平凡だ。これでよくデビューできたなって感じだよ。何か一つでも際立ったところがないと、このさき生き残っていくのは厳しいかも……」
振り返ると、溝氏がとても悲しそうな顔をしていることに気がついた。しまった、と私は思った。こと音楽のことになると、私はすぐにムキになってしまうのである。
視界から遠ざかる溝氏の車を目で追いながら、あの時もっとましなことを言ってあげればよかった、と私は思った。
溝氏のアマラントス脱退後、私と磯ピーは、例のレンタルスタジオの掲示板を利用して、再びドラマーを募集した。だが、溝氏の代わりのドラマーはいつまで経っても現れなかった(一本の連絡さえ来なかった)。
進退窮まった私は、BIGHOPのマネージャーに懇願し、二、三人のドラマーを紹介してもらった。しかし、彼らの腕前は溝氏の足もとにも及ばなかった。
永遠に萎まない筈の不凋花は、開花後僅か一年足らずで凋落してしまった。私と磯ピーは、その後次第に疎遠になっていった。
二〇一〇年の四月、私は蛯原蜜子をデートに誘った。仕事あがりに落ち合って、助手席に彼女を乗せて夜の海へと車を走らせた。見晴らしのいい岸壁のきわに車をとめ、対岸の臨海工業地帯の明かりがゆらゆらと海面に反射する様を、彼女と一緒にぼんやりと眺めた。BGMに流していたデヴィッド・シルヴィアンのアルバム『Dead Bees on a Cake』を、彼女がとても気に入ってくれた。
翌五月には、蛯原蜜子と二人で晩御飯を食べに創作フランス料理店に行った。私と彼女は、チーズフォンデュの鍋をつつき合いながら、他愛ない会話に花を咲かせた。彼女を家まで送り届ける途中、少しでも長く彼女と一緒にいたいという一念から、わざと道を間違えて遠回りをしたところ、「今のわざとでしょう?」と彼女にそれを看破されてしまった。私は、「わざとじゃないってば」と、故意に道を間違えたことを意地でも認めなかった。
その二度のデートの最中、まるで自分が蛯原蜜子の恋人であるかのような錯覚に、私はたびたび囚われた。しかし、彼女との距離が近くなればなるほど、彼女にとっての運命の人が私ではないという事実を、より強烈に思い知らされるだけであった。
私は一体彼女の何なんだ!
――ええ、友達です――
〈ギャラリーとらのこ〉での蛯原蜜子の発言が、私の脳内で繰り返し再生された。彼女に奇蹟を示すことさえできたなら……。私は自身の不甲斐なさを呪った。
張り裂けそうな胸の痛みから逃れたい一心で、私は白石麻耶に頻繁に電話をかけるようになった。彼女はいたって普通の顔のない女であったが、顔を獲得したいという願望を、漠然と抱いているように見えた。
「私は、変わりたい」
白石麻耶は、私に向かって何度もそう言った。
そのうち私は、彼女が顔を獲得できるように手助けをしようと思い始めた。私のお気に入りの小説や音楽を彼女に与え、「優れた芸術家たちは、ネジの緩みが諸悪の根源であるということを、作品を通して間接的に説いているんだよ」と解説した。そして、「変わりたいのなら緩んだネジを締め直すしかない」と彼女に説いた。私と彼女とは、まるで先生と生徒のような間柄であった。
二〇一〇年八月、私は、再び蛯原蜜子の個展を訪れるべく、車で片道約二時間の距離にある県境の町におもむいた。今度の会場は、東京駅の赤レンガ駅舎を彷彿させるような、荘厳な外観をした町立美術館であった。
広々とした館内には、蛯原蜜子の気配はなかった。私は、パーテーションで仕切られた通路を、順路に沿って歩いた。立ち止まって作品に見入っている二、三人の観客の背後を足早に通り過ぎながら、蛯原蜜子の作品をまともに直視することが出来なくなっている自分に気がついた。とにかく一刻も早く出口に到達したい、と私は願っていたのである。
やがて私は、出口付近に展示されている連作『EGOILL』の前を通り掛かった。ちらと新作らしき絵が横目に見えた。よりによって、あのシーンか……。私は立ち止まって、その絵をまじまじと眺めた。そこには、禁断のエゴイルの実を口にしている全裸のイヴが描かれていた。イヴの隣には、蛇に姿を変えた誘惑者サタンがいる。言葉巧みにイヴをそそのかしている場面である。
すると突然、絵の中のサタンが私に向かって語りかけてきた。「蜜子は今頃、お前のことなど忘れて、運命の人とよろしくやっているさ」
私は、蛇に睨まれた蛙のように硬直した。サタンはなおも続けた。「蜜子のことは綺麗さっぱり忘れちまえよ。お前とは縁がなかった。ただ、それだけのことだ」
私は、ぎくりとした。「ただ、それだけのことだ」という部分が、サタンのドスのきいた声ではなく、慣れ親しんだ私の声色で語られていたからである。
「お前には新しい恋人がいるんじゃないのか? お前、その娘と寝たんだろう?」
という私の声が脳内に響いた。喋っていたのは、絵の中のサタンではなかった。初めから私自身――私の内奥に巣喰うエゴイル――だったのである。
私は、その場から逃れるように会場を後にした。外に出ると、既に日はどっぷりと暮れていた。
私の前方を走る車の、赤々としたテールランプを頼りに、私は自宅へ向けて車を走らせた。近づいては離れ、離れてはまた近づく前方車両の二つのテールランプが、まるで人間の両目であるかのように私の目に映った。ランプに照らし出されたナンバープレートを口に見立てると、さしずめそれは女の顔のように見えた。テールランプの顔は、散々私を翻弄した挙げ句、やがて私とは別の道へと逸れていった。
自分は本当にこのゲームに参加しているのだろうか? という言葉が、ひとりでに私の口をついて出た。
その日を境に、私は蛯原蜜子に長文メールを送るのをやめた。
二〇一〇年十二月、しばらく連絡を断てば、痺れを切らした蛯原蜜子から連絡が来るかもしれない、という私の淡い期待は見事に打ち砕かれた。このままでは、私と彼女との関係が終わってしまう、という焦燥感に駆られた私は、およそ四カ月ぶりに蛯原蜜子にメールをした。
「クリスマスに久々にお会いしませんか?」とうってはみたものの、時は既に十二月中旬であった。きっと先約があるに違いない、と私は半ば諦めていた。ところが、意外にも彼女からすんなりとオーケーが出た。「お久しぶりです。その日は友だちと一緒にディナーに行く予定が入っているんですけど、その後だったらいいですよ」
何度かメールをやりとりした末に、蛯原蜜子の地元に私がおもむき、彼女の馴染みの店に一緒に行くことになった。具体的にどうするかは、全然決めていなかったけれど、私はその機会に最後の望みを託すことにした。蛯原蜜子と約束を交わす以前に、白石麻耶とクリスマスに会う約束をしていた私は、「どうしても断れない用事が出来た」と麻耶に嘘をついた。
クリスマスの前夜、蛯原蜜子からメールがあった。その夜、私は会社の同僚たちと一緒に居酒屋で飲んでいた。同僚たちからの冷やかしの言葉には一切耳を貸さず、私は急いで個室トイレに駆け込んだ。
きっと明日の待ち合わせ時間か何かの連絡だろう、と浮き浮きしながら、折りたたみ式の携帯電話を開いて、未読メールを開封した。すると、私の目に飛び込んできたのは、「急にどうしても断れない予定が入ってしまったので、明日の約束はなかったことにしてください。ごめんなさい」という予想外のメッセージであった。私は、トイレの床に崩れ落ちた。これで何もかも終わった、と思った。
翌年(二〇一一年六月)、私は白石麻耶と結婚した。結婚式の後、約半年ぶりに蛯原蜜子の携帯電話にメールをうった。結婚したということを、わざわざ彼女に報告したのである。
「おめでとうございます。第二の人生の始まりですね。末永くお幸せに」という短いメールがすぐに返ってきた。私は声を出して笑った。笑いながら、強い男に生まれ変わろうと思った。愛だの恋だのと吐かさないタフな男になってやる、と。
ハワイへのハネムーンやマイホーム購入の手続き、新居への引っ越しなどで半年ほど忙殺されたが、一旦生活が落ち着くと、私は自宅に簡易的なジムを作った。一番やりたくないことを自発的に行えば、その行為へのカウンターとして、一番やりたいことが更に出来るようになるに違いない、と考えたからである。
以後の私は、週に五回のウエイト・トレーニングと、週に二回のランニングを欠かさず行なうようになった。運動後と就寝前には必ずプロテインを飲むようにもなった。痩せ型であった筈の私の体型が、みるみるうちに筋骨隆々の体格へと変貌を遂げた。その様子に気づいた友人たちは、私に向かってこうたずねた。「何か特定のスポーツをしている訳でもなく、マラソンの大会に出場する様子もないのに、何で筋トレしたり走ったりしているんだ?」と。私が、「奇蹟的な曲を書くためだ」と答えると、友人たちはみな一様に、狐につままれたような顔をしていた。
一見すると音楽活動とは何の関連性もないような行動――例えば、ランニングや筋トレ、読書に、歯磨き、呼吸でさえも――が、実は音楽活動と密接に関わっているということを私は痛感した。以前から悩まされ続けてきた〈好不調の波〉に左右されやすい体質の改善に、私が乗り出したときのことである。
私はまず、手がかりをつかむために、滅多に振り返ることのない無益な日記を廃止して、簡単に顧みることが出来るような体裁で、日々の行動を記録し始めた。
「十八時三十分から十九時まで帰宅。
十九時から十九時三十分まで筋トレ。
十九時三十分から二十分時三十分までテレビを見ながら夕食。
二十時半から二十二時までゲームとネット。
二十二時から二十三時までギター練習。
二十三時から二十三時三十分まで風呂。
二十三時三十分から二時まで作詞作曲。」
という具合に、一切の感想を排した記録を淡々と取り続けたところ、私はあることに気がついた。今日は何だか調子が悪いな、と感じたときには、事前に必ず余計なことを――例えば、目的のないネットサーフィンに興じていたり、だらだらとテレビを見たり、ゲームをしてカッとなったり――しているということに。調子は、生理現象や自然現象に左右されるものではなかった。不調の波を呼び込んでいたのは、私自身の行動だったのである。
次に私は、好調の波を呼び寄せるにはどうしたらいいかを考えた。余計な行動を改めた上で私に何が出来るだろうか、と。そして、私は辿り着いた。日常生活において、それまで何気なく――つまり無意識のうちに――とっていた些細な行動や、新たな物事に自発的に――つまり意識的に――取り組めば、行動の相乗効果が発揮されるという秘密に。
例えそれが些細な行いであっても、意識的にとった行動は私の中に波紋を広げる。その波紋は、停滞していた他の行いに働きかけ、その行動の活発化を促してくれる。また、既に活発化している行動の波紋同士が重なり合った場合には、双方の行動に更なる弾みがつくのである。
私は、音楽活動に更なる弾みをつけるため、私の全ての行いに意図を持とうと努力した。だが、努力はなかなか実ってくれなかった。私は、自身を納得させられるような奇蹟的な曲を、どうしても書くことが出来なかった。
二〇一四年六月、私が白石麻耶と結婚してから三年の歳月が過ぎた。
ある晩、達也から「蛯原蜜子が結婚したらしい」というメールが届いた。私は、メールを見終えると、ランニングウェアに着替えて家を出た。
昼間の喧騒が嘘のようにかき消された夜道をひた走っていると、私の身体が漆黒の闇に溶かされて、意識だけが空中に浮遊しているかのような錯覚に陥ることがままある。死とは、このような状態のことをいうのではないだろうか、と私はいつも想像した。
その夜も私は願っていた。深閑とした夜の闇に紛れて、自分がこの世から消えてなくなってしまえばいい、と。しかし、夜空にはあいにくの満月が煌々と輝いていた。
歩道を走る私の身体が闇夜に溶け込みそうになるたびに、上空から照射される月光のサーチライトに邪魔されて、私はその都度現実世界に引き戻された。
私は、忌々しさを込めて満月を睨みつけた。すると、私の脳裏に〈徴と奇蹟を見ても信じなかった罰〉という言葉が、雲間から顔を覗かせた月のように、ぽっかりと浮かび上がった。
私は、月に向かって「頼むから、私のことは放っておいてくれ!」と叫んだ。そして、目の前の上り坂をがむしゃらに駆け上った。
二〇一四年七月、遂に私は自身の創作方法にもメスをいれることにした。それまでの私の曲作りは、スピリチュアルな――精神的で感覚的な――面に負うところが大きかった。まるで雨乞いをする祈祷師のように、天から降ってくる恩寵を頼みにしていた。セルフ鍼治療では霊験がないと感じたときには、自らを生贄とするために、進んで絶望の業火の中に身を投じることさえあった。地獄変の屛風を描くため、最愛の一人娘を乗せた檳榔毛の車が炎上する様を、食い入るように眺めていた『地獄変』の主人公――絵師・良秀――のように、ある種の狂気に取り憑かれなければ、奇蹟的な曲などとても書くことはできないのだ、と信じて疑わなかった。しかし、私は気づいたのである。感性至上主義は、エゴイルの誘惑――自身の怠慢を正当化するための方便――に過ぎなかった、と。怠慢とは、「せっかく今まで培ってきた経験を無駄にしたくない」。だから、「方法は変えたくない」。なぜなら、「一からやり直すのは面倒くさいから」という頑迷固陋な思考回路のことを指す。
大事なのは結果だ。結果を出せないのなら、「方法は間違っていない」という今までの前提は潔く打ち捨て、抜本的にやり方を変えてみるべきなのだ。手立てに固執することなく、刷新の労を惜しむことなく、絶えず変化をし続けることによって、具体的な行動の中に自我を埋没させ、私の中に巣喰うエゴイルを抹殺しよう、と私は考えたのである。
私は、それまでの自身の創作方法を一新すべく、日本語文法と音楽理論の勉強を開始した。文法と理論の修得には、実に三年の歳月を要した。が、私に迷いはなかった。それまで手探りで直感的に歩んでいた薄暗い小道が、照明灯の点る高速道路のように私の中で理路整然と明確化し、言葉と言葉を、音と音を、言葉と音を繋ぐ道筋が、手に取るようにハッキリと見えるようになった。覚醒した私は、堰を切ったように、怒濤の勢いで曲を書き始めた。
一年後、私が書き溜めた曲は優に百五十曲をこえていた。しかし、あらためて自分が書いた曲を聴き直してみると、すべての曲が駄作であるということに気がついた。その、能面のように無表情な、極端なまでに抑揚を欠いた自身の曲を聴きながら、私は悟った。同じことなんだ、と。
感情論だけに頼ることと、方法論だけに頼ることに大した差異はない。東の果てから西の果てに引っ越したようなものだ。どちらも極端であることに変わりはない。私は失笑した。馬鹿だ、と思った。なおも笑い続けていると、突然ブッダの〈弾琴の譬え〉が私の脳裏に浮かんだ。まるで眼前の川を過る小舟のように、言葉がゆっくりと頭の中を通過していったのである。
「弦は張り過ぎると切れてしまう。弛ませ過ぎると音が鳴らない。張り過ぎず、弛ませ過ぎず、程よく張った弦から良い音は鳴り響く……」
私は思わず天を仰いだ。
二〇一八年八月のある朝、私は、いつものように会社のデスクについていた。私の目線の先――キーボードの上――には、さる新入社員の女性からもらったプレゼントがのっていた。それは、ステッカーとリボンで可愛らしくラッピングされた小さな紙袋であった。
出張のお土産には、出張のお土産をもって返礼とするのが社内の慣例である。彼女のように、わざわざお返しを用意する人には、未だかつて一度もお目にかかったことがなかった。新入社員だから、まだ事情がよく飲み込めていないんだろうな……。私は、微笑ましく思いながら、水色のリボンに手をかけた。袋の中には桃色の金平糖とメッセージカードが入っていた。カードには「お土産ありがとうございます。大事に食べますね!」と書いてあった。
金平糖を食べながら、私は考えた。しかし、なぜ金平糖なんだろう? 金平糖が売られているお店を、私はすぐに思い浮かべることができない。――もしかして、何か特別な意味が込められていたりして?
私は、パソコンを使って〈金平糖〉と〈意味〉という二つのキーワードを検索してみた。
「金平糖は、手間暇かけて作られているお菓子です。ですから、長い時間をかけて愛を育む(永遠の愛)という意味が込められています。変な誤解を招かないように、異性にプレゼントするときには十分注意しましょう。」
女性の素振りや言い回しに、何らかの意味を見出そうとしてはいけない。
それが、過去の経験から私が学んだ教訓である。男性にとって意味深長な女性の表現には、本来何の深意も隠されていない場合がほとんどである。にもかかわらず、男性はそこに望みを託してしまう。ついつい、「俺に気があるんじゃないか?」と深読みしてしまう。うっかり行動に移そうものなら、「私はそんなつもりじゃありませんでした」とか「誤解しないでください」などと言われて、とんだ赤っ恥をかかされる羽目になるのが分かっていながら、また夢見てしまう。男の哀しい性である。
私は、モニターの陰に隠れながら苦笑した。そして、「これは誘惑のサインではないんだ」「単なる私の思い過ごしなんだ」と自分に言い聞かせた。
と、その時である。突然、私の視界が放射線状に何十キロも先まで一瞬にして開けたような、初めての感覚に襲われた。
私の視点は、つむじ風に乗って、野を越え、山を越え、谷を越え、田んぼのあぜ道に立つ一人の少女の姿を捉えた。白いワンピースを着て、白いストローハットをかぶったその少女は、まるで一羽の白鷺のようであった。
少女が差し出す両手の平の上には、一枚の桜の花びらがのっていた。その花びらをもっと近くで観察したい、という私の思いに呼応して、私の視点が少女に迫った。しかし、少女の花びらは、つむじ風に巻き上げられて、空の彼方へと飛び去ってしまった。「あぁ」という少女の嘆声を耳にすると同時に、私の視界が真っ白になった。
瞼を開けると、私はオフィスの喧騒の中にいた。電話のコール音や電話対応の声、キーボードを叩く音の中に混じって、どこからともなく甘美なメロディが聞こえてきた。私は目を瞑って耳を澄ました。微かに聞こえるそのメロディの出どころは、何と私自身であった。忘れかけていた過去の想いが、甘く切ないメロディとなって、私の胸の奥底で鳴り響いていたのである。
あの花びらが舞い降りた先は、きっと私の心の中なんだろう、と私は思った。そして私は、はたと気づいて目を開けた。
そうだ。私と蛯原蜜子のことを歌えばいいんだ。何で今までそんな簡単なことに気がつかなかったんだろう?
私は、その曲のタイトルを『エゴイル』にしようと思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
