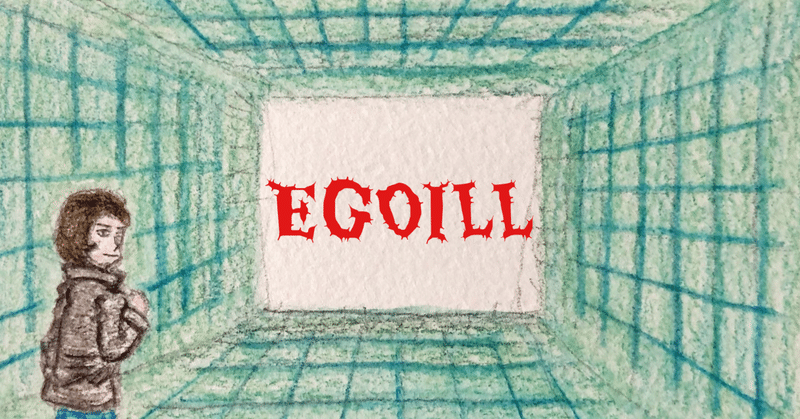
小説『EGOILL』Chapter.3
三、ストロベリー・フィールズよ永遠に
運命の人は、まるで不意に見つかった過去の探し物のように、突如として私の目の前に現れた。彼女は、意外にも身近なところに存在していた。というより、私は彼女を見知っていたのである。
彼女との再会をお膳立てしてくれたのは、大学時代の親友であった。高校まではほとんど友人を作ることが出来なかった私であったが、大学では多くの友人に恵まれた。中でも、同期生唯一の同郷出身者であり、私と同じく地元の企業に就職をした親友の達也とは、社会人になってからも頻繁に行動を共にする間柄であった。
その達也が、「たまには人前で演奏しないとギターの腕が鈍るぞ。俺の結婚式で滝夫の好きなジョンの曲でも演奏してくれよ」と言って、久しく音楽から遠のいていた私に、人前での演奏の機会を与えてくれたことが、私と彼女とを繋ぐきっかけになったのである。
二〇〇八年十月、ブルージーなコード――Am7――から奏でられる調べで、あらゆることが物語られそうな仲秋の気配を感じ始めた頃、私は、スーツの上からアコースティックギターを斜に背負い、譜面台を片手に披露宴会場を訪れた。
玄関を入ると、中は正方形をした吹き抜けのロビーになっており、正面突き当り、会場のドアの手前に受付があった。受付の長机の前に列をなしている人々の最後尾に加わり、私は頭上を仰ぎ見た。まるで蜘蛛の巣が張り巡らされたような大きなシャンデリアが一基、天井から垂れさがっていた。そのまま視線を左に移すと、二階の手すりから身を乗り出している白いタキシード姿の新郎、達也の姿が目にとまった。
「滝夫!」という達也からの呼びかけに、私は左腕を挙げて応えようとした。が、彼は既に大理石の階段を駆け下り始めていた。
「よう、よく来てくれたな」、達也はそう言いながら私のところにやって来ると、右手を私の左肩に乗せてきた。トレードマークのぼさぼさ頭が綺麗に整髪されていた。実に晴れがましい姿だ、と私は思った。
「達也、結婚おめでとう」
「早速だけどさ」と達也はいきなり切り出した。「お前の出番は、花嫁の手紙の一つ手前だから」
「え?」と私は聞き返した。達也の発言をうまく咀嚼できなかったからである。
花嫁の手紙といえば、「お父さん、お母さん、今まで私を育ててくれてありがとう」と、新婦が涙ながらに両親に向かって感謝の意を述べる、披露宴最大の見せ場である。私はてっきり、自分は中盤の場繋ぎ役――披露宴につきものの、刺し身のつまのような端役――だとばかり思っていた。ところが、蓋を開けてみたらまさかの終盤起用だったのである。
達也は、「じゃ、頼むな」と言ったかと思うと、踵を返してさっさと二階に戻っていった。
階段をのぼる達也の後ろ姿を見送りながら、私は過去に出席した大学時代の友人の結婚披露宴のことを思い出していた。
披露宴の当日、私はその友人から〈新郎の友人代表の挨拶〉を依頼された。慌ててスピーチの内容を考え、悶々としながらスタンバイしていたにもかかわらず、司会のお姉さんの口をついて出た友人代表者の名前は、私の名前ではなかった。
あいつといい、達也といい、全く私の友人たちときたら……。私は思わず苦笑した。
達也の結婚披露宴が始まってからの私はと言えば、出された料理はろくに喉を通らず、会場とロビーをせわしなく行ったり来たりし、意味もなく何度もギターのチューニングを確認し、喫煙所で無闇やたらにタバコを何本も吸う、という絵に描いたような落ち着きのない人になってしまった。
中盤の余興では、達也の高校時代の友人であるという男子四人組が、バンド演奏を行った。彼らが奏でる軽妙なロックサウンドを目の当たりにした私は、猛烈な焦燥感に駆られた。達也の野郎、わざと被せてきやがったな……と私は思った。
プログラムがキャンドルサービスまで進行すると、お色直しを済ませた新郎新婦が各テーブルを巡回し始めた。二人は私たちの席にもやって来て、テーブルの上のキャンドルに火を点しながら、私以外の連中と和やかに談笑していた。
すると、達也が私のほうを向いて、「なんだ滝夫、デザートに全然手をつけていないじゃないか。お前甘いもの大好きなのに、どうしたんだ?」と言った。何もかもお見通しのくせに、私をからかおうとして、敢えてそう言ったに違いなかった。
私は、後頭部を椅子の背もたれの上に乗せ、目線だけを新郎新婦におくりながら答えた。「うるせー、こっちはそれどころじゃねぇんだよ」
司会のお姉さんによる祝電の披露がはじまった頃、女性スタッフが中腰のまま私の元に駆け込んできた。「中村さんでいらっしゃいますか?」
私は、「はい、そうです」と答えながら、彼女の機敏な動きはまるで〈くノ一〉のようだ、と思っていた。「演奏の準備をお願いします」と、彼女は私に向かって言った。
くノ一のお姉さんに促されるまま、私は会場を抜け出した。フロントに預けていたアコースティックギターを受け取ってから、閉ざされた中央扉の前まで行って出番を待った。私の左隣に控えているお姉さんは、ヘッドセットタイプのトランシーバーに向かって、しきりに何やら話しかけている。しばらくすると、彼女の声がぷつりと途絶えた。私は、反射的に彼女のほうを見た。私と彼女の目と目が合った。彼女は私の目を見据えたまま、ゆっくりとうなずいてから言った。「出番です」
目の前の中央扉が勢いよく開いた。その瞬間、優に百人はこえるであろう出席者たちの視線の矢が、私めがけて一斉に飛んできたような気がした。
「新郎のご友人でいらっしゃいます、中村滝夫さんによるギター弾き語りです。みなさん盛大な拍手をお願いします!」
司会のお姉さんによるコールが終わると、場内から一斉に拍手が沸き起こった。
私は、気力を振り絞って最初の一歩を踏み出した。盛んな拍手を浴びながら、司会のお姉さんの前を通り過ぎ、新郎新婦席の前に歩み出た。まずは出席者のみなさんに一礼し、用意されていたパイプ椅子に腰掛けた。次にスーツのポケットからコードと歌詞を書いたカンニングペーパーを取り出して、目の前の譜面台の上にのせた。最後にスタンドマイクの位置を微調整してから、「みなさん、こんばんは。新郎の友人の中村滝夫と申します」と私は言った。そして、マイクから口を離さない程度に背後を振り向きながら続けた。「達也くん、真由美さん、この度はご結婚おめでとうございます……って、おっさん聞いてるのか!」
私が祝いの言葉を述べているというのに、そっぽを向いて誰かと談笑している達也に思わず腹が立った。「……失礼しました。それでは、ジョン・レノンのカバー、聴いてください」
一曲目は、『You've Got To Hide Your Love Away』。正確に言えば、これはビートルズ(Lennon / McCartney名義)の曲であって、ジョンのソロナンバーではない。が、ジョンがリードボーカルをとっているので、まぁいいかと思って採用した(曲の長さが極端に短いというのが一番の決め手であった)。オリジナルの音源では、アウトロの演奏にフルートが使用されている。フルートを吹けない私は、そのパートを口笛で演奏した。
二曲目は、『Strawberry Fields Forever』。この曲も同じくジョンのソロナンバーではないが、ジョンがリードボーカルをとっているし、何より私の一番好きな曲だから採用した(コード進行と歌詞を丸暗記しているので、あらためて練習をする必要がなかったのである)。「えー、みなさんのテーブルの上にもイチゴがのったケーキが置いてありますが、次の曲はストロベリー・フィールズ・フォーエバーです」という、我ながら訳の分からないMCをしてしまったと反省しながら、そつなく演奏を終えた。
最後ぐらいはジョンのソロナンバーを、と思って『Woman』をチョイスしていた。同じウーマンでも、『Woman Is The Nigger Of The World』だったら会場もさぞかしドン引きだったろうな、というような考えが一瞬頭を過ったことを記憶している。曲の最後に奏でたコードの余韻が消えると同時に、私は椅子から立ち上がった。会場全体から沸き起こる拍手喝采。ああ、この感じ、久し振りだな。達也、気を遣ってくれてありがとうな。私は、親友のお膳立てに心の中で感謝をしながら、出席者のみなさんに向かって深々と一礼した。
会場を退出する際、中央扉の前で待っていてくれたくノ一のお姉さんが、「お疲れさまです」とねぎらいの言葉をかけてくれた。彼女の笑顔を見て、私はようやくほっと胸をなで下ろした。
喫煙所でタバコを一服しながら、あーあ、明日会社行きたくねぇな……と私はひとりごちた。
二次会は居酒屋を貸し切って行われた。
元来、酒に滅法弱い私は、乾杯の際に飲んだビール一杯で、あっという間に酔っぱらってしまった。酔いに身を任せながら、私は達也の姿をぼーっと眺めていた。達也は、まるでミツバチのように甲斐甲斐しく、人々のテーブルの間を行ったり来たりしていた。あいつは昔から変わらないな。いつの間にか私は、私と達也の大学時代のエピソードを思い出していた。
それは、あるサークルの飲み会で起こった出来事である。いつものように調子に乗った私は、その場の皆に「刮目せよ」と言わんばかりに、日本酒とワインを立て続けにビン一気した(ビンに入ったお酒を一気にラッパ飲みすることを私達は〈ビン一気〉と呼んでいた)。私は、あっという間に泥酔して、前後不覚に陥った。
気が付くと、私は達也の部屋のベッドに寝かされていた。
「全裸の滝夫がトイレで倒れているって聞いて、慌てて飛んで行ったよ」と達也が私に語りかけてきた。「大丈夫か?」
私は、「大丈夫だ」と答えようとした。が、答える代わりにベッドの上に嘔吐した。
達也は、「しょうがねぇやつだなぁ、お前は」と笑いながら、私の嘔吐物を文句も言わずに片付けてくれた。彼は本当に面倒見のいいやつなのである。
そんな私の回想を知ってか知らでか、にたにた笑いを顔に浮かべながら、当時の被害者の達也が私の隣にやってきた。「滝夫、お前に紹介したい人がいるんだ。ちょっと一緒に来てくれるか」
達也に腕をとられ、私はある女性の前まで連れて行かれた。
達也は、「みつこちゃん」とその女性に声をかけた。「コイツ、俺の親友の滝夫。さっき披露宴で演奏してくれたやつ。将来のミュージシャンなんだけど、今はしがないサラリーマンなんだ」、達也は私のほうを向いて続けた。「滝夫、こちらは〈えびはらみつこ〉さん。お医者様なんだけど、絵も描いていらっしゃる。きっとお前と気が合うと思ってな」
私とその女性とが軽く会釈を交わしていると、達也は素早く私の耳元に顔を寄せてきた。そして、「後はよろしくやってくれ」と囁いたかと思うと、私たちを置いてさっさと別のテーブルへ行ってしまった。
後に残された私は、仕方なく〈えびはらみつこ〉の隣に座った。どこかで聞いたことがあるような名前だな……と思いながら、私は彼女の顔をまじまじと見つめた。
あっ、アテロームの君だ! たちまち過去の記憶がよみがえった。私の隣に座っていたのは、大学病院で私にヒップを密着させ、さらに私の盲腸の手術痕に触れた女医、蛯原蜜子その人だったのである。
三年振りに会った彼女は、がらりと印象が変わっていた。眼鏡を外していることと髪型がボブからロングに変わっていること、白衣ではなく黒いパーティードレスを着ていることが印象の変化の大きな要因であったかもしれない。が、陽から陰に属性が変わったというか、以前は快活そうに見えた彼女の雰囲気が、しっとりとして落ち着いた大人の女性のそれへと、変貌を遂げていたのである。その胸元には、三日月のペンダントがきらりと光っていた。
「披露宴での演奏、すごく良かったですよ」と蛯原蜜子が口火を切った。「実は私も『Strawberry Fields Forever』が大好きなんです。特にこの部分が――」、彼女はそう言うなり、小さな声で口ずさみ始めた。
「Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
目を閉じていれば人生なんて容易いものさ
全てを誤解してしまうのだからね」
Lennon / McCartney『Strawberry Fields Forever』より
落雷が頭頂部に直撃し、稲妻が全身を駆け巡ったような衝撃を私は受けた。――まさか、彼女がその人なのか?
蛯原蜜子は、フリーズしている私を見て、きょとんとした様子であった。
「いやぁ、実は俺も同じ部分が一番好きなんですよ」と私はようやく口を開いた。「だから、ちょっとびっくりしちゃって……」
二次会がお開きになるまで、私は蛯原蜜子と夢中になって話をした。が、「ホームページを必ず見る(彼女の絵画作品がアップロードされているらしかった)」ということと、「今度会ったら恋愛の話をしよう」という約束を交わしたこと以外、他に何を喋ったのかは一切覚えていない(ちなみに、彼女は私のことを全く覚えていない様子であった)。
三次会は、達也夫妻が宿泊するホテルの十二階にあるバーで行われた。新婦を始めとする女性陣が、みな早々に引きあげてしまったので、後に残ったのは野郎たちばかりであった。私は、落雷のショックから未だに立ち直ることが出来ずにいた。
「滝夫、今日は本当にありがとな」という達也の声がした。
「えっ、何のこと?」と言って、私は声のしたほうへ振り向いた。すると、いつの間にか隣のシートに達也が座っていた。
達也は、私の発言を特に気にする様子もなく、「お前、蜜子ちゃんのこと気に入ったんだろ?」と言ってニヤリと笑った。
「えっ、蜜子ちゃん? ああ、彼女のことか」
達也は、一瞬間を置いてから、「彼女、すごくもてるらしいから、そのつもりでな」と言った。
「そのつもりって、どのつもりだよ?」
「わはははは、まぁ飲もうぜ、今夜はとことん!」
午前三時過ぎ、私はタクシーの後部座席に乗り込んだ。運転手に自宅の住所を伝え、車が発進するのを見届けてから、私はスーツの右ポケットの中に手を入れた。蛯原蜜子のホームページのアドレスと、電話番号を書き留めたメモ用紙が、ちゃんとポケットの中に入っているかどうかを、念のため確認したのである。
私の自宅を目指して快走するタクシーの車窓から、夜空に煌々と輝く三日月の姿が見えた。蛯原蜜子の胸元に光っていた三日月のペンダントを思い出した私は、口元を三日月形に綻ばせた。

👇 続きはこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
