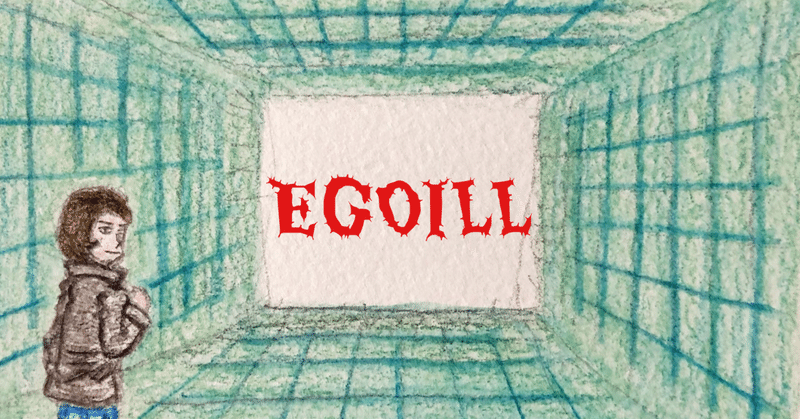
小説『EGOILL』Chapter.1
あらすじ
「〈エゴイル〉というのは、私が発見したウイルスの名前なんです」と彼女は静かに口を開いた。「エゴイルは人間をゾンビに変えてしまうんです」
予想だにしなかった回答に私は首をひねった。「ゾンビ……?」
『EGOILL』Chapter.5より
社畜(ゾンビ)人生をおくっていた滝夫は、ある女性との出会いをきっかけに、かつて志していた芸術の道を再び歩み出す。
芸術の道とは、真に人間たろうとする道。
しかし、真に人間たろうとすればするほど、滝夫個人の人間的幸福は滝夫の手のひらからこぼれ落ちていく。
エゴイルとの死闘の果に、滝夫が手にしたものとは一体?
『EGOILL』について
『EGOILL』は、2017年1月から2019年9月まで、合計805.9時間(48354分)をかけて執筆した作品である。
執筆に入る前には、丸三年をかけて準備した。具体的には、日本語文法を一から学び直したり(ことに接続詞については、その使用方法を徹底的に精査した)、macbookを購入したり、執筆アプリScrivenerの使用方法を覚えたり、構想を練ったりした。
個人的には、未だ明確に定まっていない日本語の文体「だ・である調」における文末の書き分けについて、作中一定のルールを設けることが出来たのではないか、と自負している。
noteへの投稿に際して、原文の漢数字の一部をアラビア数字に書き換えた。
2023年4月29日 タキオン=フィンク
「どうしてお前たちはわからないのか?」――それはクリストひとりの歎声ではない。
後代にも見じめに死んで行った、あらゆるクリストたちの歎声である。
芥川龍之介『続西方の人』青空文庫より
一、サイン
生きているという実感がない。
自分は既に死んでいるのではないか、と車を運転しながら時々思う。気づかないうちに事故を起こして、実際には死亡しているけれど、車ごと霊体となって、そのまま運転し続けているのではないか、と。
「中村滝夫さん、四番診察室へお入り下さい」
頭上のスピーカーから、若い女の声が聞こえてきた。大学病院の待合室のベンチに座っていた私は、顔を上げ、席を立った。リノリウム張りの中廊下に反射する蛍光灯の光が、まるで道路のセンターラインのように真っ直ぐに伸びていた。その光のラインの上を私は歩いた。コツコツという私の靴音が、しんとした廊下に響き渡った。
四番診察室の入り口には、扉の代わりに白いカーテンがかけられていた。私は、立ち止まって他の診察室の入り口を見回した。どの診察室の入り口にも、ちゃんと扉がついている。なんとなく釈然としない思いを抱きながら、私はカーテンを引いて中に入った。
診察室に足を踏み入れた私は、一瞬、入る部屋を間違ったかと自分の目を疑った。部屋の広さは四畳半ぐらい。両サイドに壁はなく、代わりに入り口のそれと同じような白いカーテンがかけられている。室内には、医療用家具が二つしかなかった。入って右手にデスクが、左手にベッドが、向かい合わせに一台ずつ配されているのみである。その二台の医療用家具に大半のスペースを占領された診察室は、まるで貧乏大学生の下宿部屋のように狭苦しかった。
診察室の中には、デスクに向かって書き物をしている女医と、私の他には誰もいなかった。私の存在をまるで意に介していないように見える女医の横顔に向かって、「よろしくお願いします」と声をかけながら、私は彼女の右隣に置いてあるスツールに座った。――にもかかわらず、女医は一向に私の存在に気づく様子がなかった。そんなに熱心になって一体何を書いているんだろうか、と不審に思った私は、彼女の手元を覗き込んだ。
女医は、ノートに絵を描いていた。人物のラフスケッチらしきものが、ちらりと見えた。思わず私は、「落書き?」と口走った。
「えっ」、デスクから顔を上げた女医が、私のほうへ振り向いた。「た……大変失礼しました。今日はどうなさいましたか?」と女医は取り繕うように言いながら、慌てた様子でこちらへ向き直った。彼女がかけている眼鏡のレンズが、蛍光灯の光を反射してきらりと光った。
私は面食らった。彼女は私と同年輩か、あるいは私よりも歳が若そうに見えたからである。この人で大丈夫だろうか? 私は一抹の不安を覚えた。
「去年もこの病院で診てもらったんですけど……」、私は右腕を少し上げ、左手の人差し指で右脇の下を指した。「前回切除してもらったアテロームが、また腫れてきて痛むんです」
「いつごろからですか?」
「一、二週間ぐらい前から、かな」
「ちょっと脇の下を見せてもらってもいいですか?」と女医は真剣そうな面持ちで言った。「上着を脱いで、そこのベッドに横になってください」
私は「はい」と答えると、着ていた黒いポロシャツを頭から脱いで、ベッドサイドの籠の中に放りなげた。そのままベッドの上に仰向けになると、女医が席を立って私の右隣にやって来た。
私は右腕を上げた。会ったばかりの若い女性に、自分の脇の下を晒すのは、何となくきまりが悪かった。
女医は、私の右脇の下にそっと触れた。そして、指先を使って腫れ物を探し始めた。
「ここですか?」
「いや、もうちょっと下のほうです」
「あ、確かに……少し腫れていますね」
腫れ物をこねくり回された私は、鈍い疼きを覚えた。
「痛みますか?」と女医が言った。
「ええ、少し痛みます」
「エコーで詳しく調べてみましょう。私の後について来てください」
「はい」
私は、ポロシャツを籠の中から拾い上げて着た。そして、女医に続いて診察室を後にした。
そういえば、去年もエコーで調べてもらったっけ。女医の背中を追いながら、私は思い巡らせた。去年ここへ来たときに私を担当してくれたのは、物腰のやわらかいスキンヘッドの中年男性医だった。あの医者はどこへ行ってしまったのだろう。この病院のどこかで、今でもやわらかい物腰をしているのだろうか?
やがて女医は、〈検査室〉というプレートがついたドアの前で立ち止まり、私のほうを振り返って言った。「ここです」
女医と共に検査室に入った私は、彼女に促されるまま再び上半身裸になり、部屋の最奥部に設置されたベッドの上に仰向けになった。
「ちょっと冷たいですけど我慢してくださいね」
女医は、ネバネバしたジェル状の液体を私の右脇の下になすりつけたかと思うと、私が寝ているベッドの右端にちょこんと腰掛けた。そして、トランスデューサー(バーコードリーダーのような形をした器具)を用いて、私の脇の下をゆっくりとなぞり始めた。
私は、女医がベッドの端に腰掛けたことに違和感を覚えていた。かつてスキンヘッドの中年男性医が、ベッドの脇にある椅子に座った状態で、器具を操作していたことを思い出したからである。
なぜ彼女は、敢えて不安定なシングルベッドの端に腰掛けたのだろうか。例えば、私の腫れ物が左脇にあるとしたら、彼女がベッドに座った理由も頷ける。私の体を越えて器具を操作するのは骨が折れるだろうから。しかし、腫れ物は右脇――つまり、彼女にとっては手前側――にあるのだ。素直に椅子に座ったほうが検査が捗る筈なのに……。
すると突然、私の思考を遮るかのように、何かが私の腰の辺りに接触し、更にそのまま密着した。眼球だけを動かして、恐る恐る下半身のほうを見てみると、私に触れているものの正体は、女医のヒップの側面であった。
驚いた私は、女医の顔を仰ぎ見た。しかし彼女は、ベッドの脇に設置された音波検査機のモニターを、食い入るように見つめているだけで、私の視線はおろか、私との接触――そして密着――のことも、まるで意に介していない様子であった。
女性の素振りや言い回しに、何らかの意味を見出そうとしてはいけない。
それが、過去の経験から私が学んだ教訓である。男性にとって意味深長な女性の表現には、本来何の深意も隠されていない場合がほとんどである。にもかかわらず、男性はそこに望みを託してしまう。ついつい、「俺に気があるんじゃないか?」と深読みしてしまう。うっかり行動に移そうものなら、「私はそんなつもりじゃありませんでした」とか「誤解しないでください」などと言われて、とんだ赤っ恥をかかされる羽目になるのが分かっていながら、また夢見てしまう。男の哀しい性である。
私は、「これは誘惑のサインではないんだ」「単なる私の思い過ごしなんだ」と自分に言い聞かせながら、何か別のことを考えようと努めた。
私の脇の下にあてがわれているトランスデューサーが、脇毛をバーコードとして認識する専用のリーダーだったとしたら、そして、モニターに映っている情報が、私の値段だったとしたら、面白いかもしれない。モニターを見つめている女医から、「私とこの男とでは価格的に釣り合いがとれないわね」、なんて思われていたりなんかして……。
「どうやらアテロームが再発しているようですね」、女医はモニターを凝視したまま言った。
「ってことは、また手術しなければならないということですか?」
局部麻酔をうたれ、メスでザクザクとアテロームを切り取られた前回の手術の光景が、私の脳裏によみがえった。もう二度とあのような思いはしたくない、と思った。
「とりあえず診察室に戻ってから話しましょうか。中村さんも裸のままでは寒いでしょうし」
女医はそう言い終えるや否や、ベッドの脇に据え置かれたテッシュ箱から二、三枚のティッシュを抜き取って、トランスデューサーに付着したジェルを手早く拭き取った。
女医がベッドから降りると、マットレスがふっと浮き上がった。彼女はそのまま、部屋の隅に設置された医療品棚まで歩いて行き、引き出しの中から畳まれた白いハンドタオルを一枚取り出した。そのタオルを私のほうへ差し出しながら、「これで脇の下を拭いて下さい」と女医は言った。私がタオルを受け取ると、女医は棚の横にある籠を指さして言った。「拭き終わったら、あそこの籠の中に入れておいて下さいね」。そして、彼女は一人でさっさと部屋から出て行ってしまった。
私は、それまで女医が腰掛けていたベッドの端に座り直した。脇の下についたジェルをハンドタオルで拭い取り、ベッドサイドの籠の中からポロシャツを拾いあげて着た。かつてスキンヘッドの中年男性医がそうしてくれたように、女医が私の脇の下を拭いてくれるものとばかり思い込んでいた私は、肩透かしを食らったような気分であった。
四番診察室に戻る途中、私は前年に聞いたアテロームの説明を思い返した。
「本来であれば、新陳代謝によって自然に体外へ排出されるはずの老廃物――例えば、皮脂や角質――が、表皮の内部に出来た袋の中に閉じ込められ、更なる新陳代謝によって肥大化したものをアテロームと呼びます。ケースによっては、アテロームの頭頂部に小さな穴が開き、そこから白くて臭い糊状の老廃物が流れ出ることもあるのですが……見たところ、中村さんのアテロームには……穴は開いていないようですね」
スキンヘッドの中年男性医の声を聞きながら、私は火山を連想した。表皮の腫れを山に、皮膚の内部に溜まった老廃物をマグマ溜まりに見立てたのである。
もし、アテローム火山が爆発したとしたら――つまり、溶岩の代わりにどろどろとした白い液体が悪臭を放ちながら流れ出し、火山灰の代わりに皮脂と角質の塊が勢いよく噴き出したとしたら――どうなるだろうか? そんな馬鹿げた空想に耽ったことも思い出した。
白いカーテンを抜けると、女医はまたデスクに向かって書き物をしていた。私がスツールに座ると、彼女はすぐにこちらに向き直った。
私は、はっとした。女医の顔立ちが意外と整っているということに初めて気がついたからである。
フレームの細い眼鏡の奥には、意思の強そうな一対の瞳が揃っている。この眼鏡と瞳との組み合わせが、いかにも利発そうな印象を見る者に与える。鼻は小さくもなく大きくもない、主張し過ぎない形をしている。口角がきゅっと上がっていて、見ているこちらの口角まで釣られて上がりそうになる。少し茶色がかった黒髪は、顎のラインで切り揃えられ、快活そうな彼女にとてもよく似合っている。胸につけている名札には、〈蛯原蜜子〉と書いてある。蛯原はいいとしても、蜜子……蜜子か……。彼女の外見のイメージとはかけ離れた、いかにも古くさい名前だ。
「少し問診させてもらってもいいですか?」と女医が語りかけてきた。
「どうぞ」と私は答えた。
「お仕事は何をなさっていますか?」
「それは私の職種をたずねているのですか? それとも、私の仕事の作業内容をたずねているのですか?」
「職種です」
間髪を入れずに、あまりにもキッパリと女医が答えたので、私は思わず噴き出してしまった。彼女も釣られて笑っていた。
「うーん、簡潔に言い表すとするなら、私の仕事はIT系に分類されると思います」
「事務系のお仕事ですか?」
「ええ、まぁそんなところです」
「過去に何か大病を患ったことはありますか?」
「十三歳のときに盲腸を切ってもらいました。それと、えーと、二年前だから……二十七歳のときに尿管結石を患いました。去年、アテロームの手術をここで受けました」
「それでは、ご家族には、どなたか過去に大病を患ったかたはいらっしゃいますか?」
私は一瞬答えに窮した。というのも、私は二歳の頃に実の両親から捨てられ、以来養父母の手によって育てられた。だから、血の繋がった肉親のことは何も知らない。そのことを医者に説明するたびに、私と医者との間に気まずい沈黙が訪れるのが、私の悩みの種であった。世の中には様々な素性の人間がいるのだから、それくらいの回答でいちいち驚かないでもらいたい、というのが医者に対する私の本音であった。
「血の繋がった肉親には、今までお目にかかったことがないから、よくわからないですね」
女医の表情が一瞬こわばった。「それは失礼しました……」
私は視線を女医から外し、何気なくベッドのほうを見た。四番診察室と隣室とを隔てる白いカーテンが、エアコンの風を受けて微かに揺れていた。
その時になって私は初めて気がついた。デスク側のカーテンの向こうで、男が誰かと電話で話をしているということに。
「なぜ、私に取り次いだのか」「この程度のクレームには、そちらで対応してもらいたかった」「いちいち応対していたらこちらの身が持たない」
医師と思しきその男は、ヒステリックな口調で内線相手をまくし立てていた。男の言葉の端々にあらわれる他者を見下したような態度に、私は不快感を覚えた。
「それでは、手術の痕を見せてもらってもいいですか?」と女医が突然提案してきた。
この人は何を言っているんだ、と私は思った。「えーと、手術の痕はさっき診てもらいましたよね?」
「アテロームの手術痕ではなく、盲腸の手術痕のほうです」
「盲腸の……って、十三歳の頃の傷痕ですよ?」
「ええ、分かっています」、女医は一瞬間を置いてから続けた。「駄目でしょうか?」
「まぁ、別に見せてもいいですけど……」
私は、スツールに座ったままベルトを緩め、右下腹部付近のズボンの縁と、パンツの縁とを一緒にめくった。が、それだけでは、盲腸の手術痕を女医に見せるには至らなかった。座ったままでは駄目だと思った私は、立ち上がってスツールの左横に移動した。手術痕が顔を覗かせるまでズボンとパンツをずり下げると、臍の下部に生えている私の腹毛が、女医の前に露わになった。病院に来て、なぜこのような羞恥プレイを受けるはめになったのか……。私は、軽いトランス状態に陥っていた。
「ああ、それですね」と女医は目を丸くして言った。
次の瞬間、何を血迷ったのか、彼女は私の下半身の前にひざまずき、両手の指先を使って私の手術痕に触れた。私は驚愕すると同時に、思わず内心で喘ぎ声をあげた。
そんな私の陶酔にはお構いなしに、女医は踵を返してさっさとデスクに戻ってしまった。我に返った私は、衣服を元に戻してスツールに座った。
女医は、おもむろにキーボードをうち始めた。彼女の指先が奏でる小気味の良いタイピング音に呼応して、デスクに設置されたモニターに映る電子カルテが、あっという間に小さな文字で埋め尽くされていった。一方、電子カルテとは対象的に、私の頭の中は次第に真っ白になっていった。
今回の診断において、私の盲腸の手術痕を見る必要性が一体どこにあるというのだ。さっきの密着の件といい、今の件といい、どう考えても彼女の行動はおかしいじゃないか。――いや、待てよ。勉強熱心な彼女は、彼女以外の医師が執刀した手術痕に興味があった、と考えてみてはどうだろう。それなら辻褄が合いはしないだろうか。彼女は、いわば手術痕マニアなのだ。……って、そんな馬鹿な。
「しばらくお薬で様子を見ることにしましょう」と女医はパソコンのモニターを直視したまま、突然口を開いた。そして、くるりと椅子を回転させ、私と向かい合ってつけ加えた。「ひとまず一週間分の抗生物質を出しておきます。それで腫れが引くかどうか試してみましょう。一週間後にまたお越し下さい」
一週間後の朝、私は再び大学病院の待合室のベンチに座っていた。その日は、月に一度の全館合同ミーティングの日であったらしく、診察が開始される筈の時刻を過ぎても、医師たちは一向に姿を見せる気配がなかった。
私は、ポロシャツの左胸のポケットに忍ばせている名刺の存在を、右手の指先でそっと確認した。裏面に、「よかったら連絡を下さい」というメッセージと共に、私のプライベートの連絡先を書き記したその名刺を、私は女医に手渡すつもりであった。
かつて掛かり付けの歯科で、この方法を用いたことがある。お相手は、栗色の髪をポニーテールにまとめた、八重歯が印象的な二十一歳の歯科衛生士であった。
治療後のお会計の際、受け付け窓口のガラスの向こう側に、八重歯の彼女が姿を現したタイミングを、私は見逃さなかった。私は、紙幣と一緒に、それを窓口の隙間に差し込んだ。彼女は、私の名刺の存在に気がつくと、初めはきょとんとしていたけれど、裏面のメッセージに目を通すなり、すぐに事の次第を承知したようであった。無言のまま、それをポケットにしまい込んだ彼女は、何事もなかったかのような態度で、釣り銭を私に手渡してくれた。
その日の夜、首尾良く彼女から連絡が来て、私達はデートの約束を交わし合った。八重歯の彼女と同じ手が、女医に通用するかどうかは分からないけれど、何もしないよりはましだ、と私は考えたのである。
頭上のスピーカーは、頑なに沈黙を守っていた。
抗生物質を一週間飲み続けた結果、私のアテロームはすっかり鳴りを潜めてしまった。綺麗に腫れがひいて、痛みもなくなった。毎夜、頼むから治らないでくれ、と念じていたが無駄であった。通院するのは恐らく今回が最後になるだろう、と私は踏んでいた。ラストチャンスである。
しばらくすると、医師達がぞろぞろと列をなしてやって来て、各々の診察室に姿を消していった。例の女医、蛯原蜜子もその列の中に混じっていた。いよいよだな、と私は身構えた。
「中村滝夫さん、一番診察室へどうぞ」
スピーカーから男の声が聞こえてきた。私は、嫌な予感がした。
恐る恐る一番診察室のドアを開けると、私を待ち受けていたのは、果たしてあの物腰の柔らかいスキンヘッドの中年男性医であった。
呆然とその場に立ちつくす私に向かって、スキンヘッドの中年男性医がにっこりと微笑みかけてきた。
「お久しぶりです、中村さん。アテロームが再発したと伺いました。薬の効果はありましたか?」

👇 続きはこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
