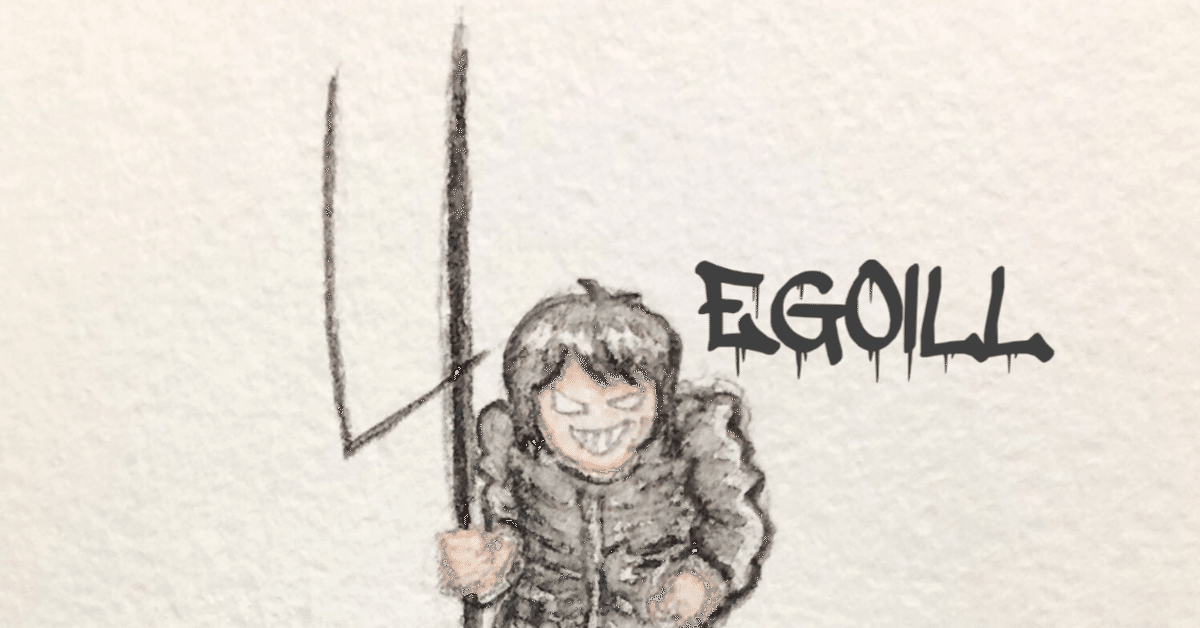
小説『EGOILL』Chapter.7
七、徴と奇蹟
道はやがてなだらかな上り坂になり、登坂車線が一本増えた。私は、アクセルを目一杯踏み込んだ。再び車線が一本に統合されるまで坂道を上り詰めると、峠にくり抜かれたトンネルが見えてきた。そのトンネルを抜けると、突然視界に青空が広がった。
山々の頭上を覆うように入道雲が悠然と浮かんでいる。眼下に蛯原蜜子の住む町を望みながら、今度は下り坂をひたすら下った。ようやく平地に出たところで、運悪く赤信号につかまった。私は、車内から周囲を見渡した。その町には、高層建築物がほとんど存在しなかった。交差点を左折して、なおしばらく直進すると、左手に個展会場が見えてくる筈であった。……が、それらしき建物は一向に見当たらなかった。
私は路肩に車をとめた。前方から、農婦然としたお婆さんが歩道を歩いて来るのが見えた。私は、助手席のパワーウィンドウを開け、お婆さんが私の車の横を通りすがるタイミングを待った。
「ほれ、あそこを右に曲がった先じゃ」と、お婆さんは道を指し示してくれた。
私は、お婆さんにお礼を述べ、車を方向転換した。そして、もと来た道を引き返し、お婆さんから教わった道を右折した。
〈ギャラリーとらのこ〉は、小高くなった丘の上に建っていた。ログハウスのような外観は、一見すると民家のようにしか見えなかったが、近づいてみると看板らしきものが丘のふもとに立っていた。ふもとには、砂利敷きの簡易的な駐車場があった。三台分の駐車スペースの一番右側には、蛯原蜜子の愛車(水色の日産・パオ)が停まっていた。
げ、彼女がいる! 私は、にわかに緊張した。
私は、パオの左隣のスペースに自身の車(紺色のダイハツ・ミラジーノ)を駐車した。車を降りると、丘の上のギャラリーに通じる木製の階段が目についた。私は、階段をのぼりながら、腕時計に目をやった。時刻は午後二時半を少しまわったところであった。
私は、丸太造りのドアに取り付けられている鉄製の取っ手に手をかけた。「こんにちは」と言いながらドアを開けると、カランカランとドアチャイムが金属音をたてた。すると、最初に私の目に飛び込んできたのは、テーブルを挟んで向かい側の席に座っている蛯原蜜子の姿であった。
うわぁ! まさかいきなり正面きって彼女と出くわすとは思ってもみなかった私は、内心ぎょっとした。
「あ、中村さん、いらっしゃい」と蛯原蜜子が私に気づいてくれた。
「やあ、お久しぶり」と私は平静を装って言った。そういえば、蛯原蜜子と昼間に会うのは四年前の病院以来だ、と思った。彼女の顔は、昼間に見える月のように仄かに白く輝いて見えた。
〈ギャラリーとらのこ〉の内部は、ギャラリー兼カフェといった感じの造りになっていた。入り口を入ってすぐがカフェスペース、左手の衝立の奥が個展会場、右手の壁の向こうにはキッチンが垣間見えた。
「ここ、すぐに分かりましたか?」と蛯原蜜子が聞いてきた。
私は、蛯原蜜子の向かいの席に腰を下ろしながら、「あ、ああ……。途中、道行くお婆さんにたずねて教えてもらったよ」と答えた。
「あら、お知り合いのかたですか?」
右手のキッチンの奥から、年配の女性がエプロンで手を拭き拭きしながら現れた。
「ええ、友達です」と蛯原蜜子が年配の女性のほうを向いて言った。
私は友達だったのか! 彼女にとっての私のポジションをあらためて確認した私は、内心ほっと胸をなで下ろした。「勝手にメールを送ってくる変態です」と言われなくてよかったと思った。
蛯原蜜子が、「こちらは、ギャラリーのオーナーの響子さんです」と年配の女性を私に紹介してくれた。
「はじめまして、中村滝夫です」
私たち三人は、しばらく雑談を交わした。蛯原蜜子とオーナーは、旧知の仲であるらしく、とても仲睦まじそうに見えた。
「それじゃあ、そろそろ作品を見せてもらおうかな」と、頃合いを見計らって私は切り出した。私は、オーナーに入場料を手渡してから席を立った。衝立の左側を回り込み、会場内に足を踏み入れると、正面突き当りの壁に、連作『EGOILL』らしき絵が三点、額装された状態で展示されていた。右手の壁には、三点の〈死〉の絵がかけられている。私は、正面の『EGOILL』と思しき絵のほうに歩み寄った。
一点目は、悲痛な面持ちをしたサタンとベルゼバブが堕天について地獄で語り合う場面。二点目は、サタンとその麾下の堕天使たちが神への復讐について地獄で謀議をしている場面。三点目は、地獄の門の前でサタンが〈罪〉と〈死〉とに出会う場面であった。
その、今にも画面から飛び出して来そうな生々しい堕天使たちの姿を見ながら、私は突然ひらめいた。徴と奇蹟だ、と。
蛯原蜜子との出会いが徴であり、この『EGOILL』という彼女の一連の作品が奇蹟なのだ。私に徴と奇蹟を見せてくれる女性が彼女の他にどこにいるだろうか? 私は後ろを振り返り、衝立の向こう側にいる筈の、蛯原蜜子の存在に思いを馳せた。
蛯原蜜子には顔がある。〈その人でなくてはならない明確な理由〉をもった女性と遂に巡り会ったのだ。私は、生まれて初めて神に感謝した。
高ぶった気持ちを鎮めてから、私は再びカフェスペースに戻った。急に空腹を覚えた私は、オーナーにサンドイッチを注文した。その日は朝から胸がいっぱいで、何も喉を通らなかったのである。私は、運ばれてきたサンドイッチを食べながら、蛯原蜜子とオーナーと一緒に芸術談義に打ち興じた。
食後のコーヒーを飲み終えた私は、持っていたコーヒーカップをソーサーの上に置いた。ふと目線を上げると、私と蛯原蜜子の目と目が合った。彼女に微笑みかけながら、私は決意していた。次は私が彼女に奇蹟を見せる番だ、と。そうすれば、きっと彼女は、本当の運命の人が私であるということに、気づいてくれるに違いない。
八月二十九日の午後三時、ショットのダブルライダース618を着込んだ私は、〈ライブハウスBIGHOP〉というロゴが描かれた雑居ビルのシャッターの前を横切った。右手にはジャガーの入ったハードケースを持ち、左手にはエフェクター類を入れたジュラルミンケースを持っていた。私は、ビルの脇にある鉄製の階段を上り、開け放たれた通用口のドアの敷居をまたいだ。開店前のライブハウスが醸し出す独特の雰囲気――薄暗がりの中に漂う緊迫した空気感――が私の鼻をついた。懐かしさのあまり、思わず私は笑みをこぼした。
私は、私より先に会場入りしていた磯ピーと溝氏と合流し、対バンのメンバーたちと挨拶を交わし合った。やがて、出場者全員が揃ったところで、BIGHOPのスタッフたちを交えて簡単な打ち合わせが行われた。その席で、ライブ本番におけるアマラントスの出番は、四番手であるとスタッフから告げられた。
本番で〈取り〉を務める〈ヘッジホックス〉というバンドがリハーサルを終えると、我々は彼らと入れ替わるようにしてステージの上に立った。私は、対バンのみんなから向けられた熱い視線の中に、「お手並み拝見」という無言のメッセージを読み取った。
ステージに備え付けられたハーフ・スタックのマーシャルアンプにジャガーを接続し、しばらく音作り(本番に向けてエフェクターやアンプのセッティングを確認する)をした後、我々は『イカロス』を演奏した。対バンのみんなを圧倒してやろうと、私はのっけからフルスロットルでシャウトした。準備は万端であった。
午後六時頃から店内にちらほらと観客が姿を見せ始め、午後七時にライブが開始されると客席はほぼ満員になった。私は、ライブを見に来てくれた友人たちに挨拶をして回った。人ごみの中に達也の姿を見つけた私は、彼のそばに歩み寄った。「よお、達也。よく来てくれたな」
久々に会った達也に蛯原蜜子と連絡を取り合っていることを報告すると、達也は急に真面目な顔をして、「彼女には、あまり深入りしないほうがいいんじゃないか?」と言った。
午後八時過ぎ、控え室のパイプ椅子に腰掛けた私は、出番の合図を静かに待っていた。三番目のバンドがステージに上がってから、既に二十分が経過している。バンドの演奏音とボーカルの絶叫とが渾然一体となって、我々のいる控え室にもけたたましく鳴り響いていた。磯ピーは、私の向かいの席で五弦ベースを空弾きしている。溝氏は、私の隣で架空のドラムを叩いている。二人ともイメージトレーニングに余念がなかった。
やがて、ぴたりと轟音が鳴り止んだ。控え室とステージとを隔てる黒い暗幕の隙間から、スタッフがひょっこりと顔をのぞかせた。「アマラントスさん、出番です!」
私は、ジャガーを持ってゆっくりと立ち上がった。暗幕を抜けると、客席側からステージを照らすスポットライトの眩い光が目に入った。私は、ライトに背を向けて、ステージの奥に設置されているマーシャルアンプの前に行った。そして、手早く機材のセッテイングを行った。
私は、深く息を吐きながら両目を閉じた。――よし、やるか。目を開けると同時にアンプの電源スイッチを入れる。「ヴォォォォオン」というポップノイズと共に、私の体内を電流が駆け巡ったような錯覚に襲われた。
私は、くるりと観客席のほうに向き直った。そして、ステージの中央に備え置かれたスタンドマイクの前まで、ゆっくりと歩み寄った――。
「初ライブお疲れさま」と言って達也は周囲を見渡した。「乾杯!」
達也による乾杯の音頭を皮切りに、ライブの打ち上げパーティーが開始された。仲間たちの笑顔の渦の中心で私は笑っていた。しかし、表向きの表情とは裏腹に、私の心は停泊する船のアンカーのように重く沈んでいた。私の書いた一連の楽曲が、奇蹟に値するような曲ではないということを、私自身が一番よく分かっていたからである。
十月に私と蛯原蜜子は再び〈語る会〉を開催した。しかし私は、〈その人でなくてはならない明確な理由〉を持った女性が蛯原蜜子であるという事実に圧倒され、彼女を前にして不覚にも舞い上がってしまった。だから、その会を通して私の記憶に残っている出来事は僅かに三つだけである。
一つ目は、創作日本料理店のカウンターに蛯原蜜子と並んで座っているとき、私の方を向いて話している彼女が凄まじく綺麗であったということ(やはり月は夜に輝く)。
二つ目は、二軒目に行ったバーで蛯原蜜子が私を前にして初めてタバコを吸ったこと。「普段は吸わないんですけど、今夜は特別です」と彼女は言っていた。
三つ目は、蛯原蜜子をホテルまで送り届ける際に、私の隣を歩いている彼女に対して、初めて肉欲を覚えたことである。
――今夜は特別です――と彼女はバーで言っていた。なぜ彼女は今夜だけ特別にタバコを吸ったんだ? 目の前の雑居ビルに掲げられたネオン看板の文字が、私の頭の中で〈求愛のサイン〉という言葉に変化した。もしかして、千載一遇のチャンスが到来したのか?
彼女が宿泊する予定のホテルは目前に迫っていた。目と鼻の先にある彼女の手を横目に見ながら、私はひとり煩悶していた。その手を握るだけでいいんだ。その手を握るだけていいんだ、滝夫!
私が逡巡しているうちに、無情にも時は過ぎ行き、私と蛯原蜜子はホテルの前に到着した。
「おやすみなさい」と言って玄関の中に消えた蛯原蜜子の後ろ姿を、私は為す術もなく見送った。
私は、アマラントスの活動に専念した。週に二度のスタジオ練習を欠かさず、月に一度のペースでライブに出演し、その都度必ず新作を発表した。
その頃、現在の私の妻である白石麻耶が私の前に現れた(正確に言えば、彼女はもっと前から私の前に現れていたのであるが、私は彼女のことを特に何とも思っていなかったので、敢えてこの表現を使った)。
麻耶は私の部下であり、私は彼女の教育係として、あれやこれやと仕事を教える立場にあった。私は仕事とプライベートをきっちりと切り分けるような人間ではない(どんなときでも私は私である)ので、彼女が仕事で失敗をして落ち込んでいるときには、食事に誘って励ましたり、彼女もまたそのお返しに私のライブを見に来てくれたりと、お互いに結構仲良くやっていたのである。
ある日、仕事中にみんなで雑談をしているとき、麻耶が突然――みんなの面前であるにもかかわらず――真剣な表情をして私に向かってこう言った。
「中村さんと出会って、私の人生が変わりました」
周囲のみんなが一瞬フリーズしたのを、そのとき私は見逃さなかった。

👇 続きはこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
