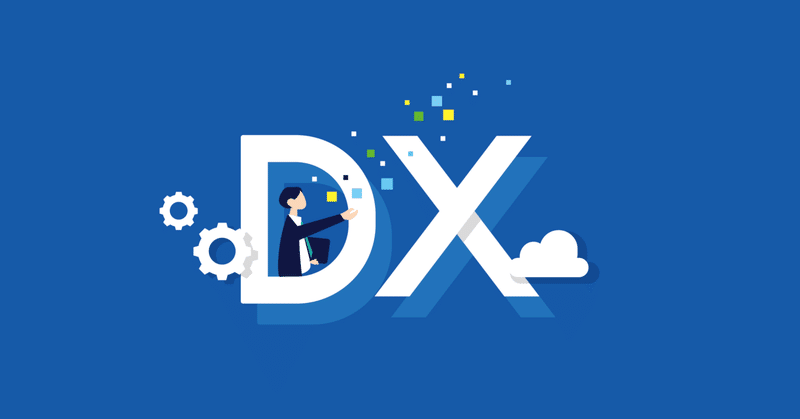
教育現場で「新しい技術とどう向き合うか」を子どもと考えながら、適切に使っていけるようにすることは大切なことだと思う
1217記事目
こんにちは、旅人先生Xです。
今日は「新しい技術とどう向き合うか」について考えたことを書いていきます。
ゆるりと目を通していただけると嬉しいです。
目次は、以下の通りです。
新しい技術とどう向き合うかを考えることが大事
生成AIが出てから、私でも分かるほど目まぐるしく進化しているように思います。
どんどん進んでいた進化がさらにすごいスピードで突き進んでいる。
そんな印象を受けています。
生成AI関係のニュースは、子どもたちの耳にも入っており、実際に家の人が試したり、使ったりしている様子を見ている子もいます。
そのような現状があるわけですので、学校現場でも自然と話題になることがあります。
中には「生成AIって学校で使えるようになるんですか?」と質問してくる子もいます。
ちょうど夏の作文を生成AIに書かせるみたいなことが話題になっていた時期だったので、近くにいた子どもたちに「生成AIってどんな風に使ったらいいのかな?」と聞いてみました。
すると、面白いことに、それぞれが自分なりの考えを持っていることが分かりました。
「自分がすることのアシストをしてもらう」とか、「参考になる情報をまとめてもらいたい」といった類の意見が多かったです。
「代わりに書いてもらうことが話題になっているけれど、どう思う?」という問いについては、「そういうことをするのは自由かもしれないけれど、目的に合ってないんじゃない?」という辛辣な意見をいただきました。
確かにおっしゃる通りだと思います。
「その使い方はどうなんだ?」という感覚は子どもの中にもあるのかもしれません。
「生成AIに書かせた文章を参考にする場合、どこまで参考にしてよいものか」というところまでは聞かなかったのですが、子どもたちはそれぞれどのように考えるのか、気になるところです。
子どもたちとやり取りをしていて、新しい技術などと「どう向き合うかを考える」ということ自体がとても大切なことではないかと感じました。
今の進化のスピードをみていると、これから先もどんどん新しい技術や道具などが身近になってくることが予想されます。
だからこそ、「どう向き合うかを考える」という経験を積み重ねていくことが大切なのかもしれません。
大切なのは使い方だと思う
新しい技術や道具は、リスクがピックアップされがちだと思います。
確かにリスクを知らずに使ったら危ないですよね。
カッターやはさみ、包丁などの刃物を使う時に、手を切ってけがをするリスクを知らなければ危ないです。
ですが、適切に使えば、どれも便利な道具であると言えます。
一人一台の端末の導入の時も同じようにPCの利用のリスクがピックアップされていました。
ですが、一人一台の端末も先ほどの刃物の例と同様に、リスクを知り、適切に使えばとても便利な道具になります。
実際に、一人一台の端末の導入で子どもたちの学習活動は大きく進化したのではないかと感じています。
生成AIなどの新しい技術も同様に適切に使えば、きっと良い変化をもたらしてくれると思います。
「生成AIをどのように使っていくのがよいだろうか。」
このことについて考えながら、実際に試行錯誤していくことがこれからを生きる子どもたちにとって大切な経験になるのではないかと思います。
年齢制限や使用のガイドラインなど、加味しなければならないことはたくさんあるかもしれませんが、そういうこともまるっと含めて前向きに考えていきたいところです。
今回は以上になります。
お読みいただきありがとうございました。
みなさんからいただくスキやコメントが私の励みになっています。
よろしければ、ポチッとしたり、コメントをいただけたりすると嬉しいです。
【最近の記事まとめ】
いただいた分は、若手支援の活動の資金にしていきます。(活動にて、ご紹介致します)また、更に良い発信ができるよう、書籍等の購入にあてていきます!
