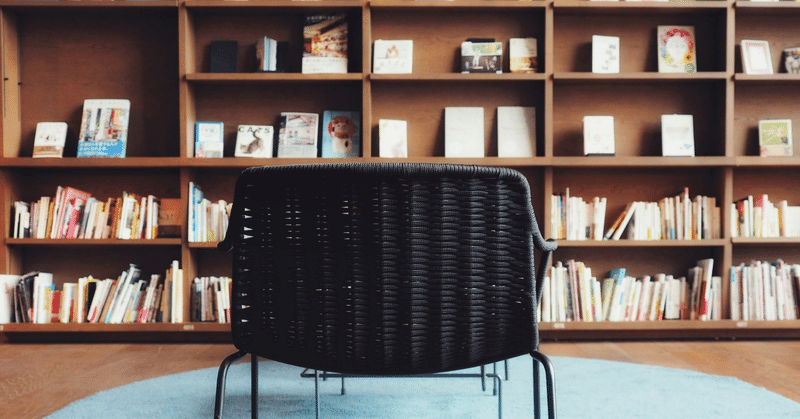
月1回の本棚の断捨離が思考を整える
今日は、本棚を断捨離していました。
積読の解消や再読することはこの先ないなと思う本を一気に整理し終えたので、気分爽快です(^^♪
毎月1回は必ず自宅の本棚を整理することを月次ルーチンにしています。これは単に部屋をキレイに整理整頓したいというものではありません。
今自分は何に関心があるのか?どの情報は不要になったのか?の選択と集中を行うことで、頭の中のノイズを取り除くという作業に他ならないのです。
自室の本棚は1つのみで、約350冊収納できます。
が、特徴はここ10年ほど、本棚を拡張することも、使わない本を収納することもありません。
再読の可能性が参照レベルでもある本や仕事で使う参考書籍のみに絞り、それ以外は入れ替えながら350冊の収納を固定化しています。(99%はビジネス書とノンフィクション、歴史本の3ジャンルで小説は1%未満)
これによって、重要度が低い情報にまみれ、スペースがなくなることを防いでいるのです。
読書家を自認しているので、放っておけば次々にAmazonでポチり、本はたまる一方です。
また、困ったことにポチって家に届いた瞬間に、本を読むテンションはかなり冷え切っています。残念ながら、買うまではモチベーション高いのに、買った後はモチベーションが急降下してしまうのでしょう。
でも、せっかく買ったのだからと、どんどん本棚の中に差し込んでいくと、本であふれるばかり。全部読みこなせないにも関わらず。
こんな反省から、サンクコストにとらわれず、”心底”必要と思う本以外は思い切って処分することにしたのです。
※サンクコスト効果とは、すでに支払ったコストに気をとられ、合理的な判断ができなくなってしまう心理効果です。あなたも、「せっかくだから」「もったいないから」などの理由で意思決定をしたことはないですか。これはまさにサンクコスト効果です。
また、「これは良い内容だったから”一応”とっておこう。いつか使うかもしれない」と思ってとっておいた本で再読した試しはほぼありません。
”一応”や”いつか使うかも”でとっておいた本たちで、実際に再読したり、触れることをした本は1年で1冊あるかないか。
であれば、「いつか使うかもは、結局使わない」と割り切り、常に本棚を固定の数に制限し、自分の興味の向き先のみに本を留めることにしたのです。
こういうと、必ず聞かれる質問があります。
「処分してしまった本で、やっぱり処分しなければ良かったなという経験はありますか?もう一回買い直せばもったいないじゃないですか~」と。
ありますよ。ただ、5年に1冊くらいはね。
でも、そんなこと僕は気にしません。本当に必要な時が来れば、また同じ本を買いなおせばいいだけなのです。たかだか1000円前後じゃないですか。
個人的には、その1000円前後のもったいなさよりも、その間(平均5年)余分なモノや情報が視界に入り、頭にノイズがたまることの方が損失だと考えているほど徹底しています。
だって、思考にノイズが入ったままの日常だと、何か新しいものを生み出し、仕事でも成果を生み出すことが難しいからです。
たかだか1冊余分に本棚に入っていたからといって、それが仕事の成果を邪魔することになるなんて因果関係はもちろんないとは思いますよ。
ただね、それくらい強い意識をもって頭の中にノイズが入ることを断ち切らないと、複雑化した情報化社会ではシンプルに考えることさえ難しいと思うのです。
つまり、僕の世界観では「本棚の中=頭の中」となっているので、月1回くらいは本棚も断捨離を行い、頭を整える時間を持っていますよ!という月次ルーチンのご紹介でした。
おしまい。
さて、今回の内容は
いかがだったでしょうか?
少しでもお役に立てば幸いです。
それでは、また会いましょう!
著者・思考の整理家® 鈴木 進介
P.S.
毎週水・日曜日に「メルマガ」でも思考整理のエッセンスを配信中です!
以下よりご登録ください↓↓↓

「LINE」でもショートコラムを毎朝7時に配信しています!
以下よりご登録ください↓↓↓

最新刊はこちらより↓
フォローしてくれたらモチベーション上がります! ◆YouTube http://www.youtube.com/user/suzukishinsueTV ◆メルマガ https://www.suzukishinsuke.com/sns/
