
行動観察トレーニングの威力。「やってみせ」から始まる運動学習
📖 文献情報 と 抄録和訳
後方歩行観察トレーニングが慢性期脳卒中の歩行パラメータとバランスに及ぼす影響:無作為化比較試験
Moon Y, Bae Y. The effect of backward walking observational training on gait parameters and balance in chronic stroke: randomized controlled study. Eur J Phys Rehabil Med. 2022 Feb;58(1):9-15.
🔗 DOI, PubMed, Google Scholar
[背景・目的] 後方歩行(BW)と行動観察トレーニングは、転倒の危険性がある人に役立つ可能性がある。さらに、行動観察トレーニングは脳卒中後の歩行を改善するための介入となる可能性がある。目的我々は、慢性脳卒中患者の歩行パラメータとバランスに対するBW行動観察トレーニング(BWOT)の効果を明らかにすることを目的とした。
[方法] デザイン無作為化比較試験。設定はリハビリテーションセンター対象者24名の慢性脳卒中患者をBWOT(N.=12)群と風景観察トレーニング(LOT)(N.=12)群に無作為に割り付けた。BWOT群はBWのビデオを見てBWを行い、LOT群は風景のビデオを見てBWトレーニングを行った(図)。

✅ 図. 後方歩行観察トレーニンググループ参加者の行動観察トレーニングの様子。
両群とも従来療法を週5日、BWOTを週3日、4週間実施した。主要アウトカムと副次アウトカムはそれぞれ歩行とバランスであった。静的バランスは5回Sit-To-Standテスト(5TSTS)、圧中心(COP)変位、患側の体重分布(WD)を用いて測定した。動的バランスは活動特異的バランス信頼度(ABC)スケールを用いて測定した。
[結果] BWOT群は、歩行速度(P=0.001、η2=0.470)、歩幅(P=0.007、η2=0.313)、歩幅(P<0.002、η2=0.431)、5TSTS(P=0.021、η2=0)に著しい向上を示しました。 231)、COP速度(P=0.022, η2=0.226), 長さ(P=0.001, η2=0.504), 患側のWD(P=0.033, η2=0.193), ABCスコア(P=0.023, η2=0.226) がLOT群より改善された.
[結論] 4週間のBWOTトレーニングプログラムは、脳卒中患者の歩行パラメータと静的および動的バランスを有意に改善した。BWOTは、脳卒中後の歩行やバランスの改善に有用な方法として、従来の治療にも応用できる身近で効果的なリハビリテーション訓練方法であることがわかった。
🌱 So What?:何が面白いと感じたか?
「まなぶ」という日本語は、「マネブ」「マ・ナラフ」という語が転じたものと言われています。
「マネブ」は「真似ぶ」「真(誠)擬ぶ」であり、マコトたる真理と誠実とについて、正しい手本をまねることです。
(中略)
「学習」とは、師によって伝授された高度な知識・態度・能力などについて、学習者が何度も何度も繰り返しまねをして、ついに同程度のものを身に着けるという、一連の主体的行為なのです。
ここには、師から施された教育的行為がなくては、「学習」が成り立たないことがわかります。
🌍参考サイト >>> site.
運動学習だって、『学習』の一種だ。
学習者は、目指す「模範」を知り、それを繰り返しまねることで、同程度のものを身につける。
いきなり、「では、後ろ歩きしましょう」では、模範がない。
それでは、(語源からして)学習の仕様がないことになる。
そして、今回の抄読論文は、後ろ歩き練習の効果に関して、模範の行動観察の有無が威力を持つことを明らかにした。
では、その仕組みは何だろう?
▶︎運動イメージを直接付与する:文字→運動イメージプロセスの割愛
臨床上、よくある場面。
とくに、認知機能が低下した患者に膝関節伸展の単関節運動を期待して、「足をあげてください」と言った時に、①少数の期待された膝伸ばしをする患者、②多数のSLRをする患者、③少数の両下肢挙上腹筋をする患者、とさまざまな実行に分かれる。
ひとつの口頭指示(文字)に対して、リンクする実際の運動は、無限にある。
その膨大な自由度の中から、最適解を選択する、そもそもそのイメージを想起する、これは難易度が高いことが推察される。
動画で模範を示す、あるいは目の前でセラピストがやってみせ模範を示す。
すると、三次元空間において、口頭指示に対する自由度が1つに収束する。
これが、練習の効力を最大まで引き上げる。
▶︎ミラーニューロン:病態レベルの話
✅ ミラーニューロンとは?
- ミラー・ニューロンとは、Rizzolattiらの研究においてサルの腹側運動前野および下頭頂小葉で見つかった、自分が行為を実行するときにも他者が同様の行為をするのを観察するときにも活動するニューロンである。
- 単に行為の視覚特性に反応しているのではなく、行為の意図まで処理していることが示唆されており、他者の行為の意味の理解・意図の理解などとの関与が提案されている。
- ヒトの相同領域でも、ミラー・ニューロンと解釈できる活動が示されている。
🌍 参考サイト >>> site.
- 最近、有望なリハビリテーション手段として、運動イメージ(motor Image: MI)と行動観察(action observation: AO)が提案されている。
- MIは,実際の動作(または筋肉の活性化)を伴わない動作を想像する能力である。MIは,運動実行時に活動する大脳皮質-皮質下のネットワークがMIにも関与している。
- AOの生理学的根拠は,"ミラーニューロンシステム "の活性化にある。
- MIとAOはともに運動学習に関与しており,運動皮質の可塑的な変化を介して,運動能力の向上をもたらす可能性がある。
📕Abbruzzese, Giovanni, et al. Parkinson’s Disease 2015 (2015). >>> doi.
模範は、ミラーニューロンシステムを活性化させることで、運動学習に関与し、運動皮質の可塑的な変化を介して,運動能力の向上をもたらす可能性があるらしい。
以下の歴史的格言は、運動学習にも適応しているようだ。
やってみせ
言って聞かせて
させてみて
誉めてやらねば
人は動かじ
山本五十六
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥
良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』
こちらから♪
↓↓↓
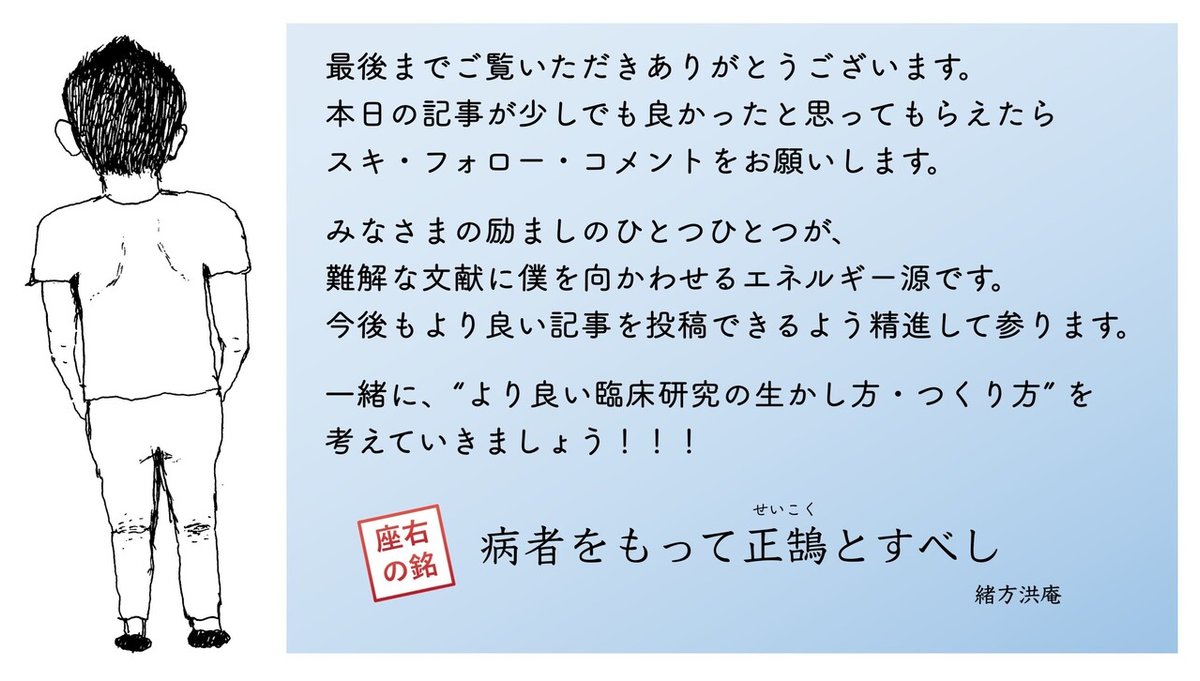
‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○
#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び
