
跨ぎ動作ができない?じゃあ、転倒リスク『10倍』です。
📖 文献情報 と 抄録和訳
論文題目:脳卒中後の退院時に将来の転倒者と非転倒者を分類するための障害物跨ぎテストの有用性。パイロットスタディ
📕Feld, Jody A., et al. "Utility of an obstacle-crossing test to classify future fallers and non-fallers at hospital discharge after stroke: A pilot study." Gait & Posture (2022). https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2022.05.037
🔗 DOI, PubMed, Google Scholar
🔑 Key points
- 障害物跨ぎに失敗することは、将来の転倒状態に強く関係している。
- 障害物跨ぎテストは脳卒中後の転倒予測を改善する可能性がある。
- 脳卒中後の転倒者は、退院時に下肢の障害が大きい。
[背景・目的] 既存のバランスと移動機能に関する臨床評価は、脳卒中後の転倒者を前向きに特定するための予測精度が低く、これは地域ベースの転倒事故に典型的な生態学的複雑性の欠如に起因している可能性がある。研究課題:退院時の障害物通過テストは、退院後3ヶ月の外来脳卒中患者の転倒状況を予測するか?
[方法] 自宅退院する外来脳卒中患者を対象に、退院時に障害物跨ぎテストを実施した。障害物は歩行開始点から5.5mの地点に設置し、人の脚長の10%の高さで標準化した(平均8.8cm、SD0.5)。転倒は退院後3か月間、前向きに追跡された。ロジスティック回帰により、退院時の障害物跨ぎテスト(合格/不合格)と退院後3ヶ月の転倒状況(転倒者/非転倒者)の関係を調べた。

✅ 図. 障害物跨ぎテスト-スコアリングシステム:obstacle-crossing test
[結果] 45名の参加者が退院時障害物検査と3ヶ月後の転倒データを有していた。21名(47%)の参加者がフォローアップ中に少なくとも1回の転倒を経験し、その52%が退院後1ヶ月以内に起きていた。21名の転倒者のうち、14名が障害物通過テストに不合格であった(感度67%)。非転倒者24名のうち、20名が障害物跨ぎテストに合格した(特異度83%)。受信者動作特性曲線下面積は0.75(95 % CI 0.60-0.90)であった.障害物横断テストに失敗した人は,退院後の最初の 3 ヵ月に転倒する可能性が 10.00 倍(95 % CI: 2.45-40.78 )に高かった.未調整のロジスティック回帰モデルでは、被験者の76%が正しく分類された。年齢,性別,脳卒中発症後日数,脳卒中後遺症で調整しても,オッズ比は6.93(95%CI:1.01-47.52)と有意であり,79.5%を正しく分類することができた.
[結論] 障害物跨ぎテストは、退院後の最初の3ヶ月間に転倒する可能性のある自宅退院する外来脳卒中サバイバーを特定するための有用な退院評価である可能性がある。障害物跨ぎテストの感度を向上させるための改良をさらに検討する必要がある。
🌱 So What?:何が面白いと感じたか?
「Gap Motion Intervention:GMI」という概念がある(※造語)。
これは、「入院中の生活では求められないが、退院後には求められる動作への介入」である。
たとえば、床の立ち座り動作。
入院中、ベッドと椅子中心の生活では、その使用を強制される場面はない。
しかし、退院後の生活様式によっては、毎日必要になる可能性がある。
そこに、入院中と退院後とのギャップが生じている。
このギャップが、退院直後を最も危険なTime pointにしている理由の1つだ。

✅ 退院直後は転倒にとって最も危険なタイムポイント
- 後方視的に転倒,福祉用具貸与,住宅改修の有無を退院から180日まで30日毎に調査し,各時期の比較を行った.
- その結果、転倒件(42.9%),福祉用具貸与(72,.2%),住宅改修(61.5%)ともに退院から30日以内に最も件数が多く、その後漸減、後半90日間では発生件数が極端に少なくなった。
📕海津陽一, 他. 地域リハビリテーション 15.2 (2020): 117-122. >>> site.
このGMIが必要な動作の1つに「跨ぎ動作」がある。
基本、病院内はバリアフリー(段差や敷居などがない)になっている。
そのため、小段差に対する跨ぎ動作は求められない。
だが、退院後の世界は、至るところに敷居やら小段差やらが存在している。
ほぼすべての患者に、跨ぎ動作は求められると考えて差し支えないだろう。
その跨ぎ動作に、定量的スコアリングシステムが提案されたのは意義深い。
そして、そのスコアリングにおいて失敗に区分された患者は、なんと「10倍」転びやすいという。
これは、患者に対しての説明として、強大なインパクトを与えるだろう。
そのインパクトは、そのままの熱量を保ったまま、「リハビリへの意欲」というエネルギーに転化する。
いずれ、GMIチェックリストやGMIスコアリングシステムとして理学療法士が使うことのできる包括的な退院支援動作介入のツールをつくってみたい。
漏れなく、重複なく。最良の退院支援を追求したい。
⬇︎ 関連 note✨
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥
良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』
こちらから♪
↓↓↓
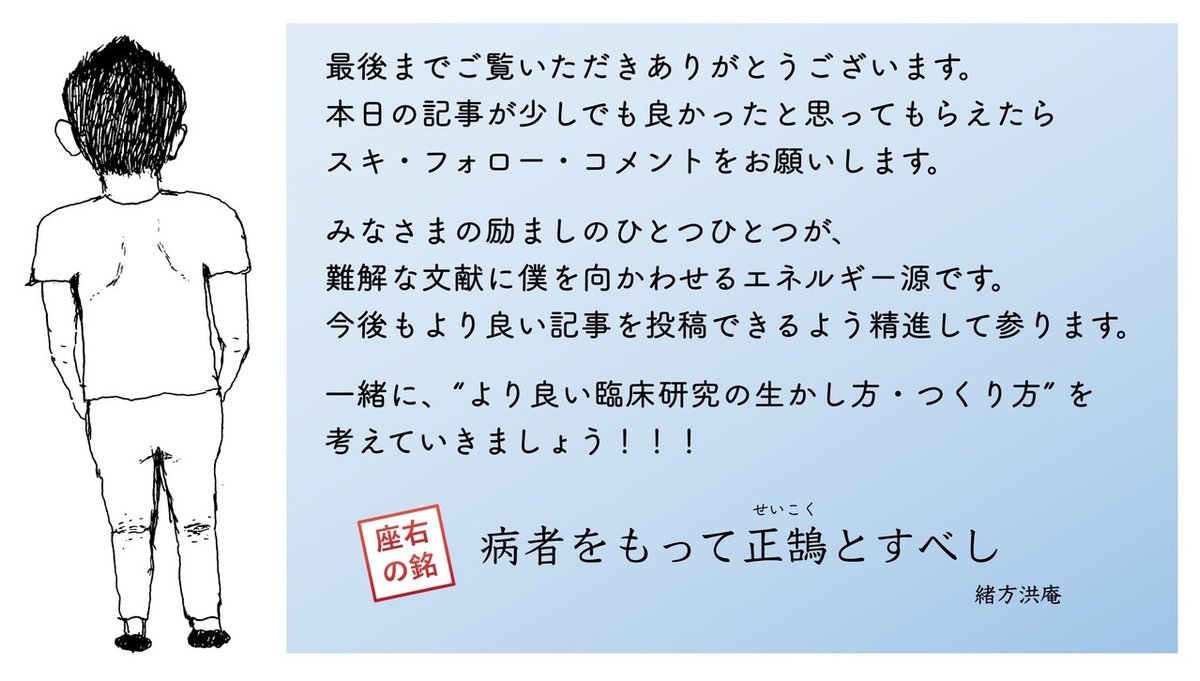
‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○
#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び
