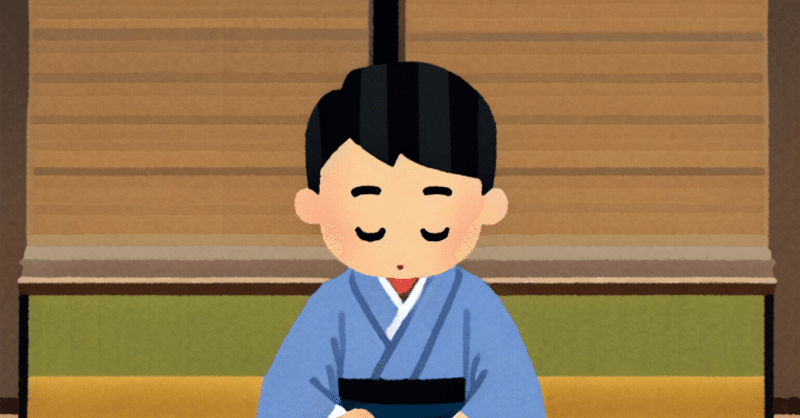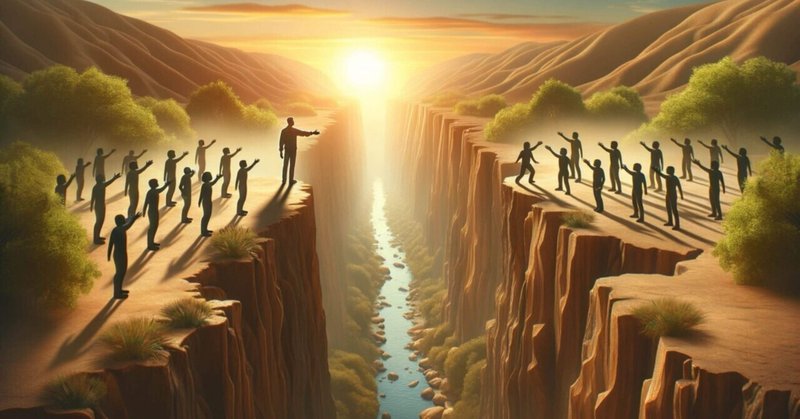2023年10月の記事一覧
信頼する人からしか価値観は学ばない
今日ふと目にした、工藤校長の言葉。
「どんなに立派なことを伝えても、生徒たちは信頼する人からしか価値観は学びません。生徒指導の基本です。」
自分の周りを見て、改めて感じる。うちの生徒たちに、信頼に足る先生はいるのかな。いるとしたら、幸せだよね。
もしいないとしたら、それはとても残念なことです。何が残念って、信頼に足ると生徒たちが判断できる大人が周りにいないことが。
どういう人を信頼に足る大
『「能力」の生きづらさをほぐす』を読んで
僕が尊敬する2人の女性にお勧めされて購入した本。
「非認知能力は定量化してはいけない」と聞いたことがあるが、その意味がよくわかった。〇〇発見力、〇〇解決力などと言って定量化できない力を目に見えるようにすることで、その力を伸ばそうとする働きが生まれる。勉強するだけでも苦しいのに、その他の力を身に付けなければならないと思う人たちにとっては、息苦しい世の中になっていく。
何でも数値化すればいいと言う
今日のICT授業日記764【授業を休んだ生徒への対応はどのように?】
先日の仙台での勉強会にて、上記のような問いをいただきました。未だに結構刺さっています。何にも対応してないなーと。
そういえば、自宅に使ってないiPhoneと使ってないガンマイクと使ってないスマホ用三脚があったなぁと(笑)
そうだ、それを使って授業を撮影すればいいじゃん。そしてそれを休んだ子に見せてあげればいいんだ!
とここまで考えて、「いやでも、『その取り組み、組織としてやってるんですか。一
SDGsカードゲームの違和感の正体
SDGsカードゲームファシリテーターのニシムラデス。前から感じていた違和感を言語化してくれた本に出会ったので、ここに記します。
カードゲームで体験したことを現実に落とし込むのが、SDGsカードゲームの役割です。でもゲームだと、現実ではまずしないであろう選択をすることがあります。
**全員での目的達成のために、お金を出し合って誰かにあげる。
**誰かのゴール達成のために、ほかの誰かに助けを求め
学び続けるって大事だなって話
とりたてて秀でたものもなく、人並みな人生を送ってきました。52年間。
それでも唯一、誇ってもいいかなと思うのは、学び続けてきたことです。
教員として、この道で生きていくために学び始めたわけじゃないけど、今では何のために教員しているか、自信をもって言えます。
「先生」なんて言われて自分が偉いと勘違いすることもありません。常に学んでいるからです。自分を客観的に見られるからです。
学んだからこそ