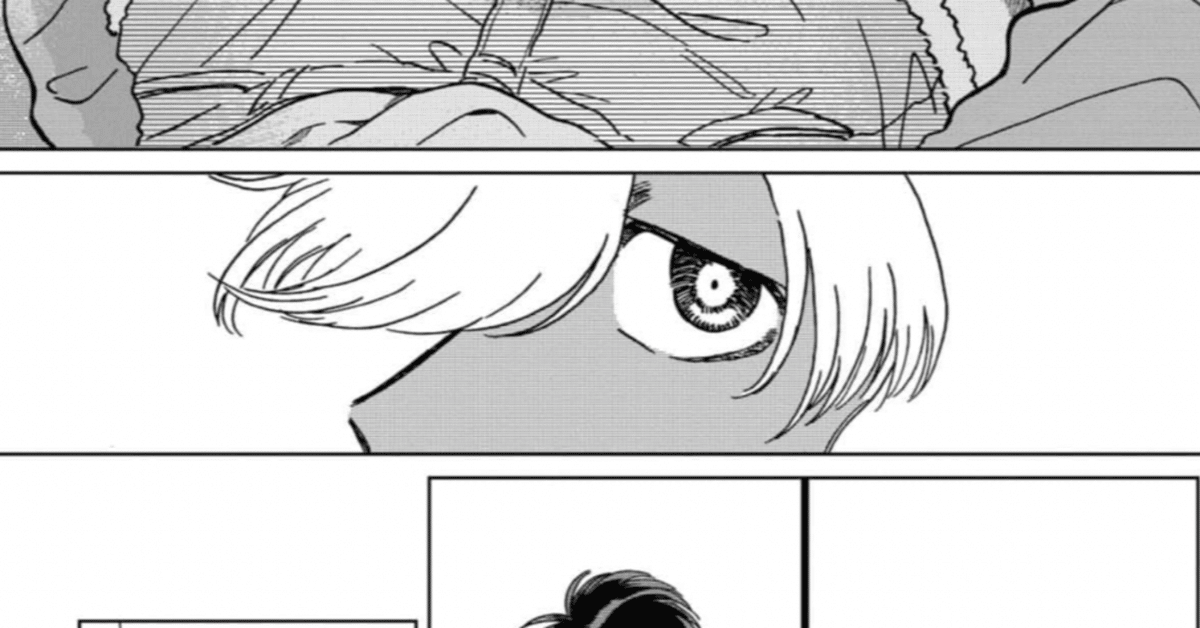
差別とプライドの本質は同じ (生きるために必要な差別を貴方は奪うことができますか?)
自尊心は差別することでしか得られないのだとしたら——、
生きるために必要な、自己防衛としての差別を、貴方は他人から奪うことが出来ますか?
差別も、プライドも、見下しも、上から目線も、教育も、社会福祉も、本質的には同じかもしれません。しかし、明確に言えるのは、
「弱者を定義し、認めること」が、平等の実現と自己実現への第一歩なのです。
「差別」には、2つの特別な意味があります。
2つのケースから考えてみましょう。
CASE:1
赤ん坊と生徒
赤ん坊や学校の生徒を、母親や教師が、自身より下の存在として見ることは差別でしょうか? もちろん、違います。子どもたちがトラブルに巻き込まれたとき、大人は自身の監督責任を省みるものです。しかし、「子どもだから、あれもこれもしてはダメだ」と、理不尽に奪ってしまうのは差別かもしれません。
答え: 弱者の存在を認める重要性
ネット上には、差別と区別を違いを解説する記事が多くありますが、一概に判断できる定義を作ることは不可能です。
例えば、子どもには選挙権がありません。しかし、子どもに判断能力がないのだとしたら、大人は子どもたちのために責任を持った判断が出来ているのでしょうか? 答えは、ノーです。
日本では、まとまった票が得やすいということから、企業や特定の集団、高齢者のサービスが充実しやすい一方で、忙しい母親や選挙権を持たない子どもへの政策は、行われづらいとされています。国家の未来を考えれば、子育て制度や、国内の外国人への社会制度の充実は、重要かつ早急な課題でしょう。このように、単純に、子どもに選挙権を与えないことが良いこととは言えません。また、差別と区別の違いを話すことに、あまり意味はないのです。
では、より平等な社会を実現するために、重要なことは何でしょうか? 答えは、子どもや母親を、「弱者として存在を認めてしまう」ことです。この、一見すると、差別的な答えこそが、平等を実現するためには必要不可欠と言えます。
CASE:2
男にも女にも相手にされないと
海外かゲイバーに行く話。
男女両方からモテなかったり、社会に馴染むことができないコミュニケーションが下手な人というのがいます。しかし、そういう人は、周囲の人より、すこしだけ頭が良いこともあるのでしょう。その結果、よく見る「海外の人からはモテる」や「ゲイからはモテる」というプライドを持った人たちの話をしてみましょう。ポイントは、彼らが、外国人やゲイをどこか見下しつつ、そのほかの大多数の他人も見下していることにあります。これは、差別なのでしょうか?
答え : プライドの高さも生まれつき
結論から言います。彼らは、差別的な心はあるが
、社会のために生きられるでしょう。
まず、考えるべきこととして、彼らが他人の自由や権利を侵害しているかがあります。差別的な感情を心に抱くだけなら、法的にも社会的にも問題ありません。なにより、彼ら自身も、心の中を他人から侵害されない自由があります。また、表現の自由もあるので、他人の自由を侵害しないかぎりは、浮いた言動を取っていたとしても問題ないのです。
次に考えたいのは、仮に、海外の人やゲイからもモテていないことが分かったとしても、それを本人に指摘できるかです。本来、ストレートの男性がゲイからモテたところで何の意味もないように思われます。しかし、そう思えることで、自己肯定できることがあるなら、とても意味があるでしょう。本心には差別的な感情があったとしても、それを安易に他人が指摘することも、不用意な自由の侵害と言えます。
プライドの高さとは、生まれつきのものであり、知性と向上心の顕れであると言えるでしょう。高いプライドがあるからこそ、ムダなプライドにならないように、時に人は頑張ることができ、弱者のために生きることもできるのです。
結論:
もし、必要な差別があるとしたら
2つのケースから分かるのは、「ある特定の人たちを見下すこと」を、差別として取り上げることは出来ないということです。むしろ、そこには、「見下す」という価値があることに気が付きます。
CASE1 では、「弱者として存在を認めてしまう」ことの重要性を考えました。これは、「ノブレス・オブリージュ」と言い換えることも可能かもしれません。ノブレス・オブリージュは、「高い身分の人が、弱者を含めた社会に対して責任を負うべき」という考え方です。例えば、24時間テレビには、感動ポルノと指摘されたとしても、多額の寄付金を集めているという事実があるかぎり、価値があります。本当の差別とは、弱者の存在を認めないことなのです。
CASE2 では、高いプライドを持っている人たちの在り方について考えました。プライドには、差別的な感情が含まれますが、差別と差別的な感情は、分けて考えられるべきです。また、プライドは、場合によっては、「心の自己防衛」になることも指摘できます。例えば、学校でいじめが起きる際には、加害者の生活環境に問題がある場合が多いと言えます。いじめ当事者である加害者と被害者には、心の自己防衛として、差別的な感情(プライド)を持つきっかけとなることも多いでしょう。同時に、いじめを起こしてしまった加害者に教育的フォローや、社会的フォローができる社会システムが十分でないことも問題とされています。高いプライドは、心の自己防衛として、機能していることも多いのです。
世の中には必ず差別があることと、自分自身にも必ず差別する心があることを認めることが、平等な社会の実現には不可欠と言えます。「見下すこと」が避けて通れないことならば、「見下すこと」に価値を見出してしまうのも一つのアイデアなのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
