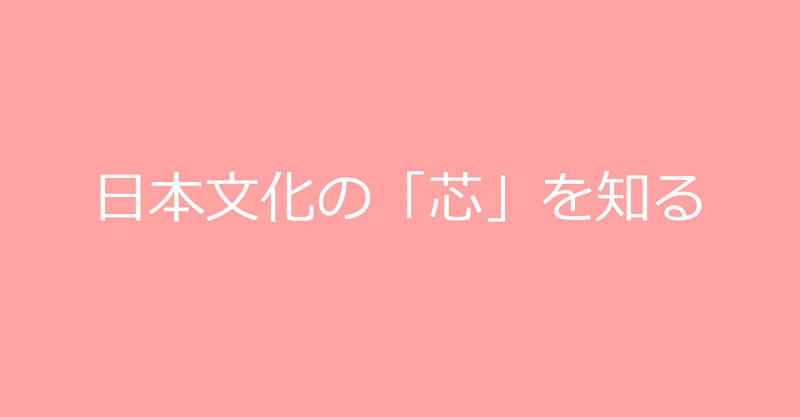
漢字文化圏のなかの日本文化
みなさんは中学・高校の国語科の授業で学んだ漢文を覚えていますか?なぜこれを国語として扱うのか疑問に思った方も多いと思います。漢文は中国語で、訓読とは漢文を日本語の語順で日本語として読む技術でした。ここには日本が置かれた地理的要素とその周辺国である中国・朝鮮との文化的影響とが交差しています。日本を漢字文化圏の国として捉え返すことで、日本固有の精神と中国伝来の学問を併せ持った学問「和魂漢才」という文化の「芯」が見えてきます。ここには明治以降から現代に続く「和魂洋才」の原型が隠れているのです。
1,漢字文化圏とは
日本は東北アジアの海洋に浮かぶ島々から成る島国です。中国文明が栄えた大陸と地続きではないものの、往来可能な海洋に隔てられていることは日本思想を形成する上で重要な役割を果たしていました。
中国文明は漢字を媒介とした書記言語である漢文を共通語とする一つの文化圏をアジア諸国との間に形成しました。これを漢字文化圏といいます。漢字文化圏には中国とその周辺国である朝鮮と日本、それに加えて見落とされがちな琉球とベトナムなどが含まれています。これらの諸国は漢字を受容し、それとともに中国の思想が流入していました。
これらの国々では今でいう英語のように外交上の共通語として漢文が用いられました。たとえば日本が台湾を統治していた時代に、日本人は台湾の漢族と漢文で筆談をしたり、漢詩を交換して文化交流したりしたといいます。また、ベトナム戦争のころに従軍記者として戦地に赴いた小説家の開高健は漢文で現地のベトナム人僧侶と筆談をしています。当時のベトナムにはまだ漢文の素養があるベトナム人がたくさんいたのです。
2,日本語と漢文
日本語と中国語の関係について見ていくと、両者は全く異なる文法と音をもつにも関わらず、日本語の語彙のうちだいたい約7~8割が漢語で占められていることが指摘できます。日本人は漢文で記された漢籍を学び、そこから抽象的な概念を表す言葉を輸入して思想を形成していったのです。思想は言葉とともにあり、言葉は思想が成立する条件でもあります。それが輸入されたとき、在来の土着的な思想との間に摩擦が生じます。この問題について日本人はどのように対処したでしょうか。
3,日本人と漢文
まず言語面でこの問題について考えましょう。平安時代前期に成立した『古語拾遺』(こごしゅうい)によると、もともと日本人は固有の文字を持たない民族であり、口承(口伝え)で物事が語り伝えられる社会でした。近い例でいうと、同じく文字を持たない民族であったアイヌの人々の叙事詩であるカムイユカラなどがそうした例です。
さて、日本において文字の受容を考えると、『古事記』『日本書紀』(これを合わせて記紀と総称します)に載せるところの伝説では、応神天皇十五年(二八四年)に天皇の要請を受けて朝鮮半島の百済から王仁が渡来し、その際に『論語』と『千字文』とが伝来したと伝えられています。これが国史にいう漢文の正式な伝来であるとされます。ですがこれは伝説上の虚構であって、実際に確認されているところでは、日本と中国との交流はもっと古くに遡ることができるでしょう。この問題についてはまだ不明な点が多いのですが、少なくとも中国や朝鮮半島からの移住者が文字を用いる技術を携えて伝えたものと思われます。
4,漢文訓読のルーツ
ここで漢文訓読に話を進めましょう。漢文訓読は日本独自の技術であるように思われがちですが、先に紹介した記紀の伝説において漢文が朝鮮半島を介して伝来したことを考えると、朝鮮半島における漢字文化からの影響に着目しなければなりません。ここには中国語である漢文と漢文の国語化である漢文訓読の間の溝を埋めるヒントが隠されています。
たとえば朝鮮半島において、漢字を用いて古代朝鮮語を記す技術であった郷札(향찰:ヒョンチャル)や、部分的に漢文の要素を残して朝鮮語の語順で読む吏読(이두:イドゥ)に加えて、漢文を読む際に吐(토:ト)と呼ばれる送り仮名を適当なところにふって漢文を読む口訣(구결:クギョル)が行われていました。郷札の技術は古代日本の文献や神道の祝詞などを表記する際の宣命体(せんみょうたい)に近く、口訣の技術は日本にける訓読の営みに近いものです。このように、日本の漢文訓読の技術は朝鮮半島においてある程度準備されていたと考えられます。
5,「和魂漢才」から「和魂洋才」へ
日本人は訓読の技術を保持し続けています。それによって漢語という外来語を日本語の体系の中に取り入れて受容し、日本語として違和感がないほどまでに国語化したのでした。このことは江戸時代に中国思想を自らの血肉となるまでに受容していたことにつながります。「和魂漢才」とはそのような中で在来思想と外来思想とを融合させることでした。そこへの批判が江戸時代の国学の形成につながります。国学については稿を改めて考察します。
またこうした訓読文化は実は日本の近代化に大きく影響しています。たとえば江戸時代に交易していたオランダから科学技術を学び取った蘭学では、オランダ語の文献を漢文訓読のようにレ点や一・二点を使って訓読していたことが確認できます。これは主語-述語-目的語という語順が中国語とオランダ語で共通していたから可能だったのです。オランダ語と英語は兄弟言語ですので、ここから英語を学ぶ素地が形成されたといえます。現代に続く「和魂洋才」の原型は漢文の受容と「和魂漢才」にあったのです。
【参考文献】
・開高健、朝日文庫『ベトナム戦記』朝日新聞出版、1990年10月1日
・斎部広成『古語拾遺』(大倉精神文化研究所『神典』所収、神社新報社、昭和十一年二月十一日)
・山口佳紀、神野志隆光、新編日本古典文学全集1『古事記』小学館、一九九七年五月二十二日
・小島憲之、蔵中進、直木孝次郎、毛利正守、西宮一民校注訳、新編日本古典文学全集2『日本書紀①』小学館、一九九四年四月二〇日
・李翊燮・李相億・蔡琬著、梅田博之監修、前田真彦訳『韓国語概説』大修館書店、2004年7月10日
・『訓點和蘭文典』総摂舘蔵板、安政四(1857)年刊
https://www.ndl.go.jp/nichiran/data/L/103/103-001l.html
執筆者プロフィール:
筆名は枯野屋(からのや)。某大学大学院文学研究科博士課程後期に在籍中。日本思想史を専攻。noteにてオンライン読書会の国文・日本思想史系研究会「枯野屋塾」を主催しています。( https://note.com/philology_japan )。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
