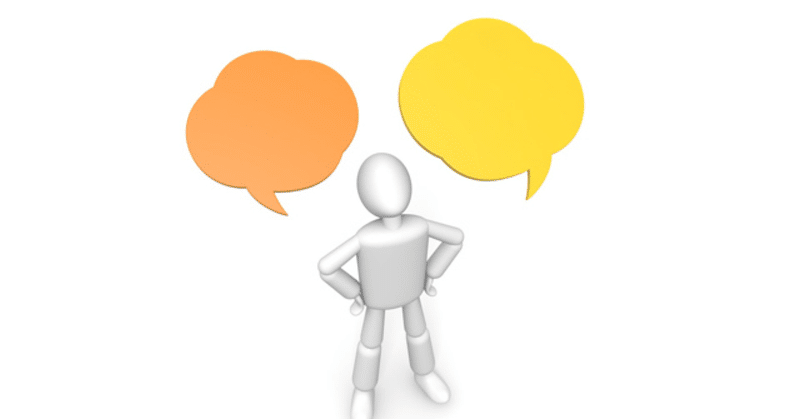#マネジメント
人材マネジメントにおいて、不安と不満の取り扱いには注意が要る
不安は吐くことで解消され、不安要素を除くことで心理的に安心して仕事に励むことができる
不満は吐くことで中毒化し、繰り返し口にすることで職場の風紀が悪化していく
不満は改良の種になるが、吐くものではない
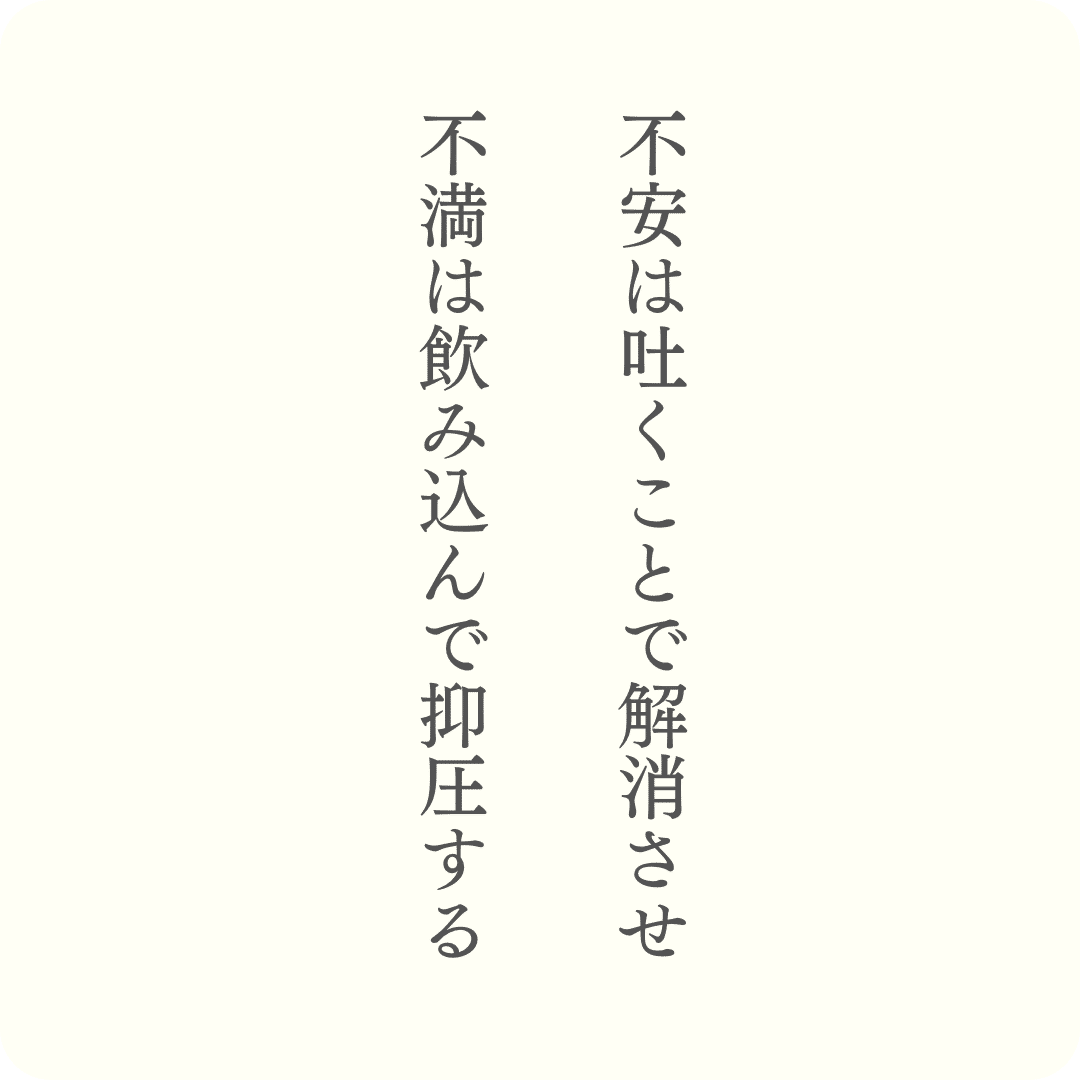
他者評価より、自己評価を重視する
それは、自己決定性と課題の分離を突き詰めた結論
評価はその人の心の状態や環境を踏まえて行うもの
他人がそれらを正確に把握するのは難しい
自分ができていると思えばそれで良い
もしも周りの認識とずれたとしたら、
責任を追うのはその人自身なのだから
心理的安全性を高める方法
それは、フォローアップ面談を定期的に行うこと
日常会話の場と面談の場では、話せる内容も濃度も違う
自分のために、向き合う時間を用意してくれたと思う
フォローアップは相手への気遣い、思いやりの時間
丁寧なフォローは、大事にされている安心感が生まれる
「他人は変えられない」
これは宇宙の法則だ
だが、そう考えると部下を育成する気が失せてしまう
そんなときは言葉を続けよう
「他人は変えられないが、タイミングが来たら変わることができる」
人は準備が整ったとき、自らの意思で変わる
今言葉が届かなくても、その日が来ることを信じよう