
‶捨てるもの″からビジネスをつくる――失われる古民家が循環するサステナブルな経済のしくみ
著者の会社「山翠舎」が手掛ける古民家・古木の再利用で、地域経済を活性化させる方法が書かれている本。
著者➔「山翠舎」代表取締役。
山翠舎➔長野県長野市に本社を置く社員25人の中小企業
・古木を使った建築物の設計と施工。
・古民家の買い取りと再生
・飲食店開業支援事業
など。
➔主に手掛けている事業。
「古民家」=戦前に建てられた一般住宅
「古木(こぼく)」=古民家から得られる木材
古民家➜良質な木材(古木)で建てられている。
=貴重な財産。
”捨てるもの”からビジネスをつくる。
キーワード)
①「アップサイクル」
➜古木をテーブルや椅子など、内装に使う。
「捨てるもの」に価値を見出す。
➜再定義して世に送り出す。
②「サーキュラー(循環)」
➜捨てるものに価値を与えて循環させる。
・人を巻き込む。
・地域を巻き込む。
=経済を循環させる。
<プロローグ>
●古民家が生まれ変わり、旧北国街道が変わる
「旧北国街道」
しなの鉄道、JR小梅線の小諸(こもろ)駅から東にある街道。
軽井沢の西にある中山道から分かれ、小諸、上田などを経て善光寺を通り、新潟県までつながっている。
小諸は小諸藩城下町、宿場町として多くの人を集めていた。
商家が軒を連ねていたので、古い建築が今も残っている。
➜当時の面影を現代に伝えている。
=「雰囲気のある街並み」
2000年以降は人口が減少し、北国街道でも活気がなくなっていた。
現在)
オシャレな新店が連続して立ち始めている。
・デリカテッセン ヤマブキ
➜自家製ソーセージやハムが好評。
・Citta Slow(チッタスロー)
➜長野県産の野菜や肉を使ったイタリアンレストラン。
・彩本堂
➜サイフォンで抽出された日本茶、コーヒーが楽しめる店。
3店は古民家を改装し、現代によみがえらせた店。
(彩本堂は著者が経営する山翠舎が内装を手掛けた)

●レトロとモダンを同時に楽しめる空間づくり
山翠舎が運営するコワーキングスペース「合間(aima)」
➜彩本堂から50メートルほど離れた旧北国街道沿い。
「合間」
もとは明示30年代に建てられた旅館。
魚屋➜商店➜下宿➜コワーキングスペースとして再生。
企業や個人がデスクワークやミーティング、研修などに利用。
➜働くだけでなく、語り合ったり休んだりもできる。

古民家への注目が高まっている。
・スローライフや田舎暮らしに憧れる人が増えた。
➜古い木やしっくいの壁など雰囲気に居心地の良さを感じている。
=古民家での生活を望む人が増えた。
山翠舎が手掛ける建物。
➜古いものを再生しただけではない。
=磨きをかけて、新たな価値を生み出そうとしている。
●壊され、ただ捨てられていく古民家と古木を再生する
現代の古民家の解体。
➜重機を使って無造作に壊し、廃材にする。
過去の家の解体。
➜丁寧に解体し、古木をよい状態で取り出す。
=新しい家に流用するのが当たり前。
過去の木材入手。
➜斧で伐採、筏にして下流の貯木場まで輸送。
=手間と時間がかかり、危険でもあった。
現代の木材入手。
➜海外から安く大量輸入。
=安全に入手可能になった。
古木を手間ひまかけて解体し、ストックするより効率よく木材を入手できるようになった。
古民家の再利用による地域経済の好循環。
集客の核となる店ができる。
➔地域への注目度が高まる。
➔お客がお目当ての店以外の店にも立ち寄る。
➔地域経済にプラスの影響をもたらす。
=新たな開店をもたらす。
店の開店=雇用を生み出す。
➔定住者アップに役立つ。
山翠舎の狙い。
➔シャッター街となった地域経済に正のスパイラルを生み出すこと。
●古民家・古木を循環させ地域経済を循環させる
2つの「循環」
①古民家・古木の循環。
管理が難しくなった古民家。
➔取り壊し。
=もったいない。
建築物としての再利用。
➔新たな価値。
=循環
②地域経済における正のスパイラル。
魅力的な店舗をつくる。
➔地域に新たな人の流れを生み出す。
=活性化
事業を通して実践すること。
「地域に良いこと」
「環境に良いこと」
<第1章 捨てられるものを磨こう>
🐾古民家と古木を新しい価値に変換する会社
古民家=日本にとって貴重な財産。
古木を新たな施工に生かす。
➔環境にやさしい建築。
=古木事業の原点
古民家=戦前に建てられた民家
(1945年までのもの)
➔築年数が古いだけでは古民家と呼べない。
=古民家の数は増えない有限な資産。
戦後日本での建築物。
➔西洋建築学の影響で建てられた家。
=釘やボルトを使って組み立てられた家。
戦後建築の木材。
➔輸入建材の割合が高い。
=まっすぐ製材された規格品。
戦後建築からの木材。
➔釘やボルトの跡がたくさん残った建材。
=古木に比べて非常に低い価値。
●均一・画一的ではないものの良さが注目を集める
現代の建築➔機能的だが没個性
=冷たい印象。
古民家=温かみ
天然の建材で作られている。
➔「シックハウス症候群」の危険性もない。
均一・画一的なものではない。
➔1点モノでつくられているため愛着がわく。
=感動や居心地の良さがある。

●硬さと温もりを兼ね備えた優秀な建材としての古木
古民家を商業店舗にする場合のハードル。
・既存の古民家を改装する。
➔ある程度のリノベーション費用が必要。
・郊外の不便な場所に建てられている。
➔集客面で難易度が高い。
・古民家を移築する。
➔多額の費用がかかる。
古木を再利用するメリット。
古民家を改装するよりもずっと手軽。
➔雰囲気のある内装にできる。
古木➔大きな存在感がある。
=内装に1本使うだけで雰囲気がガラリと変わる。
古木のマイナスイメージ。
・シロアリに食われてボロボロ。
・カビや腐朽菌で腐っている。
きちんと管理された古木のメリット。
「古木は年が経つほど硬く、丈夫になる」
➔経年劣化しない。
=年を経るごとに建材としての価値が高まる。
長年使われた古木。
➔水分が抜けきっている。
=変形する危険性も虫がつくこともない。
木材にはぬくもりがある。
➔熱伝導率がコンクリや鉄より低い
=熱を伝えにくい。
➔冬は暖かく、夏は冷たい。
●唯一無二の形状が人に安らぎを与える
古木の魅力。
➔形、サイズ、色合いが千差万別。
=すべてオンリーワンの存在。
現代建築の木材。
機械によって製材。
➔自然由来の素材でも工業製品。
=均一な出来栄え。
古木=個性豊か
・古い道具で手作業製材した跡
➔一品ものの味わい。
・暮らしの中で自然に付着した煤など。
➔何とも言えない色合いと風合い。

築120年ほどの古民家から得られた古木。
長さ3メートルほどの立派な古木梁。
●1本の柱が店のシンボルとなる
古木には積み重ねられてきたストーリーが刻み込まれている。
・子供の背比べの傷。
・建てた日付。
・棟梁(とうりょう=大工職を束ねる長)の名前。
➔などが残っている。
=長い時間人々の暮らしを見守ってきた証拠。
家の中心に立てる柱
➔大黒柱
=家全体の重みを支える役割。
(柱の近く大黒天を持つることが多いため大黒柱)
恵比寿柱
福を集めたりする縁起の良い柱。
➔大黒柱と一対にして立てられる柱
=2番めに大事な柱。

飲食店に移築された古木の恵比寿柱。
ストーリー性のある古木をシンボルとして柱に使う。
➔お店の雰囲気を牽引し、多くのお客を和ませる。
=小さな手間とコストで大きな効果が得られる。
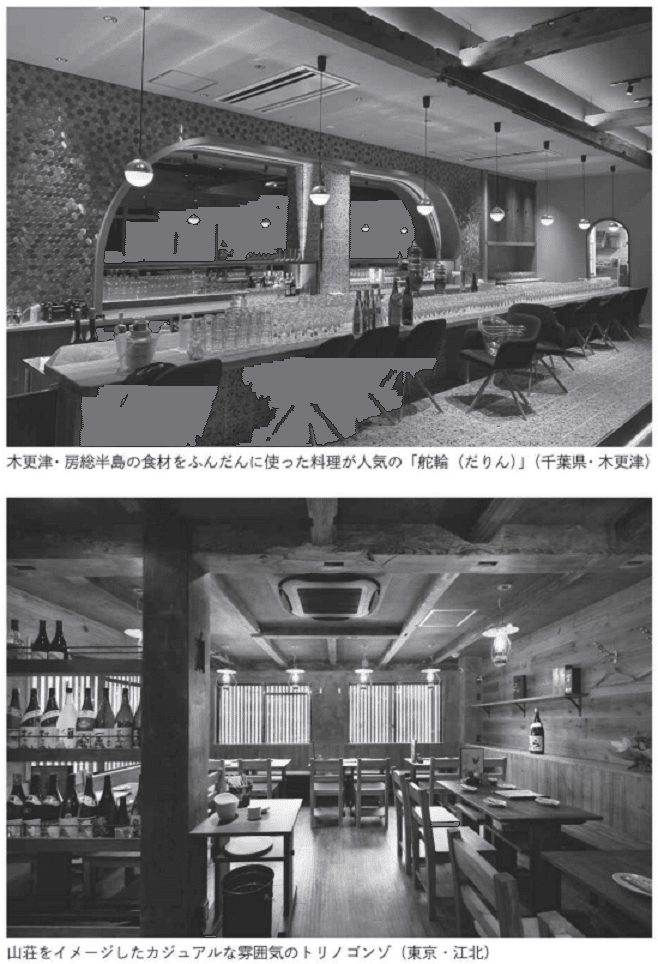
🐾捨てられる木から生まれた新しいビジネスの可能性
現時点での山翠舎のビジネス。
①古民家を解体して古木を買い取り、施工に生かす事業。
➔古木を買い取ることで解体費を安くできる。
②古木を活用した建築工事(修繕を含む)事業。
例)
日本橋にあるニューバランスのコンセプトストア。
「T-HOUSE New Balance」
➔築122年の蔵を移築して組み直した。

③古民家のサブリース(転貸)事業。
➔従来の施工会社の枠組みを大きく飛び越えたビジネス。
=「古民家・古木のマッチング事業」
➔古民家をそのままの形で残す道を考えた結果。
古民家の管理に悩む人と企業をつなぐ
家を維持するのは手間がかかること。
メンテナンスを怠る。
➔建物はすぐに劣化して人が住めなくなる。
=手間とお金がかかること。
古民家の管理に悩む人のエージェントになる。
➔古民家の活用を目指す人をマッチングする。
=今後に有望な事業。

<第2章 地方だからつくれるサーキュラーエコノミー>
🐾地域に求められる「サーキュラーエコノミー」をつくる
「サーキュラー(circular)」
「円形の」「循環する」という意味。
➔室内、車内の空気を循環させるサーキュレーターと同じ語源。
「サーキュラーエコノミー」
=「循環型の経済」
➔環境問題から注目されている概念。
●リニアエコノミーとリサイクリングエコノミー
「リニアエコノミー」
リニア(線形・直線的)に流れる従来型の経済。
原材料から製品を生み出す(生産)
➔消費者が利用(消費)
➔廃棄される。
工業化=大量生産と大量消費
➔膨大な廃棄物を生み出している。
=環境問題
「リサイクリングエコノミー」
廃棄物の中から使えるものを回収し、資源として再利用する手法。
例)
ペットボトルのリサイクル。
➔廃ペットボトルを別の製品につくり替える取り組み。
1991年「再生資源の利用の促進に関する法律」
(リサイクル法)
・リデュース(減量)
・リユース(再利用)
・リサイクル(再生利用)
=3Rの推奨
リサイクルの問題点。
・処理に電力などエネルギーを使う必要がる。
➔新たな環境負荷になる。
・ペットボトルを使って発電する。
➔燃焼時に高温室効果ガスを出す。
●廃棄物の再活用が前提のサーキュラーエコノミー
リサイクリングエコノミーの欠点を補う。
=始めから廃棄物を出さない仕組みをつくる考え方。
原材料やエネルギーの投入を最小限に抑える。
➔生産、消費、リサイクルの循環を回し続ける。
=循環負荷を抑えることが可能。
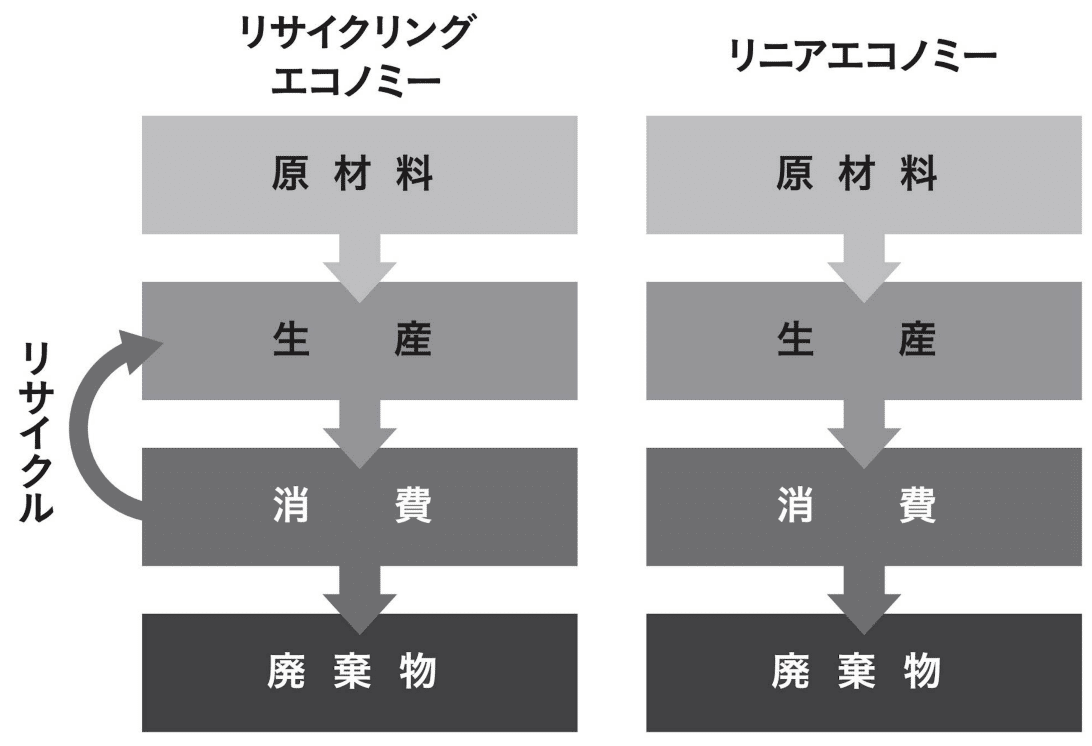
サーキュラーエコノミーの役割
「守りの役割」
=資源のムダ遣いを防ぐ。
「攻めの役割」
・社会全体を活性化させる。
・企業を持続的成長に導く。
・人々により豊かな暮らしをもたらす。
●捨てられるものに新たな価値を見出す「アップサイクル」
「ダウンサイクル」
捨てられるものを再利用する。
➔価値が下がってしまう。
例)
古着で雑巾をつくるなど。
「アップサイクル」
捨てられるはずのものに新たな価値を与えて再生する。
例)
古着を切ってデザイン性豊かなバッグにつくり替えるなど。
※アップ、ダウンサイクルはサイクルを回す際の価値の付き方で決まる。
木材の一番良い再利用法。
=加工せずにそのまま使う。
➔古い木が秘めている価値を引き出す。
=木材循環のアップサイクル。

●古民家・古木サーキュラーエコノミー
山翠舎の取り組みへの評価。
2020年、グッドデザイン賞受賞。
・古木を収集・備蓄・整備し、単なる販売に留まらず設計・施工まで行うことで再利用を促す取り組みであること。
・現在では入手困難な木材、建築技法、伝統文化の保存をしていること。
・職人の育成。
・古民家や古木のデータベース化。
・付加価値のある用途の開発。
など。
➔今後の広がりを期待できること。
事業、取り組みが認められる。
=今の時代に求められている。
循環するビジネス)
古民家トレーサビリティシステム

・空き家になっている古民家を解体・移築する。
・古木や古民家を別の建物で利用する。
➔役割を終えたら再び解体・移築。
=山翠舎が最初に手掛けた循環モデル。
廃棄する木を最小限に抑える。
➔古木を再利用する。
=地球に優しい仕組み。
企業・人とのマッチング事業の場合。
①古民家の管理に困っている人と、使いたい企業・人の情報を集める。
②マッチングが成功したら古民家の解体をする。
③移築なら別の場所へ運んで工事し、解体なら古木を倉庫にストックする。
④すべての古木に年代、場所、サイズ、種類などの情報を残しておく。
⑤利用した店に対する開業サポート。
⑥ブランディング戦略の立案・支援
⑦古木のファンを増やすことで市場全体のパイを増やす取り組み。
新たなサイクルを回す。
=サステナブル(持続可能な)社会をつくる。
●「料理人応援システム」
料理人と古民家の家主をつなぐ事業。
➔料理人の弱点の解消がコンセプト。
飲食店の廃業率は高い。
➔銀行の融資の際の金利が高くなる。
=資金繰りが厳しくなる。
開業がゴールになっている料理人が多い。
➔出店後の事業計画が考えられていない。
=銀行の融資金額が少なくなる。
資金がない。
=内装にお金をかけられない。
安っぽいお店は、お客にすぐわかる。
➔人気が出ない。
料理人応援システムの内容。
①飲食店に合う未公開物件の情報提供
➔良質の古民家の物件。
②保証金などの初期費用が最大ゼロ円
➔保証金(家賃8ヶ月分)を山翠舎が交渉・負担。
③物件を借りる際のサポート
④事業計画書作成の支援
➔中小事業診断士などが一緒に作成。
⑤補助金や助成金の申請をサポート
「創業助成金」
「新規開業賃料補助金制度」
など。
➔情報提供や申請の手伝い。
⑥保証金返却や原状回復不要などの交渉を肩代わり
➔山翠舎が間に入ってい交渉する。
※料理人のリスクを山翠舎が共有することで成り立つ仕組み。
➔料理人に対する目利きの部分でリスクヘッジする。
🐾古民家は地方に残っている貴重な資産
なぜ地方には資産になる古民家がたくさん残っているのか。
東京の場合。
➔雑居ビルなどにしてテナントを入れたほうが儲かる。
=ほとんどが取り壊された。
地方(長野)の場合。
➔開発が進まなかった。
=結果的に古民家が壊されずに維持されてきた。
※寂れた地方ほど、古民家という資産が手元に残っている。
外国人観光客のゴールデンルート。
成田空港から入国。
➔東京観光➔箱根➔富士山➔名古屋➔京都➔大阪
➔関西国際空港から出国。
2回め以降のリピーター観光客。
=海外観光客の6割
➔ゴールデンルートを外れた田舎に足を伸ばす。
=日本にしかない田園風景を満喫する。
都市の観光地はどの国も似たりよったり。
例)
東京➔スカイツリー
中国➔広州塔(広州タワー)、東方明珠電視塔(上海テレビ塔)
マレーシア➔クアラ・ルンプール・タワー
カナダ➔CNタワー
など。
➔高いタワーはスカイツリーだけではない。
日本の古民家
=日本でしか楽しめないもの。
北海道のニセコ
➔アジアでトップクラスのリゾート地
ニセコにとっての最大の資源
=パウダースノー
➔アジアには他にない雪質。
日本の古民家=パウダースノーと同様のポテンシャル。
➔魅力を引き出せば観光客を引き付けられる。
●深刻さを増す「放置古民家」問題
空き家の数が加速度的に増えている日本。
総務省「住宅・土地統計調査」
2018年
日本全体の空き家数:846万戸
空き家率ワース3
1.山梨県:21.3%
2.和歌山県:20.3%
3.長野県:19.5%
ベスト3
埼玉県:10.2%
沖縄県:10.2%
東京都:10.6%
野村総合研究所の予測
2033年
空き家数:2100万戸
少子高齢化と人口減少で空き家増加に歯止めがかからない状態。
空き家放置のリスク。
ドア、ガラスの割れた家。
・治安、景観の悪化。
・不法侵入者や動物などがいつく。
・犯罪、事故、放火などのトラブル。
空き家を解体するための費用
=300万~500万円
(建坪60坪相当の古民家の場合)
更地にした場合、固定資産税は6倍に跳ね上がる場合がある。
=経済的理由で古民家を放置してしまうケースが多い。
●「潜在的空き家」こそ磨くべき対象
国土交通省の空き家の定義。
=1年以上誰も住まず、使われてもいない家。
年に1度以上メンテナンスされている家。
➔空き家にはならない。
=「潜在的空き家」
人の手が入っている家。
➔大規模な補修なく、そのまま使える可能性が高い物件。
取り壊しせずに維持している。
=家としての価値も高い。
「潜在的空き家」=磨いていくべき対象。
●地域に本気でコミットする熱意を示す
地域にとっての「新参者」
=「よそ者」
➔地域の企業、行政、住民から支持を受けるのは難しい。
地元に受け入れられない。
=地元の人しか知らない情報が手に入らない。
➔よそ者のままでは事業の成功はない。
地域に受け入れてもらう。
①投資をする。
➔自分の本気度を示す。
・地域を盛り上げようとする姿勢を示す。
・地域に人を呼び込むための宣伝活動をする。
=お金や時間を費やす。
「私はこの地域に本気でコミットしようと考えている」
➔思いを伝えられる。
※行動することが重要。
➔言葉で熱意を伝えるだけでは不十分。
②小さな地域貢献を積み重ねる。
・地元のものを買い付ける。
・雇用を生む。
➔地域にプラスの影響を与える。
<第3章 古民家×ビジネスが地域にもたらしたこと>
地域の活性化に関わるビジネス。
➔行政担当者のパッションが重要。
=行政だけは取り替えがきかない。
<第4章 古民家でつなぐ地方と世界とこれからの社会>
🐾捨てられるものを磨き、価値を与え、市場をつくる
データベースをつくる。
①古民家に使われている古木の価値が守られる。
➔偽物との見分けがつき、本物の古木の価値を守れる。
②古木の取引市場が確立される。
古木のマーケットプレイスができる。
➔古木に相場観が生まれる。
=BtoCの他、CtoCなどの取引形態が生まれる可能性。

●プラットフォームを提供することで古民家・古木を活用しやすい環境へ
地方で放置されている古民家が活用される環境。
➔地方活性化、環境面でのプラス効果。
山翠舎が目指しているもの。
古木の調達、管理、施工状況に応じた加工、発送業務を負担。
=古木特化のAmazonのような仕組み。
建設会社にプラットフォームを提供する。
➔古民家・古木の施工に加わりやすい環境を整える。
=日本全国の建築会社との協力。
例)
古民家の解体・設計・施工などのフロント業務。
➔各地の建設会社
古木の管理、発送、加工などの裏方作業。
➔山翠舎
●特許出願で知財を多くの人と共有する
知的財産についての取り組み
例)
「古木/こぼく」
「KOBOKU」
「恵比寿柱」
➔山翠舎の登録商標
ローマ字での商標登録。
➔ブランド展開を考えてのこと。
例)
・概念的な意味。
・トレーサビリティをKOBOKUと定義
・特許出願中のビジネスモデルの名前として。
無防備な技術の公開。
➔特許出願による技術の独占。
=技術の普及が難しくなる。
例)
2022年の「ゆっくり茶番劇場商標登録問題」
技術を守るための特許。
➔安い金額で広く提供し、利用してもらう。
自社の知的財産を公開。
➔業界全体の盛り上がりを促す。
=知的財産は自分たちだけの専売特許ではない。
※知財を守ることと囲い込むことは全く違うこと。
●目指すところが同じであれば業界の垣根は問題ない
山翠舎の原点=「もったいない精神」
流通過程でのフードロス。
・腐ったものが一つでもあると箱ごと廃棄。
・運搬中に傷がついたものも廃棄。
・規格外品も廃棄。
➔腐っているもの以外は問題なく食べられる食材。
「フードロス解消レストラン」
食べられる廃棄食材を、付き合いのあるレストランで調理し、販売してもらう取り組み。

フードロス解消レストランの立ち上げ。
➔環境問題に関心を持つ消費者を引き付けられる。
=地域の魅力を高める一助になる。
ムダに捨てられるものに着目する。
=ビジネスチャンスにつながる可能性が大きい。
●人を巻き込むために情熱や面白がる気持ちを大切にする
ビジネスを拡大させる。
➔循環を加速させる。
=人を巻き込む力が必要になる。
人を巻き込むのに重要なもの。
=情熱に共感、ノリの良さ。
➔これが好き、あれを実現したいという確固たる思い。
※お金だけでは人の気持は動かせない。
情熱がある人と一緒に働く。
➔仕事はうまく回る。
知ることだけでは十分ではない、それを使わないといけない。やる気だけでは十分ではない、実行しないといけない。
合わせて読むのにオススメの本。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
