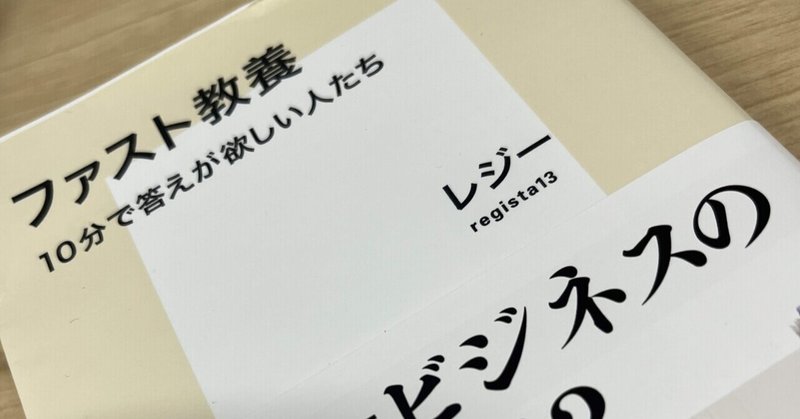
「ファスト教養」とメンタルヘルス
レジー著『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』(集英社新書)を読んだ。「教養=ビジネスの役に立つ」という認識で、短い時間で効率よく"教養”とされる文化的なモノ(映画、音楽etc..)に触れるビジネスパーソンが増えているという。本著ではファスト教養を提供する人物を詳しく掘り下げながらその歴史や近年の隆盛について解き明かしていくという内容だった。
これを手に取ったのには漠然と「胡散臭いな」と思っている人たちについて知りたいという個人的な理由が前提にあったのだが、読み進めていくうちに発見があった。自分が精神科医として診療している中で何人かの患者さんが話してくれた生き辛さと繋がるような考え方が多く記されていたのだ。
特に第3章でなされた「自己責任」への言及。"失敗できない”という考えで自らを強い緊張感のもとに晒すことは本来大きなストレスなはずだ。しかしビジネスパーソンの仕事への向き合い方で"自己責任"が当然になっているのならば、自分を高め向上せねばという思いに駆られるのも仕方ない。社会競争についていけず、心を病んだと話す患者さんが確かにいた。
また第4章には心身の不調をきたした人への言及もあった。その方は仕事が原因で体調を崩し、回復するタイミングで読んだビジネス書に共感したという。その方は「こうあるべき」という姿を示すビジネス書が「自分の頑張りが足りない」という考えを誘発し得るものという認識を抱いていた。自己啓発本を読み、休日を使い果たし続けていた患者さんの顔が思い浮かんでしまう。
診療現場の肌感覚で思っていることではあるが、ビジネスパーソンのみならず学生、特に受験生や浪人生たちへのファスト教養の影響が想像以上に強い。"失敗できない"という強い想いは若い世代にもどんどん伝播しているように見える。
人よりも上に行くしかない、成功しなければ転落するのみ、という思考に雁字搦めになって受験勉強の過酷さに心を病む学生たちは多い。クリニックに来ている学生たちも進学校の生徒たちが多く、彼ら彼女らの言葉からは人と比較し、成績を悔やみ、重く受け止めている様子が伺える。友人関係を潤滑に行うために流行は必ずチェックする、といった学生らしい仕草とも妙にリンクしているように思う。周囲から浮いて悪目立ちしたくない、というような。
うつ病や適応障害という診断がつけば、まずは休息の重要性を伝えることになる。しかし休んでいる期間でも、心安らげるためのちょっとした楽しみや没頭できる何かがないとなればストレス因に関連したことを考えこむしかなく、悪循環に陥るというケースをいくつか見てきた。ポップカルチャーを「役立つ」ではなく「楽しむ」ものとして捉えていないと、こういった事態になりやすいのではないだろうか。お節介なのかもしれないがこういう時にこそ、メンタルヘルスを守るための“大切なもの”が必要になりそうだ。
そういう意味では"好きなもの"を見つけることの重要さを説く本著の第6章の存在はかなり大きいと感じた。好きなことの見つけ方の一例も示しており、この本はファスト教養にしっかりと浸っている人たちや、そうでなくても漠然と疲弊したり社会の動きの速さに焦ったりしている人たちにも重要な意味をもって届くはずだ。
このようにファスト教養のメンタルヘルスへの影響などについて書いたりすると、ファスト教養を真正面から受け取って社会競争を“プレッシャー”や“ストレス”のように感じるどうかは「自己責任ではないか」という言葉が飛んできそうだ。そのように切り捨てていいものだろうか。何をプレッシャーやストレスと感じるか、という背景はその人の生育環境や経済状況に強く影響されるはずで、そこに社会全体が作り上げてきた"上昇志向"で"競争を強いる"ムードや、ファスト教養が説く”成功“の圧迫感は無関係とは言えないだろう。
本著で特徴的なのが"教養側"と"ファスト教養"側の対立を煽ることなく、なぜそうなったのかを丁寧に示しており相互理解の橋渡しにもなり得る点だ。誰もが"ファスト教養"に魅了される可能性も示しているという点も重要だろう。自分は医療という世界の人間ゆえビジネスとは縁遠いように思うのだがどこかで今の仕事のシステムががらりと変わることだってあり得る。そのような大きな波と対峙する覚悟は必要なのだろう。しかしやはり、どんな局面でも好きなものを楽しむことを忘れず生きる自分でありたい。そう改めて強く思える1冊だった。
#読書の秋2022 #ファスト教養 #読書感想文 #本 #小説 #読書 #書評 #本紹介 #おすすめ本 #読んだ本 #オススメ本 #新書
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
