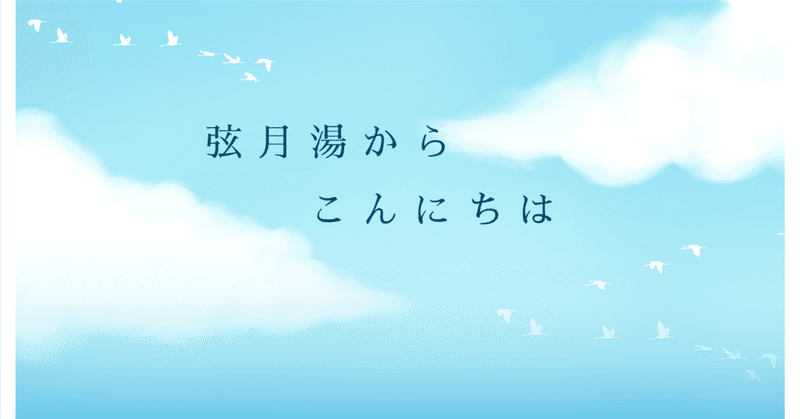
小説「弦月湯からこんにちは」第3話(全15話)
これまでのお話
・第1話はこちら
・第2話はこちら
*
第3話
*
「おはようございます」
擦りガラスの引き戸をからからと開けると、若い女性の声に迎えられた。てっきり、年配の男性が番台には座っているものと無意識のうちに思いこんでいたら、ベリーショートで丸い眼鏡をかけた小柄な女性が座っていた。驚きを顔に出さないように、番台に向かう。
「おひとり、520円です」
「はい……すみません、タオルって売ってますか?」
「無料でお貸ししてるので、よければどうぞ」
ミントグリーンのタオルを2枚渡された。背後に流れているのは、バロック音楽だろうか。典雅なチェンバロの音色が響いている。
「ボディソープとシャンプー・リンスは中にあるので、ご自由に」
「ありがとうございます」
女湯に向かおうとした時に、番台の女性が読んでいた本の表紙が目に入った。ガルシア・ロルカ『血の婚礼』。私は目をむいた。朝から読む本でもなかろうに。ロルカは好きだし、私自身も決して嫌いな本ではないが、少なくともこの時間帯向けの本ではない気がする。
私がその場から動けずにいると、番台の女性は顔を上げる。
「なにか?」
「あ、いえ……」
女性は、再び本に目を落とす。マスクで隠されたその横顔は、幼いような、老成したような、透明感を感じる不思議な面差しだった。私は気持ちを切り替えようと、女湯の暖簾をくぐった。昔ながらの脱衣所。背の低いロッカーを開け、のろのろと裸になり、マスクを外す。タオルを1枚持ち、体の前を隠しながら、風呂場の扉を開ける。
「え……?」
そこに広がる異世界に、私は驚いた。目の前に広がるのは、銭湯によくある富士山のペンキ画ではなくて、見た事もない、色鮮やかな幾何学模様のモザイク画だった。天井近くの窓は色鮮やかなステンドグラスになっていて、赤や青、オレンジの光の欠片が風呂の湯に揺れている。風呂の縁は不規則な曲線を描きながら盛り上がっていて、ここにもモザイクタイルが嵌められている。風呂場の床は、白を基調に水色とオレンジ色の花が対照的に描かれた正方形のタイルが敷き詰められている。
私は、混乱した。この色鮮やかなタイル、色合いと筆の具合から、スペインのものだとすぐに分かる。そして、この風呂場のデザインは、スペインが生んだ芸術家、アントニオ・ガウディへのオマージュを基盤にしていることも、うっすらと分かる。なんだ、この銭湯は。どうしてこんなに濃厚なスペインの気配の中で、湯に浸からなくてはならないんだ。
混乱しながらも、私は風呂桶と椅子を持って、蛇口の前に座った。風呂桶は昔ながらの黄色いもので、底にケロリンと書いてある。この異空間とケロリンのアンバランスさに、更に私の混乱は深まった。ここは、一体なんなんだ。デザイナーズ銭湯なのか? ……いや、北三日月町にそんなおしゃれな銭湯があるという情報は、これまでなかった。では、新しくオープンした? ……いや、外壁も、この風呂場のモザイクタイルも、充分に経年変化を感じる。私は久しぶりに戦略脳を回転させながら、頭と体をじゃぶじゃぶと洗った。リンスインシャンプーとボディソープは、薄いピンク色で、薔薇の香りがうっすらとした。
頭をタオルでくるみ、風呂に浸かる。客はわたし一人だけだ。浴槽は大きなもの、黄緑色の入浴剤が入った中くらいのもの、そして小さな水風呂の3種類に分かれている。大きな浴槽に、身を浸す。入っているのは、私ひとりらしい。深い息を吐く。浴槽の底には、明るい緑の2センチ角のタイルが行儀よく並んでいる。私は湯の中で腕を伸ばす。湯に波紋が広がり、緑のタイルが揺れる。こんなにのんびり、風呂に浸かったのはいつ以来だろう。今年に入ってからは、床に倒れ込んで眠ることもあったな……と思い返す。朝になってシャワーを浴びて、無理矢理に頭をすっきりさせて、店に向かう日々が続いていた。
私は、天井近くのステンドグラスを眺める。日本の季節の花がデザインされている。全部が全部、スペイン調というわけでもないらしい。まあ、いいや。なんでもいい。今は、難しいことを考える体力や気力はない。私は目を瞑り、不規則な曲線を描く浴槽の縁に頭をもたせかけた。ちょうど首や頭を載せられるようになっているのかもしれない。湯がゆらゆらと体を撫でる。ああ、気持ちがいい。私は両手で湯をすくい、顔に回した。
風呂を上がり、体を拭きながら、掲示板に貼ってあるポスターを眺める。城北区の公衆浴場組合からのお知らせ、城北区のツァイトウイルス対応について……機械的に眺めていると、不意に「住み込み募集」という手書きの文字が飛び込んで来た。住み込み? 体を拭く手を止めて、掲示板に近付く。
「住み込み募集
弦月湯のお手伝いをしてくださる方を募集しています。部屋・食事提供の現物支給。ご興味のある方は、番台まで」
私は、心がぐらりと動いた。あと4日で、今の社員寮を出なければならないのだ。けれど、この2週間はずっと布団で溶けたまんまで動くことが出来なかった。何も考えることが出来なかった。もしも、ひとまず、こちらに移って今後のことを考えていくことが出来たら、それは願ってもないことだ。現物支給というからには、給料は出ないのだろうけど、これまでの貯金があるからしばらくはなんとかなるだろう。私は手早く洋服を身に着けた。
番台に向かうと、先程の小柄な女性は『血の婚礼』を読み続けている。
「あの、すみません……」
女性は本から目を上げる。
「いまそこで、こちらの住み込み募集という張り紙を見つけたのですが……」
女性は本を閉じて、私を見つめる。眼鏡の向こうの透明な眼差しは、レントゲンのようにいろんなものを見透かしていくような気がした。
「お名前は」
「山口壱子です」
女性は無言で、じっと私を見つめ続ける。私は段々と、脇に汗が滲んでくるのを感じた。女性は番台の下から、何かファイルのようなものを出した。そして、私を手招きした。女性はファイルの中から、一枚書類を出して渡した。なにか、注意書きが書いてあるようだ。私は女性を見つめる。女性は、ファイルに目を落としたまま、言葉を続ける。
「基本的にお手伝いをお願いしたいのは、夜の8時半から10時の間。それと、朝湯を開ける前の7時から7時20分までと、夕方の営業を始める前の昼の2時半から2時50分までです。それと、週に2度、3時から8時までの間で2時間ほど番台にいらしていただければ。いま時短営業中で、うちの営業が8時までなのですが、その後に男湯と女湯の清掃に入ります。朝ご飯は6時、昼ご飯は12時。夜ご飯は作っておいたものを適宜食べていくという感じです。部屋は、ここの離れの2階、7号室が空いてるので、自由に使って下さい。6畳の和室です。布団もあるので、よければ使ってください」
「あの……?」
「いつから来られますか? 今日? 明日? 来週?」
「そしたら……明日から、お願いします」
「わかりました」
そして女性は、私を見つめた。赤ちゃんのように、そして底の見えない湖のように透明な瞳が、私を見つめていた。
「私はここの三代目で、若月いずみと申します。ここの離れの1階で、従弟との2人暮らしをしています。3月までは住み込みの方が3人ほどおいででしたが、ちょうど皆さん引越しや、大学の卒業などで、ここから去ってしまいました。なので、山口さんにこうしておっしゃっていただけて、とても有難いです。今はウイルスの影響を受けていますが、常連さんはおいでになるので、朝の7時半から9時までの朝湯と、夕方の3時から8時までの時短営業に切り替えて、銭湯を開けています」
「そうなのですね」
「お手伝いをお願いするお時間以外は、ご自由にしていただいて結構です。うちは現物支給のみですので、ほかのお仕事をしていただいても構いません。お風呂は、うちのお風呂を自由に使ってください」
「ありがとうございます」
「明日は、何時においでになりますか」
「そしたら、昼前の11時くらいには」
「わかりました。昼食も用意しておきます。アレルギーや嫌いな食材はありますか」
「いえ、特に」
「わかりました。では、また明日」
女性は赤ちゃんのように透明な瞳で私を見つめて、一礼した。そして、再び『血の婚礼』に目を落とした。必要な情報は全て伝え終わったというわけか、と私は納得する。そして、番台の女性に一礼して、木の札を持って下足箱に向かう。
なんだかよくわからないうちに、私は今の部屋から抜け出すことが決定した。早急に、準備を始めなくては……と思い至ると、頭がゆるゆると回転し始めた。たいへんだ、急いで片付けをしなくては。
(つづく)
*
つづきのお話
・第4話はこちら
・第5話はこちら
・第6話はこちら
・第7話はこちら
・第8話はこちら
・第9話はこちら
・第10話はこちら
・第11話はこちら
・第12話はこちら
・第13話はこちら
・第14話はこちら
・第15話(最終話)はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

