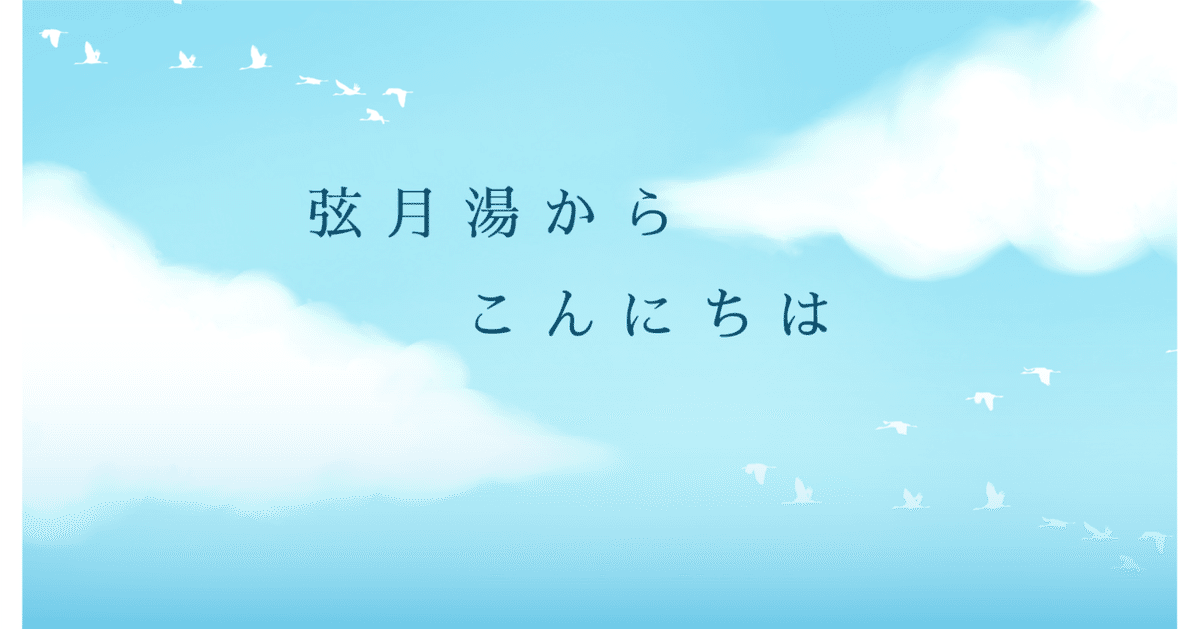
小説「弦月湯からこんにちは」第5話(全15話)
これまでのお話
・第1話はこちら
・第2話はこちら
・第3話はこちら
・第4話はこちら
*
第5話
*
ざしざし、ざし。ざしざし、ざし。鮮やかな緑色のデッキブラシで、花柄のタイルの床を磨き続ける。洗剤のミントの香りが、マスクを通じても感じられる。
「壱子さん、女湯の方はどうですか?」
「あと3割ってとこです」
「了解です、あと7分くらいで終わらせて、水流しちゃいましょう」
「わかりました」
「終わったら、青林堂さんのみたらし団子食べましょう」
「いいですね」
「あともうちょっと、がんばりましょう」
「はい」
午後の営業に向けて男湯を掃除するいずみさんと、高くて広い天井越しに声を交わす。額にじんわりと滲む汗を手の甲で押さえ、床のタイルに意識を戻す。弦月湯では、朝湯と午後の営業の間に、お湯を入れ替えているので、昼過ぎのこの時間が掃除の時間になるのだ。ざしざし、ざし。ざしざし、ざし。ざしざし、ざし。ざしざし、ざし。
弦月湯で働くようになって、2週間が過ぎようとしている。いずみさんと同居しているという従弟の方とはまだお会いできていないのだが、雇用主であるいずみさんとは少しずつ、穏やかな関係を築けているような気がする。朝昼の挨拶、そして風呂場の掃除の前後くらいしか話はしないのだが、不思議と居心地はいい。公園や路地裏にいる猫たちが、互いの領域を尊重しつつ、ほどよい距離感を保っているような感覚と似ているのかもしれない。
それにしても、デッキブラシでこのタイルの床を磨いていいのだろうか……と、最初は不安に思っていた。おそらくはスペイン製の、水色とオレンジの花柄のタイルは、アンティークショップでは、いい値段のつく逸品だ。だが、いずみさんは気にせずにざしざしと磨いていく。一度、おそるおそる尋ねてみたところ「いいんです、暮らしの中で使われてなんぼのものですから」という答えが返ってきた。
それは意外なほど、自分にとって心地のいい答えだった。そうだよな、確かに暮らしの中で使われてなんぼのものなんだよな……。そう思えるようになると、首の凝りがふわっと軽くなったような気がした。そういえば、獅子頭の男の夢も、弦月湯に来てからは見ていない。風呂の仕事で疲れて、布団にダイブして、気がつくと朝を迎えているということが多くなった。
「壱子さん、そろそろ大丈夫そうですか?」
「あ、はい、大丈夫です」
「じゃあ、水流して、上がっちゃいましょう」
「はい」
ホースから勢いよく水が出る。ミントの香りの泡を流していく。アンティークのタイルにとって、これがベストな扱い方でないというのは百も承知だが、暮らしの中の風景としてはなんとも心地のよいものだった。
「それじゃ、あとはお湯を張っておくので、壱子さん、お団子お願いします」
「わかりました」
足をタオルで拭って、まくりあげていたズボンの裾を戻す。靴下を履いて、シャツの袖を戻そうとした時、鏡の中の自分と目が合った。もさもさの髪を後ろでくくった、すっぴんの顔。眉毛の手入れもしていない。唇の皮が白く乾いて、少しめくれ上がっている。毛穴も少し広がったかもしれない。久しぶりに鏡を見たような気がして、しばし動きを止めた。
自分の店で働いていた時は、もっと鏡をよく見ていた。人前に立つ仕事なのだから、お客様に恥ずかしくないようにと思って、トイレに立つ度に化粧を直していた。とはいえ、そんなに手をかけるような化粧はしていなかったが。リキッドファンデーションにパウダー、アイブロウにアイシャドウ、マスカラにチーク、それに口紅を塗るくらいの必要最小限のものだった。けれど、眉毛が薄れていないようにとか、アイシャドウがよれていないかとか、そんな細かいことをずっと気にしていた。
けれど、本部の方針が変わり始めてからは、鏡を見る頻度が減っていたかもしれない。最後の頃は、朝に眉毛を描いたら、そのまま夜まで放っておくこともざらだった。それでも、朝の化粧だけは欠かさなかった。もしかしたら、砂の城のようにさらさらと崩れていきそうな自分を、現実に繋ぎ止めるための儀式だったのかもしれない。
その証左のように、弦月湯に引っ越す際に、アイブロウ以外は捨ててしまった。購入する時には、デパートで販売員の薦めるままに揃えたものだったから、決して安いものではなかったのだが。けれど、金と黒のパッケージで揃えられた化粧品には、あの日々が染み込んでいるような気がして、もう触れたくもなかった。開けたくなかった。
我に返って、鏡の中の自分をもう一度見つめる。相変わらず、もしゃもしゃのままだ。そういえば、最近は余っていたニベアを、顔や髪につける位のスキンケアしかしていなかった。後で、ドラッグストアを覗いてみよう。
裏に回って、台所を覗くと、いずみさんが珈琲を淹れてくれていた。みたらし団子が皿の上に行儀よく並んでいる。
「すみません、うっかりぼーっとして、お団子準備できなくて」
「大丈夫ですよ。珈琲にしちゃいましたが、いいですか?」
「ありがとうございます」
私は頭を下げる。そして、静かに注がれる湯の音と、立ち上がる珈琲の香りの中、腰を下ろした。午後の風呂掃除の後は、こうしていずみさんとお茶の時間を持つのが、このところの新しい日常になっていた。
「庭の樹さんって、壱子さんご存じですか?」
「えっと……坂の途中にある、自家焙煎のカフェでしたっけ」
「そうそう。その庭の樹さんが、持ち帰りのみで受注焙煎を始められたと伺って、お願いしたんです」
「あら、素敵」
「200gからお願いできたので、今回はグァテマラにしてみました」
「グァテマラ、いいですね」
いずみさんは手際よく、珈琲を備前焼のぽってりとしたマグカップに注ぐ。私も、流しに置いたままだった暦くんのマグカップを拭いて、その横に並べた。
「いただきましょうか」
「ありがとうございます。いただきます」
「いただきます」
私はそっと手を合わせ、頭を下げる。いずみさんが淹れてくれた珈琲は、香りが高く深い味わいだ。いい腕を持ってらっしゃるなあ、と感心する。うちの店にもこんなバリスタさんがいてくれたら、よかったのにな。マグカップに唇を当てながら、無意識のうちにそんなことを考えている自分に気付いて、苦笑する。どうしても、つい仕事のことを考えてしまうな。前の仕事のことを。
顔を上げると、いずみさんと目が合った。考えに沈み込んでいたことをごまかそうと、愛想笑いを浮かべる。だが、いずみさんは静かに私を見つめていた。ややあって、いずみさんは唇を開いた。
「私、壱子さんのお店が好きでした」
「……え?」
思いもよらない言葉に、私は驚愕した。頭が白くなる。
(つづく)
つづきのお話
・第6話はこちら
・第7話はこちら
・第8話はこちら
・第9話はこちら
・第10話はこちら
・第11話はこちら
・第12話はこちら
・第13話はこちら
・第14話はこちら
・第15話(最終話)はこちら
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
