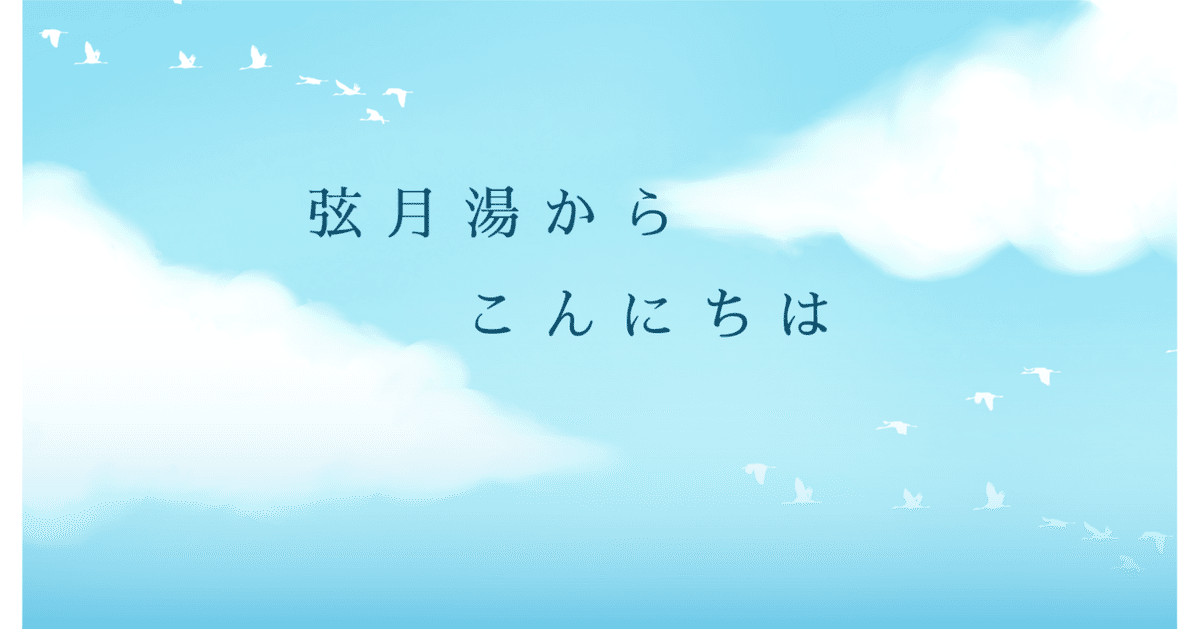
小説「弦月湯からこんにちは」第15話(最終話)
これまでのお話
・第1話はこちら
・第2話はこちら
・第3話はこちら
・第4話はこちら
・第5話はこちら
・第6話はこちら
・第7話はこちら
・第8話はこちら
・第9話はこちら
・第10話はこちら
・第11話はこちら
・第12話はこちら
・第13話はこちら
・第14話はこちら
*
第15話(最終話)
*
10月のある晴れた定休日。いずみさんと暦くんと私の三人で、隣町の王子にある飛鳥山公園にピクニックに出かけた。暦くんの個展「みんなの愛と生涯」第二弾開催前の息抜きだ。歩いて二十分もすると、こんもりとした緑が見えてきた。
「春になると、公園中が桜でいっぱいになるんですよ」
帽子をかぶったいずみさんが目を細める。
「小さい頃は、祖父と祖母と一緒に飛鳥山で花見をするのが毎年の恒例行事でした。今日も寄りましたけど、途中の平塚亭さんで豆大福を買うのもいつものことでした」
「そういえば平塚亭、どなたかのサインもありましたよね」
「小説家の内田康夫先生です。平塚亭さん、先生の小説にも登場する由緒あるお店なんですよ」
「へえ……」
「祖父は平塚亭さんのおいなりさんも好きでした。ちょっと味が濃くて、甘さとしょっぱさの加減がちょうどいいんだってよく言ってましたね」
「よだれが出そうです」
「おいなりさんも買いましたから、お楽しみに」
いずみさんは微笑んだ。
「ねーちゃん、壱子さん、どこでお弁当食べます?」
「山の上のベンチの近くにしましょうか」
「オッケー、いつものとこね」
暦くんと目が合った。暦くんが大きく笑う。私も笑い返す。
暦くんと思いを伝え合ってから、一緒にいる時間が増えた。シューマンのことにも、少しだけ詳しくなった。たまに、私が昔から好きだったノラ・ジョーンズのCDを一緒に聞いたりもしている。いろんなことをよく話すようになった。一緒によく笑うようになった。
将来のことも、よく話すようになった。現在の日本の制度では、悲しいけれど私達は法律上の婚姻関係を結ぶことは出来ない。現況での代替案として養子縁組なども視野に入れるようになったが、私達が本当に求めているものではない。
法律のことだけでなく、私達がこれから乗り越えなければならないことは多い。暦くんがあまり話したがらない、実家のご家族のこと。私の母のこと。それらを考えていると、煮詰まって焦げ付いてしまいそうになる時もある。
「壱子さん、ゆっくり、一緒に考えていきましょう。一緒にひとつひとつ、取り組んでいきましょう」
私が煮詰まると、暦くんはいつもそう言ってくれる。そして、いつもの麦わらのルフィの笑顔を見せてくれる。最強、無敵の笑顔だ。私の大好きな笑顔だ。けれど、この笑顔は、繊細な暦くんがいつも意識して作り出しているのも知っている。だからこそ、この笑顔を守りたいと願う。
「ついた!」
暦くんの明るい声が響く。小高い丘のような飛鳥山に登ると、視界が広げる。王子駅の近くを、新幹線が走っていく。親子連れが楽しそうに手を振っている。
芝生の上にブルーシートを敷いて、お重を並べる。お重には、三人で作ったおにぎり、唐揚げ、卵焼き、いんげんの胡麻和えが詰まっている。平塚亭の豆大福も、おいなりさんも並べる。紙皿を出して、水筒からお茶を汲む。
「こうして三人でピクニックするって、初めてだね。壱子さんが言い出してくれてよかったな。ありがとうございます」
暦くんが紙皿に卵焼きと唐揚げを取り分けながら、感謝の言葉を述べる。
「こちらこそよ。みんなでピクニックに行くのがささやかな夢だったの」
すこしの躊躇いの後、口を開く。
「子供の頃、父と母と三人で葛西臨海公園に行ったこと、あったんです。うちは両親が不仲だったけれど、そのピクニックではふたりとも優しくて。ずっと忘れていたんだけど、自分にも幸せな時間があったんだなって思い出してみたら、なんだかピクニック行きたくなっちゃったんです」
「……壱子さんが、ご家族のこと話してくださるのを初めて聞きました」
「そう……かもしれませんね。あまり家族のことは考えないようにして、これまで生きてきたような気がします。両親は私が小学校に入る前に離婚しました。父は、高校生の頃に亡くなったと聞きました。家には写真がなかったので、薄情かもしれませんが、父の顔は忘れてしまいました。」
私は目をつむる。夢に出てきた獅子頭のことを思い出す。
───「儂はいつでも此処で、お前の心の奥底で、お前を守っているよ。そのことを忘れるな、イチコ。いつでも、お前を守っているよ」───
幼い私がつくりだした、父の面影。夢の中でずっと怯えてきたのは、私が父を無意識のうちに拒絶してきたからだったのかもしれない。私はずっと、父を慕いたかったのだと気付いた。
「私も、両親の顔をはっきりと思い出すことはできません」
ややあって、いずみさんが口を開いた。
「両親がバスの事故で亡くなったのは、私が幼稚園の頃でした。私はその日、祖父と祖母に預けられて難を逃れました。写真の中でしか、顔を知りません。もしも今、生きていたらどんな言葉をかけてくれるだろうと思う日もあります。けれど、私にはこの道しかなかった。それを悔やむことはありません。それに」
いずみさんが桜の花のように微笑んだ。
「この道を歩み続けてきたから、いまみんなで飛鳥山に来られているのですものね」
「……そうですね」
暦くんも微笑みながら、私達の会話を聞いている。けれど彼は、自分の両親については語らないだろう。アルコイリスに勤めていた時、自分の誕生日を頑として明かさなかった暦くんを思い出す。誕生日じゃない日のお祝いで、涙目になっていた暦くんを思い出す。いつか、暦くんが自分の誕生日を祝福できる日が来ますように。私はおにぎりをかじりながら、そっと願った。
「今度、みんなで葛西臨海公園にも行こうよ」
暦くんがそう言い出した。
「考えてみたら、自分、海の近くってあんまり行ったことないな。ねーちゃんは?」
「海……スペインにいた時に、バルセロナでちょっと寄ったくらいかしら。葛西臨海公園って、水族館もあるところでしたか?」
「そうそう。マグロやペンギンがいるんですよ。あと、観覧車もありますね」
「水族館、行ってみたいな。次の休みに、みんなで行かない?」
暦くんは大きく笑った。最強、無敵、ルフィの笑顔だ。私は、暦くんの紅茶色の髪をわしゃわしゃと撫で回したい衝動に駆られた。あなたは、ほんとにいつも、みんなのことばっかり考えて。自分のことを後回しにして。髪の毛を撫で回して、胸に抱き締めて、わんわん泣きたいような衝動を胸に閉じ込めたまま、私は微笑んだ。
「いいわね。壱子さん、行きましょう。私も海を見てみたいです。マグロやペンギンにも会ってみたいです」
「……ありがとうございます。張り切って案内しますよ!」
「張り切らないでいいので、肩の力を抜いてみんなで楽しみましょう」
いずみさんの桜の花のような笑顔がふわっと開いた。肩の緊張がほどけていく。
「ありがとうございます。そうしましょう」
ああ、そうだ。弦月湯に来てから、これまでの人生で積み重ねてきた緊張が、どんどんほどけているんだ。これまでの人生で作り上げてきた鎧を、どんどん外し続けているんだ。ずっと、もっと速くとか、もっと上にとか、そういうことを自分に課してきた。けれど、弦月湯に来てからは、それまでと全く違った日々が待っていた。これまで歩んできた人生とはまったく変わってしまったけれど、こんなにも居心地のいい人生が待っていた。
「そういえば、自分、また来年も個展開きたいって思ってるんです」
しばらくして、暦くんが口を開いた。
「素敵ね。今度も写真作品?」
「いえ。今度は時間かけて、久しぶりに水彩で描いていきたいって思ってます。風呂場に飾るものは、データ印刷して展示しようと」
「いいわね」
「それで、ねーちゃんに折り入ってお願いがあって」
「私に?」
いずみさんがきょとんとした顔で暦くんを見つめる。
「ねーちゃんに、小さなお話を書いてほしいんだ」
「小さなお話?」
「うん。何でもいいんだ。小さなお話を書いてほしい。自分は、それに絵をつけていくから」
「小さなお話なんて……私には」
「自分、知っているよ。昔からねーちゃんが物語を作りたい人だってこと。なにかを生み出したい人だってこと。それをずっと、自分で否定しているけれど、本当はなにかを書きたい気持ちがマグマみたいにぐつぐつに潜んでるって、知ってる」
いずみさんは、暦くんを透明な眼差しでじっと見つめる。
「今まで、弦月湯のために……って、ずっと自分が本当にやりたいことを我慢してきたのも知ってる。でも、いまのねーちゃんはひとりじゃない。自分もいる。壱子さんもいる。自分たちがサポートしていくから、ねーちゃんにもずっとやりたかったこと、小さくてもいいから始めてもらいたいんだ」
暦くんを見つめていたいずみさんは、長い息を吐いた。空気が柔らかくなった。
「……暦には、かないませんね。小さなお話、考えてみましょう」
「ありがとう」
「こちらこそ」
「そしたら個展に向けて、二人の共作はnoteで連載にしていきましょうか。楽しみだなあ……」
「壱子さん、気が早いって」
「そうですよ、まだ題材も決まっていないんですから」
私達は顔を見合わせて、笑いあった。
空を仰ぐ。弦二郎さん、あなたの愛した子供たちは、それぞれの道を逞しく、優しく歩いていますよ。二人を、これからも見守ってくださいね。
「そういえば、明日の薬湯風呂って何を入れるの?」
「明日は月に一度のじっこう風呂よ。帰ったら準備しなくちゃ」
「じっこう風呂、常連さんに人気ですもんね。弦月湯に来て、初めてじっこうって知りました」
「お風呂屋さんの間では昔からよく知られているんですよ。壱子さん、明日の番台お任せしていいですか?」
「もちろん」
いつの間にか、銭湯の仕事がこんなにも心と体に馴染んでいる。ずっと昔からここが自分の居場所だったみたいだ。
暦くんと目が合った。ニヤッといたずら子っぽく笑う。
「壱子さん、いまいい顔してますね」
「え?」
「カメラあったら、撮りたかったな」
「いきなりはだめよ」
顔を手で隠すと、暦くんはいつもの大きな笑顔になった。最強、無敵、ルフィの笑顔。胸が温かくなる。ずっと、ずっと、暦くんが笑っていてくれますように。そんな願いを込めて、暦くんに微笑みを返した。
10月の青空に、風がどこまでも吹き渡っていった。
(完)
*
スピンオフ
・第12話であんぱんをかじっていたアーティスト、
悠平が主人公のお仕事小説「あんぱんと弦月湯」。
・いずみの視点から描かれる暦と壱子の物語、
「一人称のゆくえ」─弦月湯シリーズ─。
よろしければ、あわせてお楽しみください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
