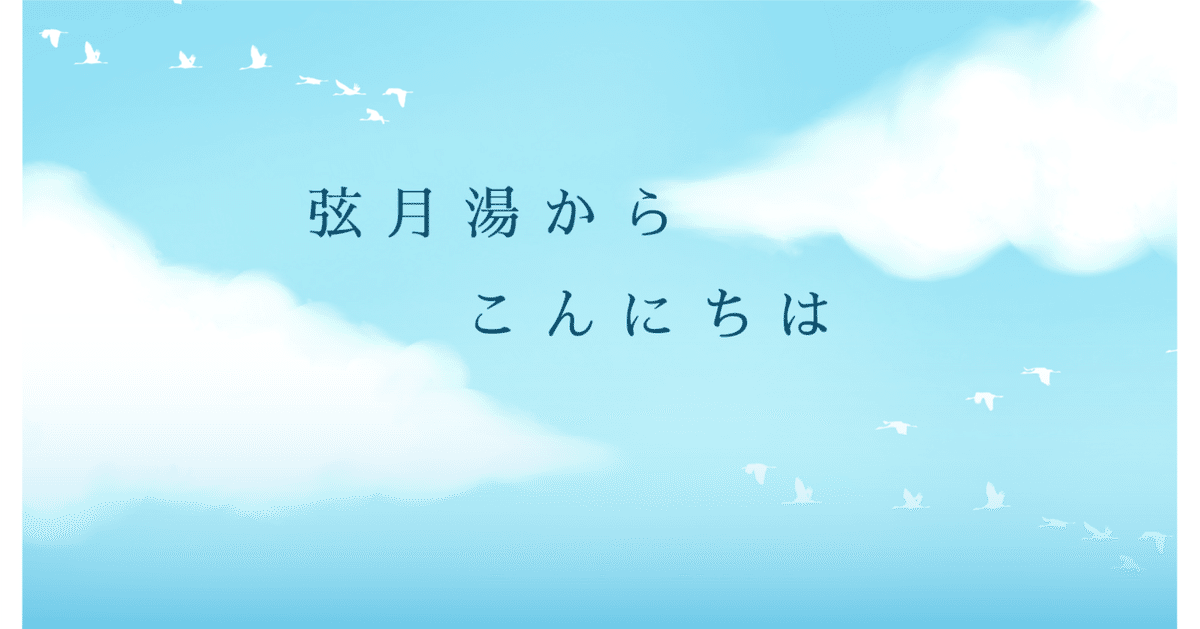
小説「弦月湯からこんにちは」第10話(全15話)
これまでのお話
・第1話はこちら
・第2話はこちら
・第3話はこちら
・第4話はこちら
・第5話はこちら
・第6話はこちら
・第7話はこちら
・第8話はこちら
・第9話はこちら
*
第10話
*
「壱子さん、ねーちゃん、まずは朝飯食いましょう。腹が減っては何とやらです」
暦くんはそう言うと、ガスをつけて昨日の豚汁を温めはじめた。卵を三つ割って入れる。
「一汁一菜でいいって、土井善晴先生も言ってるけど、あれって理にかなってるんですよね。前に土井先生が『きょうの料理』で、お椀一杯分の野菜とお水、それと少しの味噌で作る味噌汁を作ってて、めちゃくちゃ影響受けました。疲れている時でも、あったかいもの腹に入れると元気になるじゃないですか。あ、そんな自分でハードル上げなくていいんだって、ものすごく気持ちが楽になったんですよね」
朝の六時半。暦くんが起きてきて、弦月湯の時間が動きはじめた。暦くんはてきぱきと食卓の準備を整えていく。
「せっかくだから、なにか音楽かけましょうか。ねーちゃん、なんか聞きたいものある?」
「ジェシー・ノーマンのシューマンが聞きたい」
「承知」
暦くんはCDをセットし、スイッチを入れる。落ち着いたピアノと深いソプラノの声が流れてくる。朝の静かな空気の中、なんだか特別に聞こえる。
「じいちゃんも、ばあちゃんも、ノーマンの歌うシューマン好きだったもんね」
いずみさんは、子どものようにこくんと頷く。
「壱子さん、じいちゃんのこと聞きました?」
「ええ」
「じいちゃんがばあちゃんと知り合ったのは、上野の美術学校、いまの東京芸大に通っていた学生時代だったんです。ばあちゃんは音楽学校の声楽科に通っていた学生だったんですけど、学内の食堂で見かけたじいちゃんが一目惚れしちゃって、猛アタックしたって聞きました。芸大、自分も通ってたんですけど、美術と音楽の学生ってすごく雰囲気違うんですよ。だから最初、鳥の巣みたいな頭をした青年が話しかけてきた時、良家のお嬢様だったばあちゃんは、めちゃくちゃびっくりしたそうです」
暦くんは笑った。その笑顔に、胸がどきんと鳴った。鼓動の余韻をごまかそうと、私は曖昧な笑顔を浮かべる。
「ばあちゃんが学生時代に勉強してたのがドイツの歌曲で、特にシューマンの《女の愛と生涯》って歌曲集が好きだったんです。いま流れてるのも、その歌曲集。スペインにもじいちゃんと一緒について行って、向こうの楽譜もたくさん持ち帰ってきたって聞きました。たまに、風呂場で発声練習してたのをよく思い出しますね」
火加減を見ながら、暦くんは話し続ける。とくん、とくん、という胸の鼓動のようなピアノの音色と、流麗なソプラノの歌唱がそれに重なる。
「じいちゃん、ほんとにばあちゃんのことを大好きだったんで、新聞でいろんなコンサート見つけては、内緒でチケット取ってプレゼントしてました。いま聞いてるジェシー・ノーマンも、初めて来日した時に聞きに行ったみたいで、そこからふたりして大好きになったんです。いまみたいに、ネットでいろいろ調べられたり、すぐに聞ける時代だったら、ふたりとももっと喜んでいたでしょうね……さあ、出来上がり。まずは食いましょう」
とろとろの卵が入った豚汁が台所のテーブルに手早く並べられる。卵の上には七味がぱらりと振ってある。おにぎりがひとつずつと、漬物の載った皿も並べられる。
「いただきます」
手を合わせ、箸に手を伸ばす。卵に箸を入れると、鮮やかな山吹色をした黄身がとろりと広がっていく。汁を啜ると、食道から胃まで温かいものが流れていくのを感じられた。そうだ、まずは食べなくては。
「ほんと、腹が減っては何とやら、ね」
「でしょう」
暦くんがにっこりと笑う。いずみさんは静かに、おにぎりをリスのように小さな両手で抱えて食べている。小柄ないずみさんと大きなおにぎりの対比が微笑ましい。
「……壱子さん、弦月湯のためにありがとうございます」
食べ終わって、いずみさんがほうじ茶を淹れてくれた。茶碗を前に、暦くんは改まって頭を下げた。
「ねーちゃんから聞きました。自分も何か出来ないか、ずっと考えていたんです。自分に出来ることでしたら、何でもやります」
「ありがとう。話の前に、暦くんのいまの仕事について聞かせてもらってもいい? いまも以前の会社にお勤めなの?」
「一年ほど前に独立して、いまはフリーで企業からの仕事を請け負ってます」
「そうだったのね。そしたら、時間の融通はわりときくのかしら」
「そうですね、自分の采配で仕事の分量や時間配分は決められるので。いまはちょうど一段落ついて、落ち着いたところです」
「オッケーです」
私は先程書いた思考の設計図を取り出した。
「弦月湯を立て直していくためには、いずみさんと暦くん、そして私もお手伝いさせていただきますが、この三人がチームとして動いていく必要があると考えています」
いずみさんと暦くんが頷く。私は話を続ける。
「チームで動いていく上では、これからの展望を共有し、話し合うことも必要です。いずみさんは今後、弦月湯をどのような銭湯にしていきたいですか?」
「そうですね……いまいらしてくださっているご常連の方々を大事にしていきたいのは勿論ですが、もっと北三日月町の皆様方においでになっていただけたら、とても嬉しいです。町の銭湯として、ずっと長く続けていきたいです」
「ありがとうございます。暦くんは?」
「自分、実はこの弦月湯でグループ展開いたことがあるんです」
「そうなの?」
「大学卒業して仕事を始める前に、大学の友達誘って企画して、作品を弦月湯のあちこちに飾らせてもらったんです。風呂場にも、写真作品を印刷したものをラミネート加工して、あちこちに飾って。風呂に入りながら、アートを気楽に楽しんでもらえたら……って気持ちで始めたんですけど、意外と好評でした」
「行きたかったな。誘ってくれたらよかったのに」
「いや……そんな、恥ずかしいですよ」
暦くんの耳が赤くなった。
「ともかく、そのグループ展やった時の感覚がいいものだったんで、弦月湯でも何かの形で若いアーティストを応援していけないかな……とは思ってました。漠然とですけど。風呂場も、ばあちゃんが発声練習してた感じだと音響もよさそうだから、音楽会とか開いてもいいんじゃないかって妄想してたこともありました。まあ、突拍子もない考えですけどね」
「そうでもないわよ。いずみさん、パソコン借ります」
私はブックマークから、殿上湯のホームページを開く。
「ここ、隣町の駒込にあった殿上湯って銭湯なのだけど、グランドピアノをお風呂場に搬入して演奏会を開いたり、櫓を組んで和太鼓のコンサートを開いたりしていたの」
「へえ……!」
いずみさんと暦くんは、画面に釘付けになった。
「SNSで調べてみたら、暦くんたちがやっていたようなアート展示もやっていたみたい。高円寺の小杉湯って銭湯もそうよ。ここは、待合室をギャラリーとして開放したり、お風呂場で演劇や音楽ライブも開催しているらしいわ」
「すごい……そんな取り組みやっている銭湯あるんですね」
いずみさんのつぶやきに、私は頷く。
「私もリサーチを始めてみて、銭湯という場にはたくさんの可能性が眠っていることを実感しています。特に小杉湯さんでは、銭湯の中の方々だけでなく、銭湯をお客として使う、地域に暮らす方々が事業として〈小杉湯となり〉というサードプレイスを運営されている……というのも大きな特徴なんです」
私は、Amazonで見つけた一冊の本のページをパソコンで開いた。
「この『銭湯から広げるまちづくり:小杉湯に学ぶ、場と人のつなぎ方』って本を書かれた加藤優一さんという方が中心となって、〈銭湯ぐらし〉という法人を作られたようです。〈銭湯ぐらし〉さんが、小杉湯さんから委ねられて〈小杉湯となり〉を運営されているみたいですね。また小杉湯さんご自身も、これから百年先まで続く銭湯にしていきたいという願いのもとに法人化されて、新たな人材を招き入れながら経営を拡大されているようですよ」
「法人化……」
いずみさんの目が泳ぐ。確かに、法人化にあたっては乗り越えなければならない壁は多い。
「弦月湯にすぐに法人化を薦めているわけではないので、ご安心ください。ただ、長期的な視野に立ってみると、法人格を持つというのは悪くない選択肢だと思います。でも、それは別の話。私が考えているのは……」
息をひとつ吐いた。心を決めて、口を開く。
「私が、弦月湯をサポートするための事業を立ち上げるという選択肢です」
「壱子さんが?」
「ええ」
私は頷いた。暦くんの目が大きくなるのが分かった。私は話を続ける。
「加藤さんが中心となって立ち上げられた〈銭湯ぐらし〉さんの取り組みからヒントを得たんです。そして色々と検討してみると、第三者である私がサポート事業を立ち上げるというのが、この場合、いちばんスムーズに事が運ぶのではないかと思うんです。弦月湯を作られた弦二郎さんの思い。いずみさんの思い。暦くんの思い。それらを受け止めて、小杉湯さんのように、弦月湯がこれから百年続いていくためのサポートを出来るような事業を作っていきたいと思います」
「でも、壱子さんは……」
いずみさんの眉毛が八の字になっている。目が泳いでいる。珍しい。私は暦くんの笑顔を意識して、唇を二イッと引き上げた。
「いずみさん、いまの私には何にもないんです。これまでの自分はすべて、前の店を閉めた時に置いてきました。いまの自分はからっぽだけど、とてつもなく自由なんです。そんなとき、拾ってくれたのがいずみさんと弦月湯でした。ご恩返し、させてください」
「でも……」
いずみさんは困って、暦くんを見つめる。暦くんはその眼差しを受け止めた後、私を見つめた。私は頷いた。ややあって、暦くんも頷く。
「ねーちゃん、ここは壱子さんに任せてみようよ」
「暦……」
「ねーちゃんと自分では出来ないこと、壱子さんはやってくれる。ねーちゃんと自分には見えないこと、壱子さんには見えてる。自分は、それを、自分たちやじいちゃんの思いを大事にしながら、壱子さんが見てくれた未来を、一緒に見てみたい。一緒に形にしていきたい。そう思うんだけど、どうかな、ねーちゃん」
「……それは、壱子さんにとってご迷惑じゃないのかしら」
「それはない! って、自分は思うよ」
暦くんは大きな笑顔を顔中に広げた。ああ、麦わらのルフィの笑顔だ。無敵の笑顔だ。
「壱子さん、自分が納得しないことにはテコでも動かない人だもの。それに、冷静にいろんなこと考えて、分析して、その上で弦月湯の事業に関わるっていう決断をしてくれたんだと思うよ。自分としては大賛成」
暦くんの言葉を聞きながら、私は静かに感銘を受けていた。暦くんが、こんなにも自分のことを理解してくれていたなんて。そして、私のやろうとしていることの背中を押してくれるなんて。鼻の奥が熱くなった。
「……わかりました。壱子さん」
いずみさんが私を真っ直ぐに見つめる。私も見つめ返す。
「壱子さん、どうぞよろしくお願いいたします」
いずみさんは、深々と頭を下げた。
「こちらこそ。どうぞよろしくお願いいたします」
私も頭を下げる。鼻の奥はまだ熱い。シューマンのCDはいつのまにか止まっている。けれど、私の中には、さっきの胸の鼓動みたいなピアノの音色が流れているような気がした。
どこまでも追いかけてくる甘いピアノの音色を振り払うように、私は大きく手を鳴らした。パン!
「さあ、忙しくなりますよ! 暦くん、弦月湯の内観を写した写真ってあるかしら。もしなければ、今、スマホでもいいから撮影してきてもらっていいかしら」
「承知です」
「いずみさん、若月湯が出来てから今日までの年表って書けますか? あと、弦二郎さんのお写真があったら、それもお願いします」
「わかりました」
「お二人に作業していただいている間に、私はWeb周りを簡単に整えておきます」
「よろしくお願いします」
ひとまず、TwitterとInstagram。あと、noteのアカウントも開設しよう。午後までに情報を整備して、運用できるようにしよう。世間に弦月湯の存在を知ってもらうための土台を築くことなら、午後までの時間に出来る。やってみせる。
(つづく)
つづきのお話
・第11話はこちら
・第12話はこちら
・第13話はこちら
・第14話はこちら
・第15話(最終話)はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

