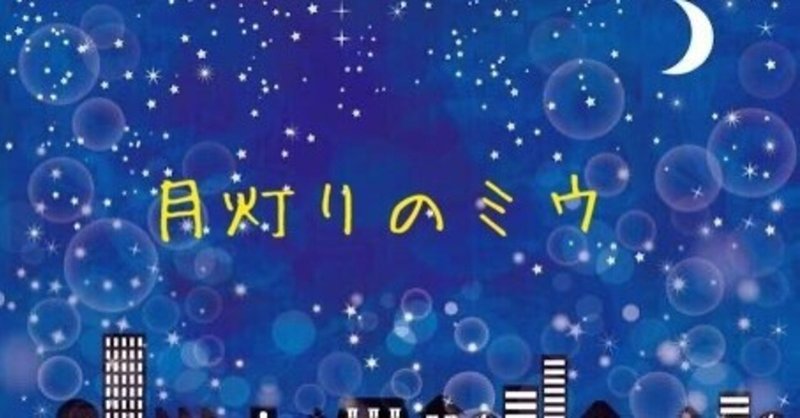
月灯りのミウ 1/16
〈プロローグ〉
突然の異動を言い渡されたのがおよそ3年前、そして今回また突然の異動で僕は再び東京に戻って来た。
この3年間は仙台の街で過ごした。仕事も日々の生活も可もなく不可もなく、何とは無しに過ぎて行った。
付き合った女性もそれなりに1人2人いたのだが、何か決定的なものが見出せずに、それきりになってしまった。
仙台の街自体は好きだった。杜の都と言われるだけあり、空や木々の緑は目に鮮やかだった。広瀬川の流れも歌にあるとおり、穏やかで人の心を豊かにさせてくれた。
そんな暮らしやすい街を去り、3年振りの東京。
ほんの少し見ない内に人も街も知らない顔をして通り過ぎる。この渋谷のスクランブル交差点、一度の青信号で多い時には3千人が行き来するという。これだけ人がいたらひとりくらい居なくなっても誰も気付かないだろう。僕は知ってる顔の誰にも会わず、雑踏の中をひたすら歩いた。
そう、思い出すのは3年前のあの日のこと……
(第1話)マコトの話
僕がその女性と初めて会ったのは渋谷のとあるJAZZ BARだった。そのBARには壁際にダーツ用のボードがかけられていて、いつでも好きな時に好きなだけダーツで遊べる。当時僕はそのダーツに滅法嵌まり込んでしまっていた。
矢が思った所へ刺さるとある種の快感があり、週末などは時間を気にせず夢中になって遊んだ。誰かと得点を争うという訳ではなく1人でそのゲームに僕は熱中した。
暫く遊んだ後はカウンターに戻ってハイボールで喉を潤し、店内に流れる静かなJAZZのナンバーに耳を傾ける。そうすることでリフレッシュ出来、1週間分の仕事疲れもいつしか消えてしまうのだった。
その日は珍しく店内は比較的混んでいたが、カウンターには僕ともう一人女性がストゥールに腰掛けているだけだった。何気なくそちらに目を向けると思いがけずその女性と目が合ってしまった。
最初に声を掛けたのはどちらだったか、今となっては忘れてしまったが、その時小1時間程、僕とその女性は会話を楽しんだ。彼女はそれがクセなのか時々セミロングの髪をかき上げ、魅惑的な瞳で僕を見るのだった。張りのある頬にふっくらとした紅色の唇が僕の目を惹きつけた。
その時どういう流れだったか話はダーツの事に及び、僕は最近これにすっかり嵌まってる事を笑い話として持ち出した。実はそれ程大した腕前では無かったのだが、お酒の勢いもあり僕は多少陽気になっていた。だから、もしもダーツの矢がボードの真ん中に突き刺さったらもう一件別の店に付き合ってくれないかと冗談半分で言ってみたのだ。彼女は即座に「良いわよ」と応えて微笑したので、すぐさま僕はダーツの矢を1本手にした。
ボードの真ん中に命中する確率などその時の僕には10%もなかったはずだが、たまにこんな奇跡も起こるものだ。それが本当にボードの真ん中に命中し、それが今後の2人の関係に発展してしまうなんてその時は思いも寄らなかった。
その夜僕は2軒目の店で少し飲み過ぎてしまったのだ。恥ずかしい話だが、その夜のその後の行動についてはちゃんとした確かな記憶を僕は失くしてしまっている。朧げながらどこかの大きなホテルの部屋のドアを開けベッドに倒れ込んだ気がする。
もしかしたら夢かも知れない。
ただ、うっすらと目を覚ました時、カーテンが開けられた窓から月灯りが射し込み、そこに映し出されるしなやかな女性のシルエットを見た。顔は見えなかったが、やや乱れたセミロングの髪をかき上げたその刹那に綺麗な横顔のラインが垣間見えた。僕にはまるでその姿態は凛とすまして窓辺に佇む仔猫の姿の様に感じた。
その仔猫は潤んだ瞳でチラッとこちらに視線を向け、ほんの少し謎めいた微笑みを浮かべると、すぐにまたすました顔で月灯りを身に纏って息を潜めた。
あたりを静寂が包み、その部分だけ現実のものなのかどうかさえよく分からなかった。その時僕の頭は意識が混濁しており、再び深い眠りの世界へ吸い込まれて行った。
それから数時間が経ち、再び目を開いた時、僕は大きなダブルベッドの上で1人身体を横たえていた。枕元のデジタル時計を見るともう朝の8時を回っていた。窓の外もすっかり明るくなっている。そして彼女の姿は消えていた。
僕は起き上がって窓辺に置かれたテーブルの上に小さなメモを見つける。そこには可愛く丸まった文字で
『昨夜はありがとう、またね。ミウ』
と青いインクで書かれてあった。
それが僕がミウと出会った第1日目の出来事だった。
その後も僕は週末になるとそのJAZZ BARに行き、ダーツをしてはハイボールを飲みながらミウが現れるのを待った。
ミウは翌週もまたその翌週も姿を表さなかった。
ただのひと夜の出来事かと諦めかけた時、おそらく1ヶ月半くらい過ぎた頃、突然2度目の出会いがやって来た。
今にもダーツの矢を投げようとした瞬間、ドアを開けて店内に入って来るミウの姿を、僕は目の端に捉えた。
ダーツの矢はやはりボードの中央に刺さった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
